デジタル全盛時代に見直されるアナログの価値
音楽配信サービスが右肩上がりの成長を続ける一方、アメリカでは今年上半期、1980年代以降で初めてレコードの売上がCDを上回りました。
広告、デザイン、ファッション、建築、写真、アートなど、さまざまな分野で活躍するクリエイターが参加し、クリエイティブの本質、発想の原点について語り合う。

音楽配信サービスが右肩上がりの成長を続ける一方、アメリカでは今年上半期、1980年代以降で初めてレコードの売上がCDを上回りました。

いったい今、どんなメッセージが求められているのだろう。コロナ禍で、私たちの暮らしや常識が大きく変わる中、アウトプットや表現について悩んだ人も多くいることでしょう。今回の、青山デザイン会議のテーマは「言葉」。

新型コロナウイルスの影響を受けて、これまでリアルで行われていた多くのイベントがオンラインへと移行しました。対面でのコミュニケーションが失われる一方、VRなどテクノロジーを駆使した新たな体験も生まれています。今回集まってくれたのは、テレビ東京の工藤里紗さん、日本マイクロソフトの鈴木敦史さん、VR法人HIKKYの代表、舟越靖さん。

ここ数年ムーブメントになっている、クラウドファンディングをはじめとする「応援消費」。さらに、コロナ禍を受けて窮地に陥った生産者や飲食店を支援しようという動きが加速、共感できるものにお金を使いたいと考える消費者はますます増えています。
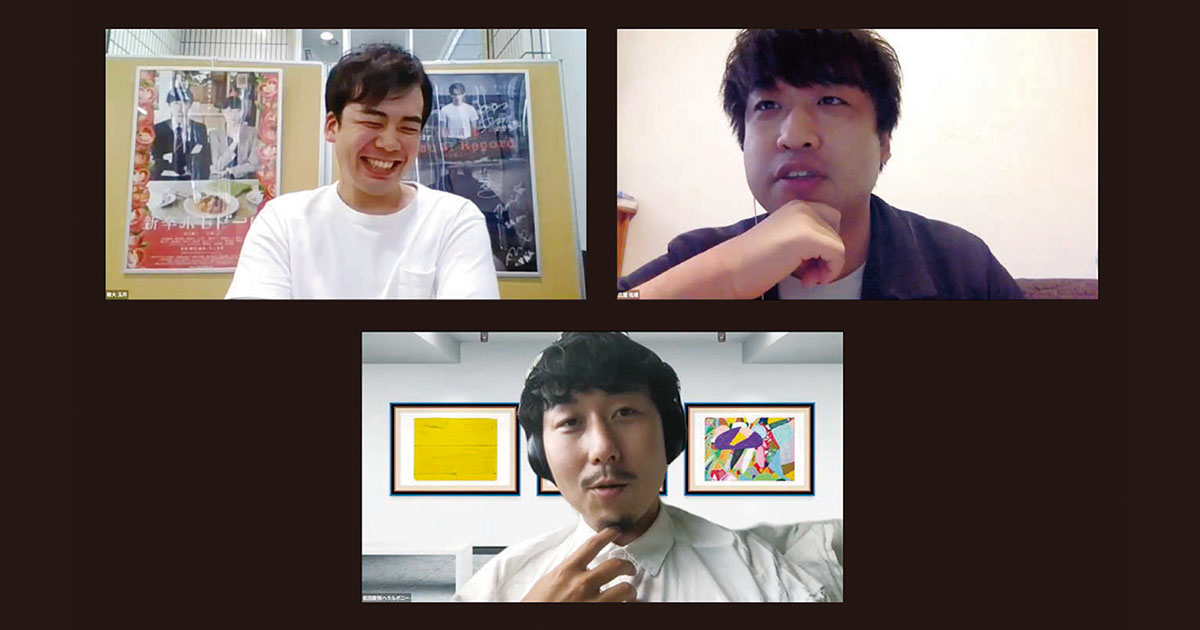
体験価値の高まりとともに、ここ数年、成長を続けていたライブ・エンターテインメント市場。しかし、コロナウイルスの感染拡大にともない、音楽・映画・演劇・アートといった業界が苦境に立たされています。今回集まってくれたのは、そうした厳しい状況の中、いち早くアクションを起こした3人。

人口減少や大都市への一極集中が進み、もはや自治体や行政だけでは解決できない課題が生まれるなかで、持続可能な「地方創生」や「地域活性化」が模索されています。前回に続いて、リモートで行われた青山デザイン会議に集まったのは、「地方創生から地方覚醒へ。」をミッションに、富山の魅力を再発見し世界に発信していくまちづくり会社「TOYAMATO」を設立した青井茂さん。埼玉県三芳町の公務員として、ハロー !プロジェクトとのコラボなど斬新なプロモーションを手がけ、行政広報デザイナーとして活躍する佐久間智之さん。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの暮らしや働き方が、否応なく変わらざるを得ない局面を迎えています。今回、オンラインで行われた青山デザイン会議に集まってくれたのは、Takram 代表で、ハードウェア・ソフトウェアからアートまで、幅広い分野で活躍するデザインエンジニアの田川欣哉さん、広島と東京を拠点に活動する設計建築事務所、SUPPOSE DESIGN OFFICEを率いる谷尻誠さん、そして「い・ろ・は・す」をはじめ数々のブランドやプロダクト開発を手がけるcanaria クリエイティブディレクター 徳田祐司さん。

「出版不況」という言葉が叫ばれ始めて、早20年あまり。単行本や雑誌の売上が右肩下がりな一方で、最近では、独自のセレクトを売りにする小さな書店やブックカフェ、また個性的な本を手がける“ひとり出版社”が登場。さらに、本を通じたイベントやコミュニティが活性化するなど、新たな動きが生まれています。

アメリカでは、ポッドキャストやオーディオブック市場が急成長。日本でもスマートスピーカーの普及とともに定額音楽配信サービスが定着したほか、ネット経由でラジオを聴く人が増えるなど、音声コンテンツが今、再び注目を集めています。
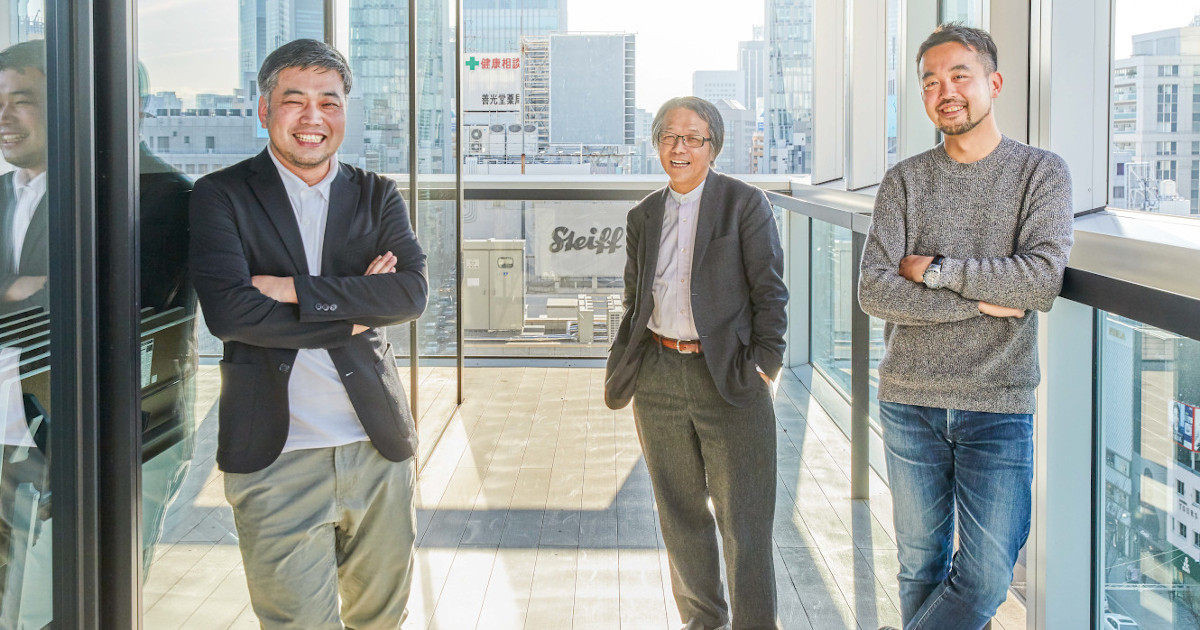
2007年生まれの2人に1人が100歳を超えて生きるといわれる「人生100年時代」。広告・クリエイティブの世界を見ても、60代、70代を超えて活躍することはもはや珍しいことではありません。