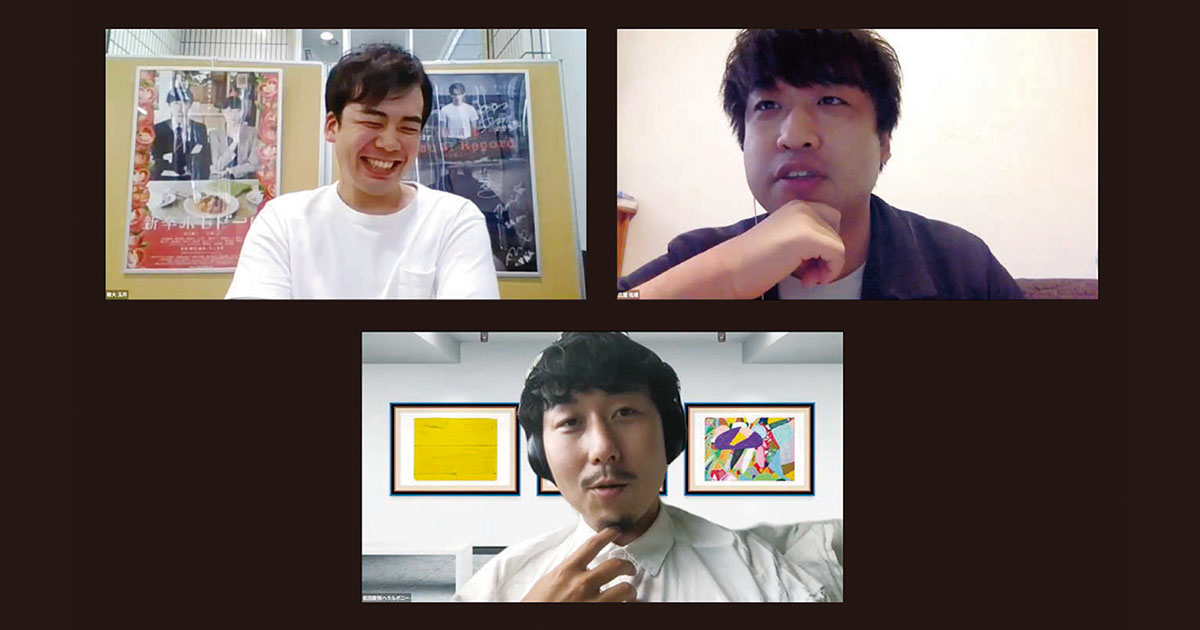新型コロナウイルスの影響を受けて、これまでリアルで行われていた多くのイベントがオンラインへと移行しました。対面でのコミュニケーションが失われる一方、VRなどテクノロジーを駆使した新たな体験も生まれています。
今回集まってくれたのは、『シナぷしゅ』『昼めし旅』など人気番組のプロデューサーを務めるほか、6月に行われた「テレ東無観客フェス2020」をはじめオンラインイベントの企画も手がけるテレビ東京の工藤里紗さん。年間150回以上のイベント登壇や講演会を通じて、「HoloLens 2」をはじめ最新のデバイスとクラウドを活用したワークスタイルを提案する、日本マイクロソフトの鈴木敦史さん。そして、特集でも取り上げた世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」を主催するVR法人HIKKYの代表、舟越靖さん。
それぞれ異なる立場から、オンライン・バーチャル空間ならではの体験価値のつくり方、またその可能性について語ってもらいました。

Text:rewrite_W
年齢も性別も関係のない世界
工藤:私はテレビ東京で、『シナぷしゅ』や『昼めし旅』といった番組のプロデューサーをしていて、他にも今度、『生理CAMP2020』という生理のみにフォーカスした特番も放送されます。最近では、池袋にオープンした施設「ミクサライブ東京」で行われた「テレ東無観客フェス2020」というオンラインイベントの中で、「withコロナ時代に必要な『新・性教育』セクシャルマインドセットをバージョンアップせよ!!」という企画をプロデュースしました。
鈴木:ふだんは法人のお客さま向けに、マイクロソフトのクラウドやデバイスを活用した、働き方改革のプレゼンテーションをしています。ここ半年くらいは、リモートワークが難しい工場など現場の方が、密にならず、最低限の人数でこなせるような仕組みの提案もしていました。
工藤:我々がやらなければと思っていることを、先がけてなさっているんですね。
鈴木:移行せざるを得なかったというのが現状ですね。これまではリアルなイベントで話をすることが多かったのですが、すべてオンラインになりました。
舟越:うちの会社は元々、ゲームやイベントの制作をしていたのですが、2年ほど前に、役員のひとりが「バーチャルの空間上に経済圏をつくる」と言い出したんですね。そこで「バーチャルマーケット」を立ち上げたところ、累計100万人以上が集まる世界最大規模のVRイベントに成長して。
工藤:ちなみに今、舟越さんが背景画像にしているのは?
舟越:バーチャル秋葉原です。今はコロナの影響で問い合わせが殺到していて、どうにもさばけない状況ですが、成功事例がまだとても少ないので、僕たちのノウハウを多くの人に共有したいと考えています。
工藤:オンラインイベントって、どうしても映像を流すだけになってしまいがちなので、バーチャル空間にはそのヒントがありそうだな、と感じていて。
舟越:実はまだ、ライブ関連のコンテンツには技術的な制約が多くて、現実のように大勢で盛り上がるといったことをしようとするには、工夫を重ねなければいけません。
鈴木:一方的に観ているだけになると飽きられてしまうし、画面の向こう側だけで盛り上がっているという“距離感”が出てしまうのが悩みどころですよね。
工藤:先ほど「経済圏」とおっしゃっていましたが、「教育圏」もつくれそうですよね。というのも、私はずっと番組制作現場で育ったので、「ディレクターの背中を見て学ぶ」という時間がありました。本当に学んでいるのか、待っているだけなのかはわかりませんが(笑)、今はそういうやりとりをオンラインでしなければならないので、新人の研修としても使えるのでは、と。
鈴木:そうですね。今年入社した新入社員って、集合研修もできないし、上司にすらなかなか会えない。うちの会社では、研修にゲーミフィケーションを取り入れて、バーチャルのチームをつくって競わせたところ、受講率がぐんと上がったんです。
舟越:僕らのバーチャル空間では、関わるクリエイターがアイデアを出して、しかもノウハウも公開してくれる。そのオープンソースマインドを活かして教え合ったり、リタイヤした方が子どもの先生をしたり、そんな仕組みができたら最高ですね。
鈴木:この世界に進んで入ってくる人たちって、広げていくのが本当にうまいですよね。あとは自分からは入っていけない人たちへの、ラストワンマイルをどうするか。
舟越:最初に出会うひとりが決め手になるので、コミュニケーションが上手な人にガイドをやってもらおうと考えています。
工藤:ひとつ感じたのは、バーチャルの世界ってジェンダーや年齢があまり関係ないということ。この間のオンラインイベントでは、女性ばかりだと偏るし、男性にこそ知ってほしいという想いから、伊藤(隆行)Pという上司に男性代表として登壇してもらいました。でも、それってリアルの世界にとらわれているのかなあ、とも。
鈴木:たしかに性別も年齢も国籍も、あまり意識することはないかもしれません。
工藤:対面だと、雰囲気に押されて言うことを聞いちゃう、みたいなケースってありますよね。でもオンラインだと客観視できるので、「あれ、この人の言ってること意外と古いぞ」なんて気付ける(笑)。もし全員がアバターだったら、仕事の仕方も全然違ってくると思うんです。
舟越:そのとおりですね。うちの会社ではアバターで会議をしていますが、かわいい見た目で発言されると、なぜか角が立たない。年下が発言しにくい空気もなくて、僕もがんがんダメ出しされています(笑)。
鈴木:僕個人の話をすると、リアルなイベントでは、終わった後に名刺交換の列がずらっとできて、結局誰が誰かわからないということがよくありました。それがオンラインの場合、本当に仕事をしたい人とだけつながれる。意味のあるつながりがつくりやすくなってきたとも感じます。
工藤:とはいえ私たち世代は、飲み会などから仕事やアイデアの種をもらうことも多かったと思います。でも今は「誰々も連れてきちゃった」という偶発的な出会いがない。
鈴木:オンラインって、廊下でばったり会って盛り上がる、みたいなことが難しいんですよね。それをバーチャル空間に求めるというニーズはあるんじゃないかな。
舟越:まさにそうなんです。バーチャルSNSになぜ何度もログインするかというと、コミュニケーションをしたいから。人とのコミュニケーションって絶対飽きないし、それが最高のコンテンツになる。
工藤:そう考えると、お年寄りに特化したバーチャル空間なんかもあり得ますね。『昼めし旅』のロケで地方に行くと、道の駅に地元のお年寄りが集まっているんです。何か買いたいというよりは、あそこに行けば誰かがいるという感覚で。
舟越:昼間、『ドラゴンクエストX』上で井戸端会議をしている主婦の方もいるらしいので、可能性は十分ありますね。
LISA KUDO'S WORKS

withコロナ時代に必要な「新・性教育」セクシャルマインドセットをバージョンアップせよ!!
テレビ東京のプロデューサー・ディレクター陣が9日間連続でイベントを実施した「テレ東 無観客フェス2020」で生配信。SHELLYさん、鈴木涼美さん、宋美玄さん、峰なゆかさん、ゆきぽよさんが現代の性を語った。
©テレビ東京

シナぷしゅ
民放初の0~2歳児向け番組。子育て奮闘中の社員がプロジェクトに参加し、「自分の子どもに見せたい」と思える良質なコンテンツを開発。テレビ東京にて、毎週月~金の7:35~8:00/17:30~17:55に放送中。
©テレビ東京

インベスターZ
©『インベスターZ』製作委員会

アラサーちゃん無修正
©峰なゆか/扶桑社/KADOKAWA ©「アラサーちゃん無修正」製作委員会

池上彰vsニッポンの社長100人大集結!SP
©テレビ東京
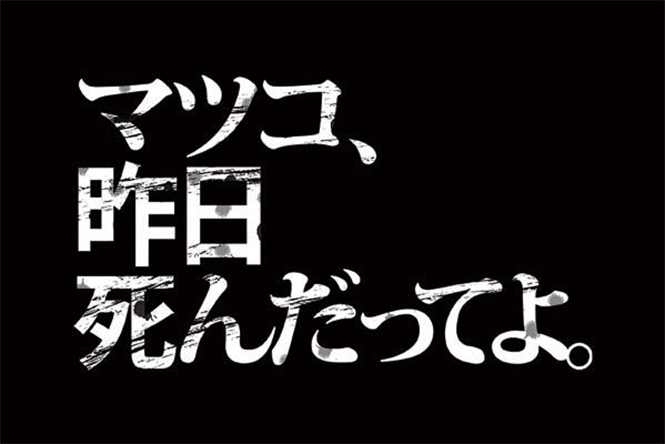
マツコ、昨日死んだってよ。
©テレビ東京

東急ジルベスターコンサート
©テレビ東京