いま、写真にできること
Facebook、インスタグラムなどのSNSに始まり、いまや誰もが当たり前のように写真を撮る時代になりました。写真とは本来、私たちの目の前にあるものを写し出し、記録として残すことに重きが置かれていましたが、2011年の震災以降、写真そのもののあり方や活用方法が変わってきました。多くの写真家が自分自身の地元やさまざまな地域を訪れ、その地域と結びつく形で写真を発表しています。
広告、デザイン、ファッション、建築、写真、アートなど、さまざまな分野で活躍するクリエイターが参加し、クリエイティブの本質、発想の原点について語り合う。

Facebook、インスタグラムなどのSNSに始まり、いまや誰もが当たり前のように写真を撮る時代になりました。写真とは本来、私たちの目の前にあるものを写し出し、記録として残すことに重きが置かれていましたが、2011年の震災以降、写真そのもののあり方や活用方法が変わってきました。多くの写真家が自分自身の地元やさまざまな地域を訪れ、その地域と結びつく形で写真を発表しています。
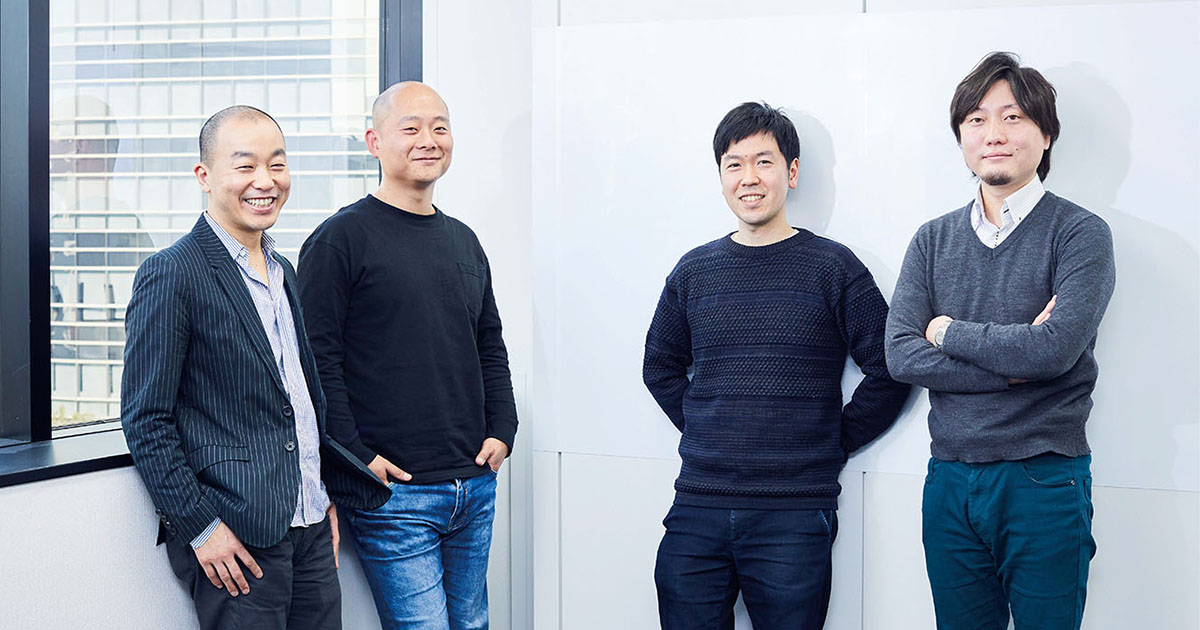
ジブリ作品にはじまり、近年は『君の名は。』『この世界の片隅に』など大ヒットするアニメーション映画が続々と生まれている。また、テレビにおいても、子ども向けのものだけではなく、深夜枠のアニメーションも人気を集めている。こうした傾向と共に、近年広告の世界においても、CM等でのプロモーション動画にアニメーションを使うケースが増えている。トライのハイジシリーズ、日清食品「カップヌードル」アオハル、アフラックやYKKの動画、さらには丸井がアニメCMの声優を募集したり、「ごはんですよ」のアニメーションの復活など、話題は尽きない。

いまさら語るまでもなく、ダンスブームが続いています。さまざまなタイプのダンスが流行る中、それに呼応するかのようにダンスを使った映像表現が増えて、話題になっています。ポカリスエットの高校生によるガチダンス、金鳥のカップダンス、Yモバイルの双子ダンス、クレディセゾンの社員による東池袋52…などのCMや地方自治体のPR動画、さらには「恋ダンス」以降のテレビドラマのエンディングをはじめ歌番組でも。最近では大阪・登美丘高校のダンス部も話題となり、プロ・アマ問わず、ダンスはいまや映像表現の核になりつつあります。そして2020年に向けて、今後ダンスを使った表現はますます増えていきそうです。
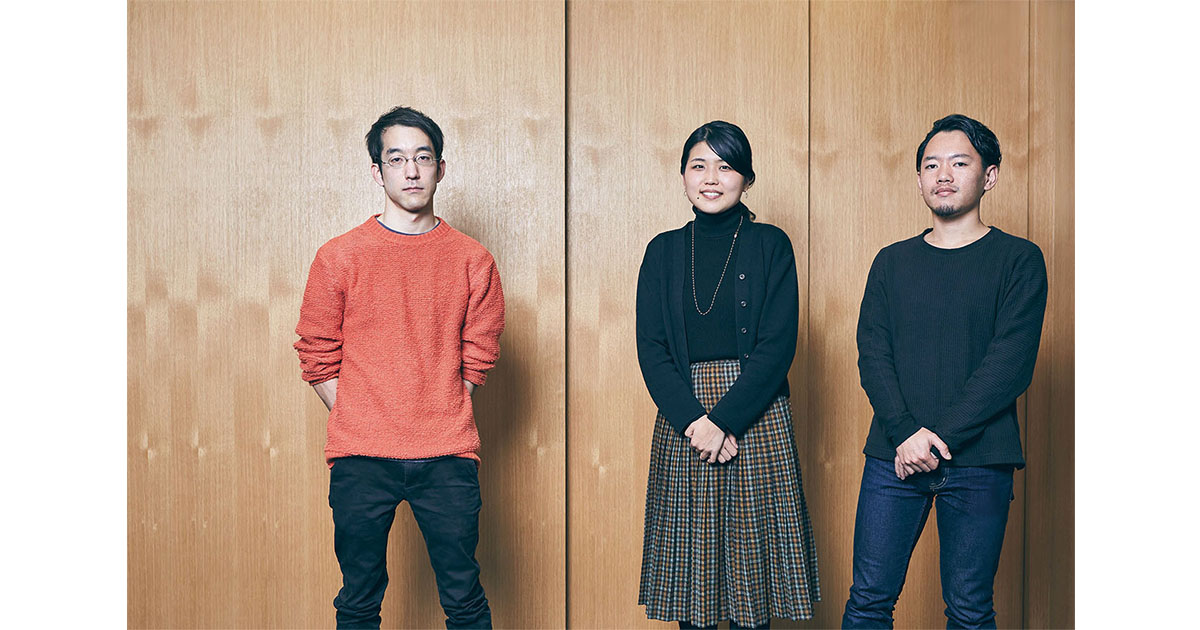
グローバル化が謳われながらも、クリエイティブの世界でもまだまだドメスティックな日本。そんな日本を飛び出し、ミラノサローネをはじめ海外の展示会に個人で出展したり、専門知識や技術を学ぶため留学をするなど、国や文化の垣根を越えて自分の力を試そうとするデザイナーの姿が散見されるようになりました。海外での学びは彼らをどう変えて、そのクリエイティブにどのように生きているのか。
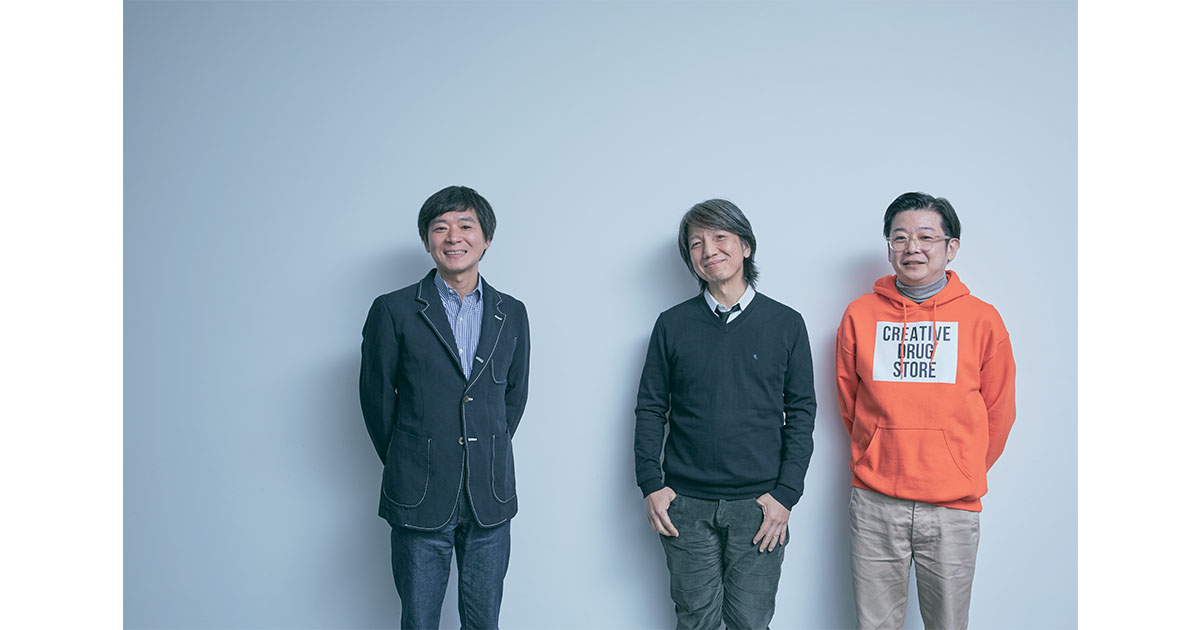
広告・デザイン界で活躍するクリエイターのみなさんは年齢を重ねても元気で、変わらず現役プレーヤーです。一般企業にある定年とは関係なく、会社を卒業後も仕事を続けていく方が多くいらっしゃいます。クリエイティブの仕事とは自身にアイデアと続けていく意志があれば、年齢に関係なく続けていけるものであることを、まさに証明しています。

近年、企業の中でデザインやクリエイティブに対する意識が高まり、社内にクリエイティブ組織を設けたり、外部のクリエイティブディレクターと連携して仕事をする企業も出てきています。しかし、その一方で"インハウスデザイナー"の存在が見えにくくなっているようにも感じています。

今年も11月に、世界最大の写真見本「パリフォト」が、フランス・パリで始まります。「パリフォト」は写真家、ギャラリー、パブリッシャーが世界中から集まり、写真に関わる人にとって重要な場であり、日本の写真家や写真集はこの場で高く評価されていると聞きます。
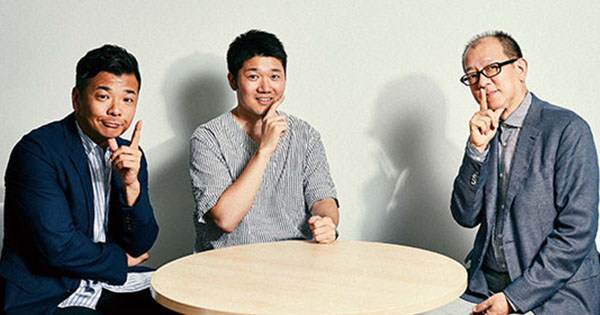
私たちは、毎日の生活の中で当たり前のように歩いたり、食べたり、人と言葉を交わし、メールやSNSで言葉を送りあっています。そして私たちは何かのきっかけで、こうした「当たり前のことができなくなる」ということを普段あまり考えていません。思いもよらぬ病気や事故、高齢による体の変化などにより、どんな人にも「当たり前のことができなくなる」可能性は十分にありうるにもかかわらず、です。
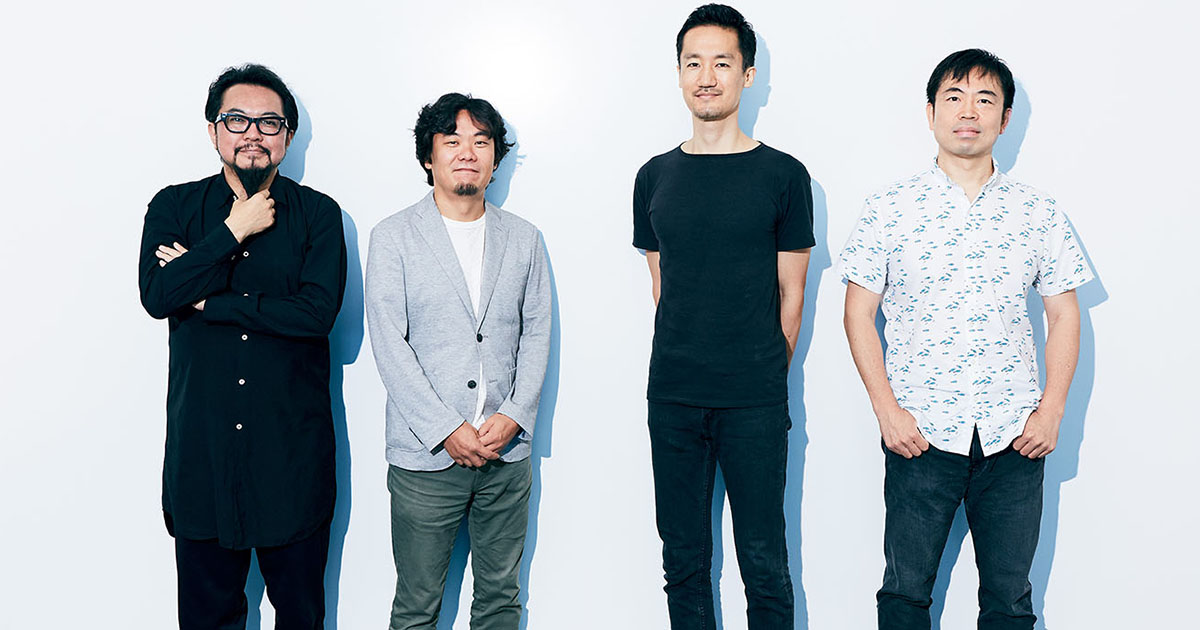
今年もD&AD、One Showに続き、カンヌライオンズが終了しました。ここ数年は広告の領域の広がりと共に、部門が増え、複数の領域にまたがって出品される作品が増加。従来の広告よりも、デジタルやイノベーションに注目が集まっていたカンヌライオンズですが、今年はエンターテインメントとしてのフィルム復権の兆しも見られました。社会的な背景が作品に大きく影響し、さまざまな表現や企画、さらにはテクノロジーが混沌と交じりあった今年のカンヌライオンズは、広告界にどんなメッセージを放ったのでしょうか。
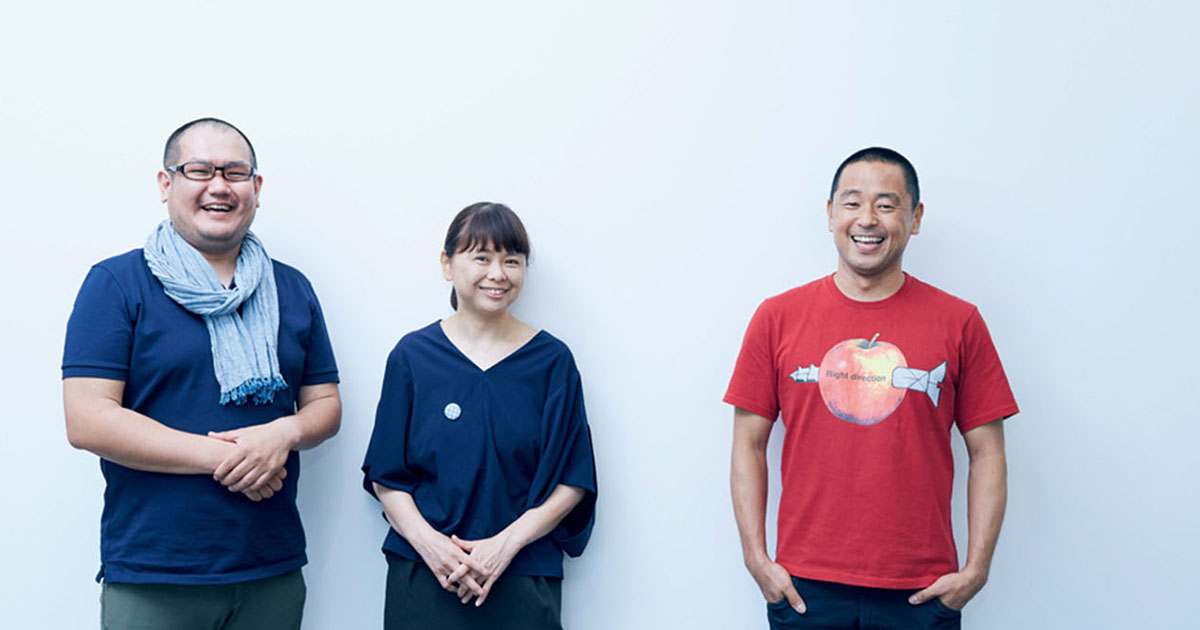
地方創生という言葉が広く浸透したこの3年。観光PR、ふるさと納税、移住など、さまざまな形で"地域"への注目が続いています。また広告会社に限らず、最近ではさまざまなジャンルの企業が地方創成事業に取り組み始めています。しかし、そこにはまだまだ課題も多く見られます。東京などから施策を持っていく人たちと地域の人たちとのコミュニケーション、動画など人気の手法に頼ってしまいがちになったり、うまくいったにも関わらず1年で終了してしまったり――。コミュニケーションに携わる多くの人が「地域」に携わり始めている今だからこそ、あらためて見直しておくべきことがあるように感じています。