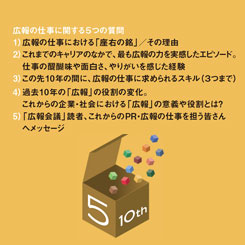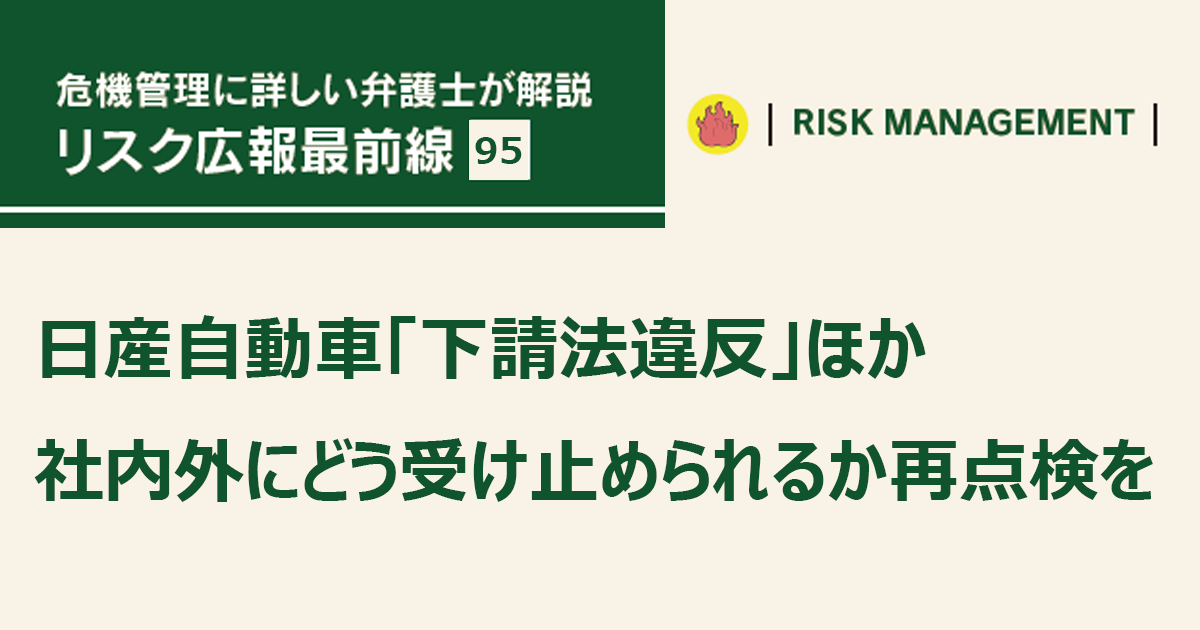この10年、現場で挑戦を続けてきた35人の実務家の皆さんが考える広報の仕事の醍醐味とは? 企業はもちろん、自治体や大学まで、あらゆる場面で広報の力を実感したというエピソードも満載です。未来への提言、読者へのメッセージもいただきました。
 |
博報堂 PR戦略局 局長1981年博報堂入社。25年間営業畑を歩み、大手流通グループをメインに、食品・飲料、外資金融などを担当。2007年より博報堂アイ・スタジオ代表取締役社長(デジタル制作会社)出向、2011年に本社に戻り、現職。 |
Q1:広報の仕事における「座右の銘」/その理由を教えてください。
A1:「その違いを、カタチにする」/市場競争の歴史は「差別化」と「同質化」の繰り返し。試行錯誤の中から“格の違い”を生み出し、それを具体的な成果として世の中に送り出す。違いをカタチにしていくそのプロセスから、本物の競争力と強固な関係性が生まれる、と実感しています。
Q2:これまでのキャリアのなかで、最も広報の力を実感したエピソード、仕事の醍醐味や面白さ、やりがいを感じた経験を教えてください。
A2:業務上の守秘義務があるため、残念ながら書けません。むしろ、原発の風評被害や、中韓外交でのギャップや、食品会社への正論モンスターなどの事例を見るにつけ、逆に空気読みの難しさや的確な情報発信のあり方について、考えさせられる毎日です。
Q3:この先10年の間に、広報の仕事に求められるスキルを教えてください。(3つまで)
A3:[1]ネタ開発力やメディアを巻き込む技術
[2]国内経済を世界市場視点で発想していく力
[3]収益デザイン力
Q4:過去10年の「広報」の役割の変化。これからの企業・社会における「広報」の意義や役割とは?
A4:デジタル化・グローバル化・生活者の成熟化で、企業や商品の寿命が短くなり、得意先自身が何をやっていいのか、分からない時代。10年前までは広報の専門性だけで勝負できたものが、今やPRスキルを源泉とした「コミュニケーション全体設計能力」まで、問われるようになっています。必要なのは、言われた課題を解決するだけでなく、培ってきた専門性をベースにして、得意先事情から一旦幽体離脱し、バリューチェーン全体を多面的・双方向的に捉え直すこと。課題解決型の仕事から、ひとつ上を行く「課題設計能力」が身につけば、信頼される本物のパートナーになれるはずです。
Q5:「広報会議」読者、これからのPR・広報の仕事を担う皆さんへメッセージをお願いします。
A5:人も企業も国家も、毎時・毎日・毎月・毎年、必ず変化しています。だからこそ、我々の仕事には、途切れることのない需要があります。「○○の専門家」に安住していると、時代が変わった瞬間、用済みになる危険性がある。「次のPRのあり方」を自問自答しながら、変化に対応していく姿勢と顧客志向性を持ちましょう。