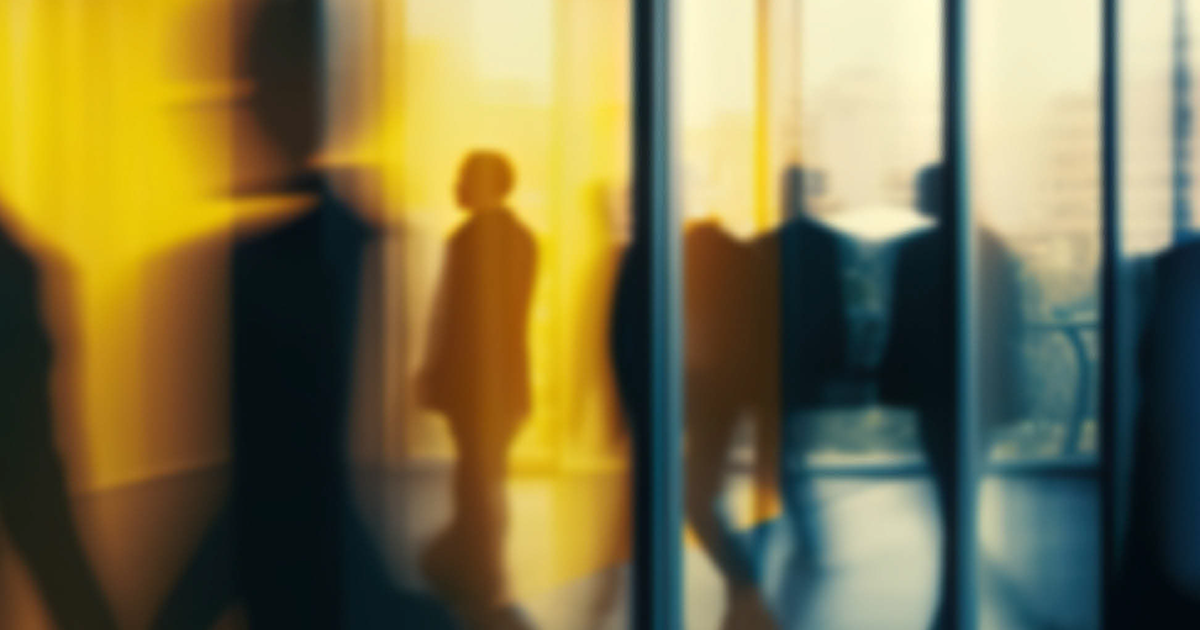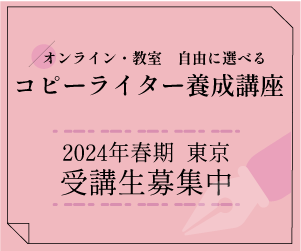【あらすじ】
季節を問わず、多くの宿泊客が訪れる千葉県の「ホテルシーサイドマリーナ木更津」。広報課の白坂ひろみは、1年ぶりに帰省するため仕事を終えた足でホテルの玄関前から空港行きのバスに乗り込む。入れ違いに降りた客から、わずかに火薬の臭いを感じ、念のため同期の酒井茉由にメッセージを送ろうとするが……。

たった一人の躊躇が、リスクを増やす
夕陽を背負った富士山頂は朱色に染まり、中腹から下は灰色に見える。コントラストが鮮やかだった。遊歩道を歩いている家族連れが「きれい!」と歓声をあげる。頬を撫でる風がようやく春を感じさせるようになった。
「陽のあるうちに帰るのもいいものだわ」ホテルから続いている宿泊客専用の遊歩道を歩きながら白坂ひろみが微笑む。三日間の休暇を取って、佐賀県の実家に帰る。一年ぶりの帰省だった。「そろそろ行くか」ホテルの玄関から羽田空港に向かうバスが出ている。19時30分発の航空券を取っていた。ホテル業界は他の業種と比較して従業員の勤続年数が短い。世間からはほぼブラック企業と言われ、それは白坂が勤めるホテルも同じだった。転職しながらスキルを磨きたいと前向きにホテルを転々とする者もいるが、三年も勤務すれば一人前のホテルマンとして見られる。
専門学校の卒業を間近にしたとき、旅行で泊まったホテルでドアマンの口調やスーツの着こなし、指の先まで気配りされた対応に〝電流が走った〞。アルバイトでもしながら好きな絵を描こうかと考えていたが、ドアキーパーとの出会いが進むべき方向を示してくれたと勝手に思い込むことにした。
「とりあえずはアルバイトでいいかなあ」と軽い気持ちでホテルのアルバイト募集を探した。やるなら東京と決め、次々に応募した。いくつかのホテルで面接までたどり着いたが、採用には至らない。だが、面接で見た他のアルバイト応募者と比較しても劣っているとは思えない。
「どうして採用されないんだろう。たかがホテルじゃん、人手不足なんだから私を採用しなさいよ」応募画面につぶやく日々が続いた。「これで一八社。今日もダメだったかあ」東京がダメなら隣の県を見てみるか。地方出身者は東京で働いてみたい、住んでみたいと一度は思う。誰もが夢を抱いて上京する。しかし、白坂は憧れだけで応募していたわけではない。
正社員になると自分の時間は取れないだろう。アルバイトで生計を立てながら得意とする絵を描き、いつか世に出てみたい。それには東京がもっともチャンスがあると思っていた。しかし現実は甘くない。アルバイトといえど、しっかりと見られていた...