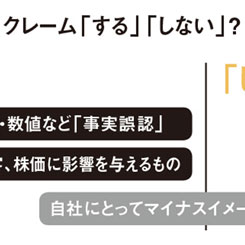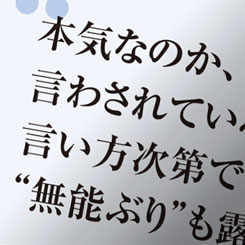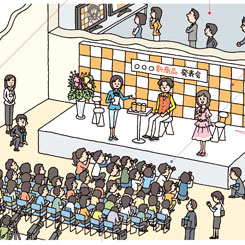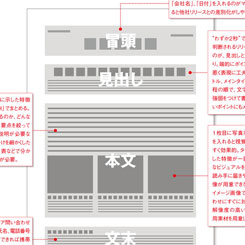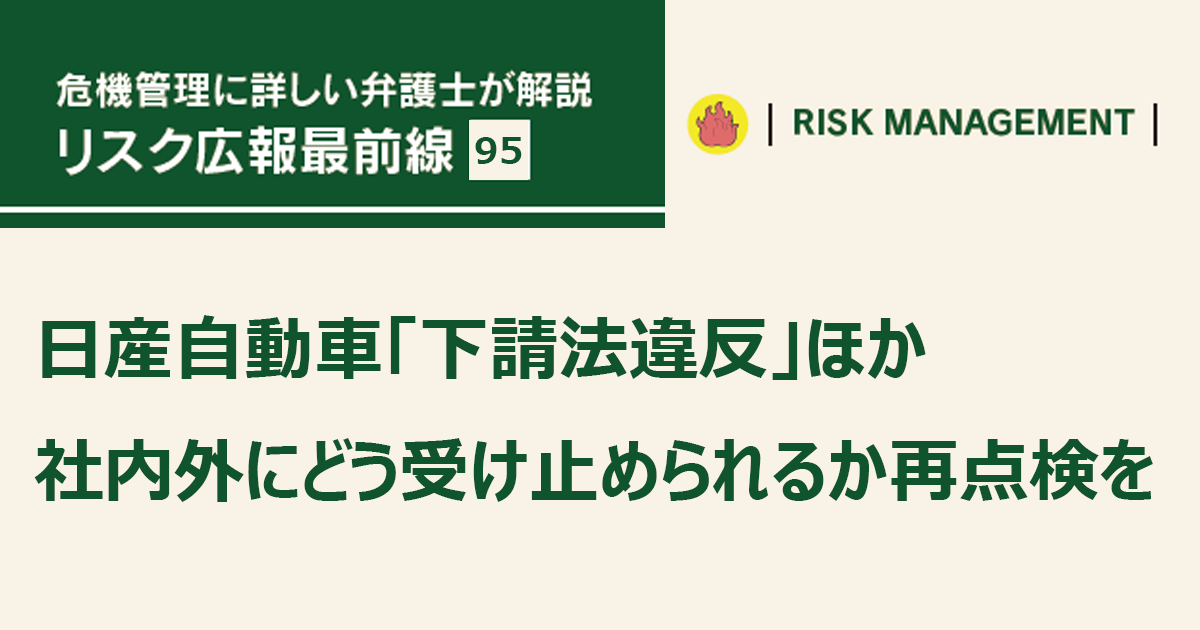クレームを受ける側はどう考えているのか
本気なのか、言わされているのか。言い方次第で“無能ぶり”も露呈します。
月刊「サイゾー」に加えウェブの「日刊サイゾー」をオープンしてから、非常にクレームが増えたと同誌の岩崎貴久編集長は話す。「クレームを入れてくる人と、私たちの間には温度差があるなと思うことが度々です」と岩崎氏。その温度差の正体とは何か。
「私たちサイゾーは、大手メディアと違い、時にマイノリティの声をピックアップするのがメディアとしての役割。恐らくクレームを入れる方は、一般論を語り、私たちは個別事例を語っているというギャップがあります」。たとえば、某テレビ局と芸能プロダクションとの癒着。もちろん、全員がそういうことをしているわけではない。しかし、一部でそういう事実があるのであれば、それはメディアとして報道せざるを得ない。「メディアにはそれぞれ役割があり、それを理解しないで頭ごなしに話すのは、かえって広報の勉強不足を露呈することになり、逆効果です」。
さらにもう一つ、広報の価値を下げるのは、「言わされている感」が強いクレーム。「上が怒っている、会社で問題になっていると感情的に言われても、私たちには関係のないこと」。上司や事業部から言われても、そのまますぐにクレームを入れるのではなく、自分ごととして落とし込んで話してくれれば印象は変わる。「あるレコード会社の役員が、アポイントなしで会いに来たことがありました。要件は、所属アーティストの記事を書くのをやめてほしいというもの。よくよく聞くと、そのアーティストのことを本気で考えていると分かり、あれは効きました」。