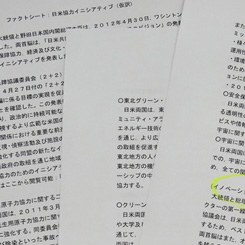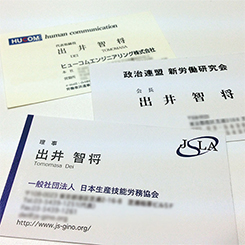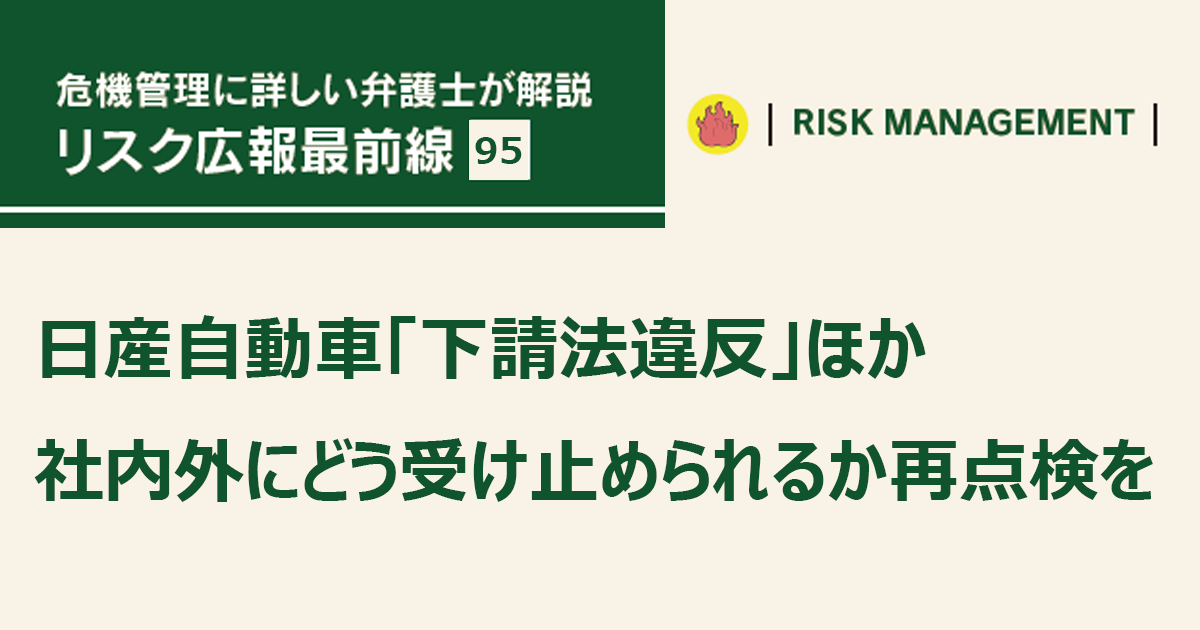パブリックアフェアーズは、「企業経営の世界流儀である」とフライシュマン・ヒラード・ジャパンの田中愼一社長は話す。世論との対話力を培うために、企業がすべき備えとは。

日本車メーカーへのバッシングの嵐の中、7年以上にわたり、アメリカ世論を味方につけようと奔走した。手前は本田宗一郎氏、奥に筆者。
今日の企業経営は大きく3つの「フィールド(競技場)」において判定されると言えよう。まずは「市場」で競合他社と戦う、次に「法」に照らした企業行動が求められる、そして3つ目が、「世間」で世論に裁かれる。それぞれのフィールドでは、市場のルール、法のルール、社会のルールを基準に判定される。社会のルールは、人々の常識や通念、思い込み、また場合によっては人々の無知などから形づくられる。
「世間」の厳しい判定にあった最近の例では、不正融資のみずほ銀行、食品偽装の阪急阪神グループが挙げられる。今、企業経営は不祥事などのクライシスに直面した局面に限らず、常に「世間」に晒され「世間」と対峙することを余儀無くされている。パブリックアフェアーズ(PA)とは、社会の中にあって企業が存続、成長していくために、この「世間」としっかり向き合う、企業経営の戦略処方箋である。
日本バッシングの中で
「PRってなんですか?」、「分からぬ、ただ、これからの企業にとって大事なものらしい。ホンダは目に見える"ものづくり"は得意だが、見えないものにはどうも弱い、その見えないものを相手にするみたいだ。まあ、頑張って来い」。1983年10月、筆者が27歳の時、PR担当としてワシントンDCへ赴任する前の、上司からのはなむけの言葉である。
80年代当時、ホンダの最大の関心は生命線の米国戦略が日米自動車通商摩擦によってどのように影響を受けるかであった。ホンダにとって「見えないもの」とはアメリカの世論の動向だ。日本の自動車メーカーは、今日では想像できないほど激しい反日世論にさらされていた。シビックやカローラが失業者達の手で燃やされ、壊される事態が頻発していた。その背景には、日本車が不当な競争力で市場を席巻、アメリカ人の職を奪っているという、アメリカの人々の強い思い込みがあった。