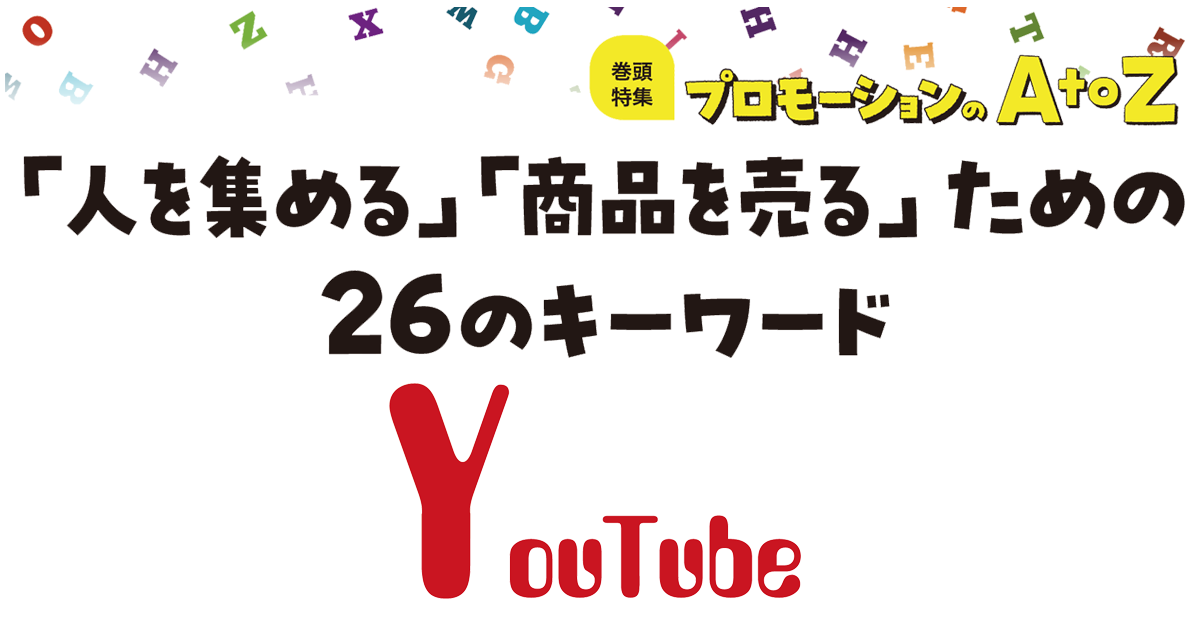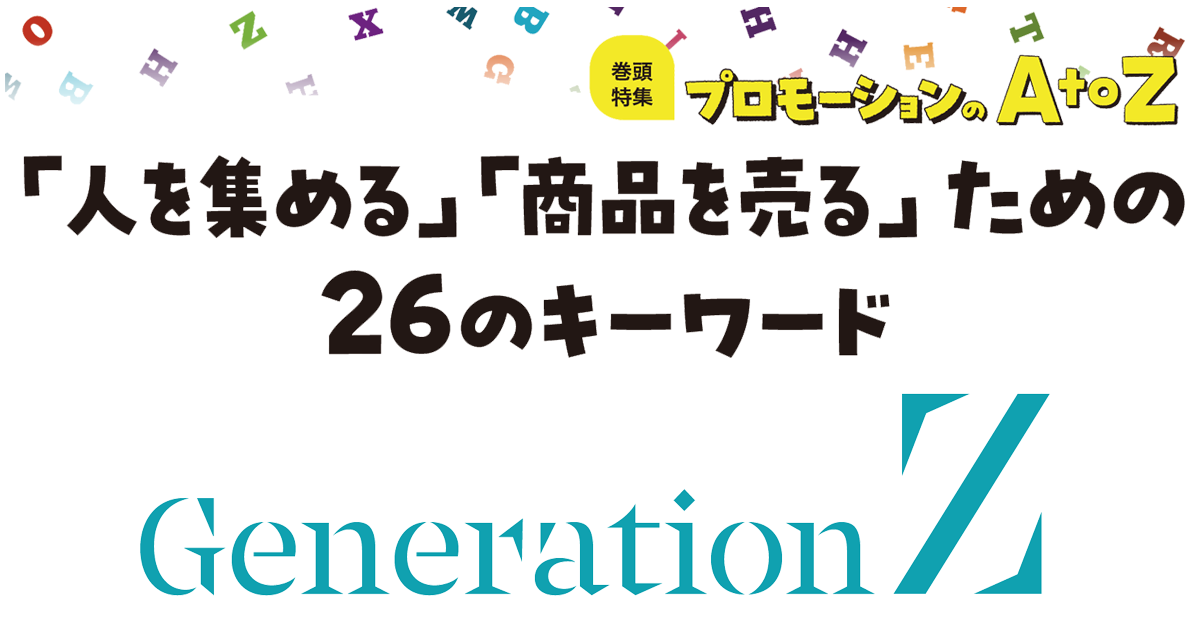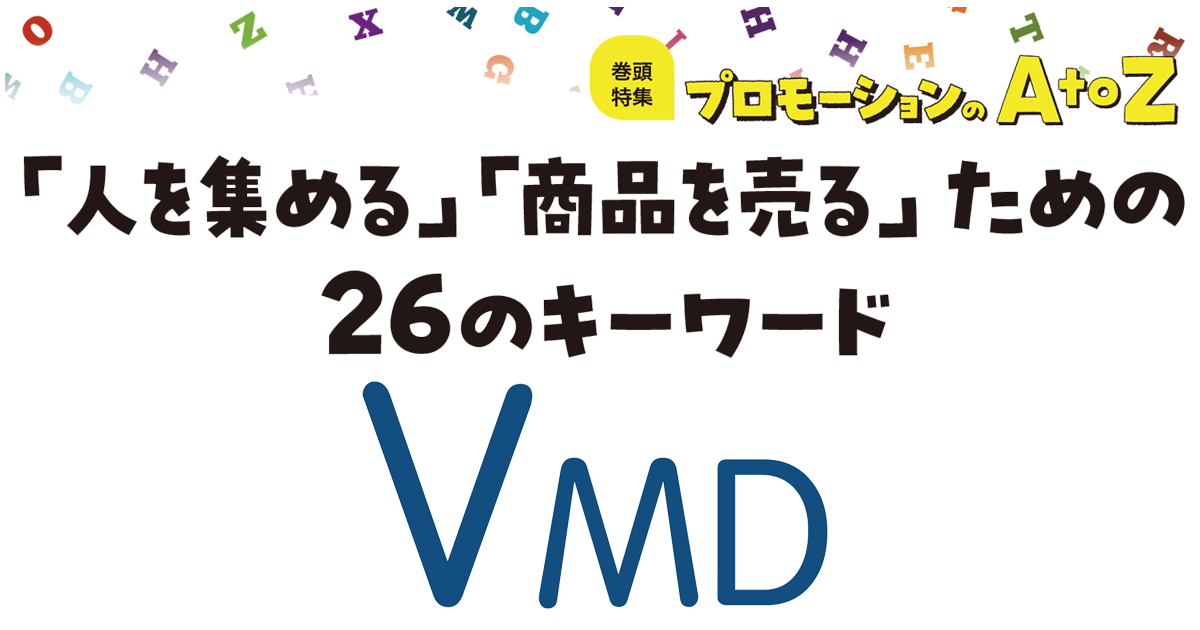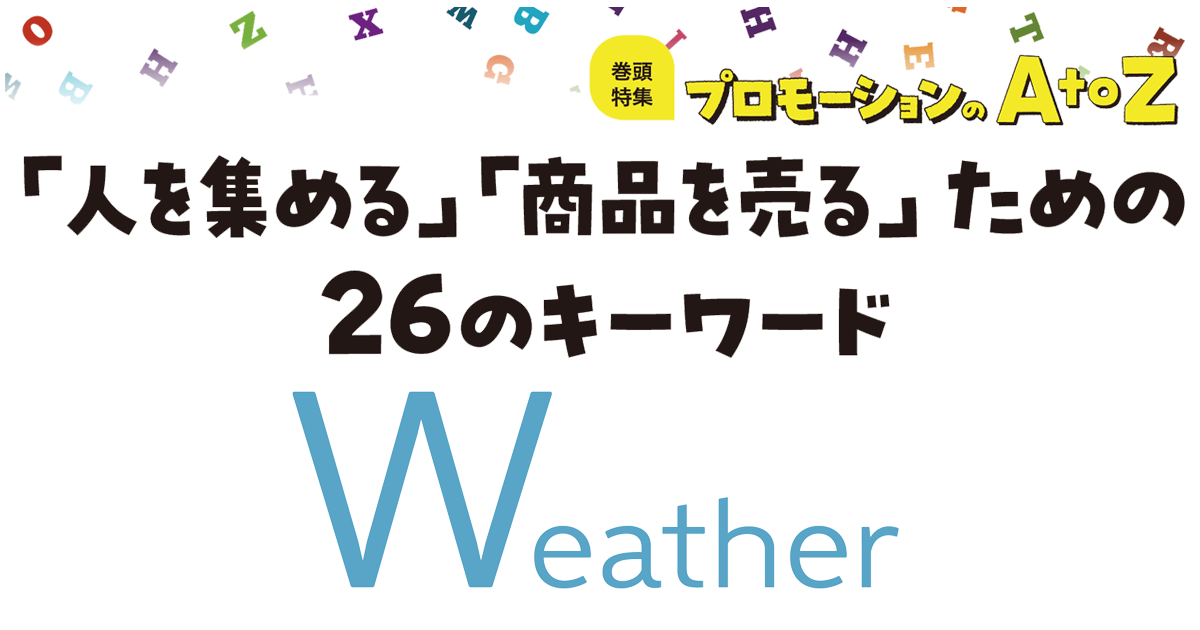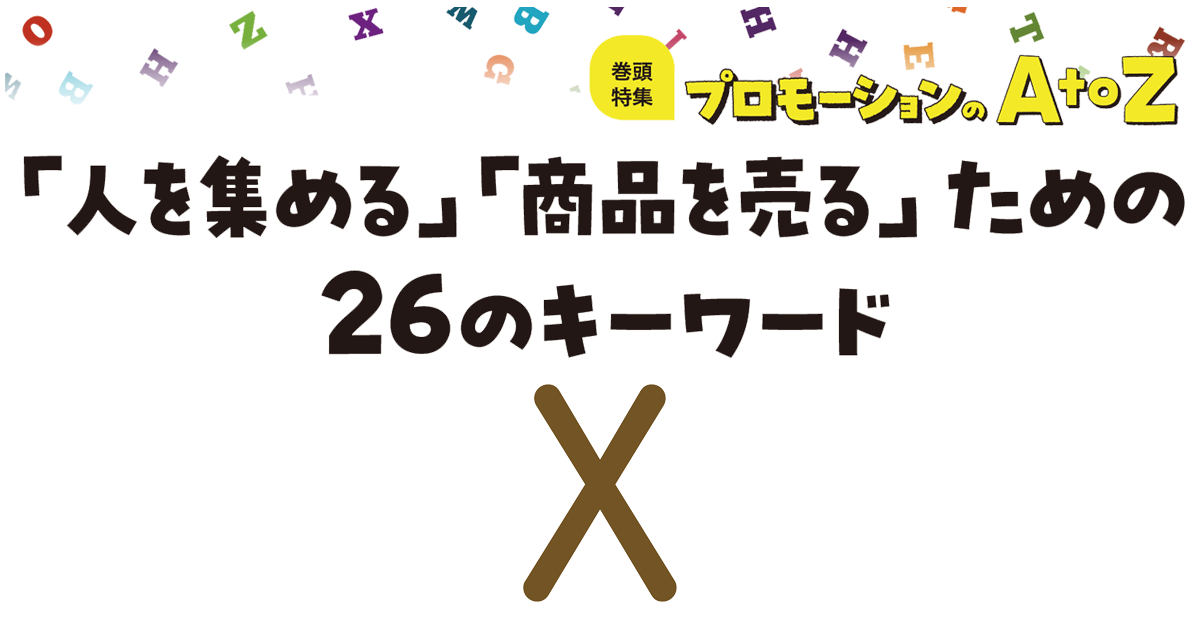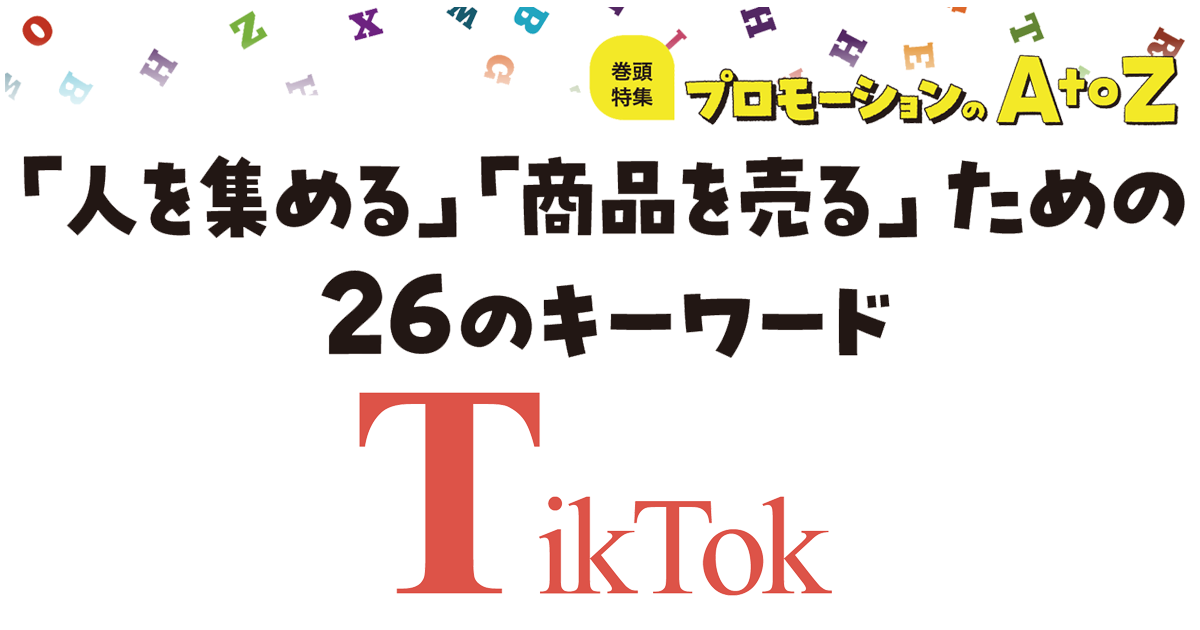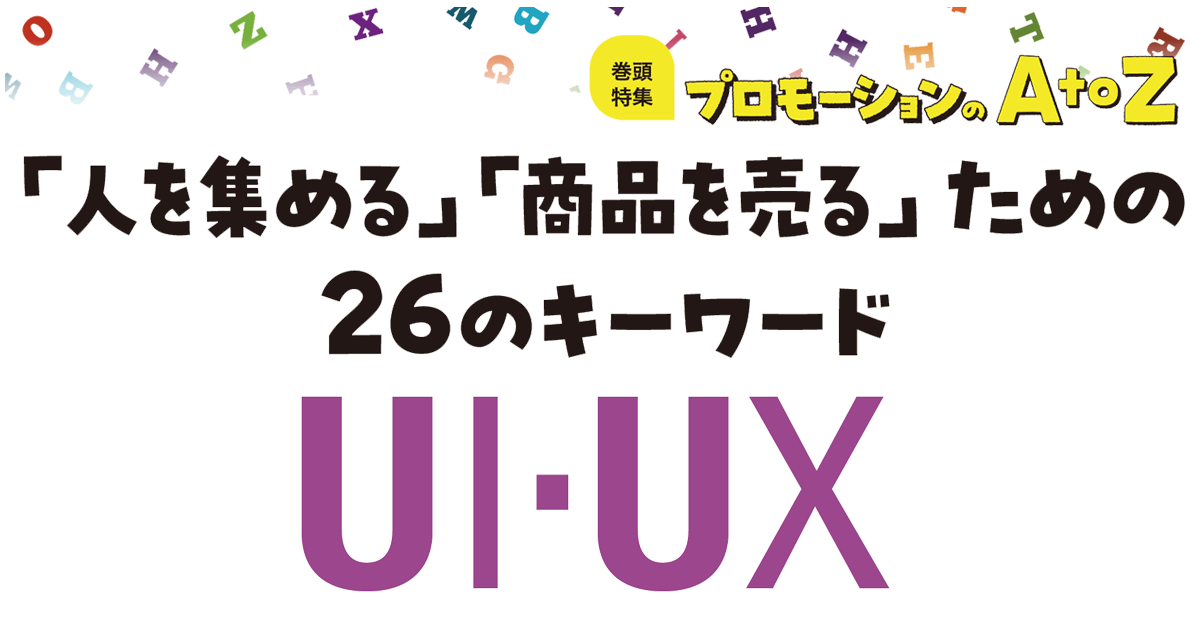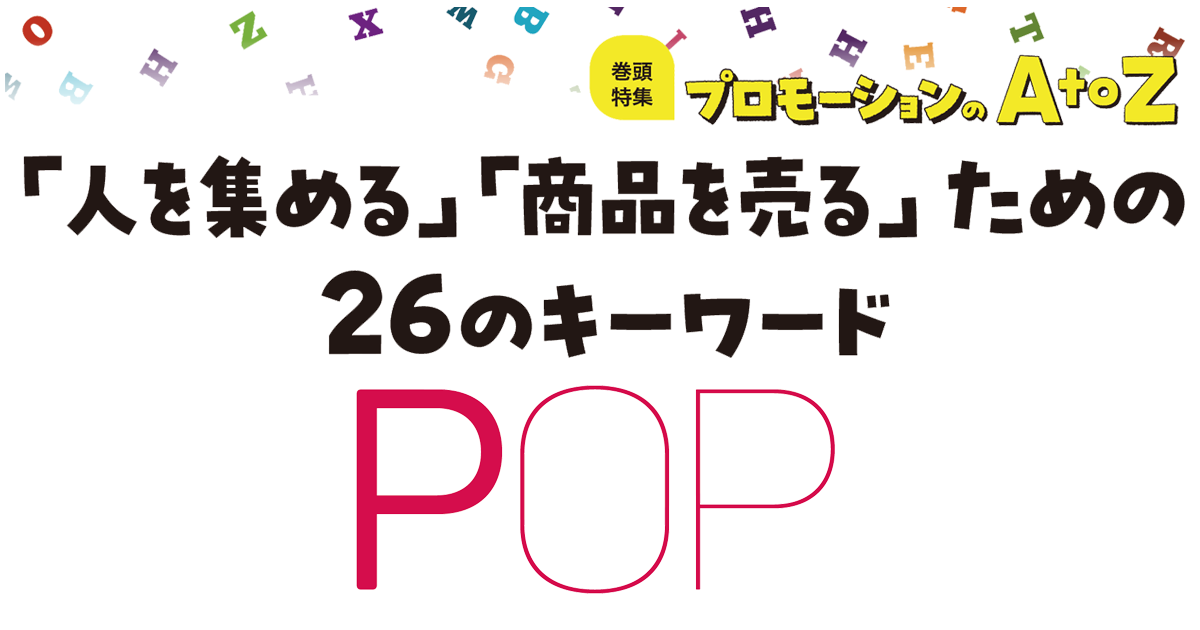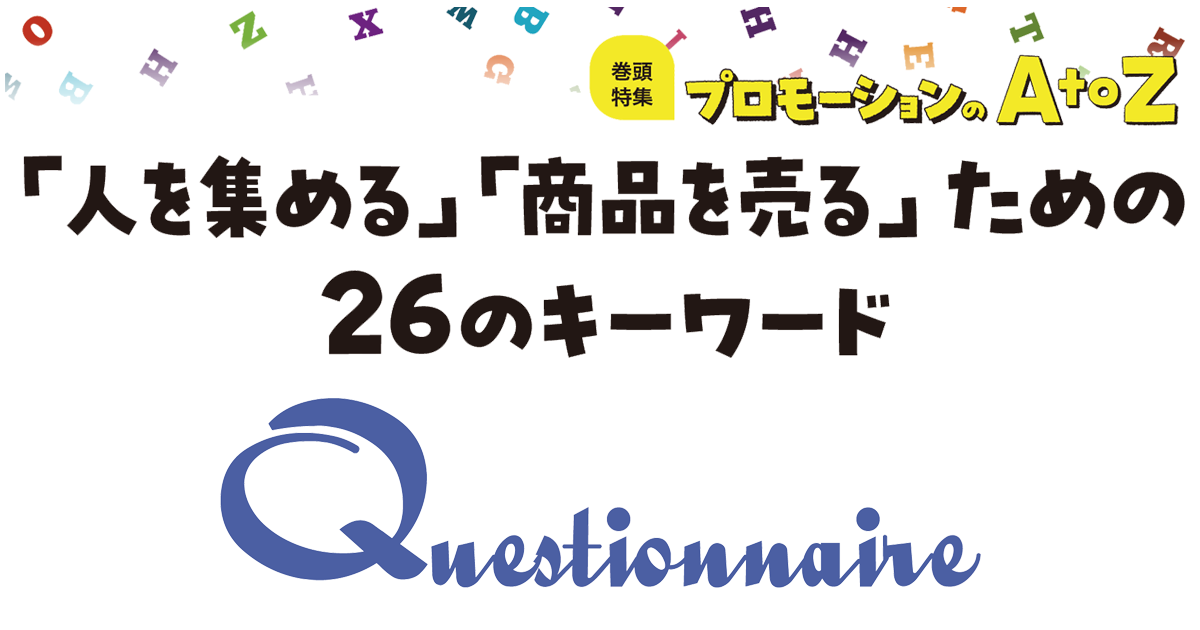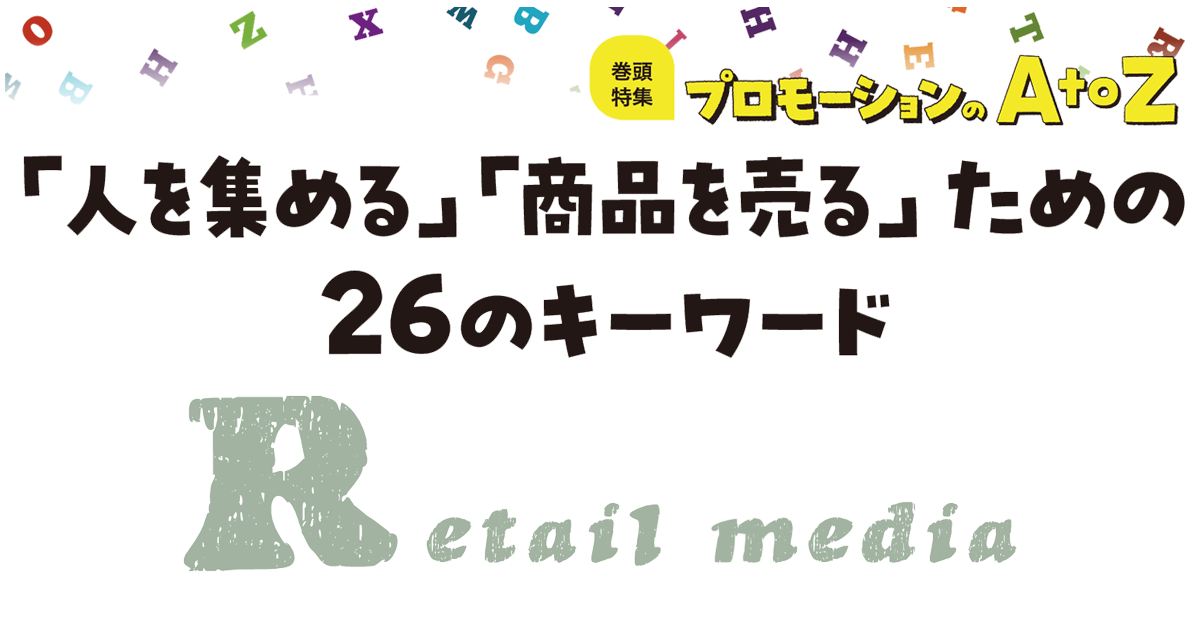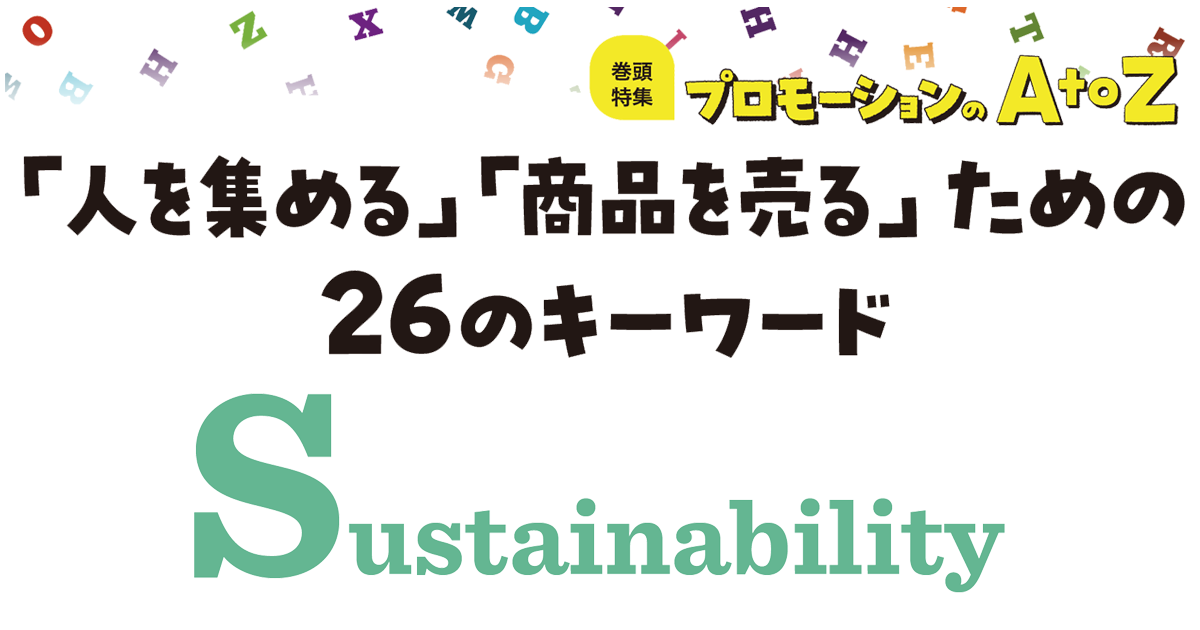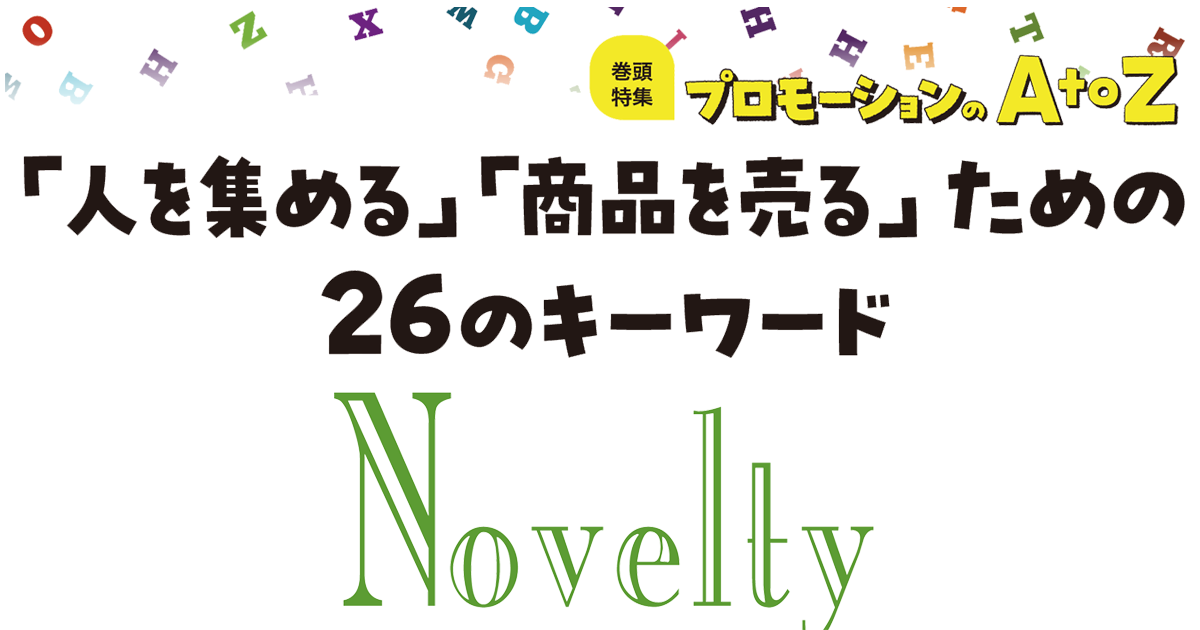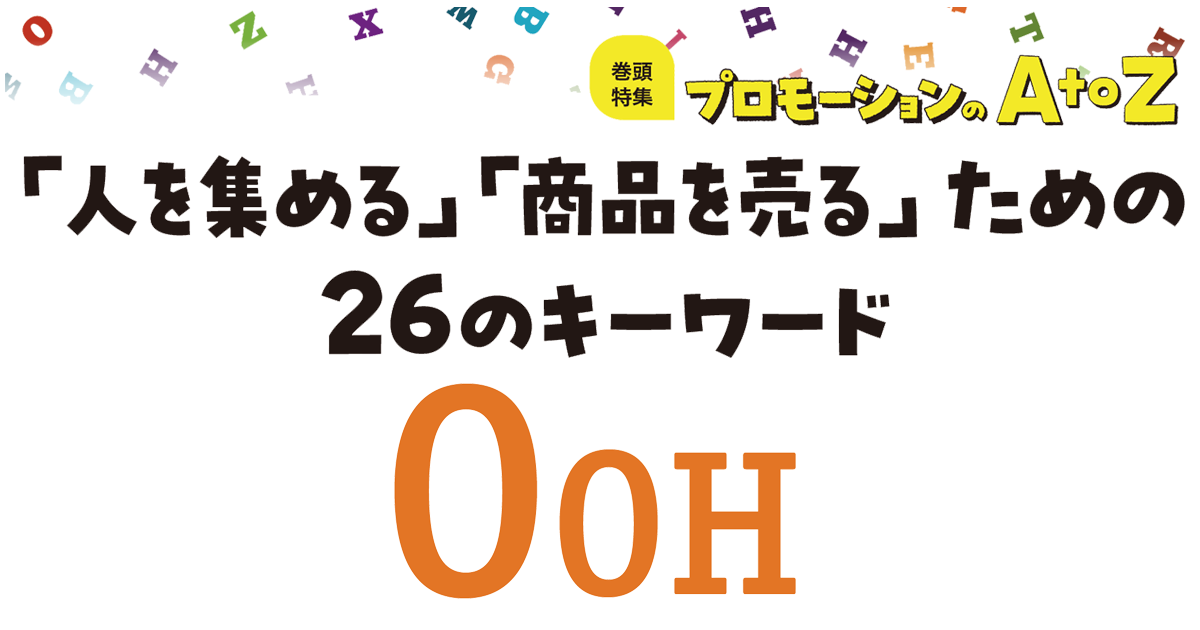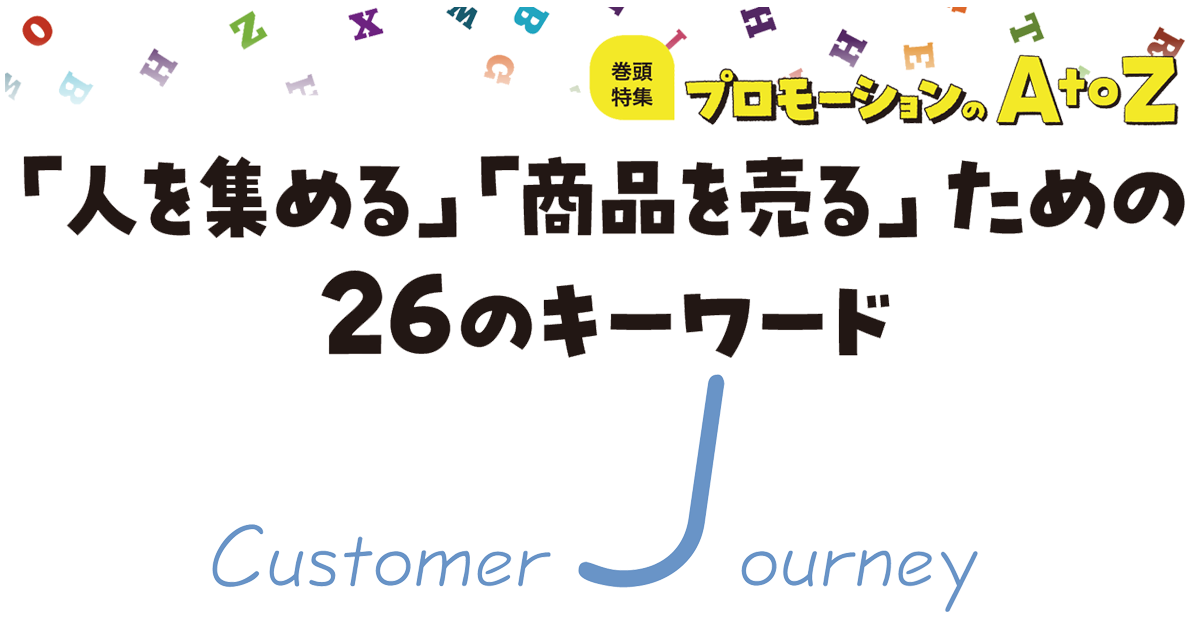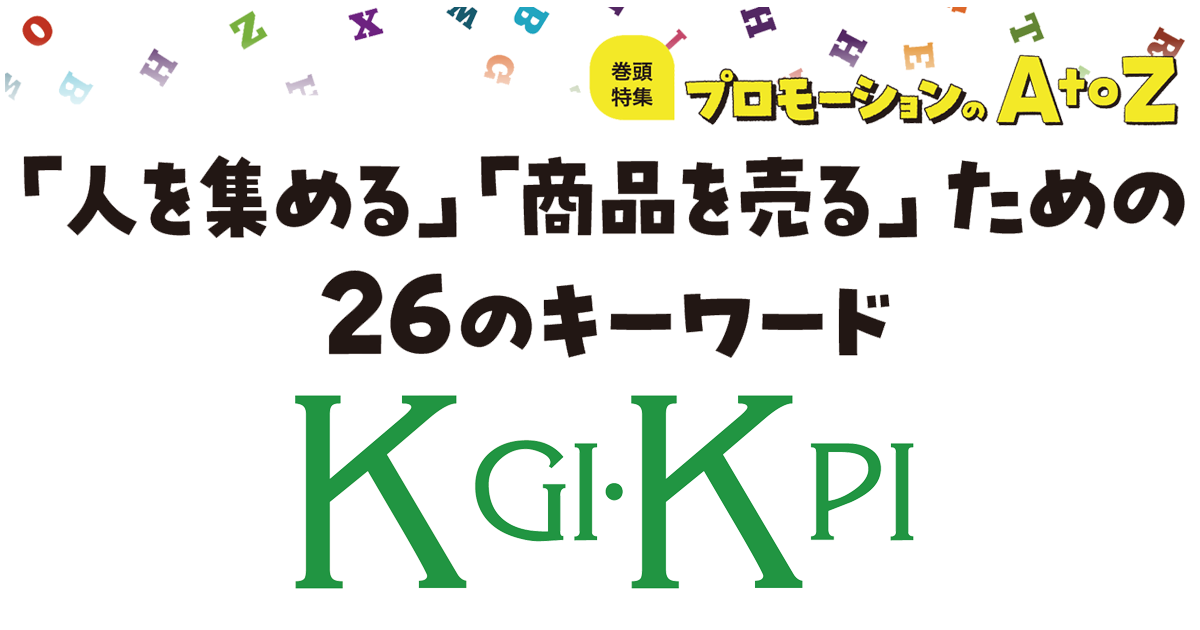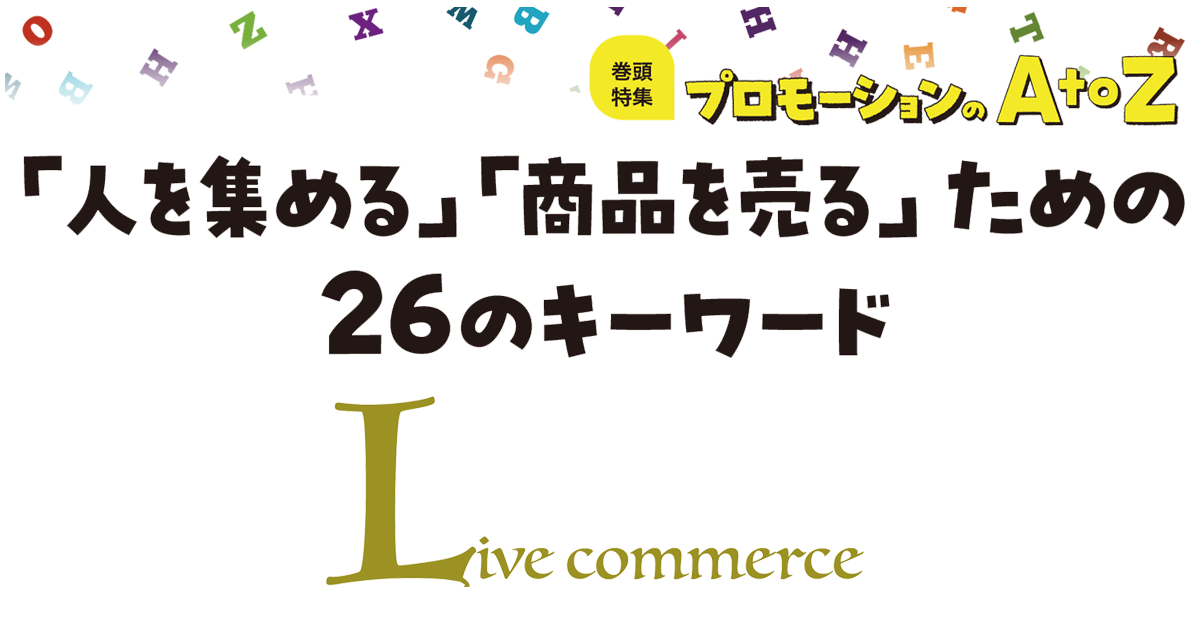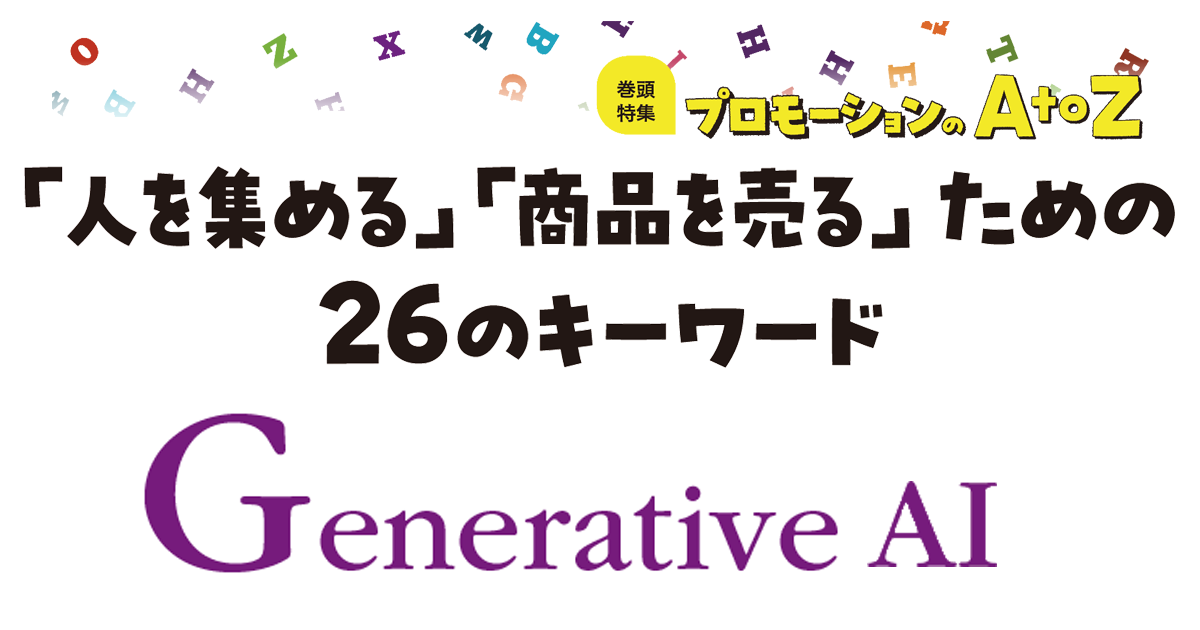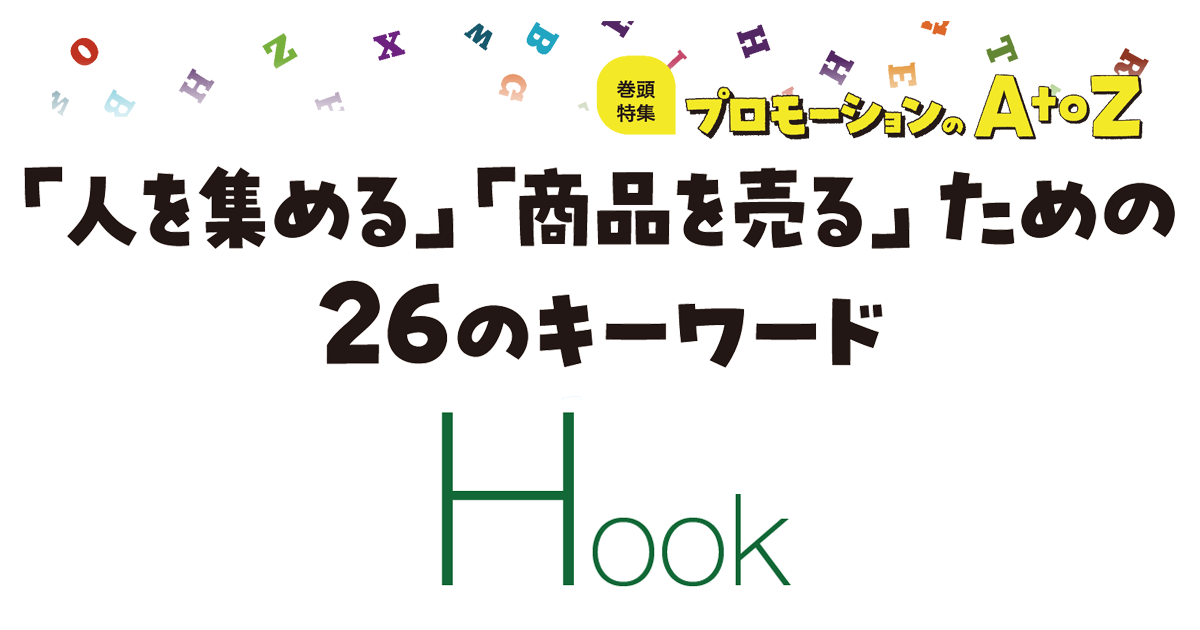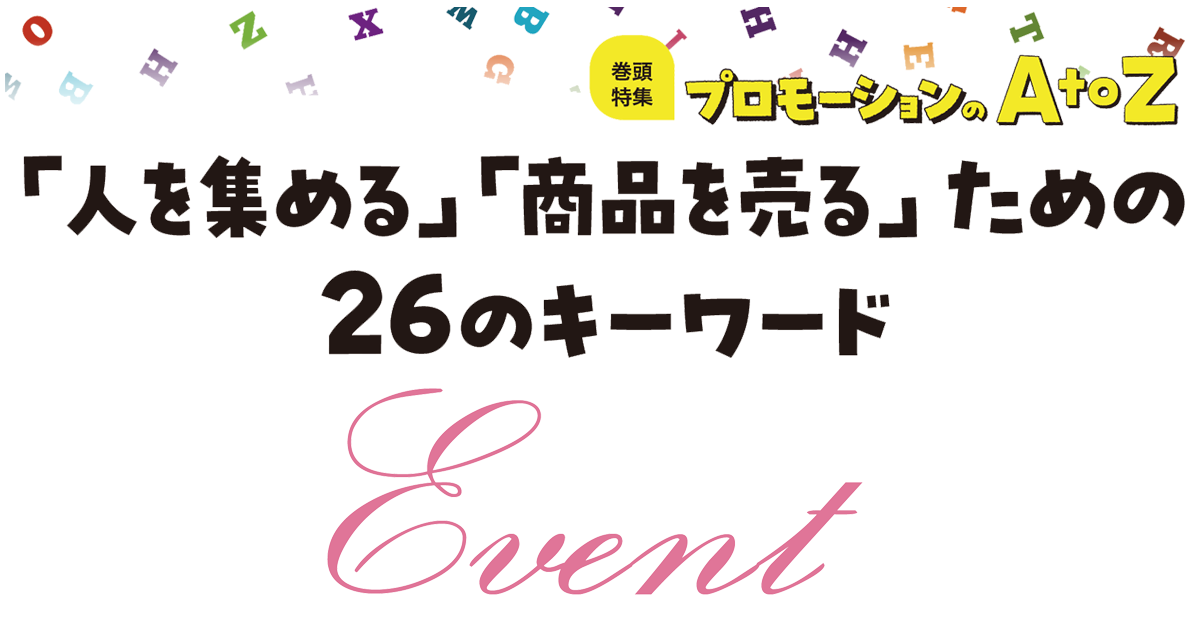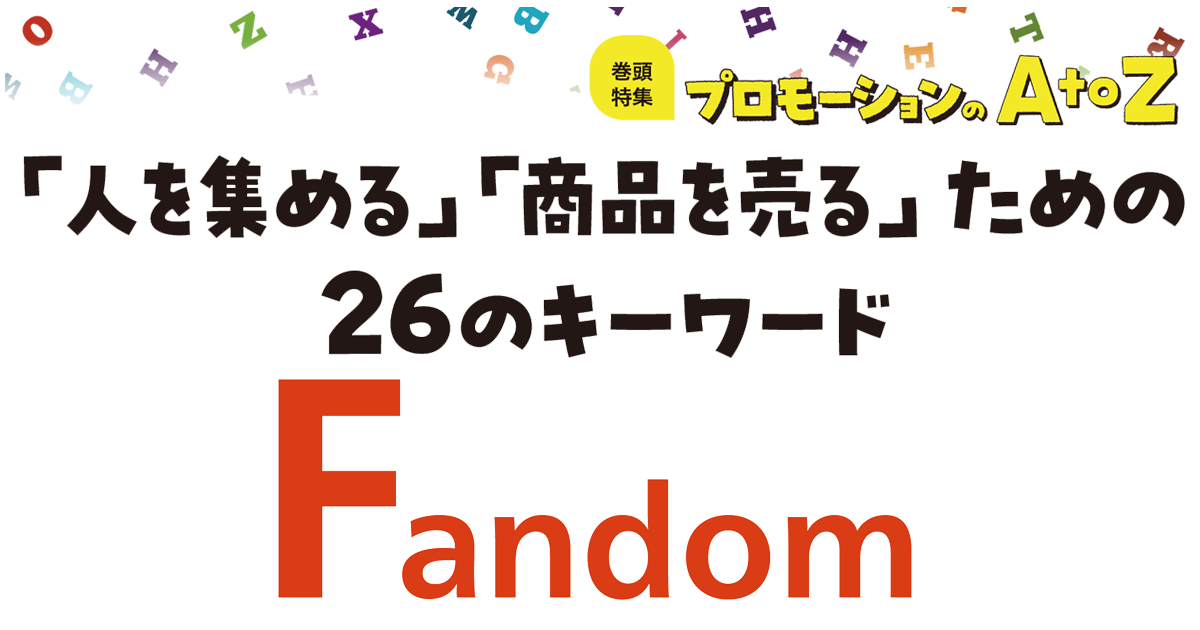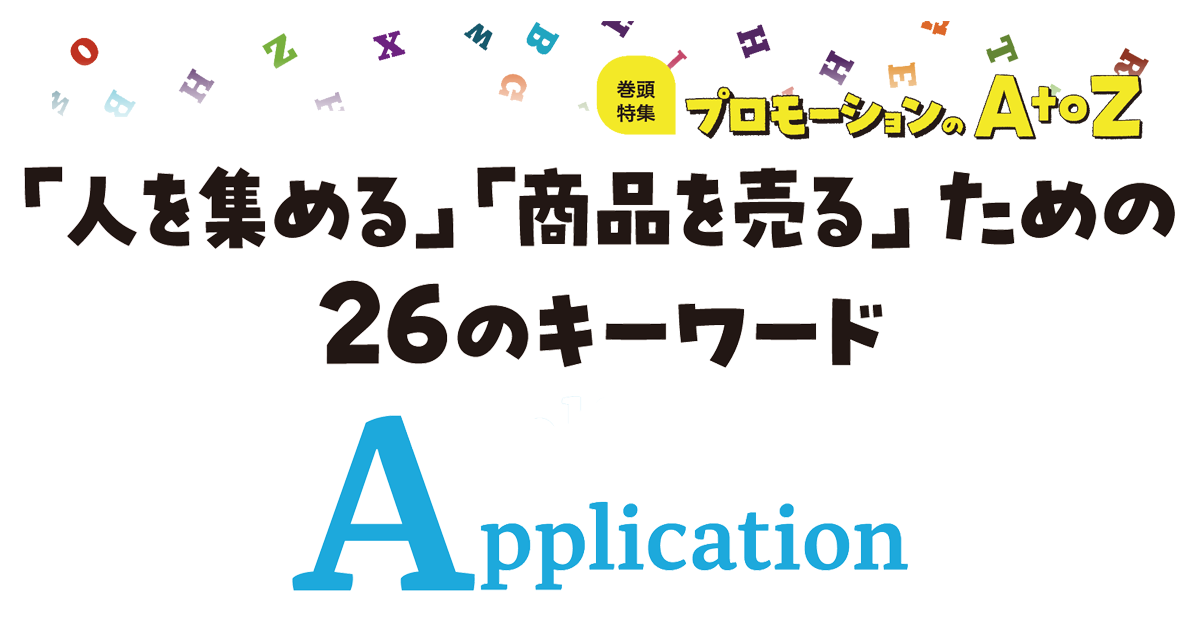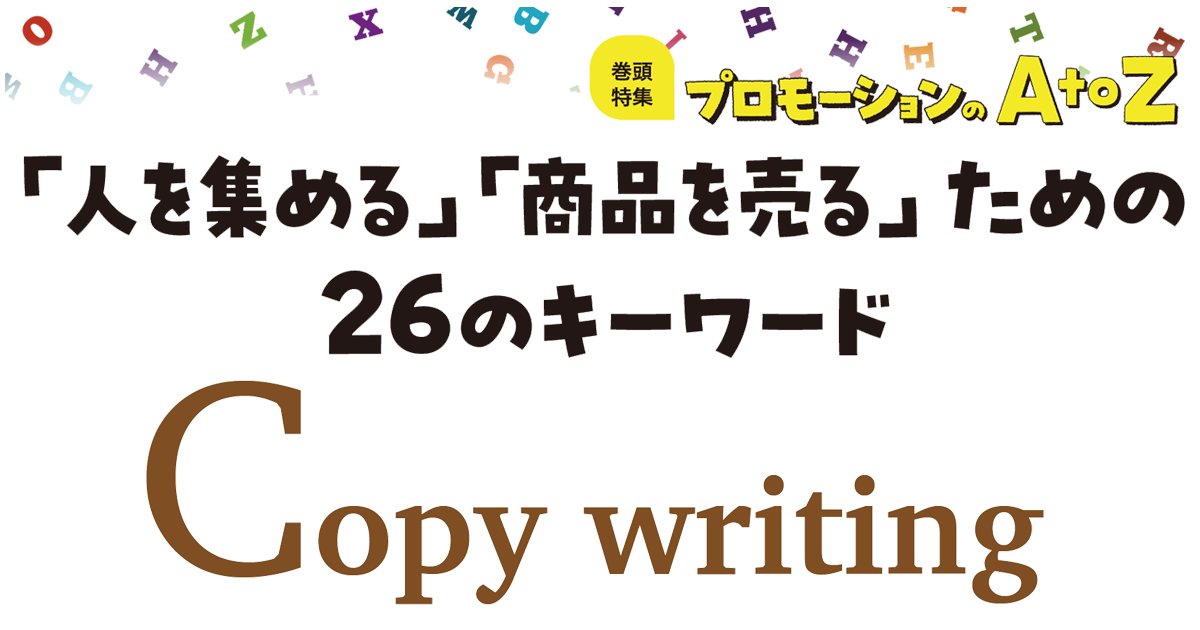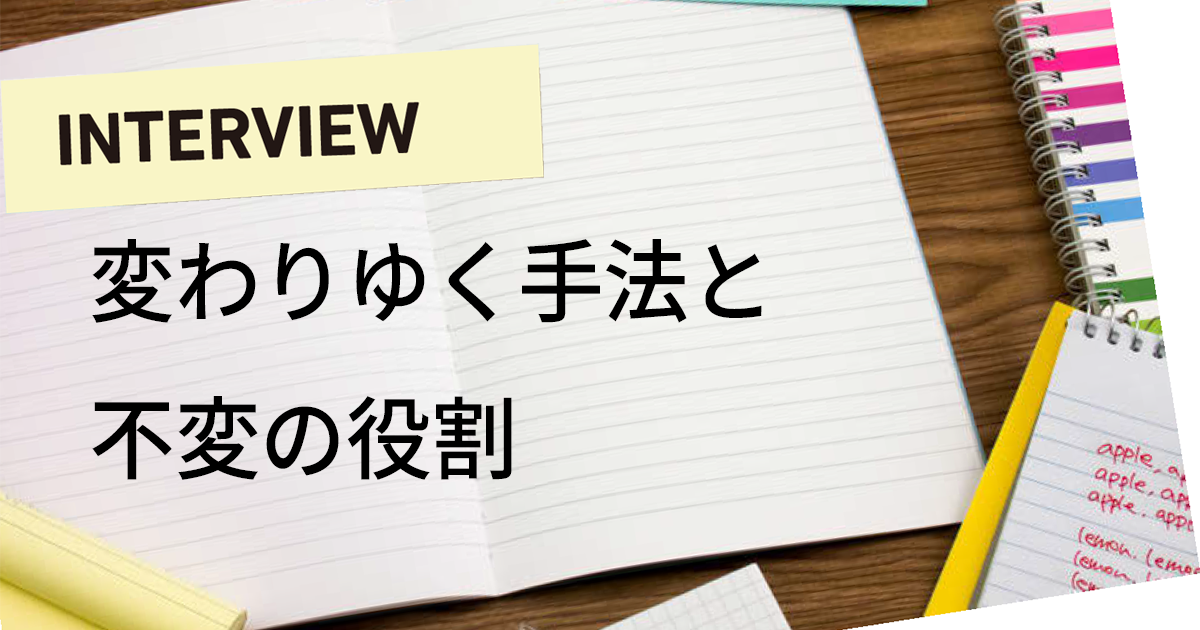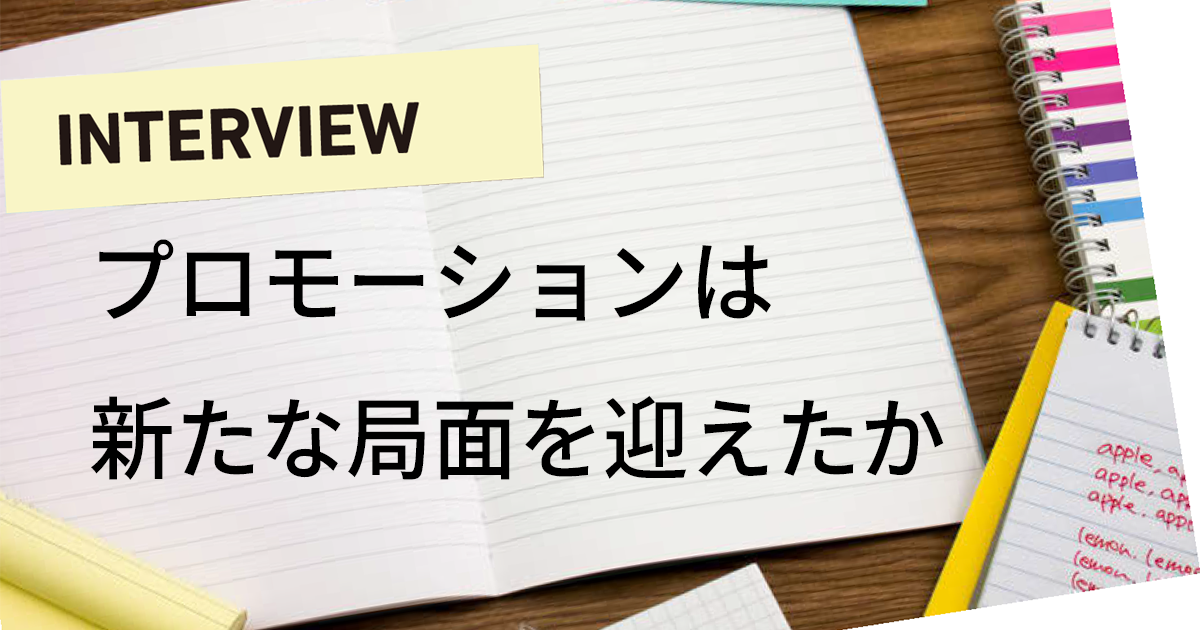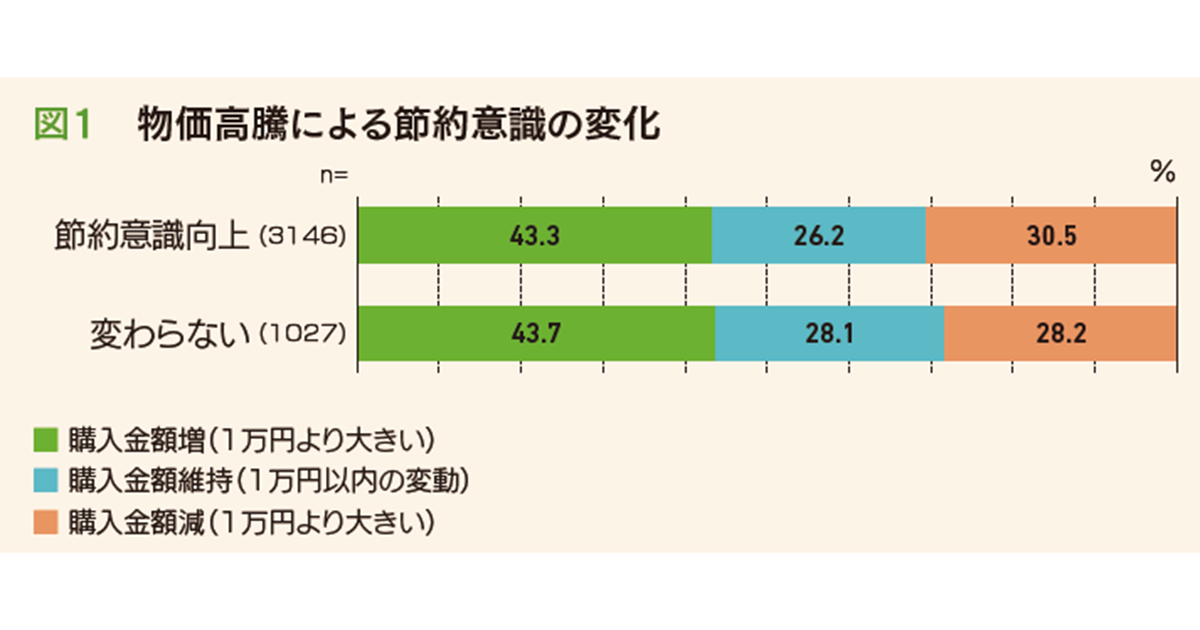昨今の広告とプロモーションの世界は、急速な「変化」と「進化」を遂げている。マーケティングコミュケーション手法は、テレビCMからWeb上の多様なプラットフォームへシフト。デジタルやSNS戦略、データ分析などの知識も不可欠になった。プランナーにも、時代や消費者の変化に合わせた戦略立案が求められている。本記事では、今後のプランナーに求められる役割について、これまで数多くのキャンペーンを手がけてきた藤井一成氏(ハッピーアワーズ博報堂 代表取締役)に取材。不変のスキルに焦点を当てると、ブランドの核を捉えた提案を生み出す姿勢が見えてきた。
「本当に人が動くか」ブランドの哲学を見つめること
──これまでのプロモーションの変遷を教えてください。
昔話にもなりますが、過去、マーケティング施策は主に「ATL(Above The Line)」と「BTL(Below TheLine)」という、2つに分類されていました。ATLは、大衆に向けた広告やテレビCMなどのマス広告を指し、BTLはキャンペーンや店舗内でのプロモーションなど、マス広告に比べ見えづらい活動とされていました。コミュニケーションは長い間、テレビCMやメディア広告が主役であり、ブランド戦略においても重要視され、プロモーションはマス広告の影に隠れた、マスマーケティングの一部として位置づけられていたのです。
しかし、2000年に入り、デジタル化が進むにつれて、徐々にマスマーケティングから、1to1マーケティングが増えてくるようになります。Webの可能性が広がり、あらゆるものがデジタルと接続をしたことでマス広告一強から、様々な進化が起こりはじめました。それにより、プロモーションの重要性が徐々に高まり、ポジションに変化が起きました。
──変遷の過程で変化した、プランナーに求められるスキルや資質は何でしょうか。
求められるスキルや資質は昔も今も変わっていないと思います。プロモーションは、生活者に近いタッチポイントで展開されるため、ブランドの思いが直接伝わってしまう領域です。「何が評価されて愛されているブランドなのか」といった、ブランドの普遍的なアイデンティティや人格、ビジネスモデルへの理解が絶対的に必要です。テレビCMの出稿と比べて安価に進行できるプロモーションだからといって、ブランドの理解が浅いまま、ただ来場者数などが獲得できればよいという考えでプロモーションを進めるのは危険です。その行動がブランド「らしい」ものなのか、生活者と間違った関係性を構築しないように、しっかりと精査することが必要です。
ブランドの「今この瞬間」 に携わるプロモーションでは、「らしさ」を築いてきたこれまでの価値づくりも掴みながら、「過去」と「現在」、そして「現在」と「未来」を結び、ブランドとして一貫性と納得性のある戦略に落とし込むことが大切だと思います。
ブランドに相応しい選択か 「個性に新しさを足す」役割
──以前と比べて、昨今のプランナーにはどのようなスキルや資質が求められているのでしょうか。
手法は増え続け、あらゆるトライができる豊かな環境なのが…