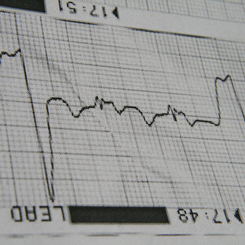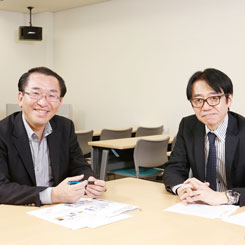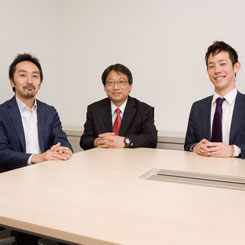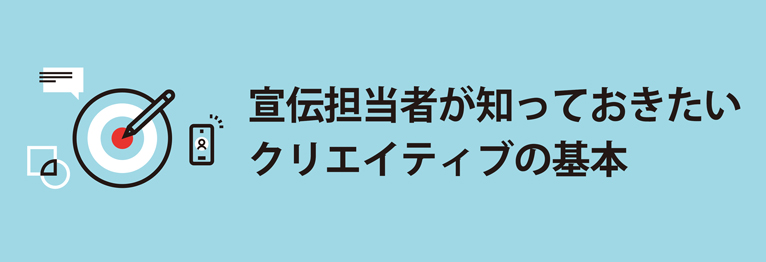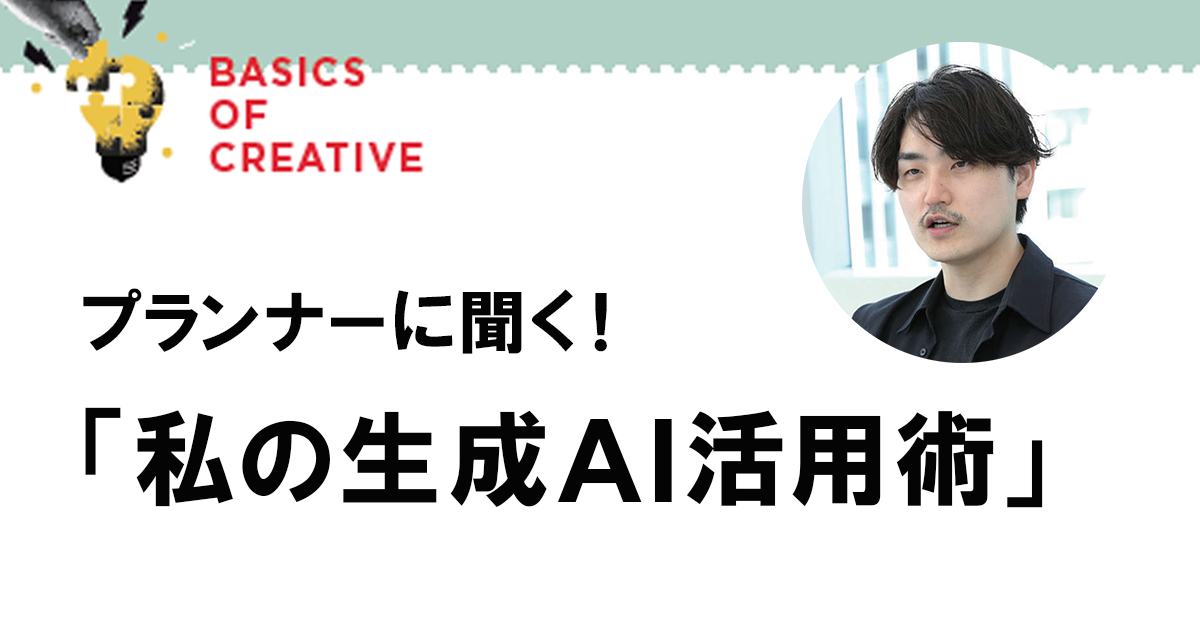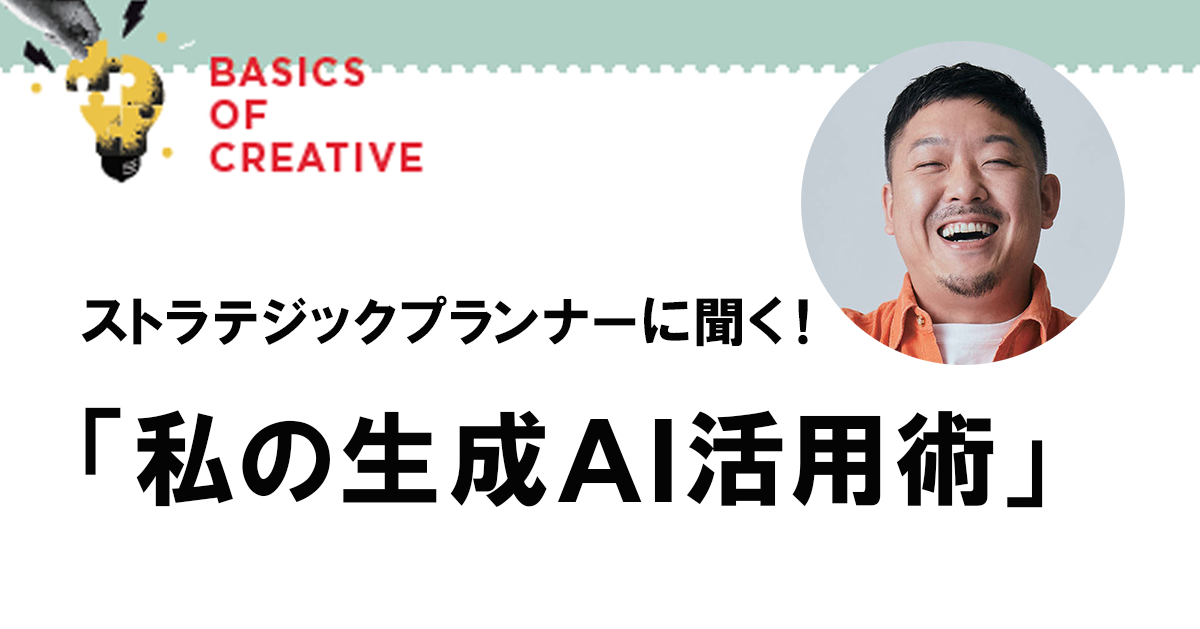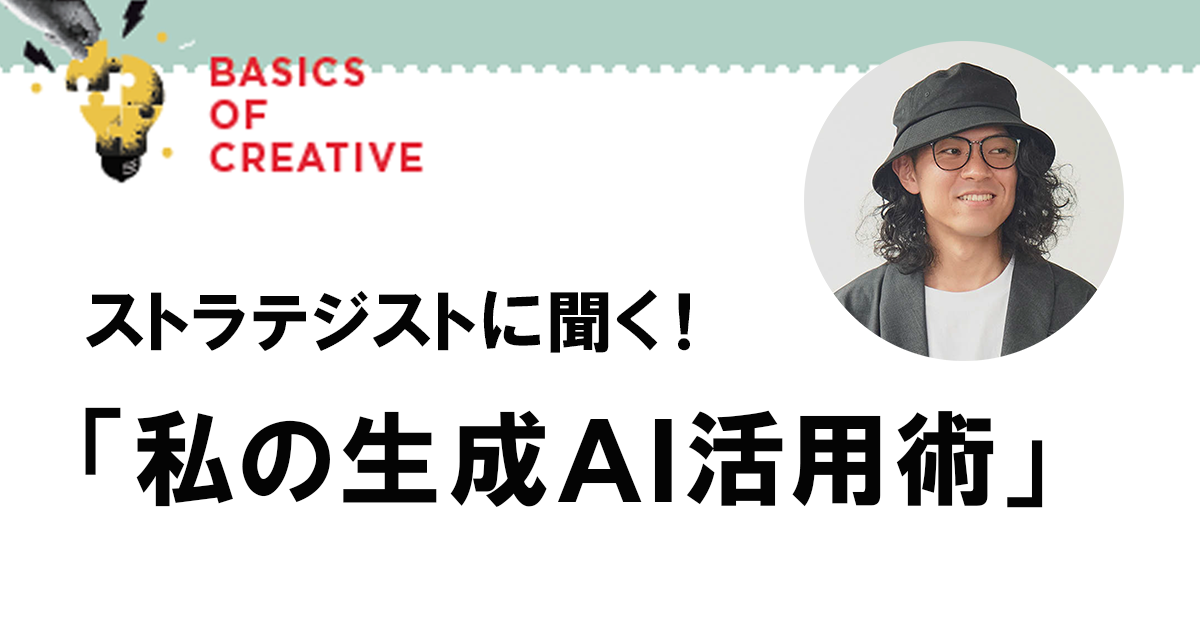スマートフォンの普及を背景に、人々の可処分時間の使い方は大きく変化しています。生活者のニーズを捉えにくくなった時代、マスメディアがとるべき対応とは? 各メディアで新たな取り組みを進めるキーマンと、メディア環境の変化を見つめる研究者が意見を交わしました。

(左から)日本テレビ放送網 編成局メディアデザインセンター 副部長、太田正仁、東海大学 文学部 広報メディア学科 水島久光教授、世界文化社『GOLD』 内山しのぶ編集長、朝日新聞社 メディアラボ プロデューサー、野澤 博
水島▶ 新聞、テレビ、雑誌と、皆さん異なるメディアに携わっていらっしゃいますが、今、共通して重要なのは「接点を開発すること」ですよね。
内山▶ そうですね。たとえば『GOLD』では会員組織を立ち上げる準備を進めています。イベントなどのリアルな場に読者を集め、そこに広告主企業も招いて、両者をつなぎ、新しいビジネスの可能性を広げていくことが必要だと思っています。雑誌をきっかけとして、リアルに集まる場――雑誌誌面だけでなく、こうしたライブ感(注1)のある接点もつくっていかないと、雑誌ビジネスの成長が難しくなってきています。
太田▶ ライブ感について言うと、特に報道番組にとっては辛い時代だなと感じています。最近は、事件や災害が起きた時、そこにいるのが記者ではなくユーザーになっている。番組内で使われる映像も「視聴者の映像」が増えている。一次情報の発信が、視聴者側に委ねられる状況になっています。
野澤 ▶ そうですね。「速報」「ライブ」という点では、もうユーザーに勝つのが難しくなっていると感じています。「このメディアが発信する情報こそが真実」と言えるようなクレディビリティを持たせる要素を加えるとか、読者・ユーザーからの疑問に答えるとか、提供する情報に深みを与える方向に舵を切っていかないと、マスメディアとしては生き残れないのではないかと危機感を持っています。ライブ感を意識した取り組みとしては、WEBによる速報ニュース配信はもちろん、ツイッターやフェイスブックを使った情報配信も行っています。でも、それって完全にメディア側の視点ですよね。自分たちの手札である「情報」と「メディア」を使って、できることをやっている、という状況に変わりはなくて、ユーザーにしてみればあまり興味が湧かない。これほどまでに多様なサービスやテクノロジーが存在する今の時代、その取捨選択はユーザーに委ねられます。ツイッター、フェイスブック、NAVERまとめも、読者からすると、新聞と並列の存在。何が一番自分にフィットするのかという観点で、どれを利用するかを無意識に判断していると思います。ライブ感だけではダメで、もっとユーザー目線で考えなければと、いろいろ模索しているところです。
太田▶ 我々はここ2年ほど、いわゆるソーシャルテレビの実現に向けたさまざまなトライアルを行ってきたのですが、デジタルを活用してライブ感・参加感をつくっていくという取り組みとしては、たとえば「JoinTV(注2)」があります。スマートフォンを媒介としてテレビとソーシャルと連携し、"バーチャルお茶の間"をつくって、空間を超えて視聴者同士でわいわい交流してもらおうという仕掛けです。特にバラエティや情報番組は、画面の前で釘づけになって見るというよりは、点けたままにしている人が多い。そういう視聴スタイルをヒントに、ソーシャル上で友人と交流しながら見るという新しい「視聴の仕方」を提案したのです。開始当初は注目を浴びましたが、一年半経って気づいたのは、重要なのは「友人とつながれる」というような仕掛け・機能そのものではなくて、「それをやることで、どんなふうに楽しいのか」だということ。視聴者を動かすのは、結局はクリエイティビティのみが為せる業なんだなと。コンテンツ制作はテレビ局の得意分野ではあるのですが、僕らにはデジタル系のクリエイティブのノウハウはない。今はそういう領域に強みを持つ企業と組みながら、勉強している段階です。