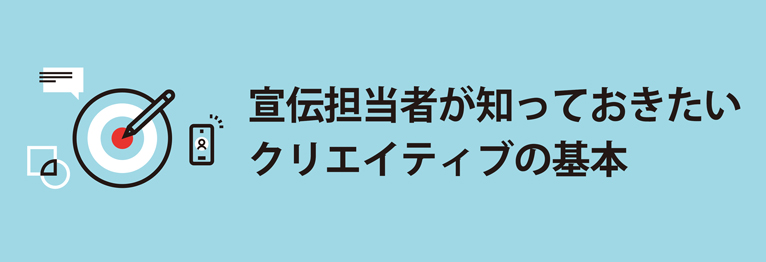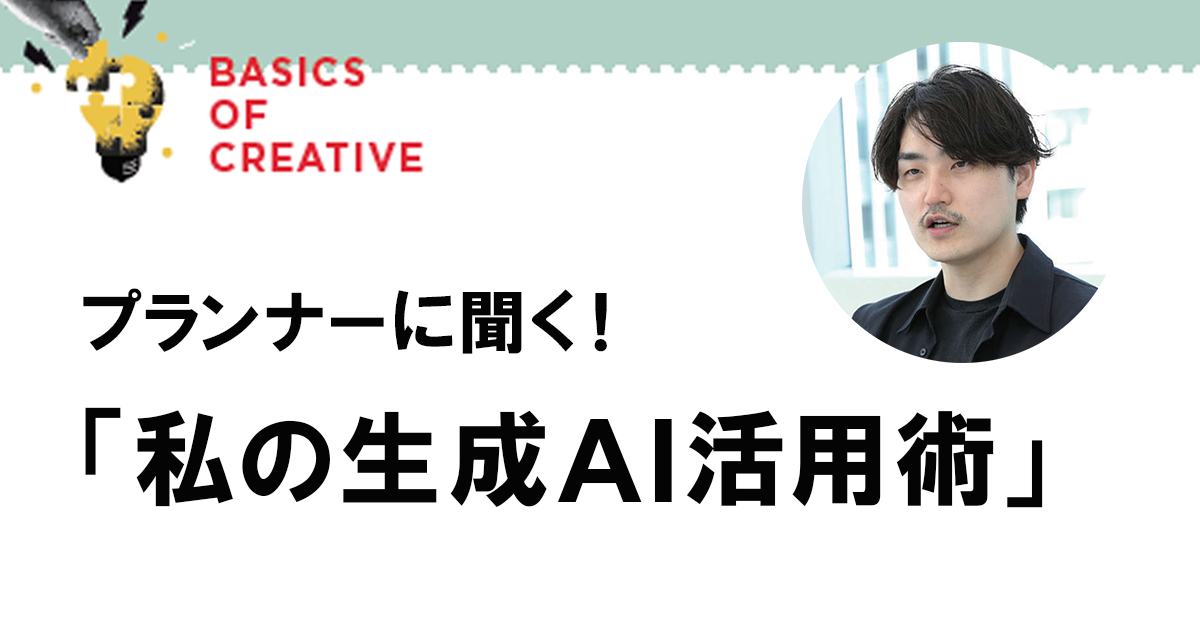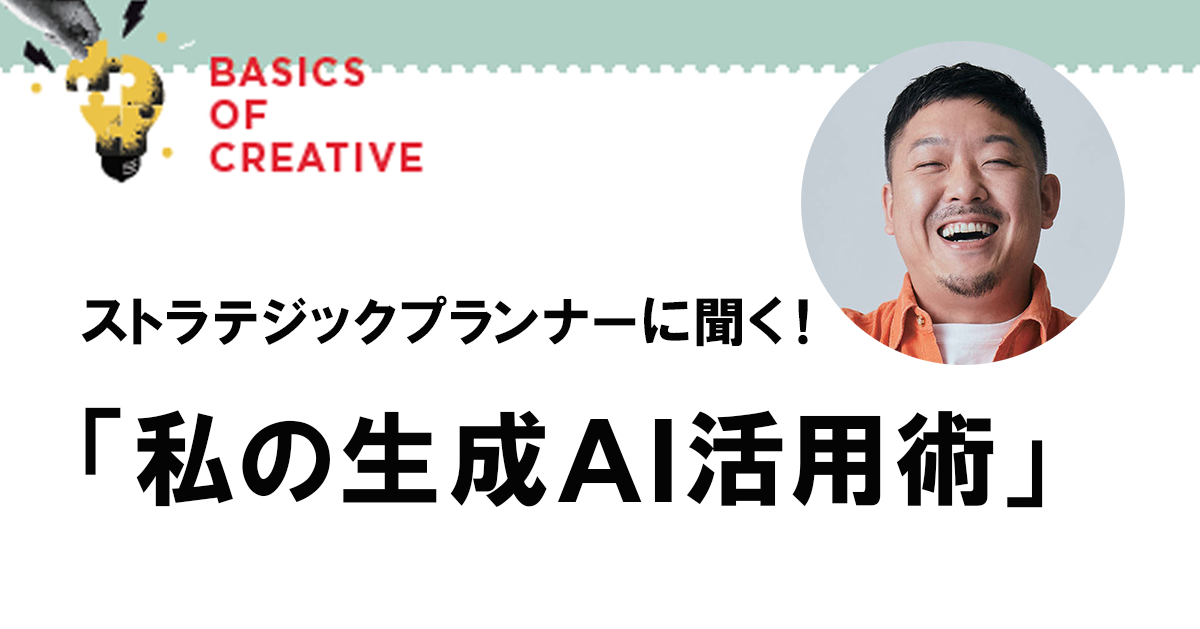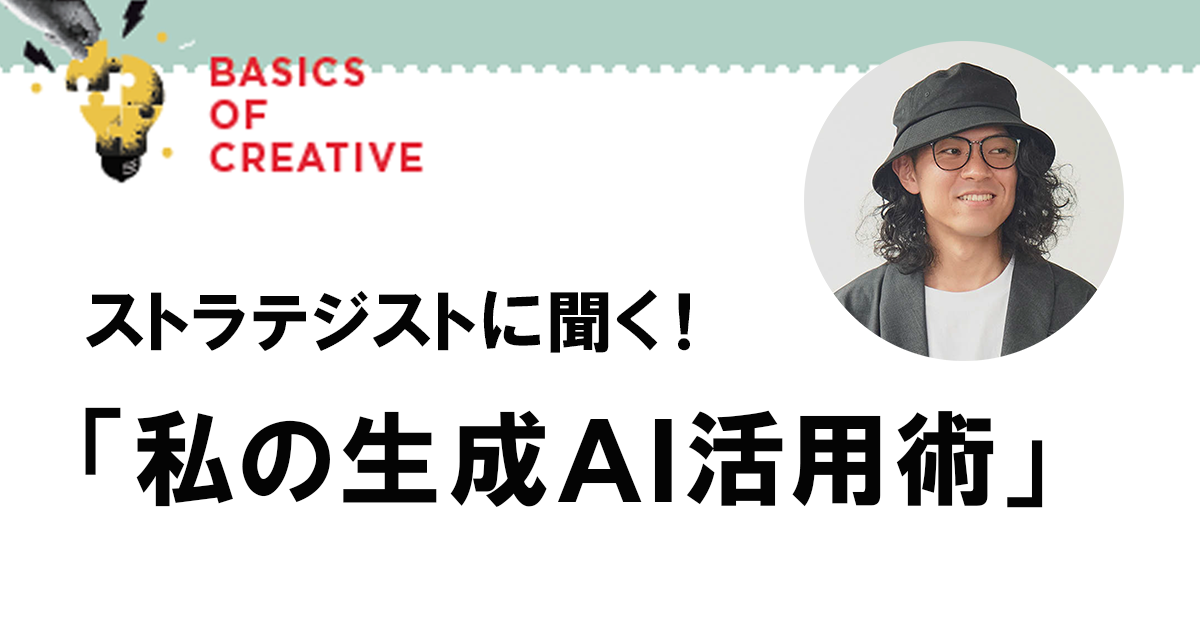スマホの浸透で視聴シーンが広がるオンライン動画。しかし新しい手法だけに方法論が確立されていない部分も多く、課題も多い。宣伝会議はオンラインならではの動画アプローチの開発に取り組んでいるオプトと共同で「オンライン動画活用を考える」企業研究会を設立。2回に渡る研究会を実施した。そのサマリーをレポートする。

企業のマーケティング担当者が集まった研究会の様子。
どんな目的で使う?方法論が確立されない課題
生活者のデジタルシフトが進む中、企業のコミュニケーション設計はますます複雑化している。その多様な接点の中でも近年、特に期待を寄せられているのが、スマホの浸透で視聴シーンが広がるオンライン動画だ。しかし新しい手法だけに、オンライン動画のクリエイティブ、効果測定、効果の予測に基づく適切な制作体制・コストの設定、さらにマス広告とオンライン動画の予算配分の最適化など、方法論が確立されていない部分も多く、課題が多いという声も聞こえてくる。そこでオプトと宣伝会議は共同で「オンライン動画活用を考える」企業研究会を設立。2回に渡り、企業でオンライン動画に携わるマーケティング担当者に集まってもらい、各社の事例や課題をディスカッションしてもらった。第1回研究会には大塚食品、カルビー、モスフードサービス、ローソンの4社が、第2回研究会には大塚家具、武田薬品工業、日本コカ・コーラ、富士フイルムの4社の参加があった。
2回の研究会で出てきたマーケティング担当者の課題は「オンライン動画を活用できるシーンは多岐に渡るだけに、どの場で活用したらいいのか模索している」「どうしたらコアファン、ユーザー以外にも動画が広がるのか?拡散させるための方法を知りたい」「テレビをはじめとしたマス広告とオンライン動画の適切な投資配分をいかにして実現したらいいのか?」「テレビCMを制作する場合と違い、低コストで多く制作したい。どんなパートナーと組めばいいのか?」「どう効果を測定すればいいのか?」など。参加者同士が互いに質問する場面も多く見られた。


写真上から1回目の研究会、2回目の研究会の参加者。
態度変容のプロセスと効果的なコンテンツ
研究会に参加をしたオプト・オンラインビデオアドソリューション部の松田清部長は効果測定に関する課題など、最近マーケティング担当者が悩むテーマについて知見を発表。「動画は認知から購買に至るまでの消費者の態度変容のあらゆるフェーズで活用可能なもの。だからこそ目的に合わせたコンテンツのバランスとメディアの組み合せをコントロールする視点が必要」と話した。
具体的には
「(1)リーチ・認知」→「(2)イメージ」→「(3)好意」→「(4)購入意向」→「(5)購買」
の5つのフェーズの中でも、
「(1)リーチ・認知」→「(2)イメージ」
の段階では、コンテンツは企業が伝えたいことを主軸にアテンションを獲得することを目的にしたものが適しており、オンライン動画でもペイドメディア中心の配信が効果的。
続く
「(2)イメージ」→「(3)好意」
の段階では、コンテンツはターゲットの興味があることを主軸にエンゲージメントを深めることを目的にしたものが適しており、ソーシャルやキュレーションメディアなどのアーンドメディアでの拡散が向いている。最後の
「(4)購入意向」→「(5)購買」
の段階では、コンテンツはHow to動画など購買の後押しになるような、商品・サービスを詳細に紹介する内容が適しており、自社サイトなどオウンドメディアでの展開が効果的という。
また2回の研究会には企業のマーケティング担当者だけでなく、1回目には佐藤達郎氏が、2回目にはグーグルの中村全信氏がゲストとして参加。国内外で最近、話題になった動画の事例を基に30分ほどのレクチャーを行った。中村氏は「グーグルでは動画コンテンツ戦略は、
(1)インサイトの掌握、
(2)戦略的なコンテンツの仕分け、
(3)コンテンツの活用法
の3点がカギになると考えている」と説明。加えてYouTubeで公開された世界の動画事例をもとに、生活者のインサイトに合わせたクリエイティブのタイプとしてグーグルが提示する「3H」の考え方についても言及した。
「3H」とは「Hero」(多くの人の心を揺さぶるメッセージ)、「Hub」(ブランドと消費者をつなぎ続ける、生活者の興味関心に沿ったカテゴリーコンテンツ)、「Help」(具体的ニーズへの説得力のある答えや提案)で、これらの3つのタイプの動画を組み合わせながらキャンペーンを企画していくことが成功のカギになると話した。
横のつながりで新たなヒントを得る
研究会に参加をしたマーケティング担当者らは「テレビCMとWebの関連付けに悩んでいたので、その点が整理できて良かった」(ローソン・鈴木啓子氏)、「動画制作を発注する立場以外に、発注される側の話も聞け、参考になった。マーケティングの手段が多様化する中で悩むことも多いが、こうした情報交換の場があると仕事のヒントが得られる」(大塚食品・垣内壮平氏)といった声が上がっていた。
研究会の最後にオプトの中野宜幸氏は「そのブランドが置かれているステージ、あるいは消費者の態度変容プロセスのどの部分で活用するものなのかなど、各ケースに合わせた活用目的の明確化が必要。そこを整理できると正しいKPIの設定につながり、ビジネスにインパクトを与える動画活用の方向性が見えてくるはず」と総括した。

写真左からオプト・執行役員 オンラインビデオ/ソーシャルメディア/コンテンツマーケティング管掌の中野宜幸氏、オプト・オンラインビデオアドソリューション部の松田清部長、コミュニケーション・ラボ代表の佐藤達郎氏、グーグル ブランドソリューションエキスパートの中村全信氏。
お問い合わせ
株式会社オプト
〒102-0081 東京都千代田区四番町6 東急番町ビル
http://www.opt.ne.jp/