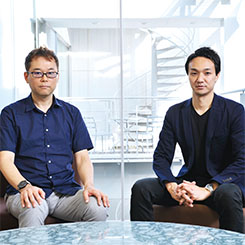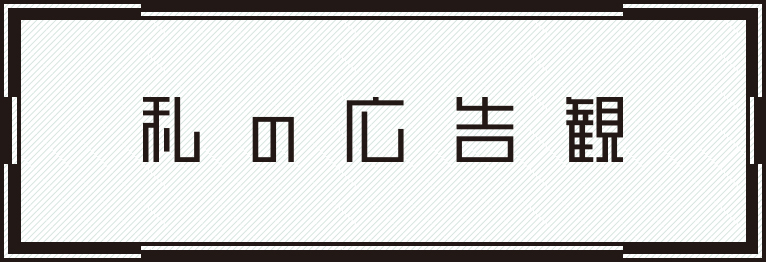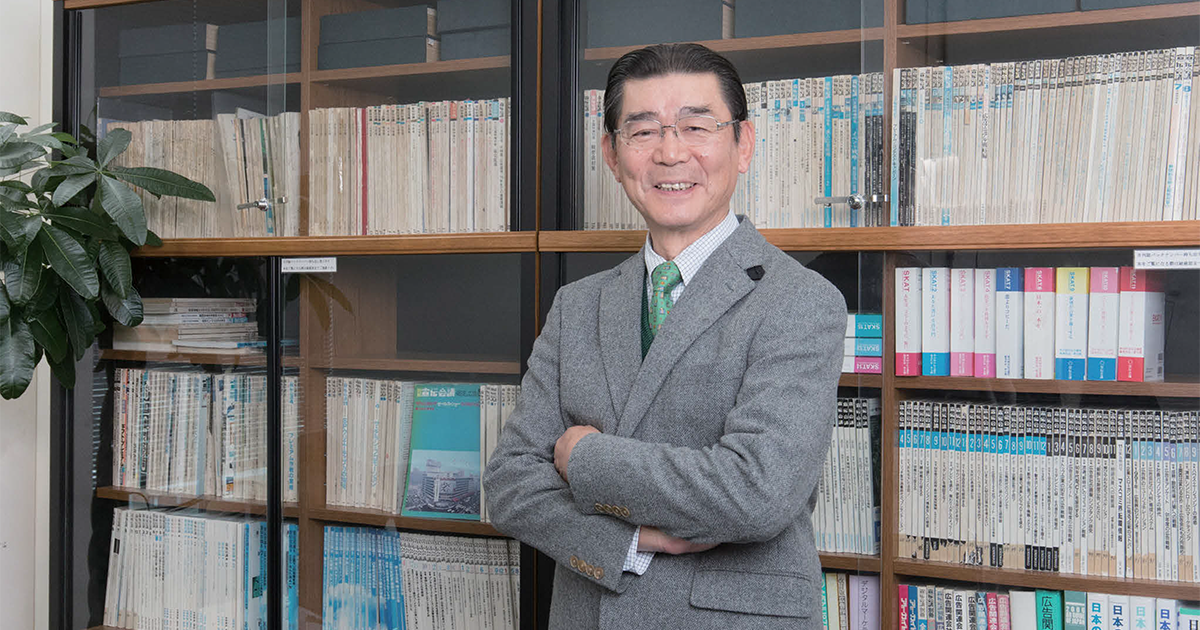東京・青山にある、宣伝会議にて8月7日「青山マーケティング朝大学“テクノロジーが変えるマーケティング”」が開催された。ビジネスパーソンにとって貴重な時間である朝こそ、有意義に活用してほしいという考えから、日本アイ・ビー・エムの協力のもと、今夏よりスタートしたプログラムだ。

日本アイ・ビー・エムの伊東祐治氏。
“個客”マーケティングが必要とされる理由
今回の朝大学の講師は、日本アイ・ビー・エム コマース事業部 プロダクト・マーケティング&セールス・リーダーの伊東祐治氏。「マーケティング・オートメーションは何を自動化してくれるのか?」をテーマに国内外の事例を中心に伊東氏が講義を行った。
オムニチャネル、ビッグデータというキーワードとほぼ同時に広まって来た「マーケティング・オートメーション」。国内では2005年からマーケティング先進企業によって活用されてきた。徐々に認知が広がり、2015年マーケティングトレンドランキングの調査結果によると、「マーケティング・オートメーション」が3位に浮上。近年、特に注目が集まっている。
そもそも、マーケティング・オートメーションとは、興味・関心、行動が異なる個客と最適なコミュニケーションをする時に、オンライン・オフラインチャネルを組み合わせた煩雑な業務を自動化するツールだ。
「キャンペーンとは、『顧客の獲得』『アクティベーション』『購買促進』『ロイヤルティの向上』『離反防止』などのあらゆるフェーズにおける顧客とのコミュニケーション活動全般を指します。マーケティング・オートメーションは、これら“キャンペーン”という顧客との対話を自動化するものです。それぞれの顧客に、“適切なコンテンツ(オファー)”を“適切なタイミング”で、“適切なチャネル”を使ってコミュニケーションを行うのです」と伊東氏は話した。
また、その実行に際してはWebログだけでなく、コールセンターでの対応や、店舗への来店履歴などあらゆるデータを活用し、最適なアプローチをしなければならない。だからこそ、クロスチャネルが重要と訴えた。「例えば、メールが開封されなければ、コストは上がるがDMを郵送してみる。または、コンテンツを変更し、効果測定をしてみる。施策自体はマーケターが考え、しっかりと効果検証を行うのがマーケティング・オートメーション活用の基本」(伊東氏)。
顧客は、いろいろなタッチポイントから入ってくるので、クロスチャネルでの注意点は、一貫性のあるサービスを行うことだ。「よく起こりがちなミスとして、商品案内のDMが来たので、顧客はECで購入。すると、その数日後に店頭に行って、さらに値引きされて売られているのを発見してしまったり…。クロスチャネルになっても、サービスの一貫性を保つべき」と伊東氏は指摘した。
この他、マーケティング・オートメーションを使った事例がいくつも紹介された。最後に伊東氏は「戦略を考えることに時間を使えることが大事。マーケティング・オートメーションを導入すれば、効率が上がり、マーケターがやるべき仕事に集中できる環境がつくれるはず」と話した。

朝大学のスタートは8時半。参加者は朝食を食べながら、和やかな雰囲気で講義に聞き入った。
お問い合せ
日本アイ・ビー・エム株式会社
製品情報/Silverpop
URL. ibm.com/innovation/jp/smarterplanet/commerce/
TEL. 0120-550-210 E-mail. Commerce@jp.ibm.com