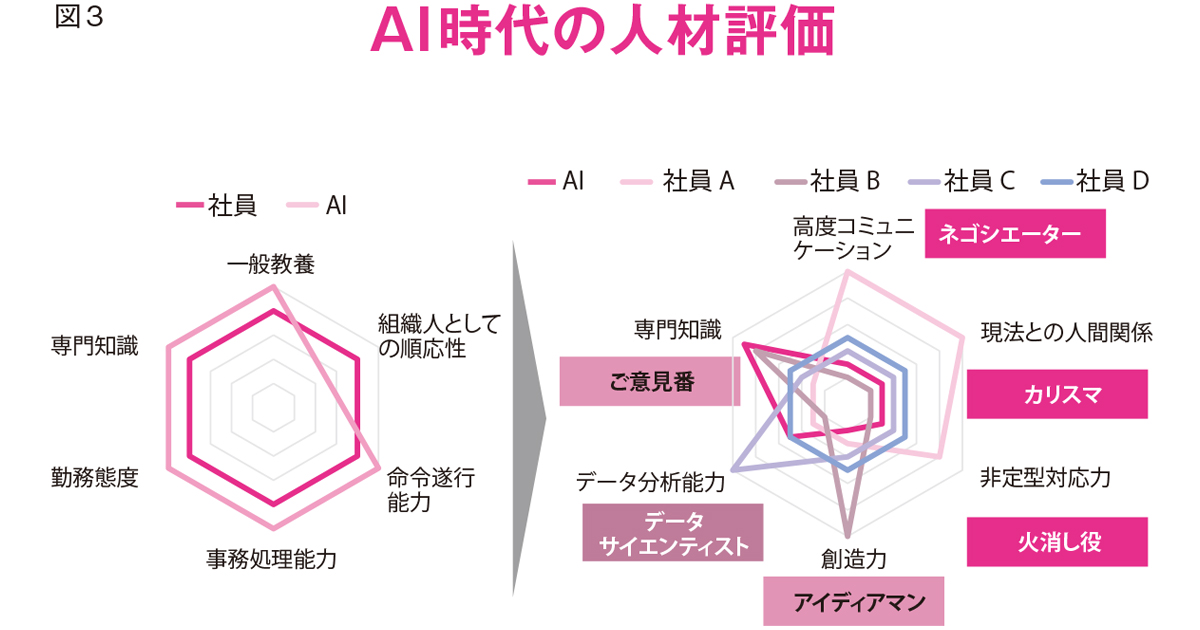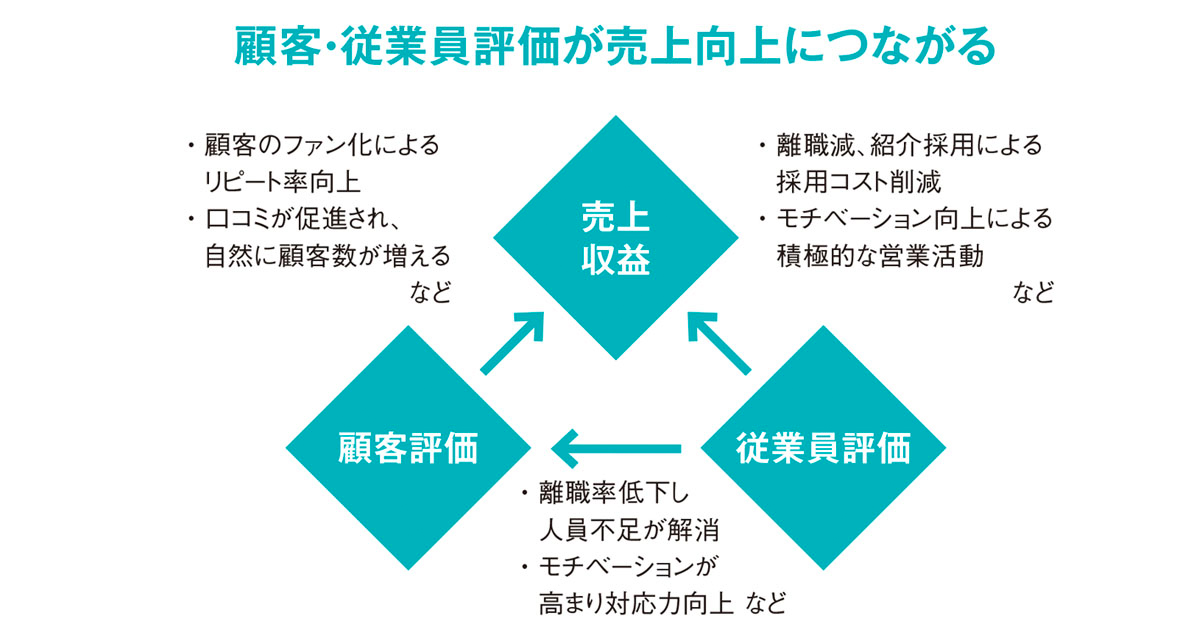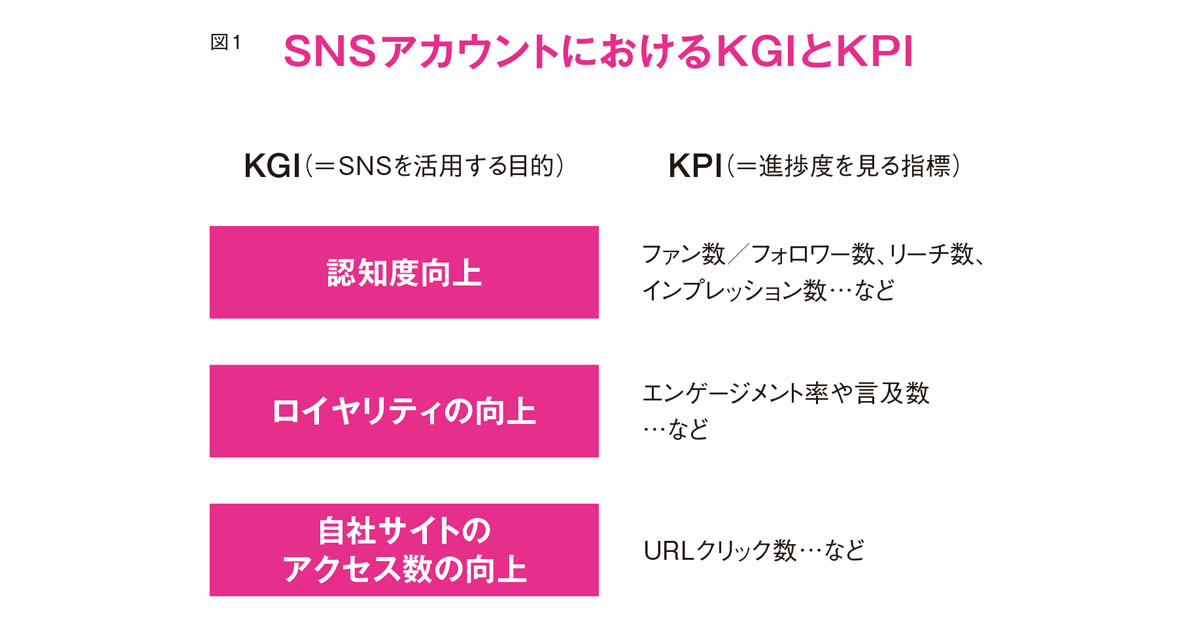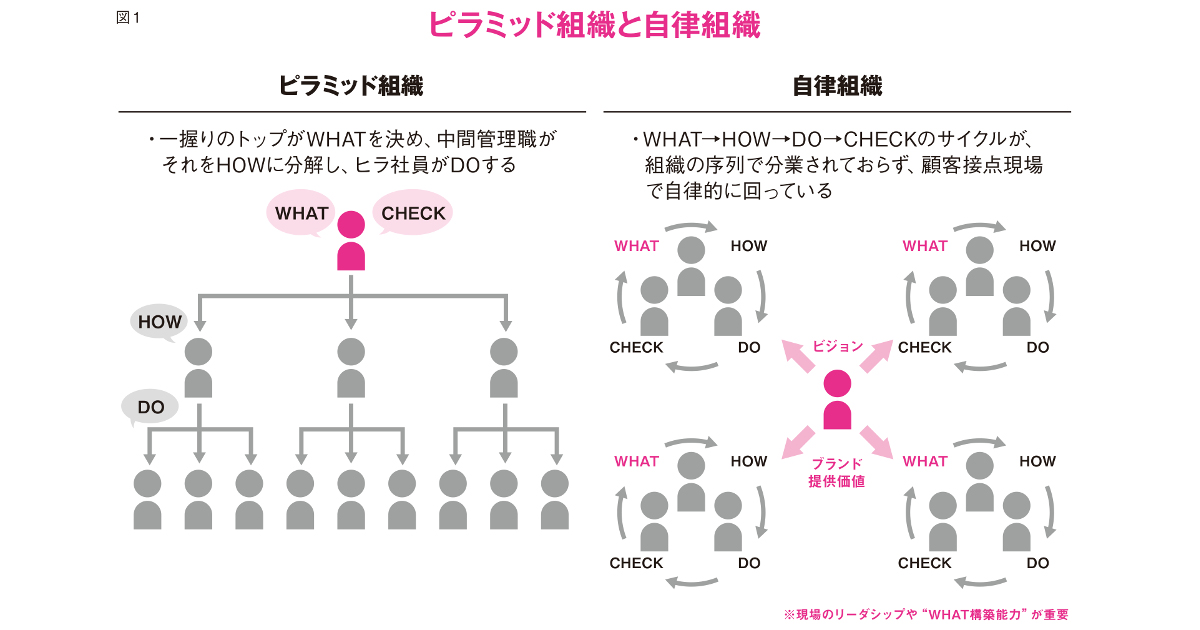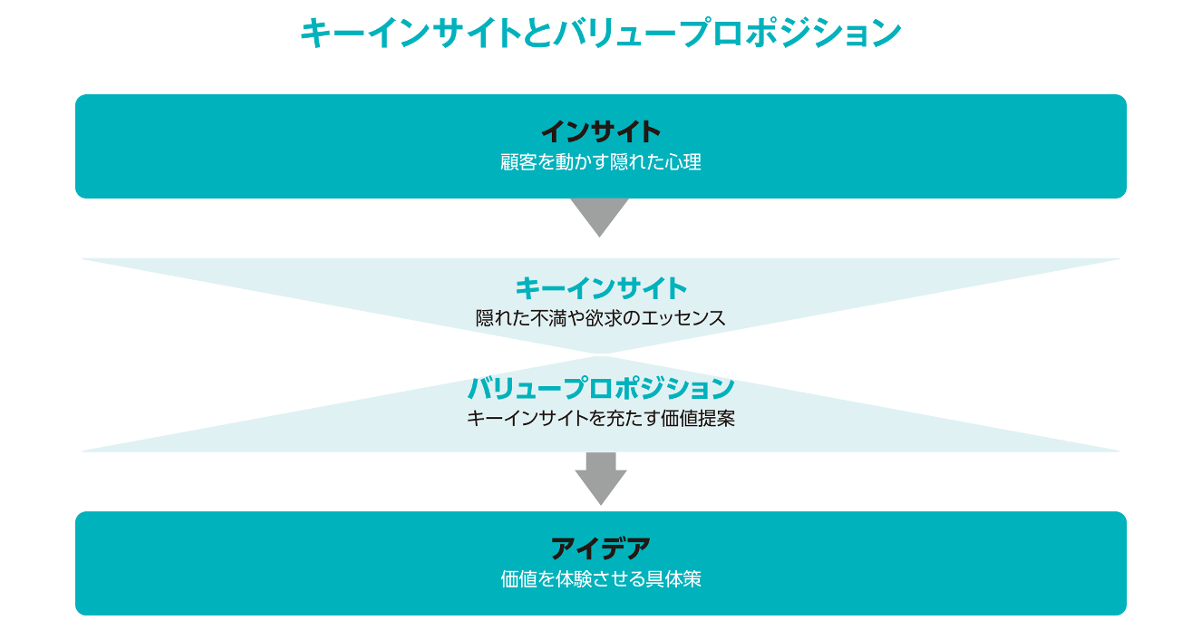「人通りが多くなければ繁盛しない」─バルニバービにとっては「幻想」だ。1995年に大阪・南難波にカフェ「アマーク・ド・パラディ」を開いて以降、現在は東阪に50ブランド80店舗(グループ全体では95店舗)を抱える。かつて人のまばらだった「アマーク」周辺はいまや賑わいにあふれている。同社の出店戦略について、バルニバービグループの安藤文豪・常務取締役COOに聞いた。

東京・小石川のガーデン・ピッツェリア「AOI NAPOLI(青いナポリ)」。もともと印刷工場だった施設を全面改装し、2008年11月にオープン。いまでは地域に溶け込んでいる。
──「人の多いところに店を出す」のではなく、「人は店を中心に集まる」という出店方針を掲げていますが、それは具体的にはどのような考え方なのでしょうか。
安藤文豪氏:当社では「バッド・ロケーション戦略」と呼んでいるのですが、戦略と言っても、形式張ったノウハウがあるわけではありません。ただ、いわゆる激戦区のようなところに出店するのは、一見、合理的だと思えても、実際はそうではないと考えています。
どういうことかと言うと、たとえば東京・銀座のような一等地は、多くの飲食業が店を持ちたいと考えるような場所です。そういうスペースは、賃料が1坪あたり5万円~7万円します。
そのような場所に出店した場合、事業を成立させるため、家賃に基づいた事業計画を立てます。どれくらいの回転率が理想か、全体のコストもふまえて収益率をどの程度に保つか、といった計算をします。すると、必ず犠牲になるものが出てきます。「坪当たりの売り上げを高めるために、席数をできるだけ増やす、結果、席幅が犠牲になり、窮屈になる」といったようなことです。
そうなれば一般的には、お客さまには狭苦しい印象を与えることになります。また、そうした店舗で働くスタッフも、通勤電車で揉まれて、店でも揉まれて、といった生活を送ることになります。しだいに日々の楽しみも失われてしまうかもしれません。
これは、席数に限らず、どのみち発生する歪みなんです。繁華街の、人通りの多いせわしない場所で、競合との価格競争に追われながら、満足度の高いサービスを提供することは、理論以上にむずかしいことです。
また、そうした場所は往々にして、賃貸契約に期限のある「定期借款(契約)」の場合が多い。高い家賃を払いながら、営業を続け、いずれは退店しないといけない。いい手だとは考えられませんよね。
私たちが出店しているのは駅から少し離れていて、人通りはまだ少なかったり、まだ商業が発達していなかったりする場所。そうしたエリアで、住民の息づかいを感じる場所です。さきほど「バッド・ロケーション戦略」と言いましたが、極端な話、人がいない山奥にお店を出すことではありません。探すのは、いまお話ししたような「レッドオーシャン」に残された「ブルーオーシャン」です。
そして、そういう場所は比較的、家賃が安かったり、店作りの自由度が高かったりする傾向にあります。期限なしの「普通借款(契約)」を結べることも多い。居抜きみたいなところに出すより、倉庫を改装して店をつくる、というケースもざらにあります。実際、いま取材を受けている、ここ(ルーフトップバー「Privado」、東京・台東)も、もともとは楽器メーカーの倉庫でした。
家賃が安いことで、店内空間も広くできます。子どもが動き回っても気になりませんし、隣のテーブルを気にすることはありません。スタッフたちも開放感のある場所で働けますから、同じ労働時間でも受けるストレスは少ないと思います。
──そういった場所は、どのように探すのですか。
安藤氏:決まった条件はありません。当社の代表の佐藤(裕久氏)の感覚が大きいですね。私も店を出すことを決めてから場所を探すのではなく、ふだんから、街を歩くときに意識しています。「ここに店があったら面白いかなあ」とか、「仲間が楽しく働ける場所かなあ」とか。
漠然とした感覚でやっているように思われるかもしれませんが、(代表の)佐藤が創業して26年、私も、自分で物販系の会社を立ち上げた後に加わって9年が経ちますが、それなりに試行錯誤を重ねてきました。
いま、バルニバービで運営するのは80店舗あって、5坪の店もあれば、300坪の店もあります。
複層階やら路面店やら、いろいろな場所に店舗を構えてきて、どんなメニューがあれば楽しんでもらえるのか、足しげく通ってもらえるのか、ここでご飯が食べられたら気持ちいいだろうか、といったことを考えて、日々街を歩いています。以前は3店舗オープンして1店舗閉めるような、さまざまな成功や失敗を繰り返し、いま赤字の店舗はほとんどなくなりました。そんな中で1号店、2号店がいまでも残っている、というのも業界では少ない例ではないでしょうか。
本来、飲食というのは本能で行うものだと思うんです。私も7年前に2人めの子どもができたのですが、赤ちゃんというのは、生まれて30分もすれば母乳を飲むんですね。その姿を見たとき、「ああ、この子は飲食している」と感じました。「人間はリクツで飲食しないんだ」という実感があったんです。
しかし、「業」がついて飲食業になると、一般的には理論に基づいて、数字で検証しようとする。最寄り駅の乗降人数だとか、店前通行人数だとか、客単価だとかを計算しはじめます。実感から離れて、ロジックにすがってしまう。だからこそ、みんなが同じところに向かう。繁華街にたくさんの店が集まっていく。結果、争いが激化する。
そうやって決まりきったプロセスを積み上げて、できたお店って、人が集まりたくなるものなんでしょうか。私たちはそうは思いません。「ここに、こんな店があったら、きっと人が集まりたくなるだろうな」というイメージから逆算して、形にすることのほうが、むしろ理にかなっていると思います。出店をくり返すうちに、自然とそういう方針になっていきました。
外部の方に話すと驚かれるのですが、上場会社として、予算などの開示すべき事項はありますが、「売上高100億円」とか、「出店300店舗」「ブランド数を100に」といったいわゆる数字的な目標はないのです …