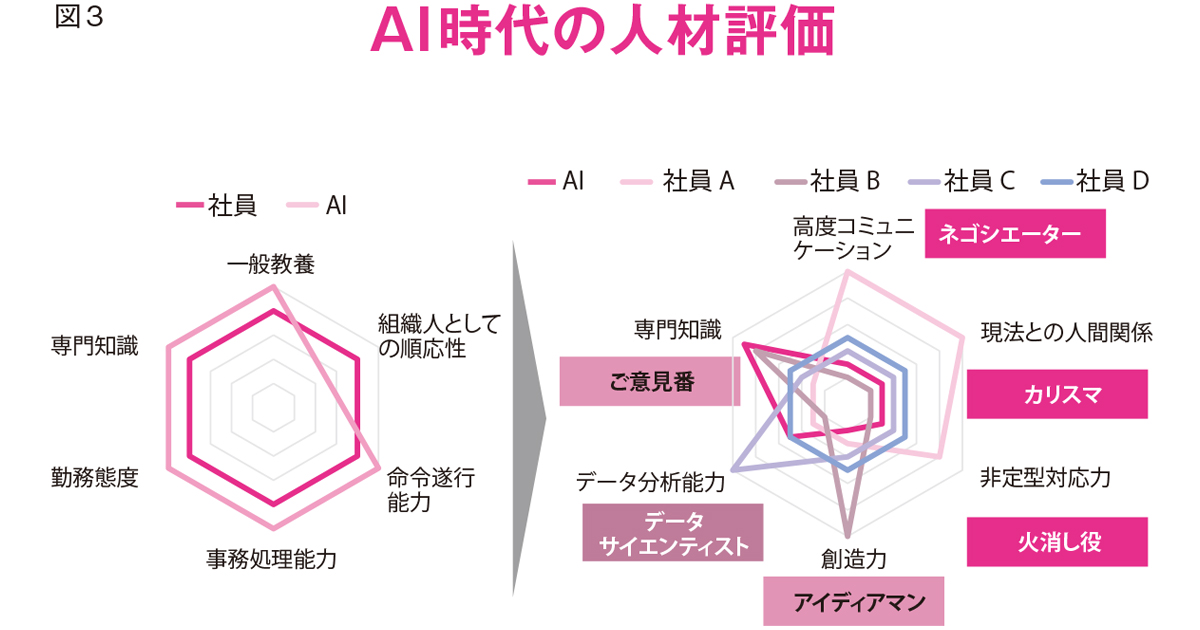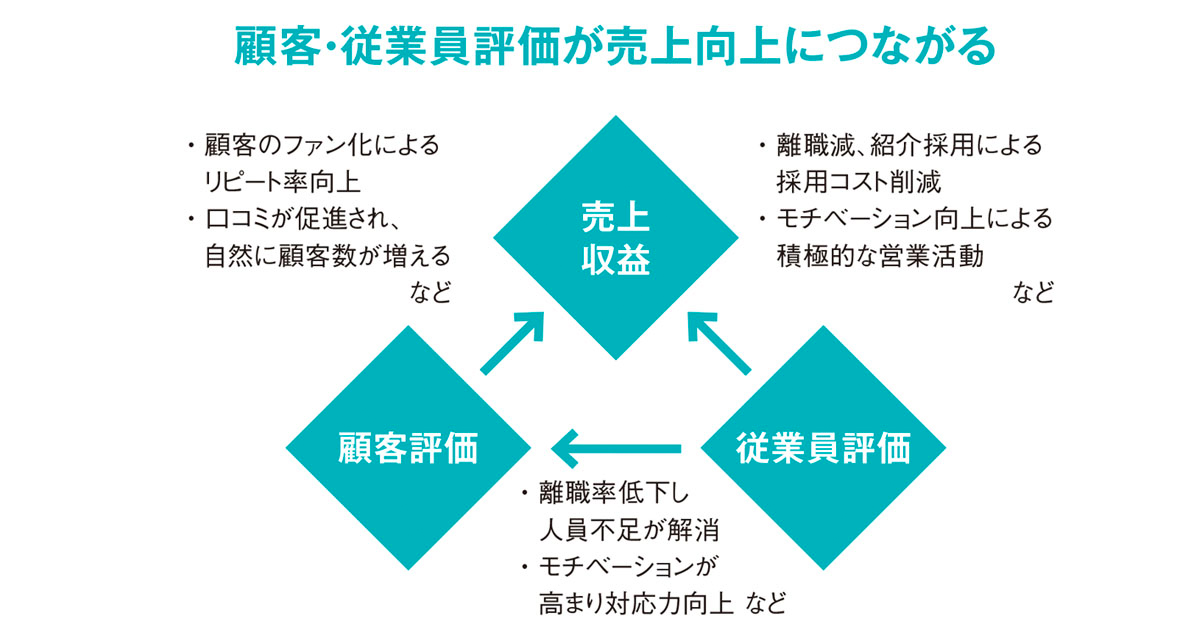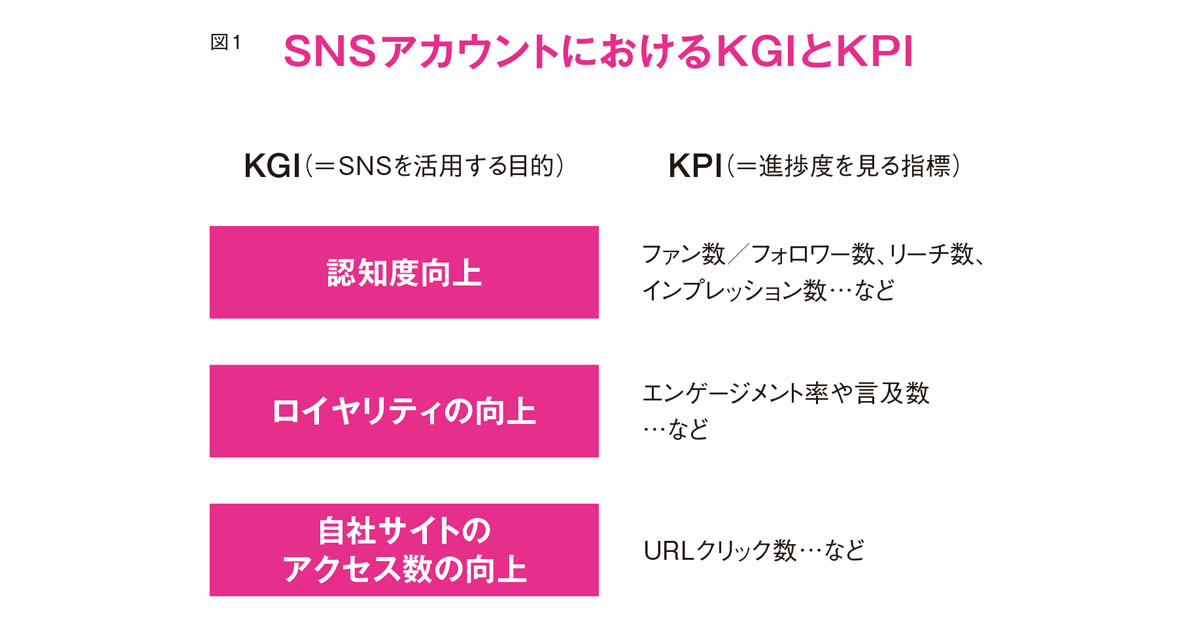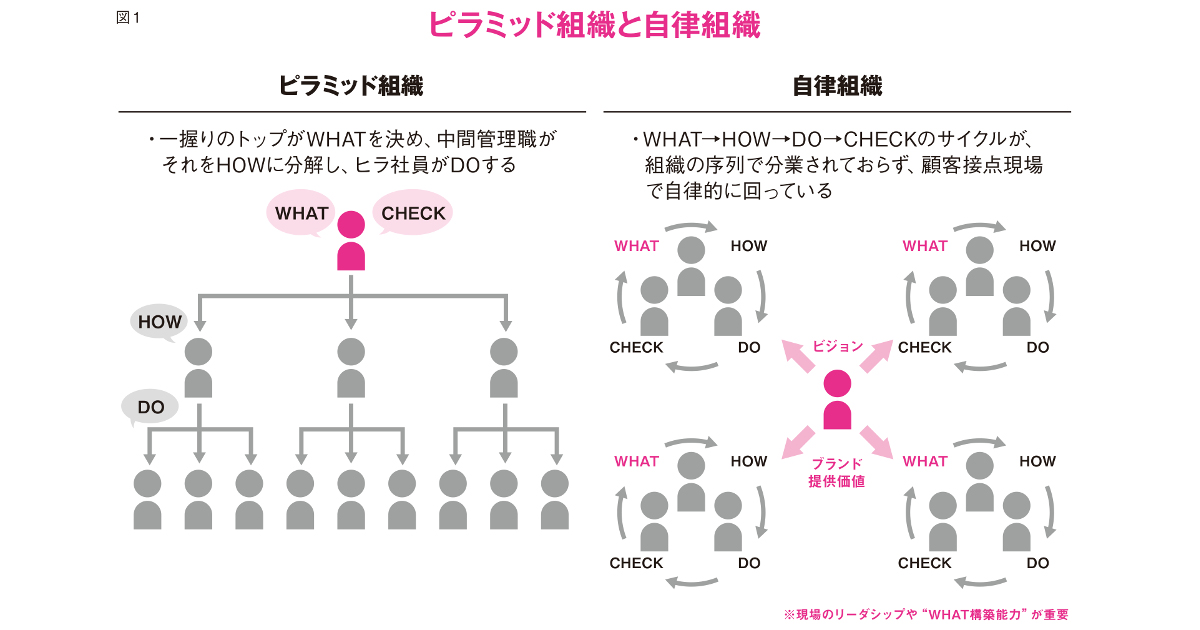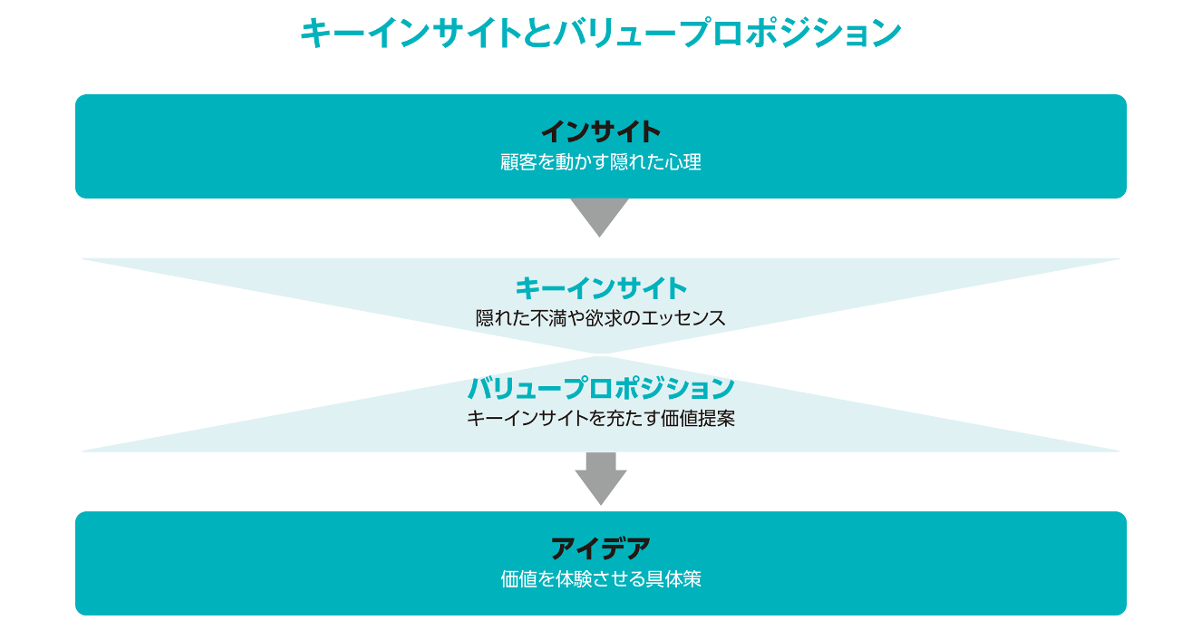ターゲットとしたい消費者に効率的にアプローチするためにはどうすればいいか。そこで登場するのが、その消費者の動線を考慮し、各種の接点=メディアを適切に組み合わせ、予算配分をする「メディアプランニング」だ。その基本的な考えと、これから注意したいことがらや望ましい人材像について、電通第1統合ソリューション局の高橋大昌氏に聞いた。
─メディアプランニングとは、何でしょうか。
メディアプランニングは、あくまでもキャンペーン設計のひとつです。その基本は「誰の、何を、どのように変えるのか」。そして、目的に沿っているかで判断すべきものです。その目的は、ひとことで言えば「ターゲットとする層の、商品やサービスに対する態度を変化させること」。ターゲットの態度変容とは、「商品やキャンペーンについて知らせる」「ブランドイメージを高める」「購入などのコンバージョン」などを指します。
それぞれの態度変容について、最適なメディアの組み合わせ、時期、出稿量などを規定するのが、従来からあるメディアプランニングです。「商品について知らせる」、「買おうという気持ちを高める」という役割を各々のメディアに割り当て、認知から購入までの、ターゲットごとの道のりに合わせて、メディアを配置します。
態度変容を起こすための指標は主に、届いた(リーチした)人の実数や、ターゲット全体のうちリーチした人の割合(%)などで表します。昨今では、割合(%)よりも、実数に目を向けるのがトレンド。オンライン広告で、消費者を細分化して扱えるようになったことも大きいですね。
─昨今ではオンライン広告が花盛りです。
オンライン広告の利点は、広告の閲覧数からWebサイトへの来訪者数、商品購入者数と、顧客の流れがわかりやすいこと。コスト効率を細かく管理できるようになりました。また、購買実績をもとに、より買ってもらいやすいターゲットを探し、重点的に露出させることもできます。
逆に、これまでのオフラインはここが弱みでした。視聴率、閲読率といった指標はあったものの、消費者の購買行動に、どれだけ寄与したかがわかりづらいからです。アンケート調査などで間接的に推測できるものの、購買に直接寄与しているかどうかはわかりにくい点が課題です。
この点で、誤解されることもあります。通販商品のテレビCMを流した場合、直接の購買行動の指標を電話での申し込みだけにしてしまうと、計測もれが発生しかねないのです。
なぜなら、「そもそも電話をするのがおっくうな人」や、「くわしい商品情報や、購入者による評価を知りたい人」がインターネットに流れた場合、そのまま販売サイトに流れると考えるほうが自然だからです。
すると、Webは順調だが、入電数は増えない、という現象が発生し、表面的にはテレビの効果がなかったように見えてしまいます。メディアの効果は個々で計測するのではなく、横断的に分析する必要があるのです。
オンライン広告は見込み度の高い顧客に絞って配信する結果、新規の需要を掘り起こしづらい傾向があるともいえます。その点では、テレビに一日の長があるのは間違いありません。
さらに現在、当社では統計手法を用いて、オフラインとオンラインそれぞれの広告と、目的達成の因果関係を推論できるようにもなっています。データ分析は今後ますます、メディアプランニングでも力を発揮するはずです。
テレビとオンライン広告の連携も日進月歩で、テレビの視聴ログを取ってターゲット配信をする手法も弊社では実用化されています。
テレビCMを見た人と、見ていない人のオンライン広告の出し分けや、CM視聴の有無が、その後のカスタマージャーニー(購買までの経路)にどのように影響を及ぼすかもわかります …