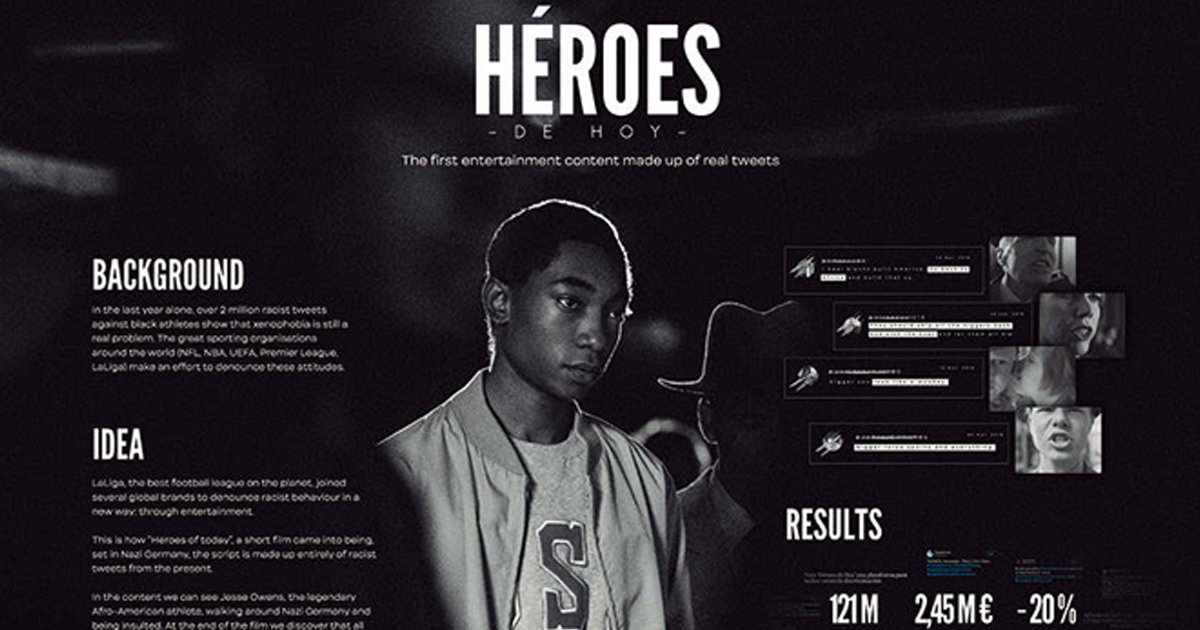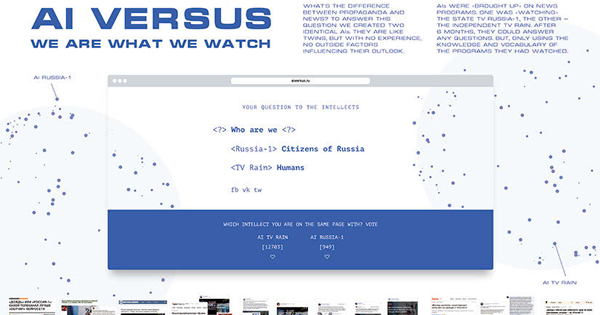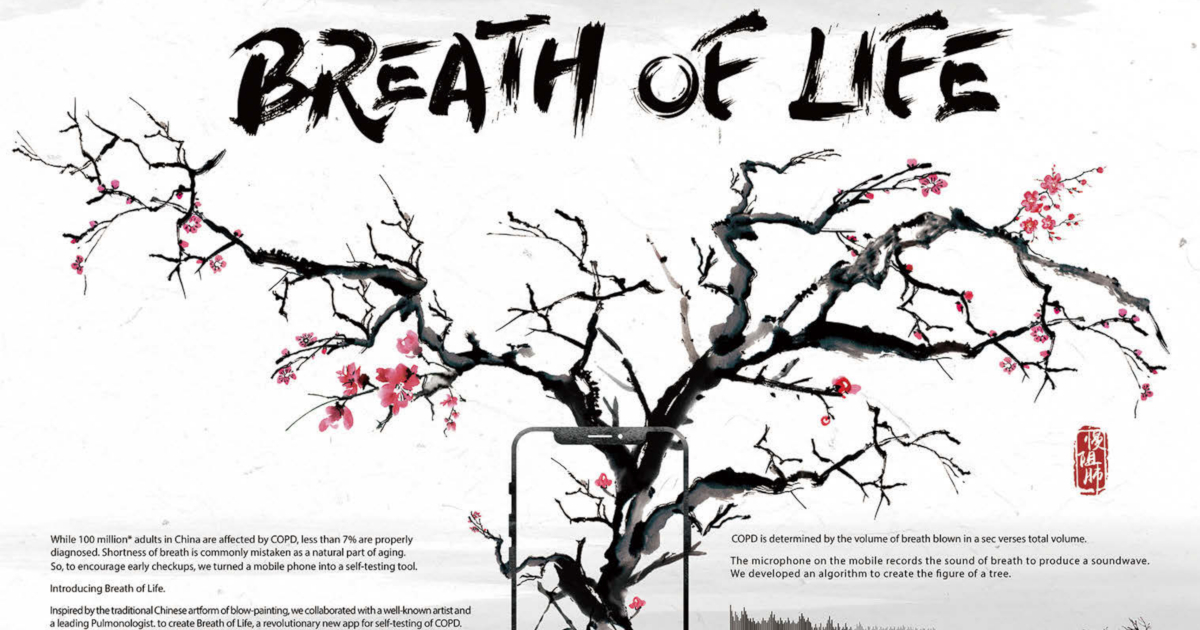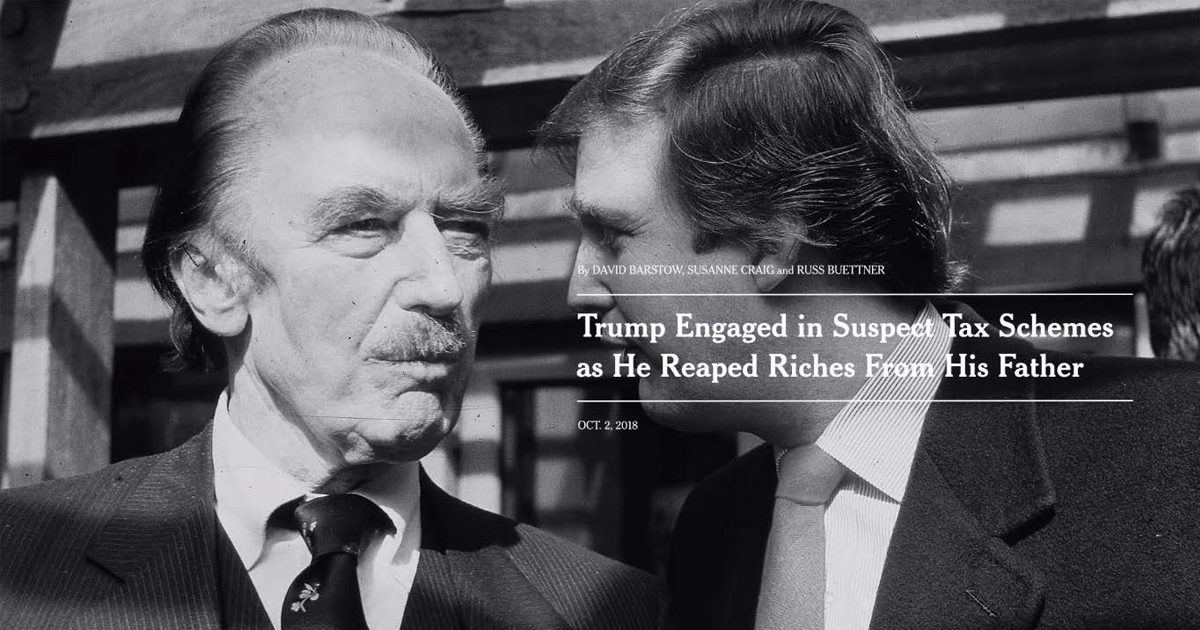カンヌライオンズでは毎年、選出されるクリエイティブやテーマが変わっていく。その切り口、手法は、日本でクリエイティブを制作する上でもヒントになるものだ。そこで、カンヌライオンズに参加し、自分なりに作品の分析を行っている4人に、今年のキーワードとこれから日本のクリエイティブが考えるべきことを話してもらった。
エクスペリエンスはブランド体験から購買体験へ
嶋:今年、カンヌライオンズのキーワードとしてアクティビズムが挙げられますが、いままさに本当に人を動かすことが求められているんです。かつてのエクスペリエンスは、ゴミ箱をバスケットゴールに見立てたナイキの広告や、フォルスクスワーゲンが階段を登ると音楽が鳴るというように、ブランドの世界観を疑似体験することだった。
でも、いまのエクスペリエンスはそのまま商品購入につながる。街中のグラフィティから商品を購入できるという仕組みをつくったナイキの「AIR MAX GRAFFITI STORES」(9)は、まさにその一例ですよね。今後スマートホームが実現し、家の鏡がメディアになれば肌診断ができるようになり、その場で化粧品を購入できるというように、エクスペリエンスの場が即ビジネスの場になるはず。

09 NIKE/AIR MAX/AIR MAX GRAFFITI STORES
ブラジルのストリートアート集団InstaGraffitiと提携して、サンパウロで展開された施策。Air Maxのニューモデルを購入する場所は、街中の壁に書かれたグラフィティ。キャラクターの足には、新作が描かれている。ファンは位置情報を使って目的の壁まで行き、そこでNike.comにアクセスして、靴を入手できる。これによって、Nike.comへの訪問が22%増加したという。
だから、アクセンチュアがドロガ5を買った理由として「エクスペリエンスを作れるからだ」と明言していたのは、エクスペリエンスがブランドの疑似体験からブランドの購買体験になっていることに他ならない。「The Whopper Detour」もマクドナルドに行く=ワッパーを買う、まさにエクスペリエンス=購買体験。エクスペリエンスデザインがビジネスに直結する時代になったからこそ、お金がわかっている人が強いんだとすごく思いました。
細田:今の日本的「PR」の考え方のままだと、今後受賞するのは簡単じゃないだろうなと思いました。目指している結果が違う。PR露出や会話が生まれたことで満足するだけでなく、法律を変え、政府を動かし、国連で議題にしようと設計されている。
嶋:PRに関して言えば、ビヘービアーチェンジの上位概念とも言えるルールチェンジャーの仕事が増えた。つまり、結果をより担保する仕事が増えた。日本がPR部門で入賞できなかったのは、それができていなかったことが大きいと思う。
嶋野:僕は毎年、個人的にカンヌライオンズで見た作品を分析しているのですが、今年のPR部門の結果を見ると15%程度は日本でも実現できそうなものがあると思います。だから「社会課題」は言い訳にはならないし、したくないなとは思います。
嶋:G20の開催が日本の経営者にいいインパクトを与えたし、企業の海外進出や社外取締役制度が進み、日本企業が社会課題に向き合うベクトルは生まれつつある。でも、はたしてどこまで向きあえるのか。さらに言えば、こうした動きと実際のマーケティングが日々どうつながるのか、そこに断絶があるのは否めない。ただ近い将来は若年層を取り入れるためには、マーケティングとして社会課題に向き合うことが必要になってくるだろうし、ネット社会でローカリティが無くなって世界中の若年層が同じ価値観を持つようになると、日本企業も変わらざるを得なくなるのではないかなと。
細田:確かに海外のエージェンシーは、必ずしも善良な心でFor goodやSDGsに取り組んでいるわけではなくて、それがマーケティングに効くからだ、と言っていますね。
HATEを「やめよう」から「向き合う」姿勢に
嶋野:今年もいろいろと見た中から、いくつかのキーワードを立てました。一つは「Eat the Hate(ヘイトを食べちゃおう)」。ヘイトに関するキャンペーンは増えていますが、そこにある傾向が見られました。一つ目がディーゼル「ha(u)te couture」(10)。ディーゼルに対する悪口やクレームをそのまま服のデザインにして販売したというものですが、その服もかっこいいんです。
10 DIESEL/HA(U)TE COUTURE(PUBLICIS ITALY)
「ヘイトなんて、着ちらそう」と、ディーゼルはSNS上のブランドに対する誹謗中傷を反映させたファッションのアイテムを販売した。ムービーには、アメリカ人ラッパーのニッキー・ミナージュら著名人がそのアイテムを身につけて登場している …