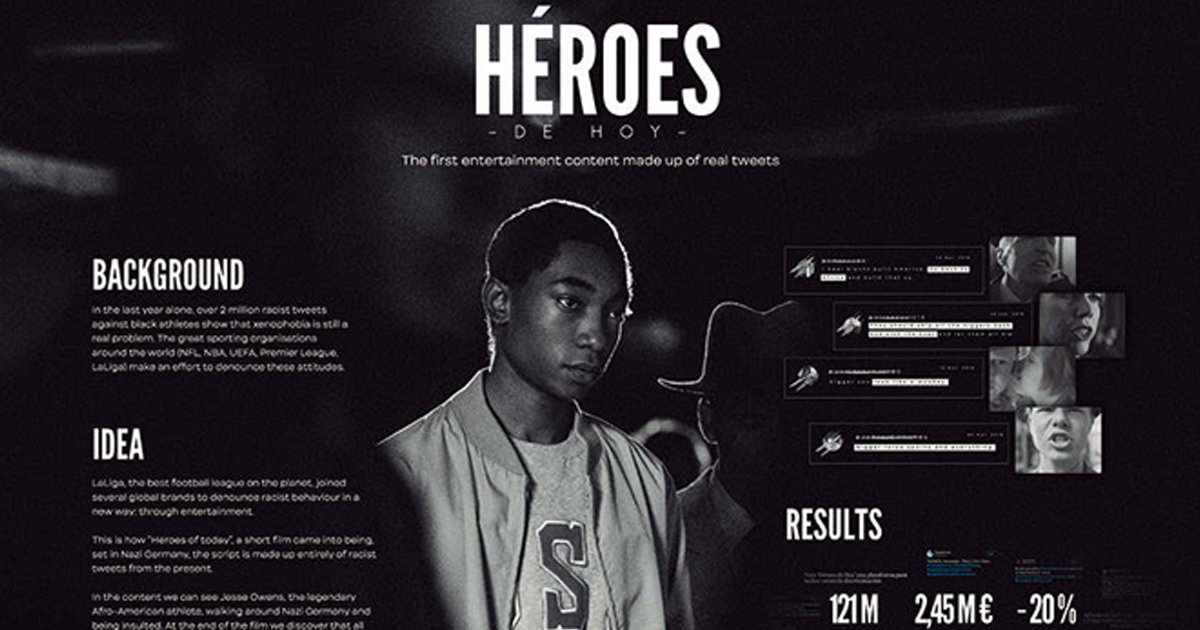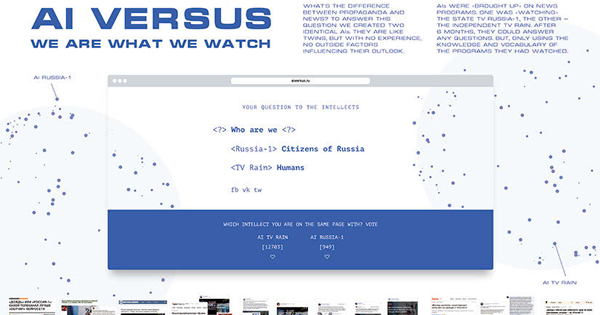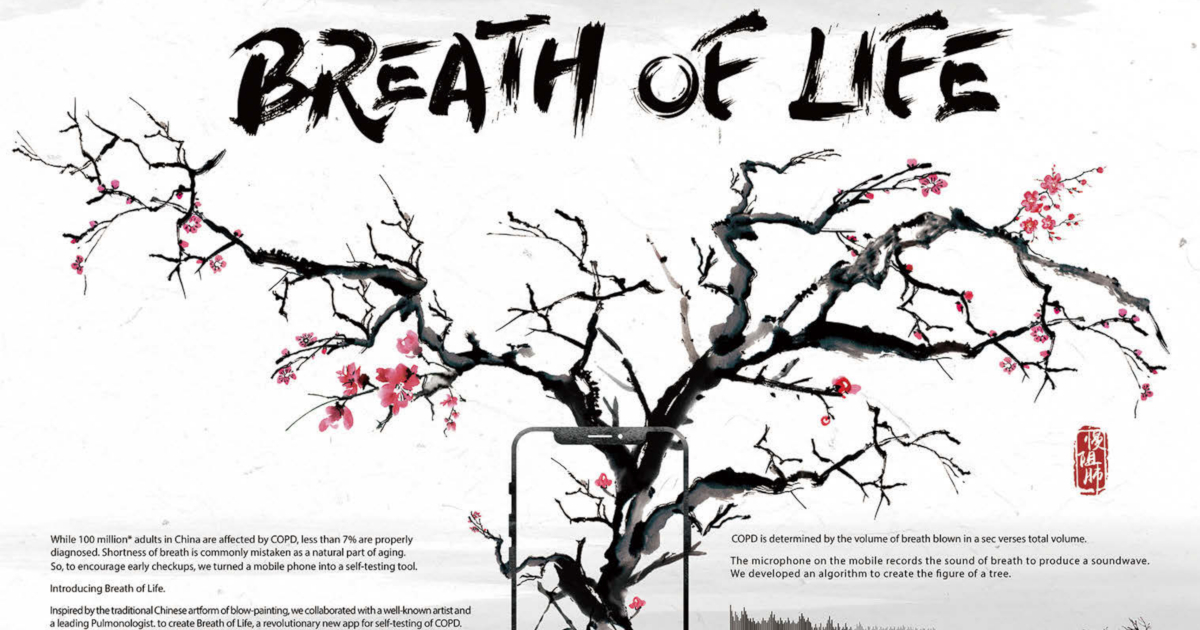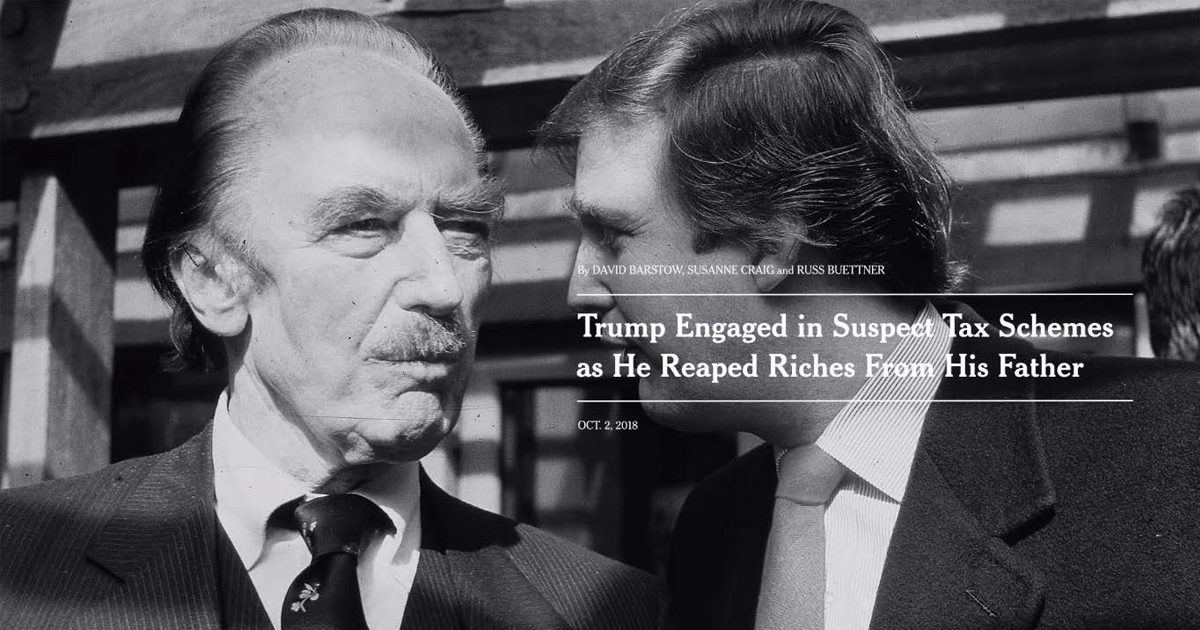カンヌライオンズでは毎年、選出されるクリエイティブやテーマが変わっていく。その切り口、手法は、日本でクリエイティブを制作する上でもヒントになるものだ。そこで、カンヌライオンズに参加し、自分なりに作品の分析を行っている4人に、今年のキーワードとこれから日本のクリエイティブが考えるべきことを話してもらった。
ソーシャルグッド"バッド"にも目を向ける
尾上:今年のカンヌライオンズの結果を見て、少し気になるところがあって。「THE LAST EVER ISSUE」では、これまでポルノ雑誌として流通していたものを、内容を大きく変えて最終号を発売したわけですが、意識を変えるべき対象のこれまでの読者のことを考えているのかな、と。届けるべき情報を考えましょうと提案するのはいいけれど、最終号はこれまでの読者は絶対に読まないだろうし、買わないですよね。購買層が移動するだけで、届けたい人には届かない強権発動すぎる気がして。
嶋野:これはグラス部門での受賞だからリザルトより、やったことに意義があるという評価なんだと思います。
尾上:もうひとつ気になるのが、これまで雑誌に登場していた女性たちが全人類の敵になってしまうのではないかということです。間違っていました、という記号になるので。
嶋:確かにそういう面はあると思います。ネットは価値観を二項対立化しがちなので、「こっちが正しい」という雰囲気が作られてると、少数意見の人が無視されやすい環境に陥ってしまうのは確かですね。本来、意見はグラデーションであるのが健全なはずなのに。
尾上:カンヌライオンズの審査員だったりこういった業界の人はどちらかと言えばマッチョ思想で、女性も強い。でも、実際に店頭で目立っている「THE TAMPON BOOK」を買うのは恥ずかしいという人もいるのではと。そういうところから思想を変えていくという話なのはわかりつつ、急に変えようとしすぎがち。「Miss America」にしても、自分の体に自信があって見せたい人もいたはずなのに、とにかく隠しましょうという流れになっているのはどうかと。
嶋:それだけ、広告に影響力があるってことなんだろうけど、僕らには責任があるよね。
尾上:以前に、日本でレースクィーンが槍玉に挙げられたことがあります。その時、彼女たちは「誇りを持って仕事をしているのに、仕事の存在自体を否定された」ことに対して怒っていました。どんな領域でも、そこで誇りを持って仕事をしている人がいるのに、とにかく現状を変えようとする人の声が世の中では強くなりがち。どちらかと言えば、カンヌは後者を褒める傾向にある。いろんな立場の人がいることを鑑みないとうまくいかない気がします。
嶋野:ナイキ「Dream Crazy」は反トランプを表明しています。アメリカの半分はトランプ派だけど、カンヌは反トランプが勝利。つまり白人のエリート主義が強い場というか。
尾上:そういう背景を知らずに受賞作品を手放しで褒めてしまうと、おかしなことになるなと思って。
細田:ソーシャルグッドが生み出す闇の部分というべきか、ソーシャルグッド"バッド"みたいなものがあるとして、そこに目を向けることも必要ですよね。
尾上:女性のジェンダーの話が多かった一方で、今後は男性の話がもっと出てくると思うんです。最近「ガラスの地下室」と言われていますが、男性にも同じような差別がある。さらに一方で、今年はゲイプライドの話は減ってしまい、どうなっているんだろうと思ったり。毎年トレンドが変わりすぎていて、結局何も解決していないのに、イナゴの群れのように課題間を移動しているだけなんじゃないかと感じる部分もあります。
嶋野:2年前はプラスチック問題が最盛期だった。日本にはようやくプラスチック系の波が来ましたが、今年はプラスチック系が全く受賞していないし。
尾上:そういう流れがあることを加味した上で、自分たちも仕掛けていかないと、何か足元をすくわれそうで。
嶋野:テーマは同じでも、取り組みを変えないと評価してもらえないというのはありますね。以前に「GAYTM」で話題を集めたオーストラリア・ニュージーランド銀行が、今年展開したのが「SIGNS OF LOVE」(21)。
21 ANZ BANK/SIGNS OF LOVE (TBWA\MELBOURNE + REVOLVER/WILL O'ROURKE)
オーストラリアのLGBTQ+の象徴であるオックスフォードストリート。そこから離れて暮らす人々に向けて、各地にあるオックスフォードストリートの看板を虹や愛の心からフラミンゴやユニコーンの船乗りまで、LGBTQ+文化の表現である「サインオブラブ」の彫刻に変更。グーグルと共同でグーグルストリートビューに道路標識を表示し、世界中の人々がインスタレーションを見ることができるようにしている。
今年はシドニーのオックスフォードストリート(ゲイカルチャーの中心地)だけではなく、オーストラリア中にあるオックスフォードストリートをゲイストリートの象徴にするべく、オブジェを掲げたというプロジェクト。LGBTがテーマであっても、同じことをやっていては賞は獲れない。普及期に入ったら普及期に入ったなりのやり方で展開していく。施策の意味が進化しているものは賞につながっているのかもしれないですね。
嶋:でも、こうしてやり続けている企業は偉いと思います。マーケティングエフェクティブネスで受賞した「Black Supermarket」もそうだけど、きちんと継続している。日本の広告界は、どちらかというとアイデア一発で、終わってしまうものが多いから。過去、いろんなアプリが広告賞を受賞したけど、あれ今も使っている人いるの?っていう。
広告業界って短期的な価値を追い求める人がやっぱり多いと言わざる得ない。でも、ネットでつながる世界になっていけばいくほど一発芸ではなく、つながる仕組みを作ることが大事になっていく。企業も一度取り組んだものはすぐに終わりにせずに、継続していくべきだと思います。
尾上:大きな課題に向き合うには...