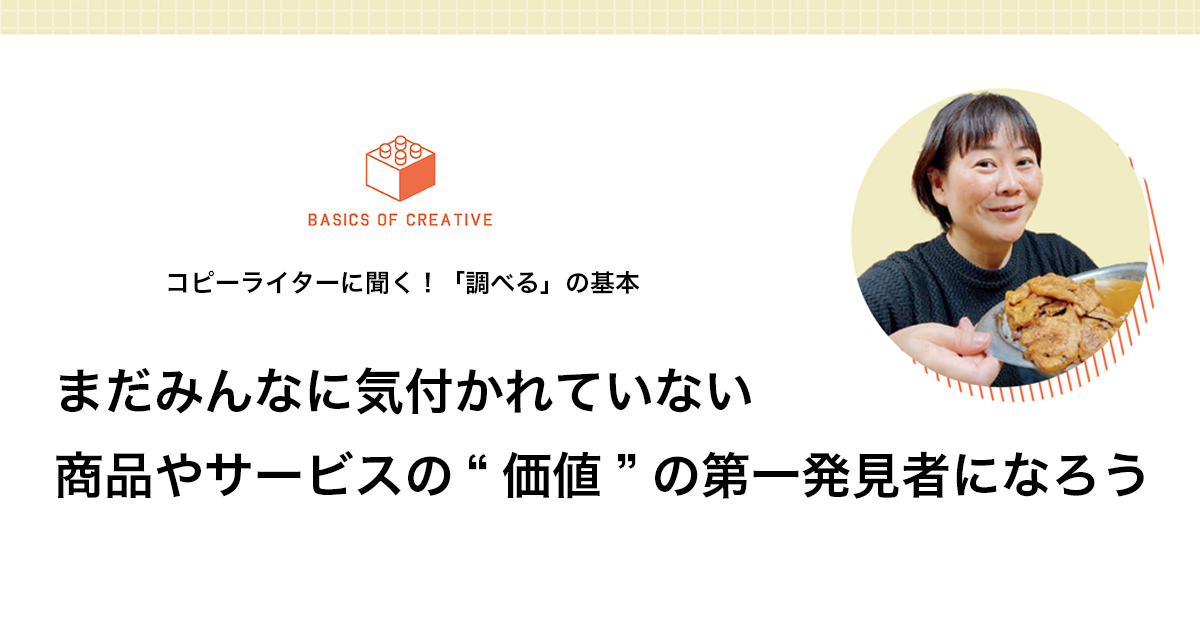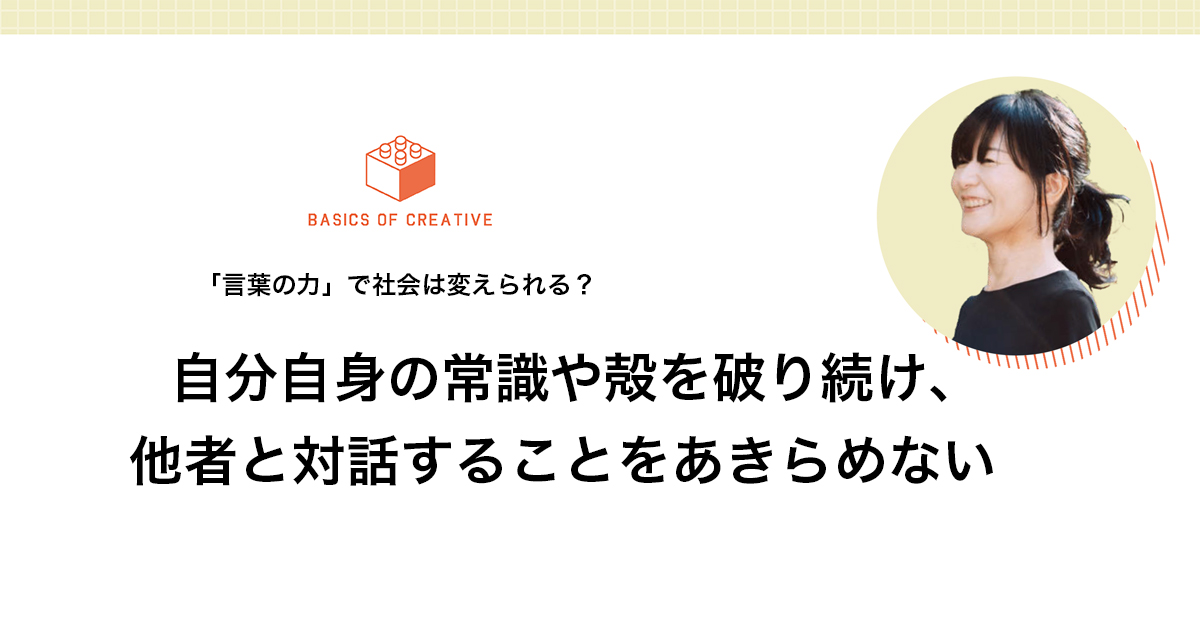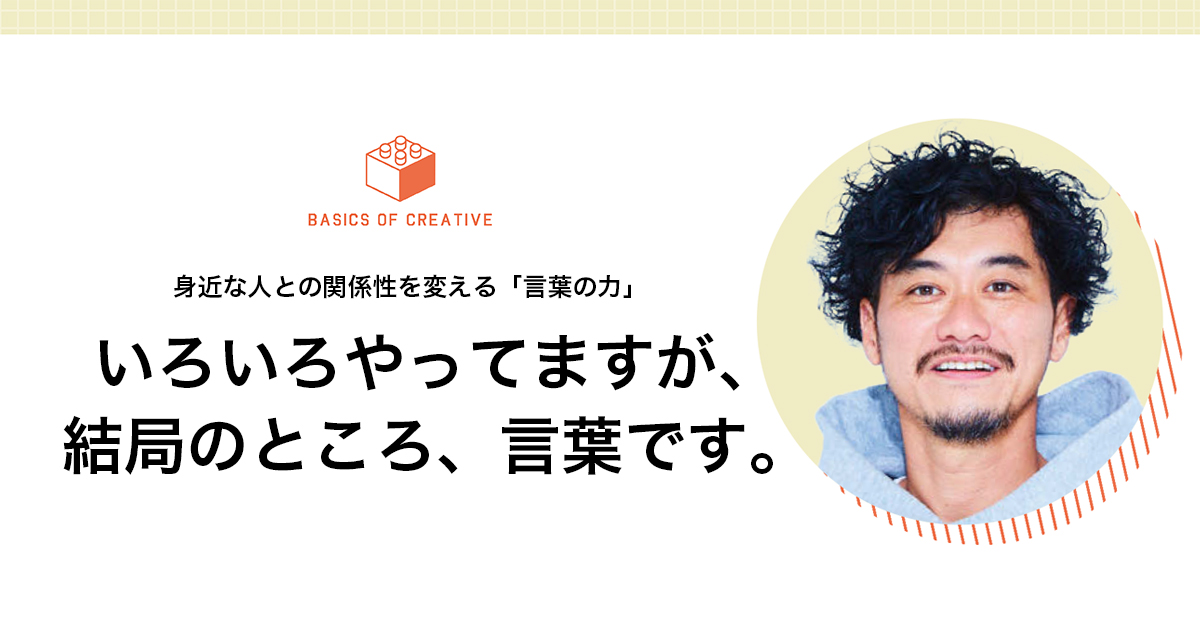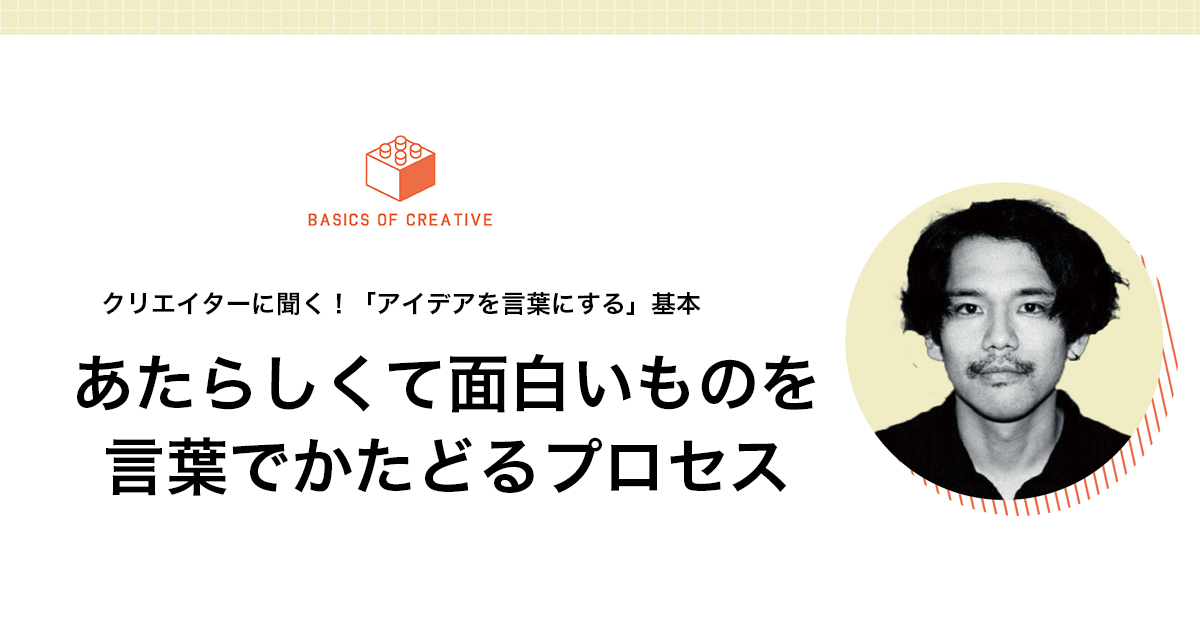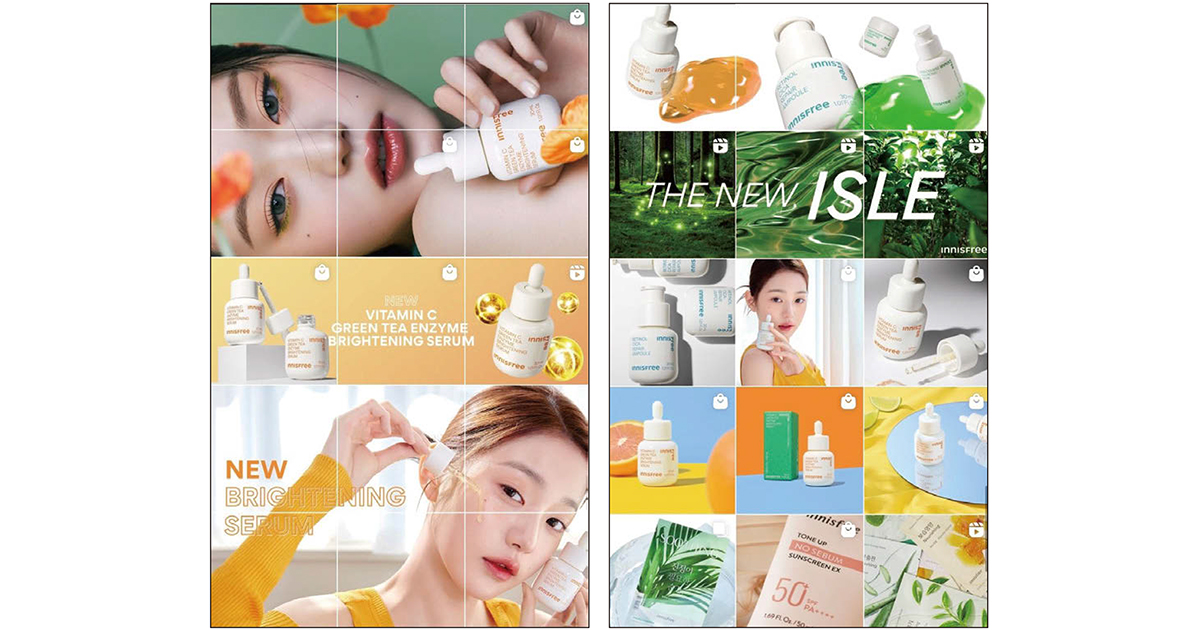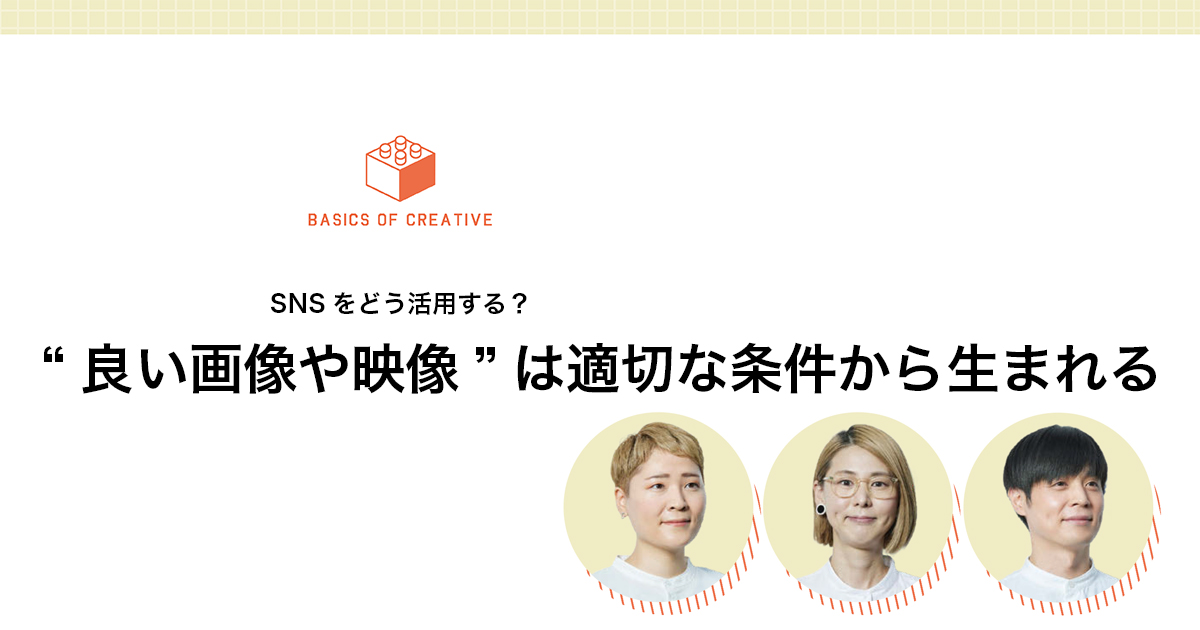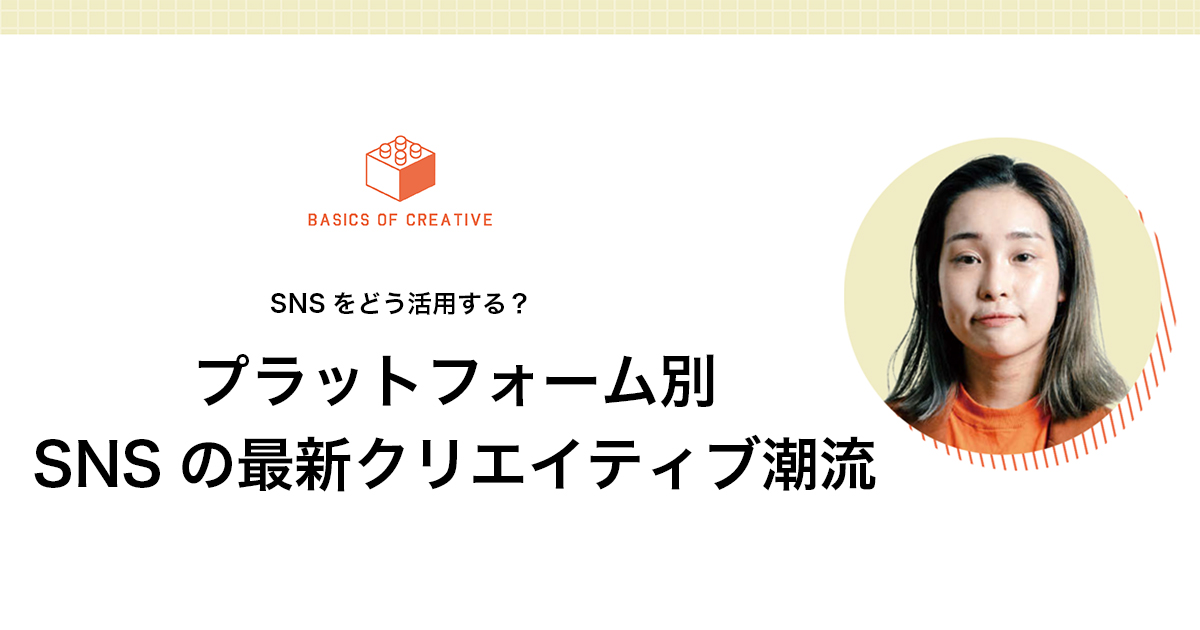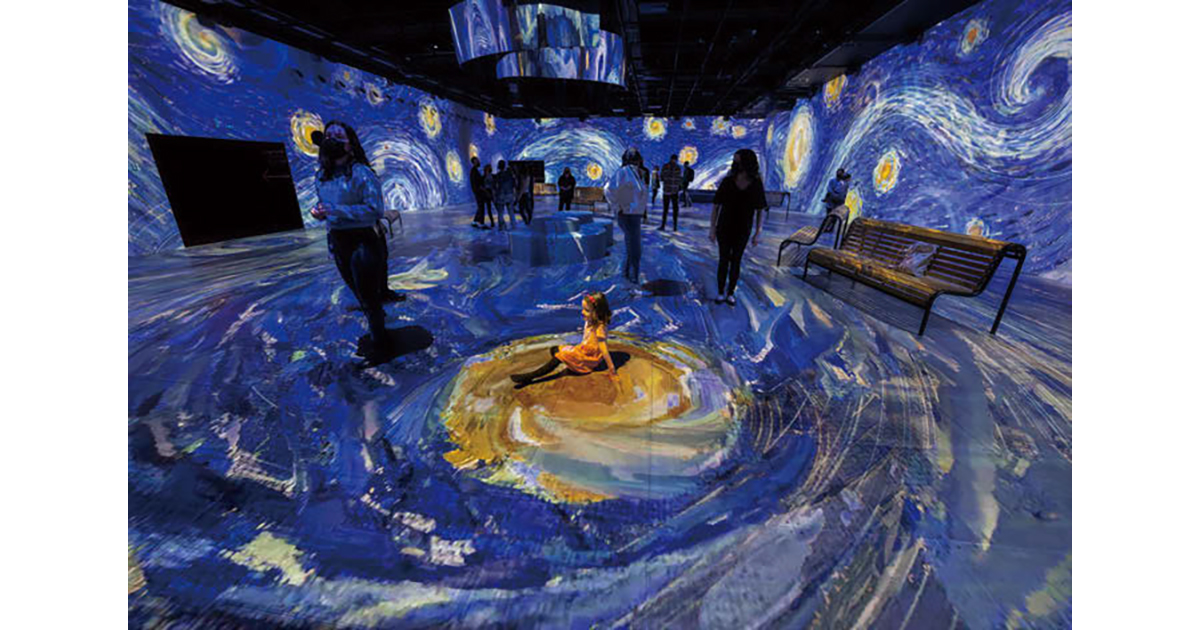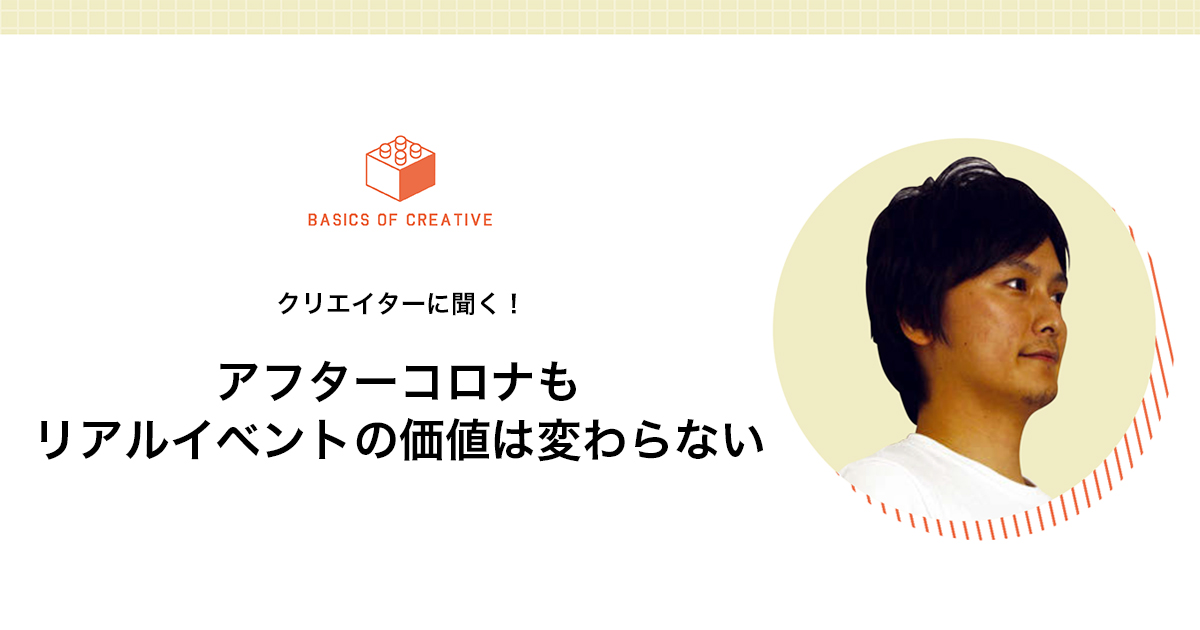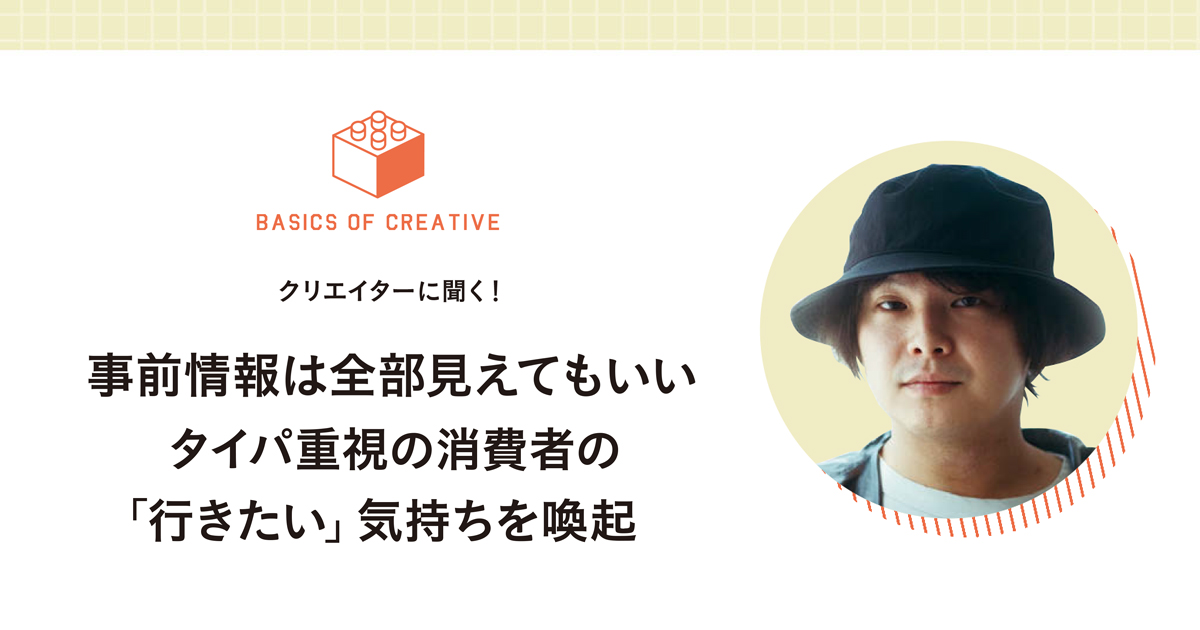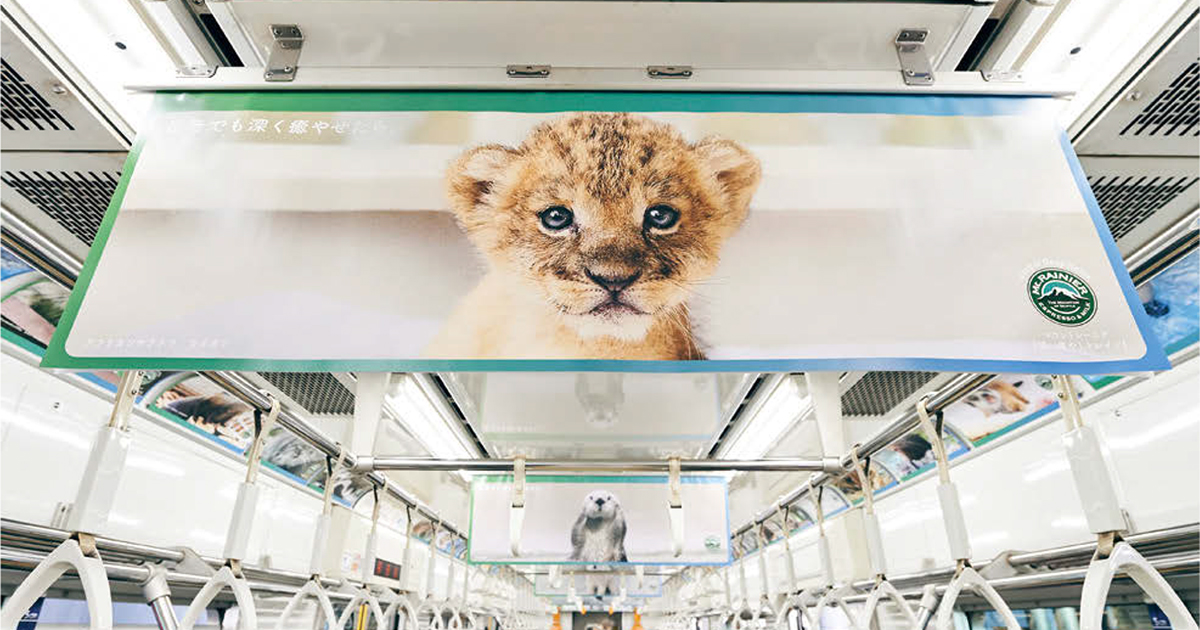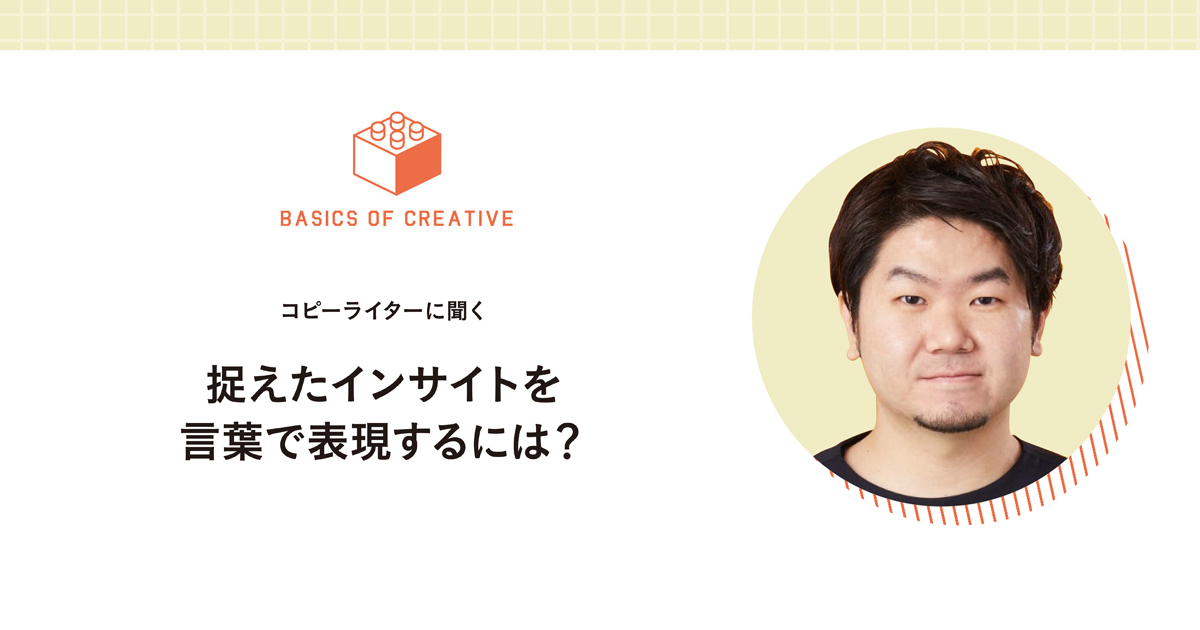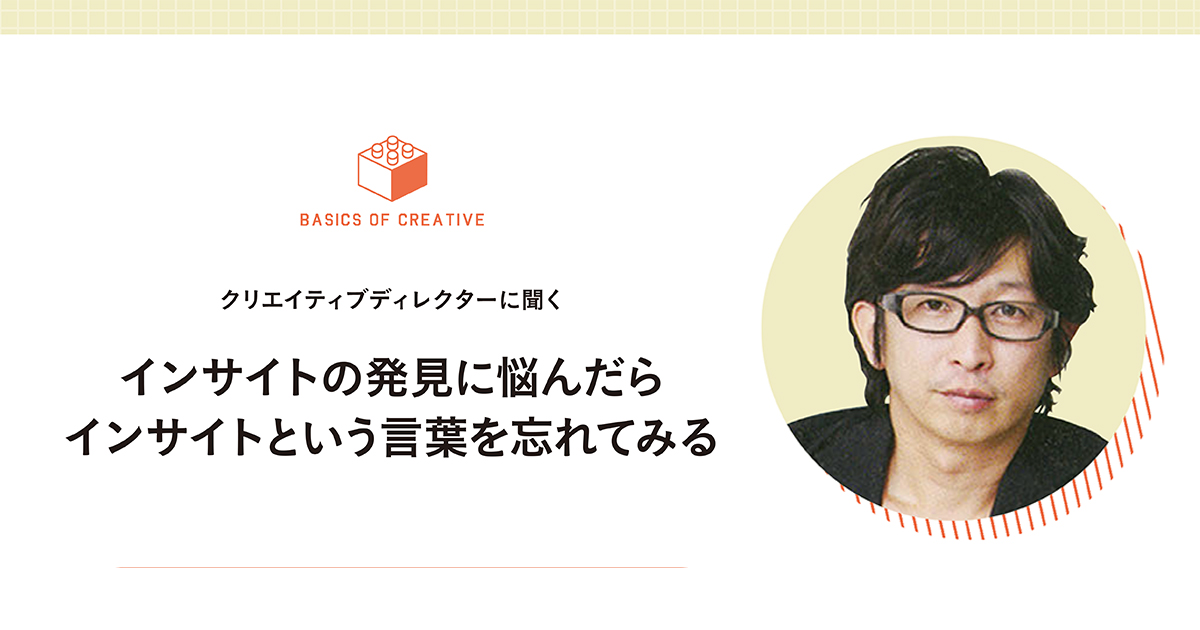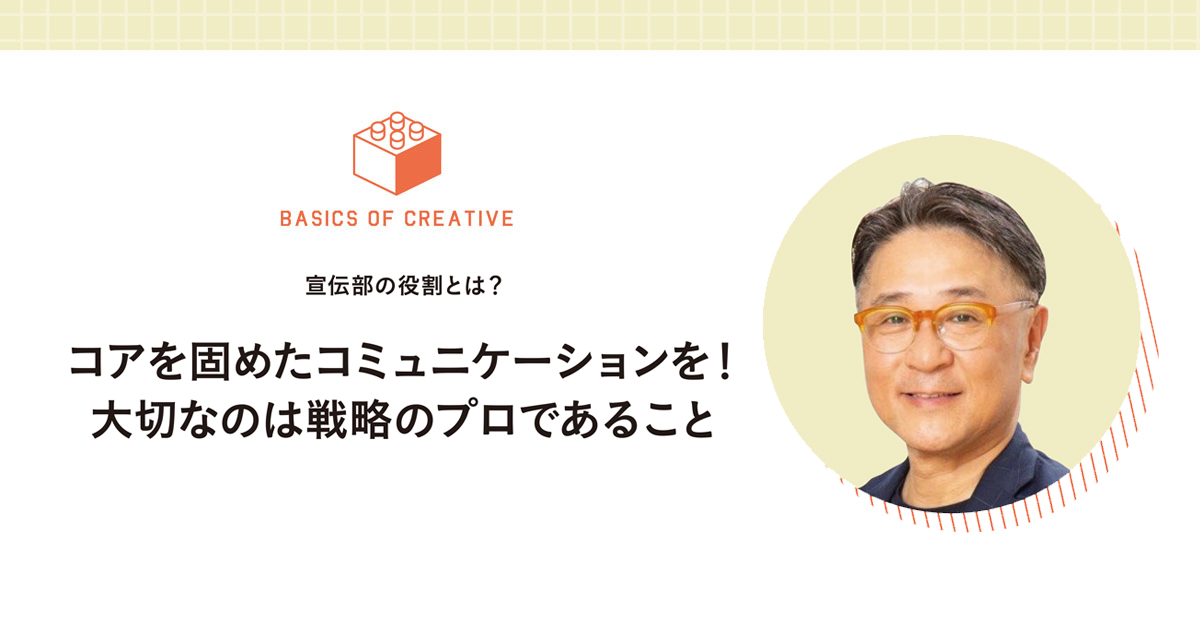社会や誰かの常識を変えた言葉 3選
☑「ゆるスポーツ」
☑「注文をまちがえる料理店」
☑「時は流れない。それは積み重なる。」
大切にしたいのは、熱が伝わる想いや声
──細川さんはコピーをつくるとき、どんなことを大切にしていますか。
私はコピーをつくるとき、生活者に共感や納得を生む言葉を見つけることはもちろんなのですが、そのためにも「何のためにそのブランドが存在するのか?」について、関わる人の熱が伝わる想いや声を聞くことを大切にしています。そして、その結実であるファクトの部分を集め、掘り下げることにも力を入れています。その上で、生活者に関心を持ってもらうための時代性と普遍性も意識しながらコピーを考えています。
──言葉には、「社会を変える力」があるでしょうか。
できるだけ正直に言うと、私はコピーを書いたり、企画をしたりする際に、「社会を変えたい」からスタートしていません。でも、一方的な物の見方を変えたり、固定観念に縛られている状況を変えたい、という想いは持っています。なぜなら、そうしたものが存在することによって対立が生まれていて、苦しむ人がいるのが、いたたまれないからです。
生きていくのは、とても大変なこと。だからこそ「誰かに対立を煽られている場合じゃなくて、できるだけ力を合わせて支え合って生きていこうよ!」という気持ちがなぜだか常にあります。
でもそうやって、自分自身の常識からはみだして、誰かへの想像力を持てたときに、一人ひとりの心が動いて、結果として、社会が変わるのかな、と考えています。
そもそも長く続くサービスや商品はどれも、人間をちょっとでも生きやすくしてくれるために、今までの常識をこえて懸命に発明されたもののはず。ですから、こうした考え方も企業活動と共鳴できるものだと考えています。
──「これは社会を変えたのでは」と感じたコピーはありますか。
自分の書いたもので言うと、「#この髪どうしてダメですか」(P&Gジャパン「パンテーン」/2019年)と「#常識をはきかえよう」(大王製紙「アテント」/2020年)でしょうか。社会まではいかなくても、誰かの常識を変えるきっかけになれたかもしれない、という手応えがありました。
前者は、中高生の髪型校則について、生徒と先生、どちら側の声も聞きながら、世の中に対話の場をつくることを目指したキャンペーンのコピーです。
後者は、大人用紙おむつをこれからは「パンツ」と呼ぼうと提案し、「もっといいパンツになる」をブランドからの約束として...