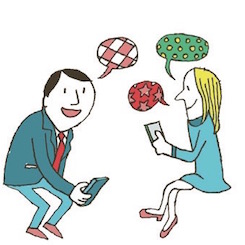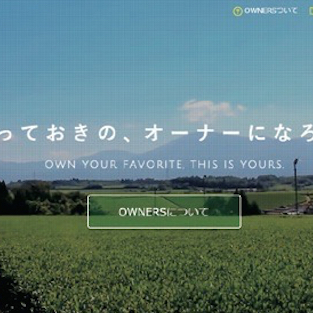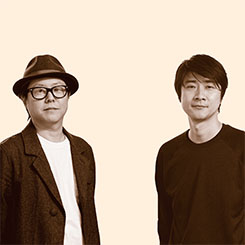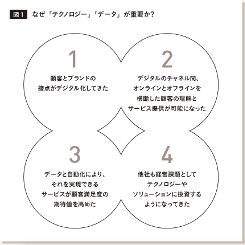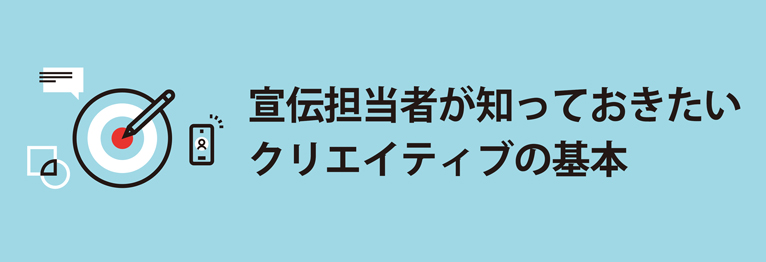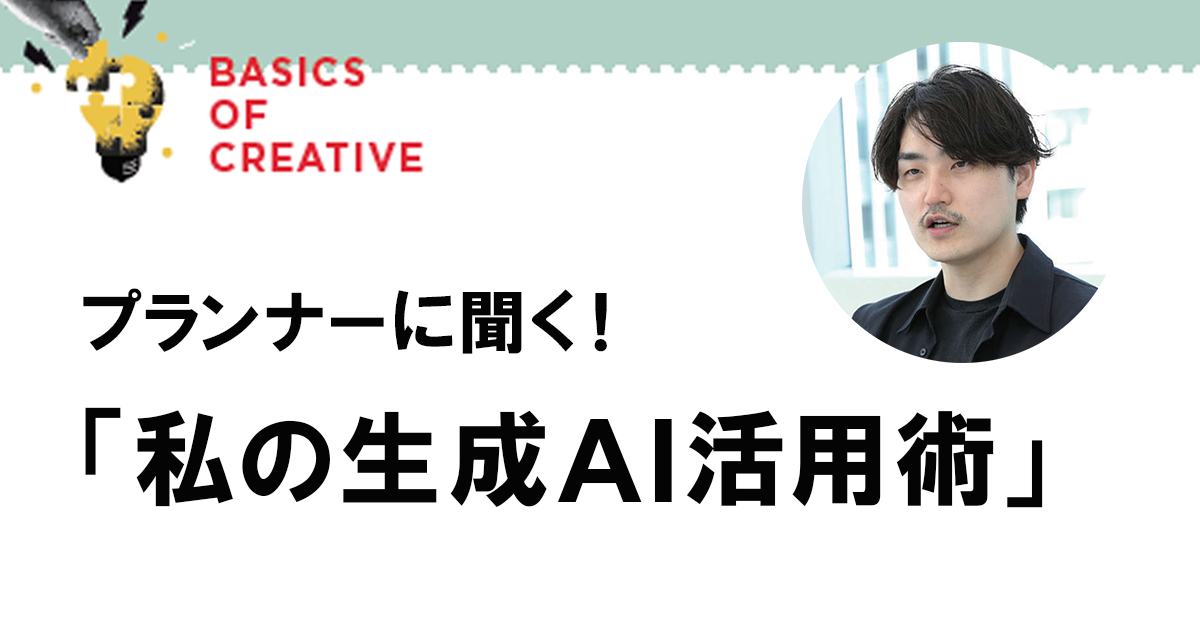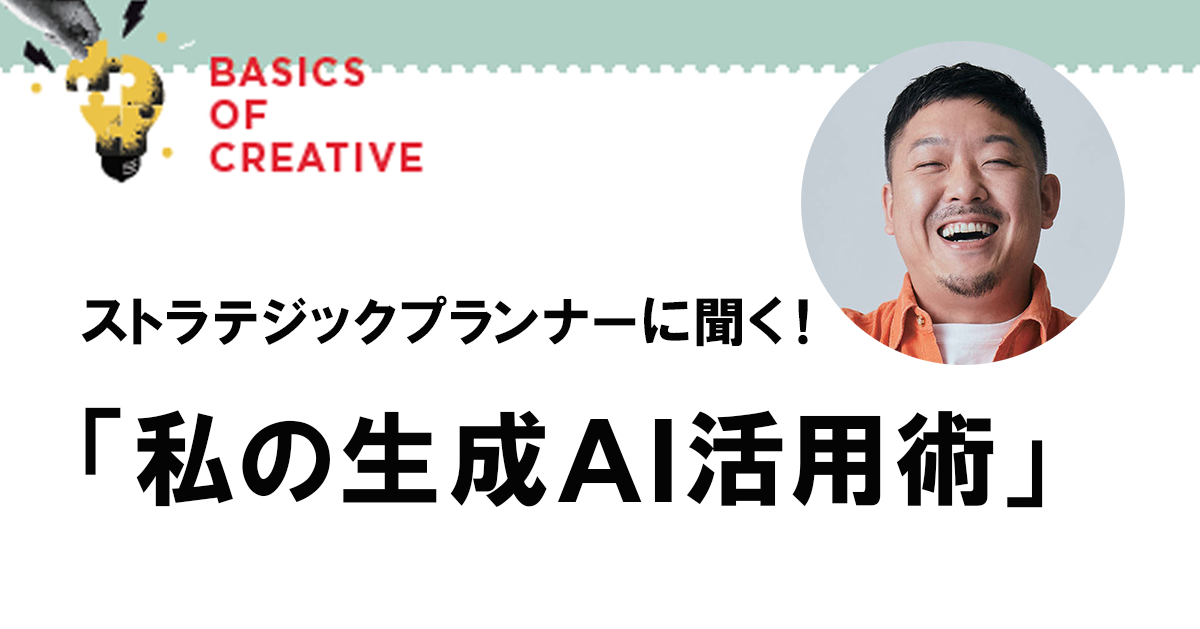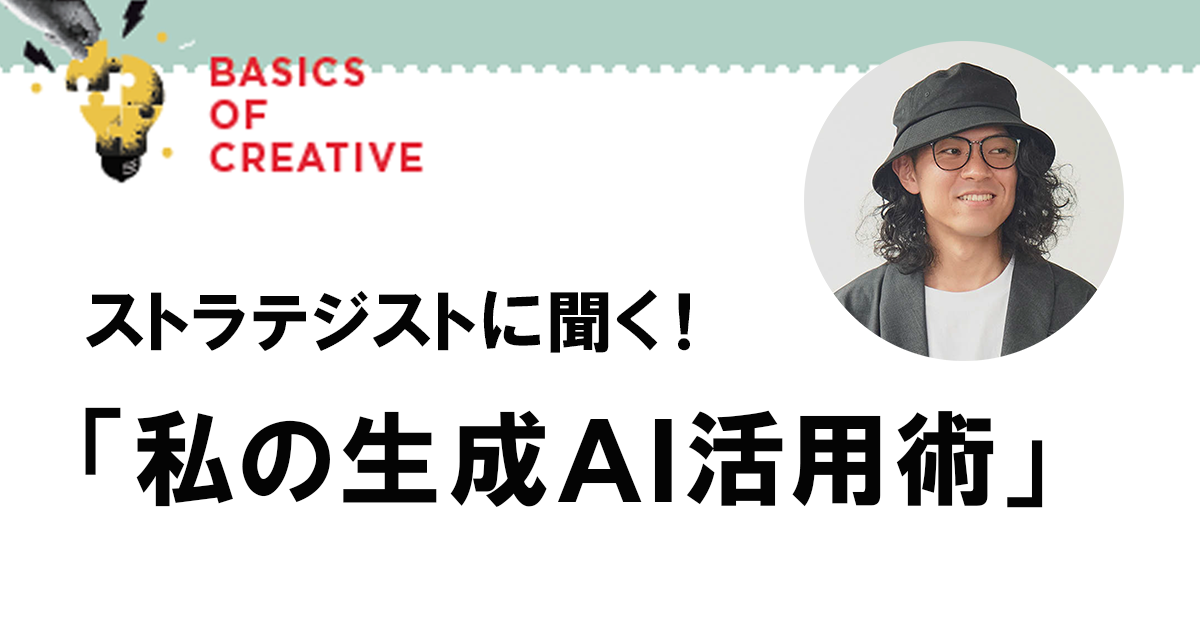あらゆるメディアやプラットフォームなどが、ユーザーの“時間争奪戦”を繰り広げている。その戦いを制するためには、どのような戦略を描き、サービスの設計を行うべきか。LINEのコマース・メディアを統括する島村武志氏に聞いた。

LINE 上級執行役員 コマース・メディア担当 島村武志 氏
2007年、ネイバージャパン(現LINE)設立時より「NAVERまとめ」全体の責任者を務める。LINE事業においては、メディア・ECサービスの責任者として従事。2014年4月、現職に就任。
「いいね!」が情報流通を左右する
―2015年のメディアや情報環境の変化の潮流について、どのように捉えていますか。
「情報が生まれること」と「流通すること」に分けて考えることができると思います。潮流という意味で言えば、現在、情報流通の中心には、TwitterやFacebookといったソーシャルメディアがあります。情報の多くは、自分がフォローしている人に向けて発信されるようになり、そこで反応されることが重視されるようになりました。そして反応されないことは、語られづらくなっている。共通理解される事柄でないと広まらなくなった結果、最大公約数的な情報ばかりがあふれるようになっているんです。インターネットによって情報は多様化されるはずだったのが、実は偏向してきている。そうした傾向が年々強まっていると感じます。
――ソーシャルメディアで、バズることが目的化されてしまっていると。
それがすべてになってしまっている側面があり、そうであるがゆえに、情報の生成のされ方も閉塞感が増してきていると思います。例えば、一昔前のブログの記事は、いつか誰かが見てくれるかもしれないと思って書かれていて、書く前から読み手を意識しすぎていなかった。自分の専門や趣味などの情報を発信することで、新たな出会いや発見がありました。
―最近はバズることを指標とするのではなく、深さを測る指標の重要性も語られるようになりました。
深さももちろん大事ですが、そもそもリーチする情報が偏向しているんです。ソーシャルメディア上で「いいね!」をされない限り、広くリーチできない状況は、質以前に、流通のバリエーションの問題です。私はもともと情報検索が専門なのですが、「NAVERまとめ」に携わるなかで、以前「グーグルの検索ページの10ページ以降は存在しないのと同じではないか」と問題提起したことがあります。検索サイトは多くの場合、ページ数が深くなるほど見られにくいじゃないですか。本当はその先に膨大な情報があるのに、そのワードを検索したとしてもそうした情報にはアクセスできない。それはつまり、例えば10ページ以内に入らなければ情報として存在しないのと同じということです。だからこそ、検索全盛時代にはこぞってSEO対策が重視されました。今、ソーシャルメディアの浸透で起きている現象も同様であり、「いいね!」がつかないコンテンツは流通しないという構造が生まれています。
インターネットの可能性を考える
―「いいね!」がつきバズることが、流通上の唯一の軸になってしまっていることが問題だと。
善し悪しの問題を言っているつもりはありません。確かに、ソーシャルメディアが情報流通の中心になっていることで …