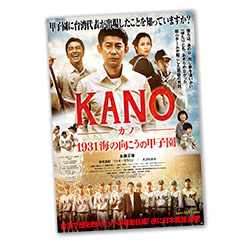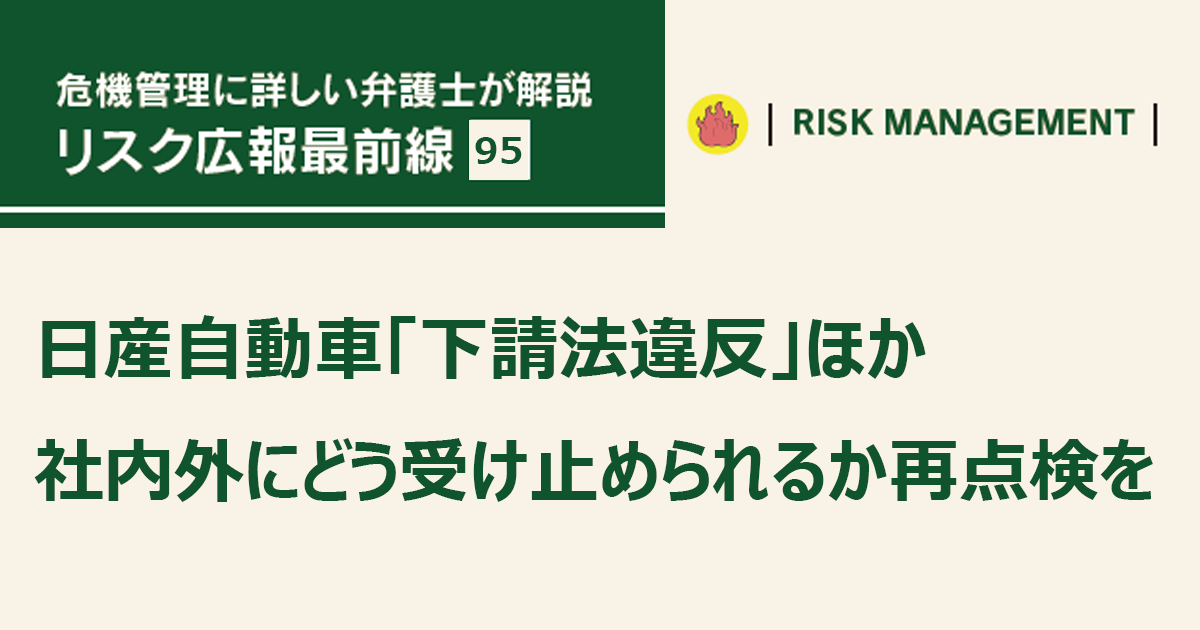ふるさと納税は、返礼品を通して全国に地域を紹介する仕組み。「マーケティング」と「イノベーション」という2つの視点からふるさと納税が自治体に与える影響について分析する。

東川町ではふるさと納税による「株主制度」を実施している。この制度を通して寄附者は株主となりまちづくりに参加でき、「株主証」と「東川町特別町民認定書」が渡される。
ふるさと納税」は地方創生の一環として設けられた税制上の仕組みだ。地元で医療や教育などの住民サービスを受けた地方出身者が進学や就職を機に都会に移住すると、そのまま納税するようになるため、地方の自治体は税収を得ることができない。生まれ育った「ふるさと」に納税させるために「ふるさと納税」はつくられた。
神戸大学大学院経営学研究科の保田隆明准教授は、ふるさと納税の功績を「自治体にマーケティングとイノベーションの視点を与えたこと」と分析する。消費者が商品を購買するまでの行動モデル「AIDA(アイダ)の法則」を自治体に置き換えると、返礼品は最初の注意を引く「Attention」となる。特産品という試食品を通じることで町を知ってもらい(Interest)、「その町へ訪問したい」「特産物を購入したい」という意欲を喚起(Desire)、最終的には商品の購買や観光といった「Action」につなげる。自治体がふるさと納税を通じて行っていることはマーケティングそのものと言えるだろう。
また地方の財政難に対し、ふるさと納税により自助努力で稼ぐことを促した意義は大きい。「地域の資産を見直し、新たな価値として提供するイノベーションが実現されています」。
一方、寄附金は恒久的な財源ではないため、ふるさと納税において重要なのはお金の使い道だ。例えば、北海道の東川町では2008年からふるさと納税のスキームを使い、投資(寄附)によって株主(寄附者)になってもらう「株主制度」を実施している。ワイン事業、オリンピック育成事業など、町が指定したプロジェクトから事業を選び、一口1000円以上の投資をすることが条件で、自治体の将来的な収入源となりえる新事業になる。「寄附金は投資に充てるものだと定義すれば、どのくらいのリターンが見込めるかを考える必要も出てきます。地方自治に経営学の視点が必要になった今、お金の使い道も戦略的に考えていかなければなりません」。
自治体の経営、広報活動も支えるふるさと納税に期待は高まる。

東川町のふるさと納税では、ワイン事業、オリンピック育成事業など、将来の新事業に投資できる。
 |
神戸大学大学院経営学研究科 准教授 著書:ふるさと納税の理論と実践 (地方創生シリーズ) |