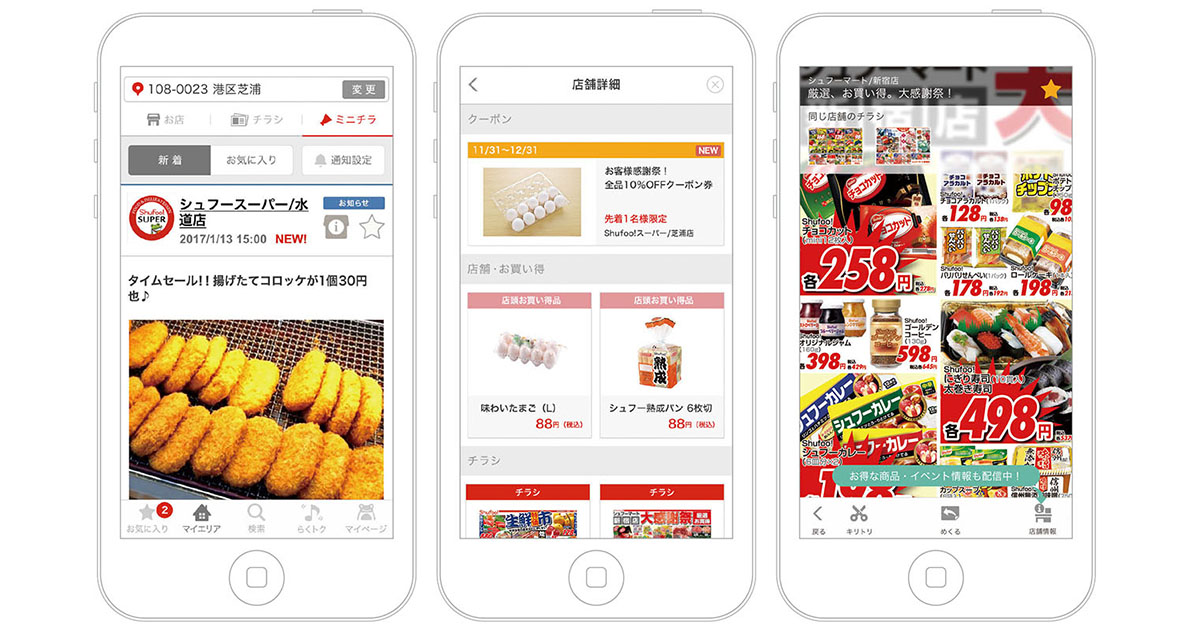購買と同時に得られるデータ、それをうまく消費者へ還元することが、顧客維持の明暗を分ける──。オイシックス・ラ・大地の奥谷孝司氏に、データ時代における、顧客とのダイレクトなコミュニケーションのあり方を聞いた。

オイシックス・ラ・大地 執行役員 Chief Omni-Channel Officer
奥谷孝司(おくたに・たかし)氏
1997年良品計画入社。店舗経験後、ドイツ駐在。帰国後、「World MUJI企画」運営、企画デザイン室立ち上げ。05年、衣料雑貨カテゴリーマネージャー、10年、WEB事業部長を歴任。「MUJI passport」をプロデュースする。15年10月より現職。15年4月から日本マーケティング学会常任理事を務める。
現代のデータマーケはサブちゃんにも及ばない
ダイレクトメールを送る際、顧客データをもとにしますが、こうした顧客データを、どう顧客に還元するか。消費者と直にコミュニケーションする際の大切な論点です。小売業は「利益還元」などと称してセールを開催しますが、そのデータ版です。
ふつうモノの売り買いは、モノを消費者に渡し、代金をいただきます。そして同時にデータもやりとりしています。消費者は、商品の対価を渡すだけでなく、データも渡している。
従来うやむやだったデータのやり取りには、消費者も気づいています。年齢や性別、住所、Webの閲覧履歴、購買履歴、数々のデータを提供している。それはきちんと消費者に還元するべきではないでしょうか。
データの還元は、何もいまに始まったことではありません。たとえばインターネットのない時代。『サザエさん』に出てくる三河屋のサブちゃんは、お得意の磯野家の台所について深く知っています。御用を聞いて、あれが必要だろうと想像をめぐらせ、「これはいかがですか」と提案する。それがサービスでした。昔から獲得した個人データは還元されていたのです。
ところがいまは、サザエさんが「そういえばみりんも切れそうだったかしら。まだあるわね。今度でいいわ」と言ったのに、行く先々で物陰からサブちゃんが現れ、「みりんです!」「みりんです!」「みりんです!」とアピールしてくる。
つまり、商品ページの訪問者を追いかけるターゲティング広告です。買ってないならまだしも、買ってても出てきますから、サブちゃんの細やかさには到底及びません。
「商品ページに来たことしかわからないのだから仕方ない」というのはもっともでしょう。そこで課題として、「顧客理解のためのデータ不足」が浮かびます。
「データはあるが適切に活用できていない」のかもしれません。アウトプット=消費者への還元の理想は、ふと届いたダイレクトメールがとっても助かる内容だった、というもの。そんなアウトプットのためには、やはり顧客理解が不可欠になります。
では、顧客理解とはそもそもどういうものでしょうか。
同時多発的ニーズはIoTデバイスが理解の鍵
「たまには夫婦で映画でも見たいね」「子どもどうしよう」「チケットは先にネットで取るか」「ベビーシッターっていまから頼めるかな」「ガソリン入れたのいつだ」「お義母さんに頼むか」「駐車場空きあるかな」「夕飯はどうしよう」「お金が足りないかも」「駐車場ないな」「ガソリン」「ワインも飲みたいな」「お金」「代行頼むか」──てんでバラバラの思考のようですが、人はふつう、ひとつのことだけを一から十まで考えるのでなく、同時多発的にいくつかの物事を進めるものです。
一般にカスタマージャーニー(顧客時間)はこのように重層的です。もっと関係のない思考がはさまってくることもあるでしょう。
重層化した顧客時間を想像だけで構築するのは不可能ですが、把握できる環境は広がっています。クルマがインターネットにつながれば、移動情報についてはわかります。スニーカーや体重計からは、運動や健康状態がわかるかもしれません。
「ネスカフェアンバサダー」のようなサブスクリプションサービスからは、1日に何人がどれくらいコーヒーを飲んでいるかもわかる。
まず重要なのは、こうした種々のデータに横串をさし、横断的に活用できるようにすることです。どんなメーカーでも、すべてに情報接点を設けることはできませんから、自社で得られるもの、他社が収集しているものと連携すべきです。
擬似的にネットにつなげるというのは、見た目ほどむずかしくないものです。ダイレクトメールに2次元コードを印刷してアクセスしてもらうことも、その一端です。そういう実装からやっていくべきでしょう。
売れた、で終わりにせず、どのように使われているのかを把握することは、重層化する顧客時間を理解する上で強い味方となります。種々のコミュニケーションの接点でデータが取れないことは、すなわち消費者の商品への関与(エンゲージメント)をわからないままにすることを意味します。これは、新規獲得型から顧客維持型にマーケティングが移行する過程で、企業の成長に大きな差となるはずです。
発達したマーケティングは顧客の意思と区別ができない
データを見る際に陥りやすいのは、「そんなの知ってる症候群」です。「なんだ、結局知ってることを出してるだけじゃないか」というのは、すでにデータの見方に誤りがあるおそれがあります。
経験で得られていることを追認する作業には意味がありません。知ってる、知ってるではなく、もしかして本当はこうなんじゃないかと思ってデータを見る。異常値を見つけないといけない。
不都合な事実を取り入れると、既存の信念を書き換えねばならなくなることもあります。それはあまり気分のよいものではないかもしれません。しかしデータを用いて戦略を立てるのなら、ときには従来の考えを捨てる勇気を持つことも重要です。
データの還元のゴールは、顧客が解決せねばならないが、まだ認識していない課題を可視化することにあります。その課題を発見するために、データが不可欠だということです。
顧客理解が進むと、ほどよい距離感というものも見えてきます。ロイヤルティが高いことがわかっていれば、金銭的なインセンティブでなく、イベントに招待する、未発売の商品を内緒で送る、そういう手立てのほうが見合うこともわかる。
それは直近の売り上げだけでなく、顧客の商品への関与(エンゲージメント)を築くことにつながります。
SF作家アーサー・C・クラークに「十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」という言葉があります。言い換えると、「十分に発達したマーケティングは、顧客の意思と区別がつかない」ということかもしれません。顧客が解決する必要のある課題を発見すると、究極的には、自分の意思で買っているように思えるものではないでしょうか。
企業の壁を超えたデータの連携は、実務上の必要から、5年か、10年かで実現されるでしょう。そのときに大事なのは、企業から顧客へのアプローチ手段──メッセージアプリかEメールか、ダイレクトメールか──そういったメディアの形態もふくめて、顧客へのサービスであることではないかと思います。
[第33回 全日本DM大賞]DM応募受付中!締切は10月31日

実際に発送されたダイレクトメール(DM)を戦略性、クリエイティブ、実施効果の3つの観点から評価し、優れたDMを顕彰する「第33回 全日本DM大賞」の応募を受け付けています。オフィシャルサイト(http://www.dm-award.jp)よりご応募ください。
お問い合わせ
全日本DM大賞事務局(株式会社宣伝会議内)
Tel. 03-3475-7668
E-mail. info.dm-award.jp