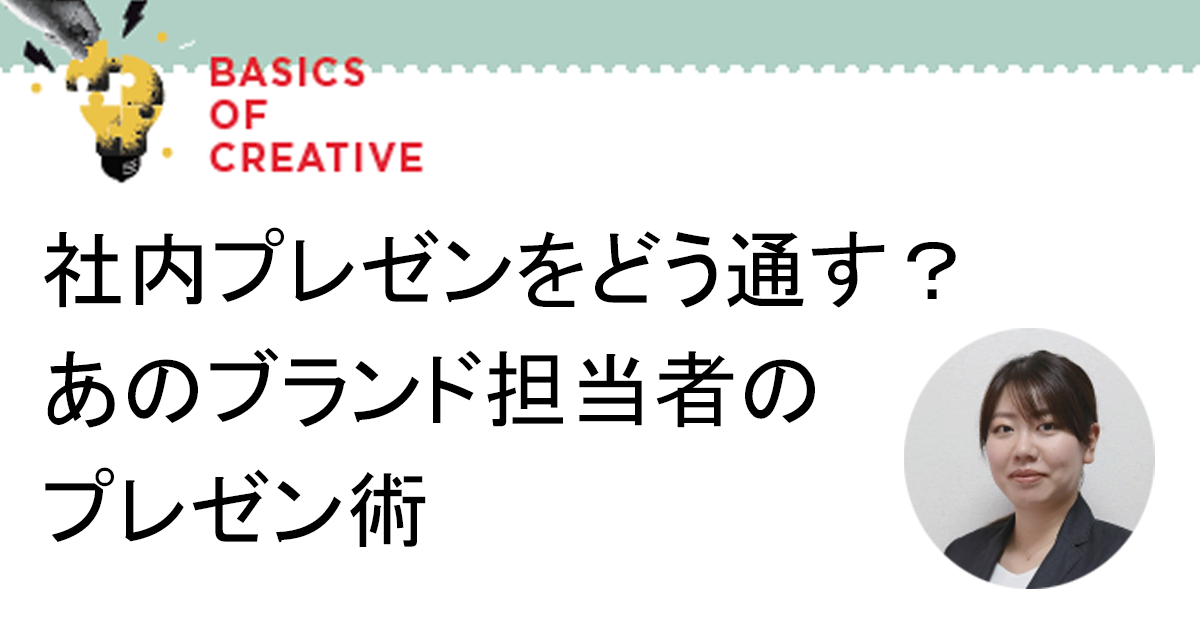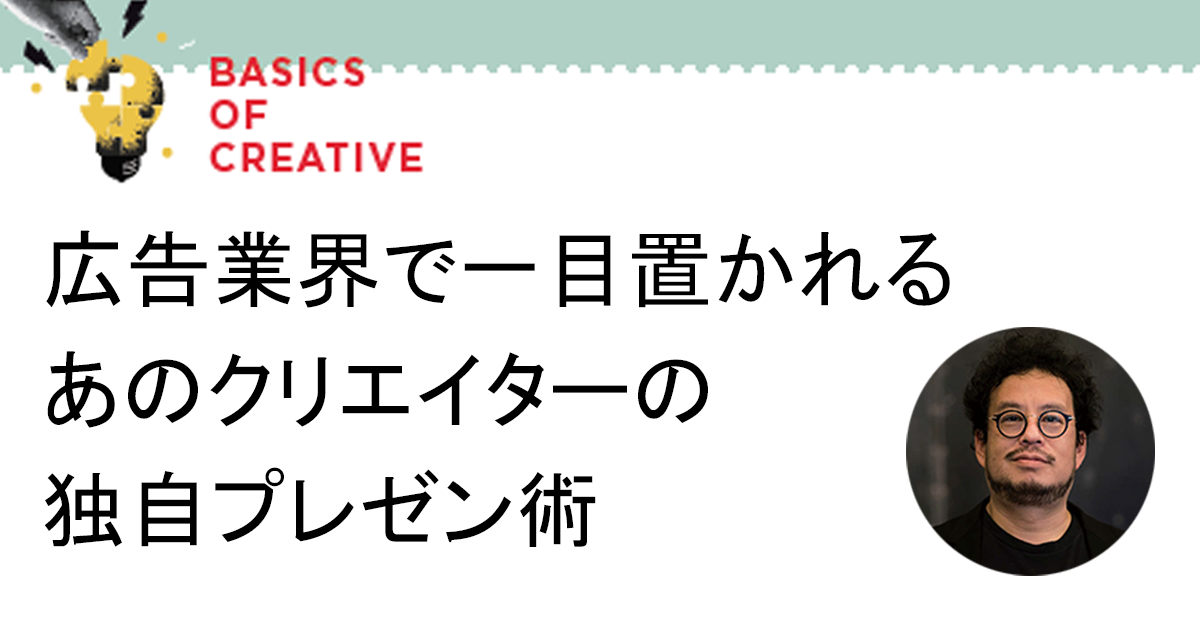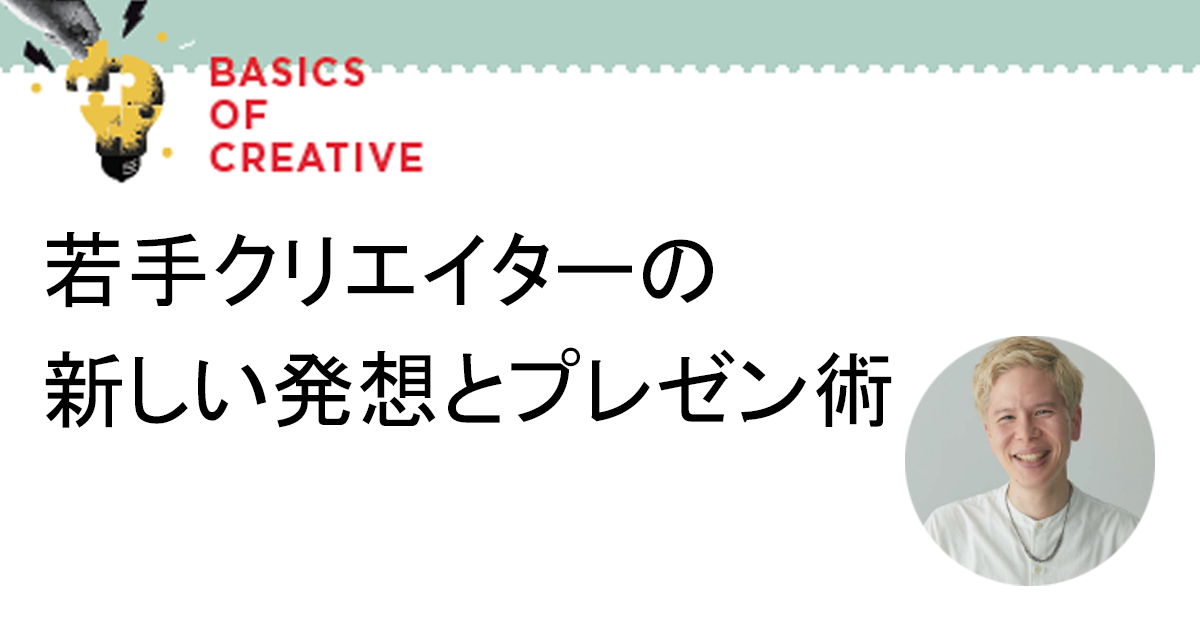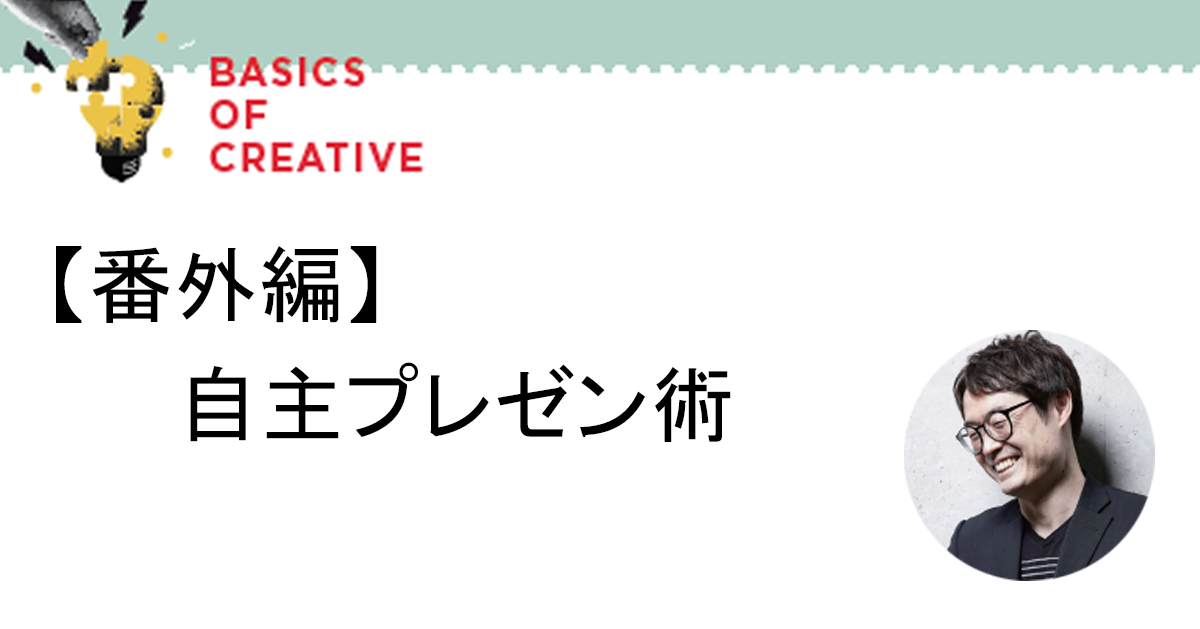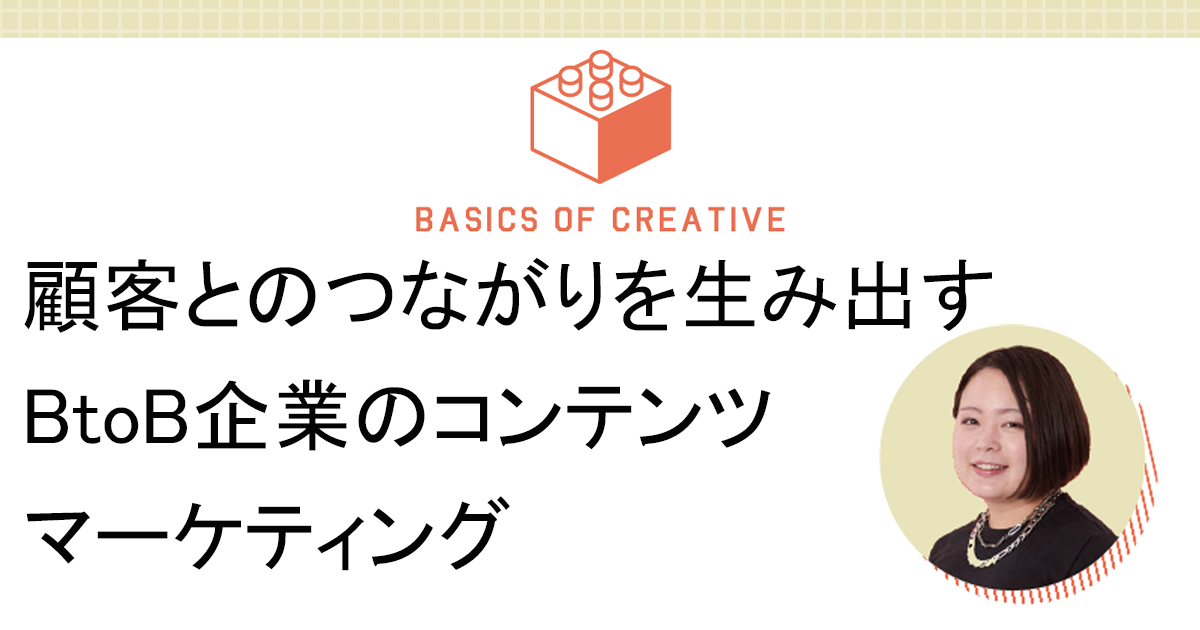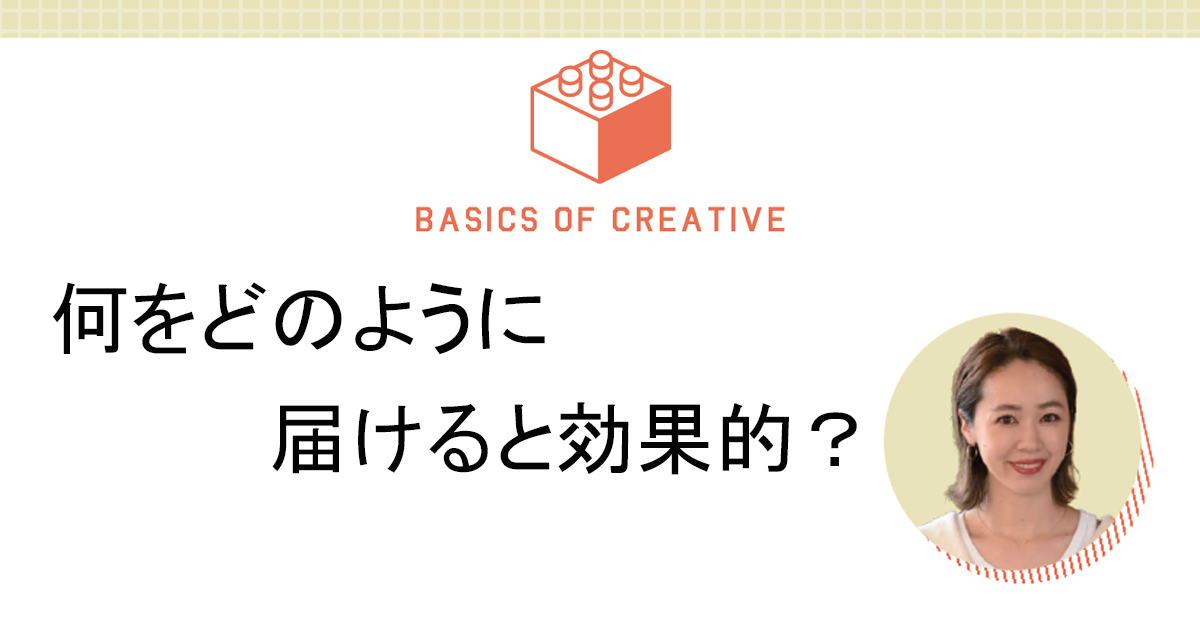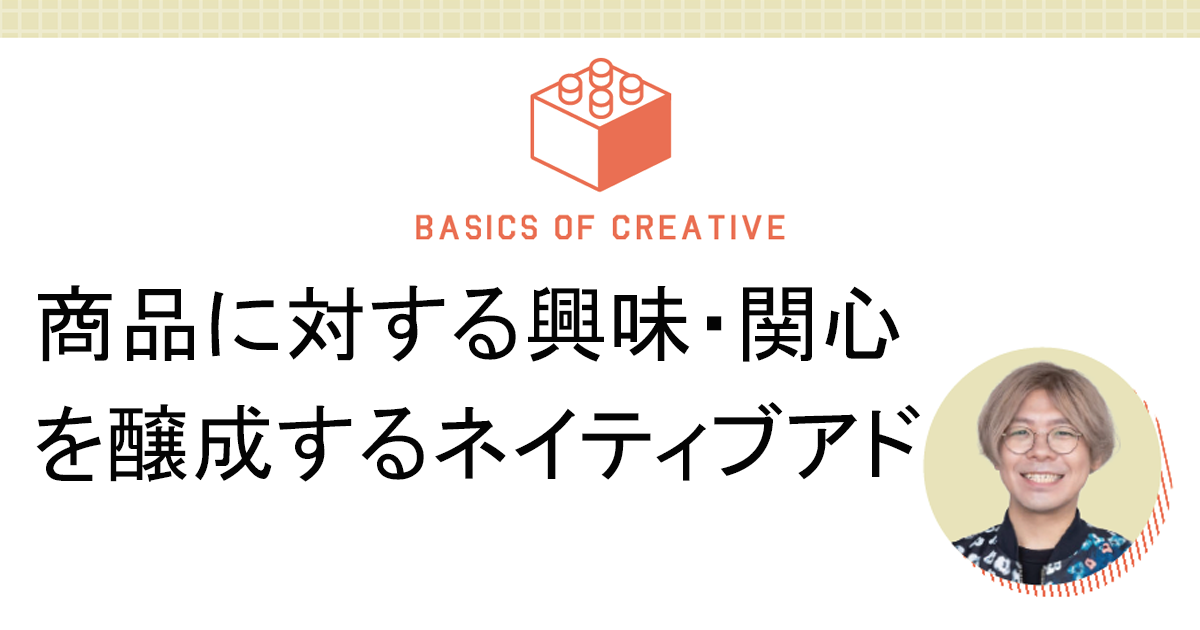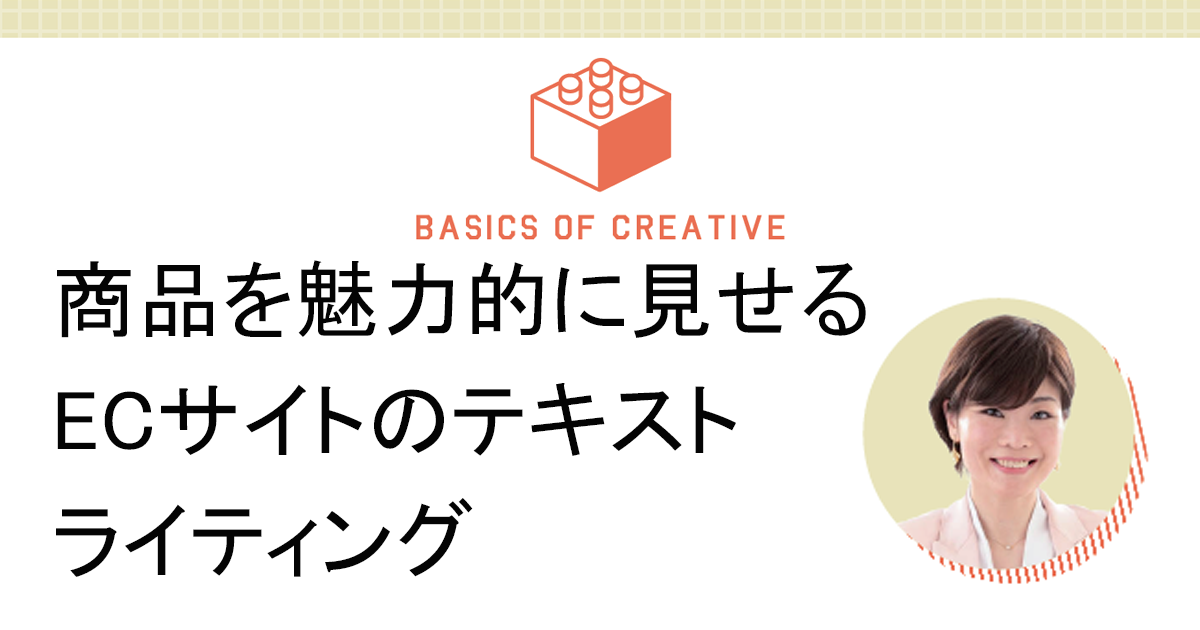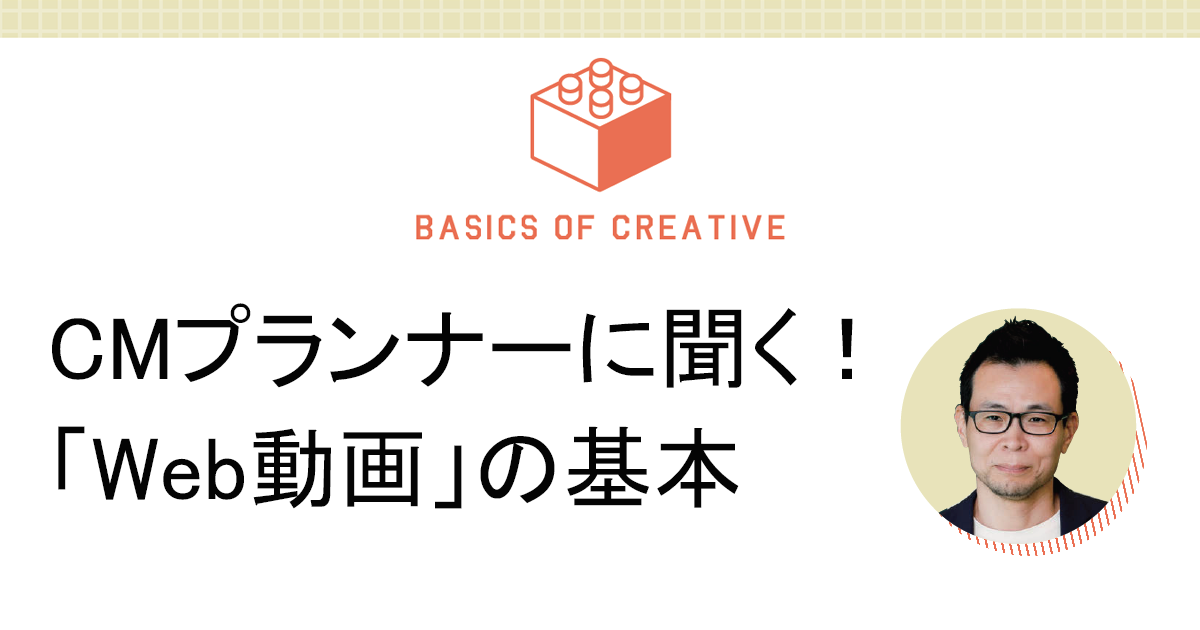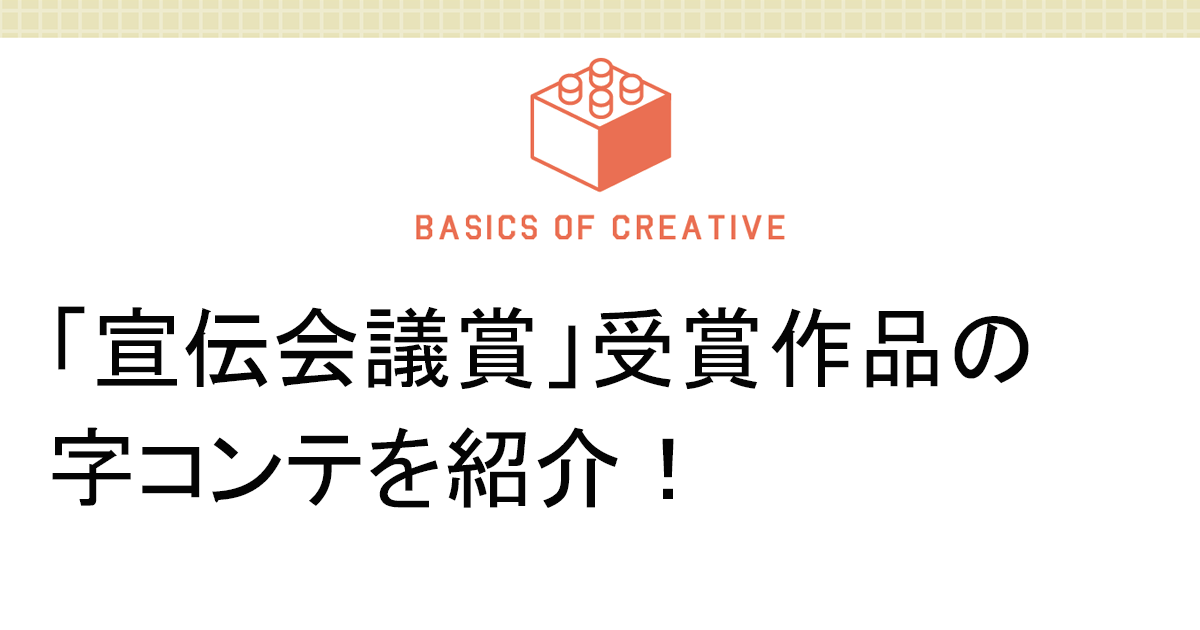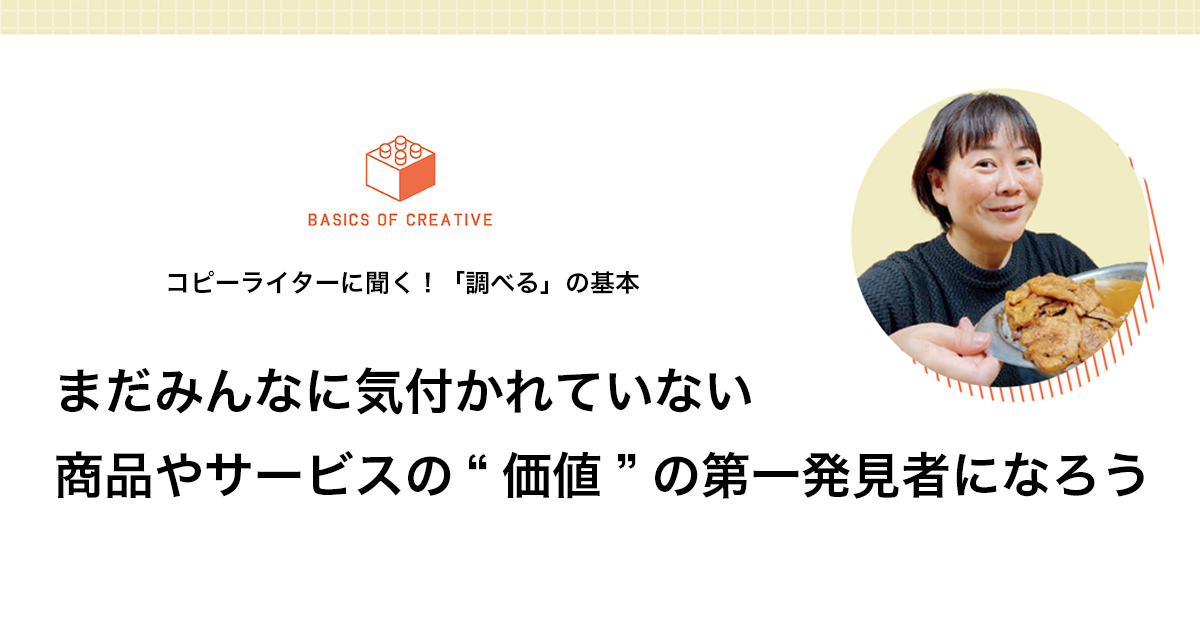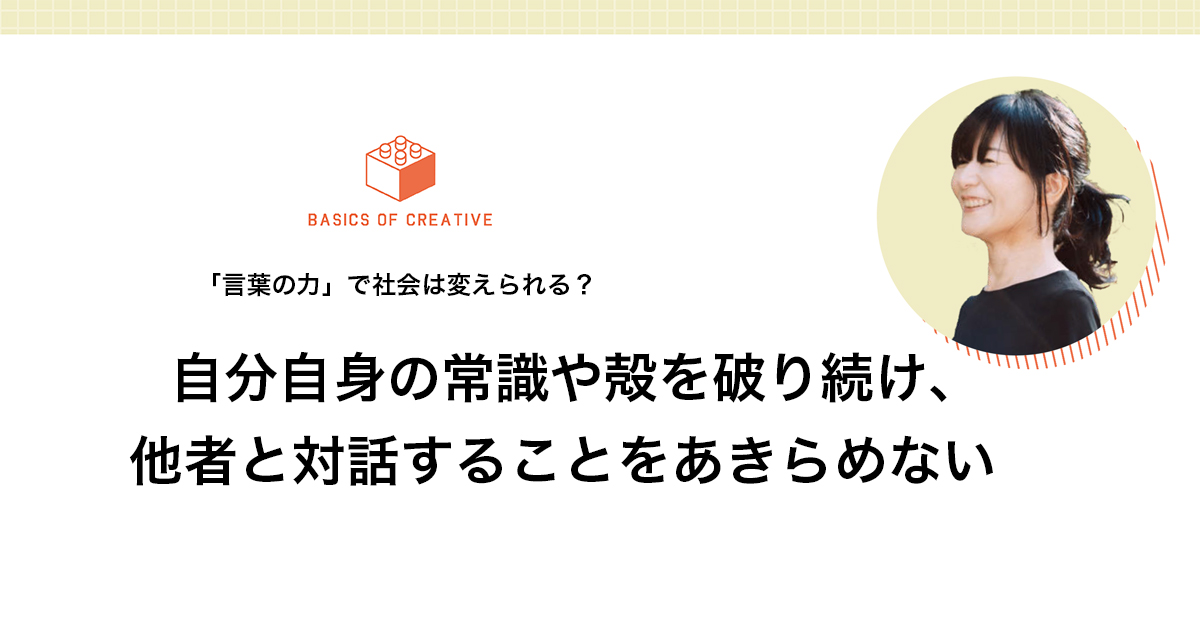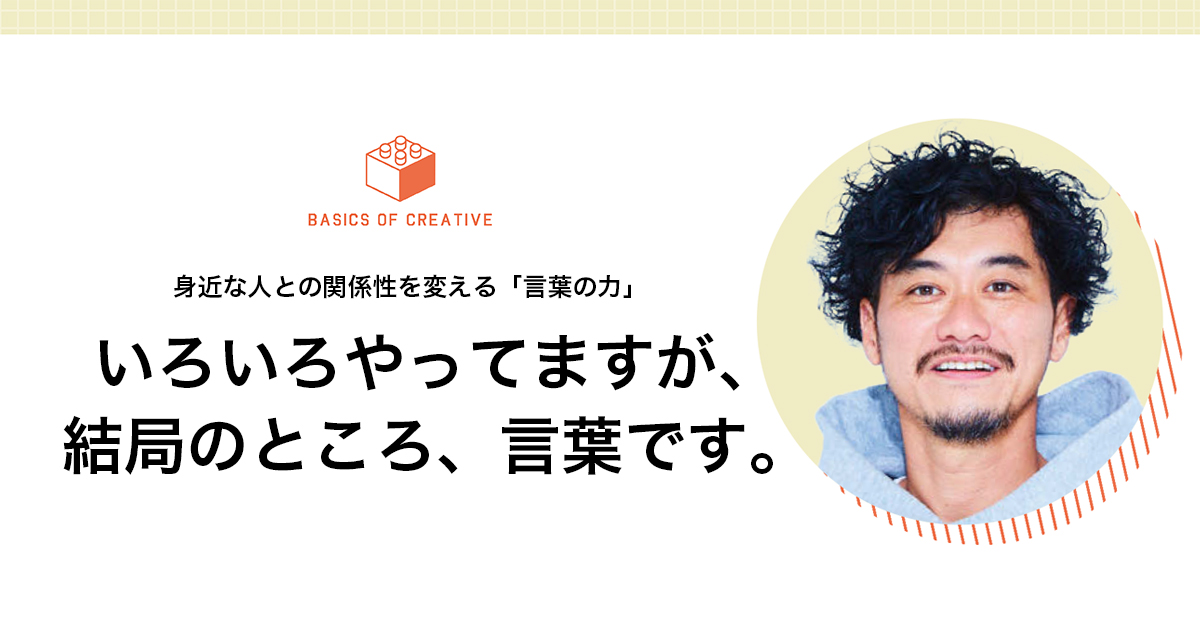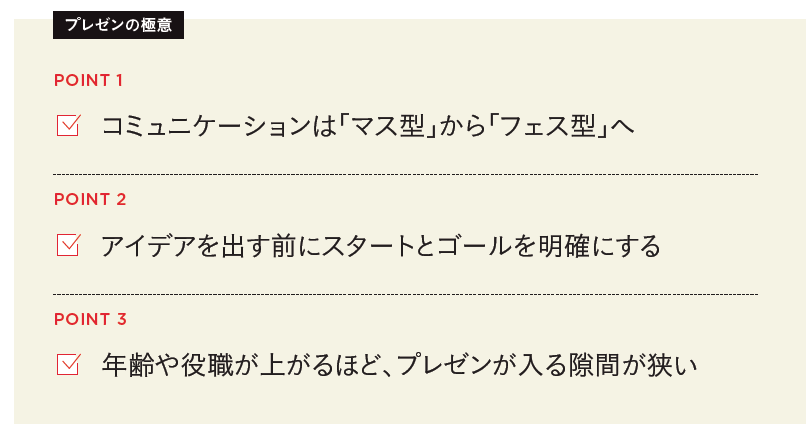
LINEやメールで提案も 進化するプレゼンの方法論
プレゼンまでの大まかな流れは、「オリエンで出た課題を問い直す・課題設定→ゴール設定→アイデア出し・クリエイティブ制作」です。時間がない時は、僕がコンセプトやストーリーなどを考えて、メンバーに肉付けをしてもらいます。時間があれば、方向性を出したあとみんなからアイデアを集めて2、3回の打ち合わせをし、早い段階で荒い企画書をまとめるようにしています。なぜならアイデアを企画書の形に当てはめてみるとアイデアの良し悪しや、骨組みができているかどうかが見えるからです。そのあとブラッシュアップをしつつ、提案前にひと目で伝わる企画書になっているかをチェックするというのが流れです。
僕がプレゼン案をつくる時によくやるのが、企画内容を3分の映像にするという想定でプレゼンのナレーションを書くことです。これは企画書の骨組みそのものですが、この内容が伝わらなければ、骨組み自体にぶれがあるということなので見直していきます。基本的に骨子が3分ぐらいでまとまるプレゼンじゃないと伝わらないとも考えています。
企画を理解してもらう上で、最大のポイントは発信者側が「伝える」のではなく、「伝わる」意識を持つことです。もちろん内容や言葉の選定もそうですが、相手の年齢が高い場合は、文字が小さいと伝わりません。「見えない」と思った瞬間にどんなに良い案でもムッとなってしまう。細かいですが、僕はプレゼン場所のモニターのサイズまで聞き、サイズに問題があれば、モニターを持ち込んだり、紙に出力したりもします。
プレゼンでは、「伝えたい側の理屈や言いたいことを全部伝える」ということをやりがち...