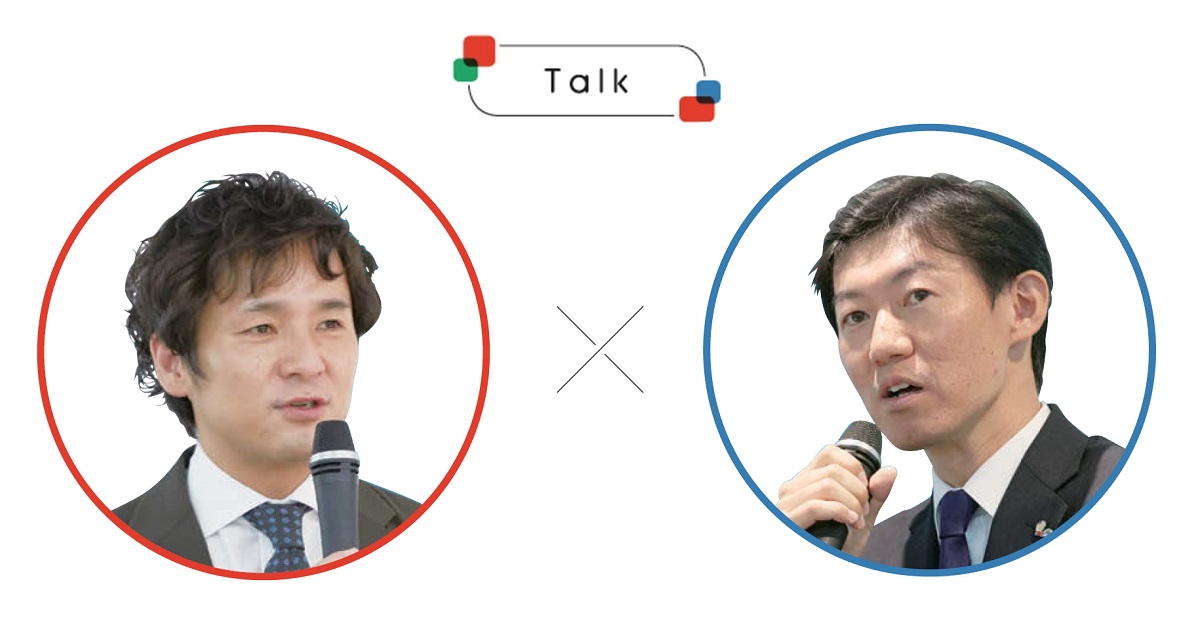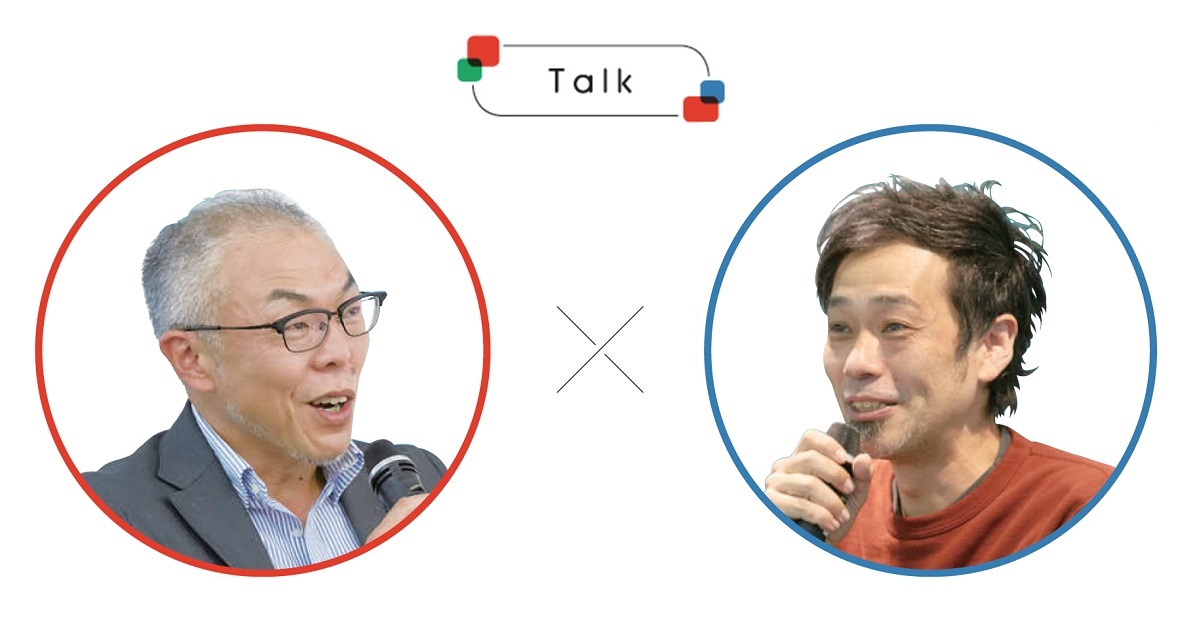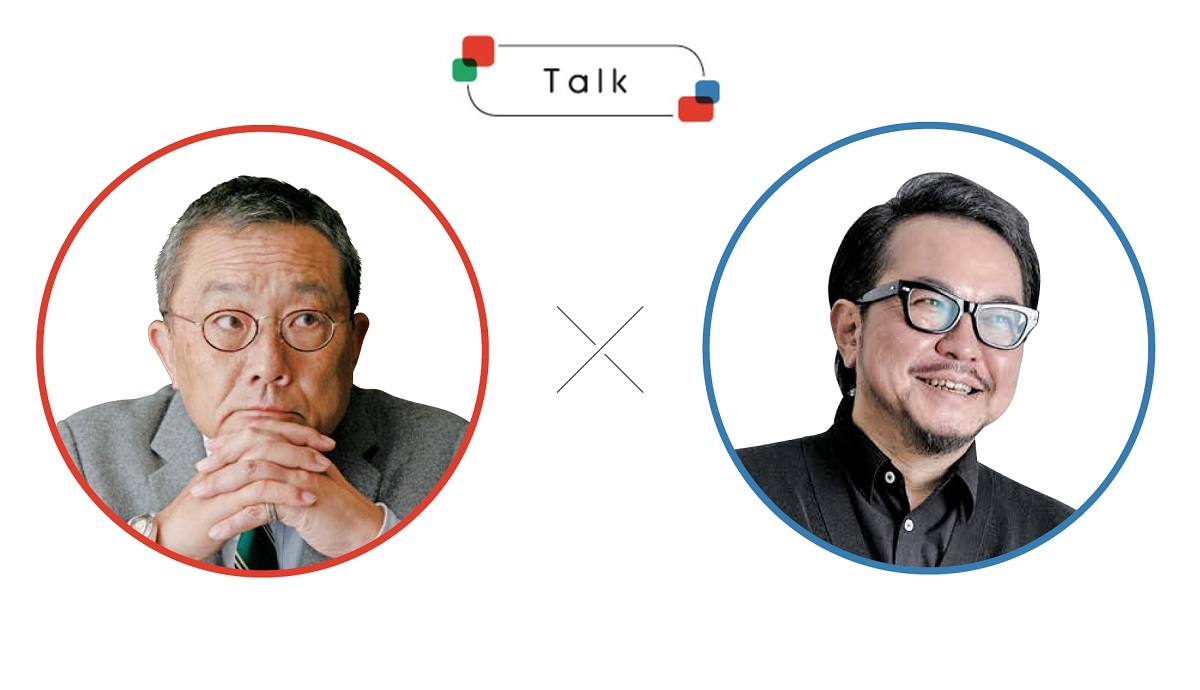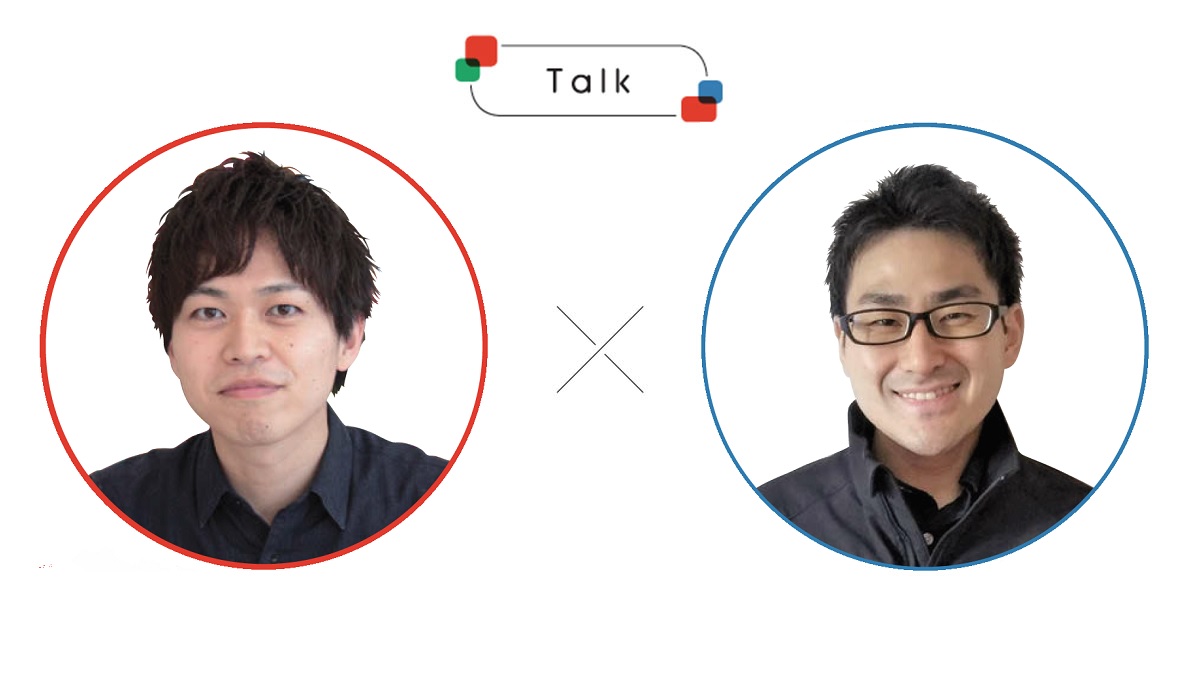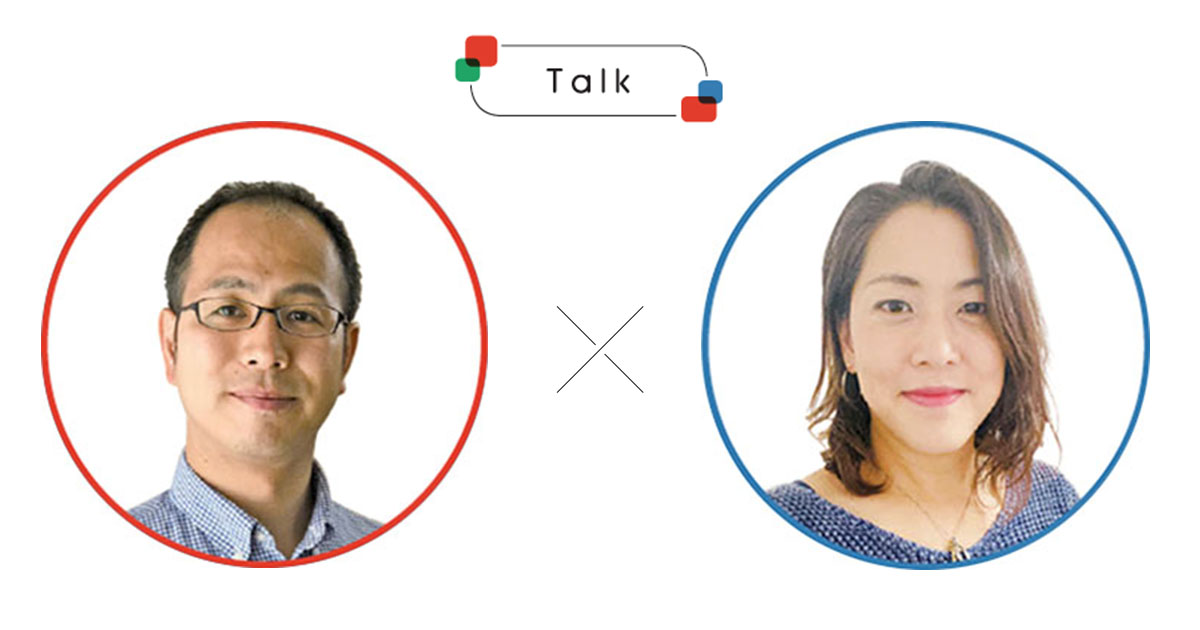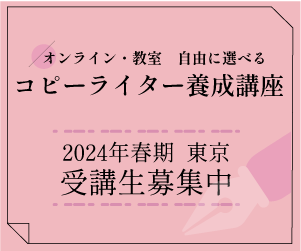人々の嗜好性の多様化に伴い、企業が世に送り出す広告クリエイティブの評価・判断はますます難しくなっている。しかし効率だけでなく、効果を考えれば、クリエイティブジャンプの余白をいかに残せるかは重要な要素と言える。テレビCMの黄金時代をつくったレジェンドともいえる杉山恒太郎氏と、クリエイティブディレクターの原野守弘氏が議論する。
「名物宣伝部長」はなぜ消えた? AIとデータがもたらす危うさ
──以前は「名物宣伝部長」と呼ばれる方が複数名いました。しかし、宣伝部も人事ローテションの対象となり、3~5年で宣伝部長が変わっていく今の環境においては、特にクリエイティブのジャッジが難しくなっているのではないかと感じます。
杉山:失敗しないものを選びたい!それはそれでいいんだけれど、データを使って精緻に予測しようとすればするほど、結果的に全員が同じ答えを選ぶことになりかねない。今のAIとビッグデータのジレンマって、そこにあるんじゃないかと思う。
これは、僕の後輩の山口周がよく主張していることなんだけど、ビックデータやAIを使ってぐるぐると解析し続けると、どこからでも正解が出てきてしまうんだ、と。そうなると、もはや正解というものにほとんど意味がなくなってしまうというのが彼の主張で。僕もなるほどその通りだな、と思うんだよね。
──データをもって予測をし、失敗しない方を選びたいという方向に向かっているとするならば、その背後に何かしらの組織的な課題があるのでしょうか。
杉山:以前は、宣伝部というのは社長の脇にいるような組織だった。だからこそ、大きな決断ができたと言えるかもしれない。
加えて、名物宣伝部長と言われた人たちは、企画を見る前に人選びに時間をかけていたと思うよ。クリエイターを選ぶ際には、まずは面談を行って、その人のフィロソフィーや商品に対する考え方をじっくりと聞く。つまり、面談自体がすでに競合プレゼンになっていた。そうして「彼に決めた」となった時点で、選んだ側の肚はもう決まっている。それが名物宣伝部長の仕事の仕方だったわけです。
こういう風にして仕事が決まると、選ばれた側にも強い責任感が生まれた。「選ばれたからには、変なものはつくれない」という緊張感の中で、お互いが向き合っていたよね。
それからもうひとつ。データというものにはトリックがあるんだよね。データはすべて、過去のものでできている。考えてみると過去をもとに未来を決める方が、よほどリスクがあることに気づかなければいけない。その認識がないまま、データにおんぶに抱っこしてしまうのは、かなり恐ろしいことだと思うけど。
原野:広告クリエイティブがよく話題になる、某企業のオーナー経営者の方も、クリエイティブの統括者を選ぶ時に面談をしているという話を聞きました。そして、そこで「君の企画やアイデアには興味がない。君の“社会の見立て”が知りたいんだ」と言われた、と。僕はこの「社会の見立て」こそがクリエイターに求められることだと思うんですよね。
AIが苦手なのは、問いを自ら考えること。AIやビックデータが駆使される時代には、問題への正解を出すことではなく“どんな問題を立てるのか”に価値があるのではないでしょうか。
そしておそらく、名物宣伝部長や杉山さんのような伝説のクリエイターというのは、「問題の立て方」の達人だったのではないかと思います。
杉山:僕がいろんな企業のセミナーに呼ばれていつも話すのは「もうソリューションというのは終わっている」ということ。
これからは問題解決ではなく問題 “開発” なんだよ、と。じゃあ、どうやったら問題ってつくれるんだろうか? というのが次の大事なテーマになる。
原野:その部分が、社会の見立てと関係があると思うんです。かつてかかわった「日本は、義理チョコをやめよう。」というゴディバのキャンペーンは反響があった。なぜあのキャンペーンを実現できたかといえば、僕の中に日本のジェンダー・イクオリティへの問題意識があったからです。
広告を「社会の見立て」「問題」「答え」という3層構造で見た時、今の日本の広告は社会への見立ての部分が弱いと感じる。同じ問題を立てて同じ解き方をしているから、同じ答えになってしまうんですね。
理想と現実との「乖離」が豊かなテーマを生む
杉山:最近の広告は社会と向き合っていないものが増えている気がするよね。でも、それって、かなり虚しい。じゃあ、魅力的な問題をつくるってどういうことなの?て言ったら、やっぱり「今の時代とどうやって対峙しているか?」なんだよね。
あとは、自分自身の理想があるかどうか。これは夢といってもいいんだけれども“こうあって欲しい”とか“こうありたい”という理想と、目の前の現実の...