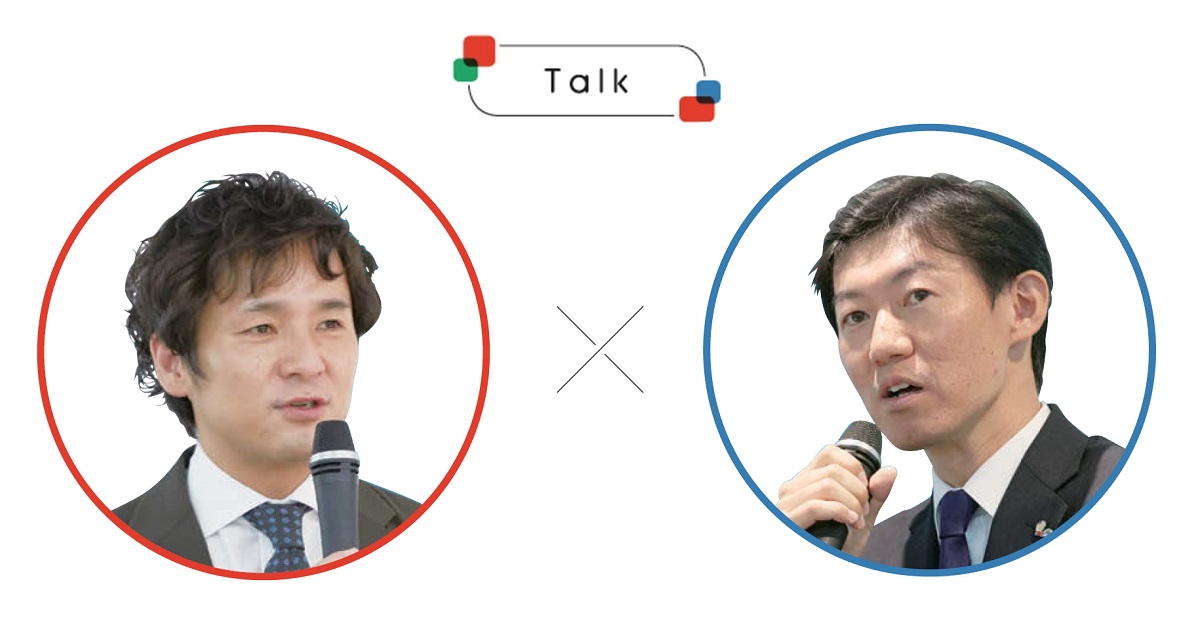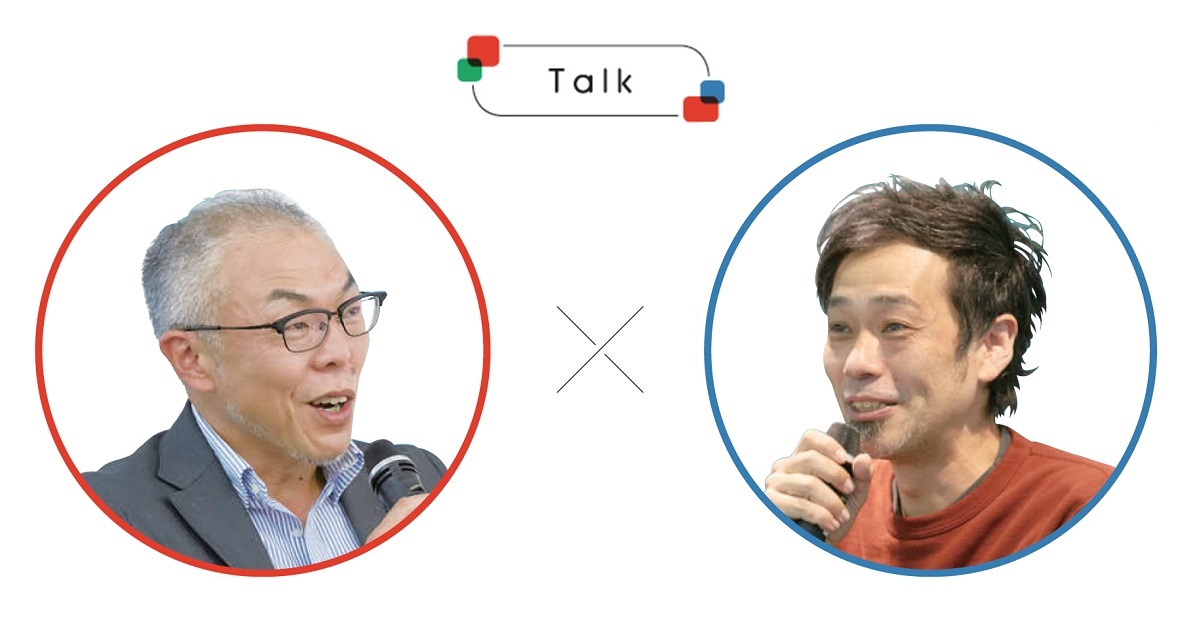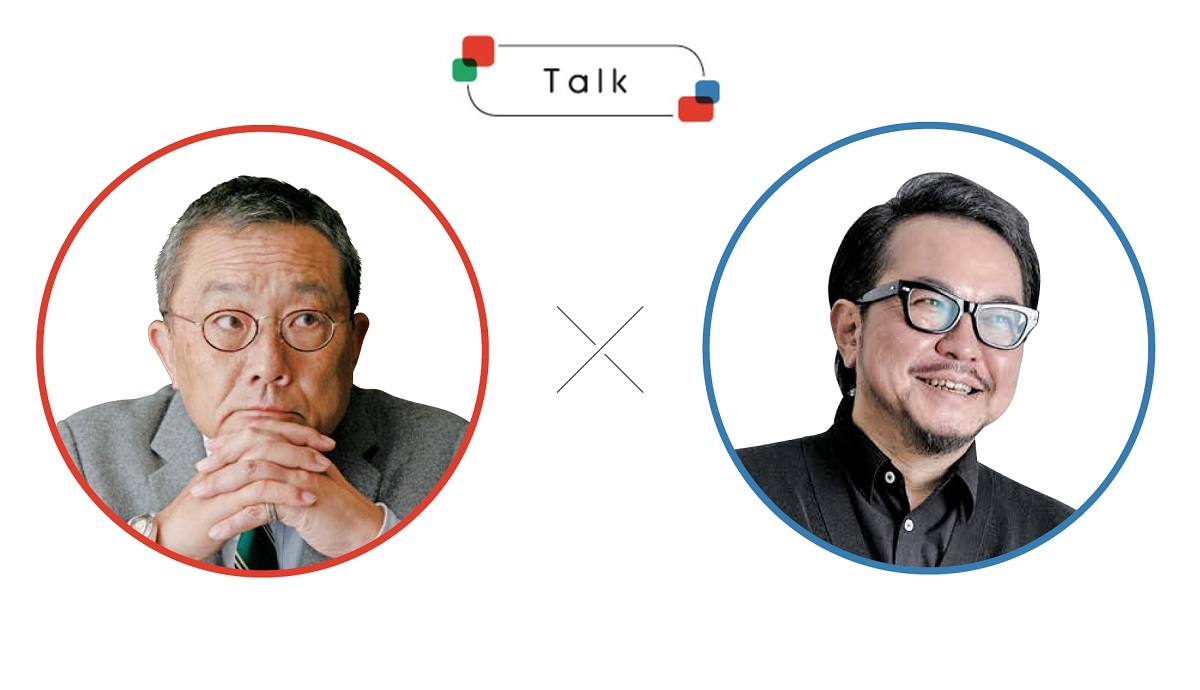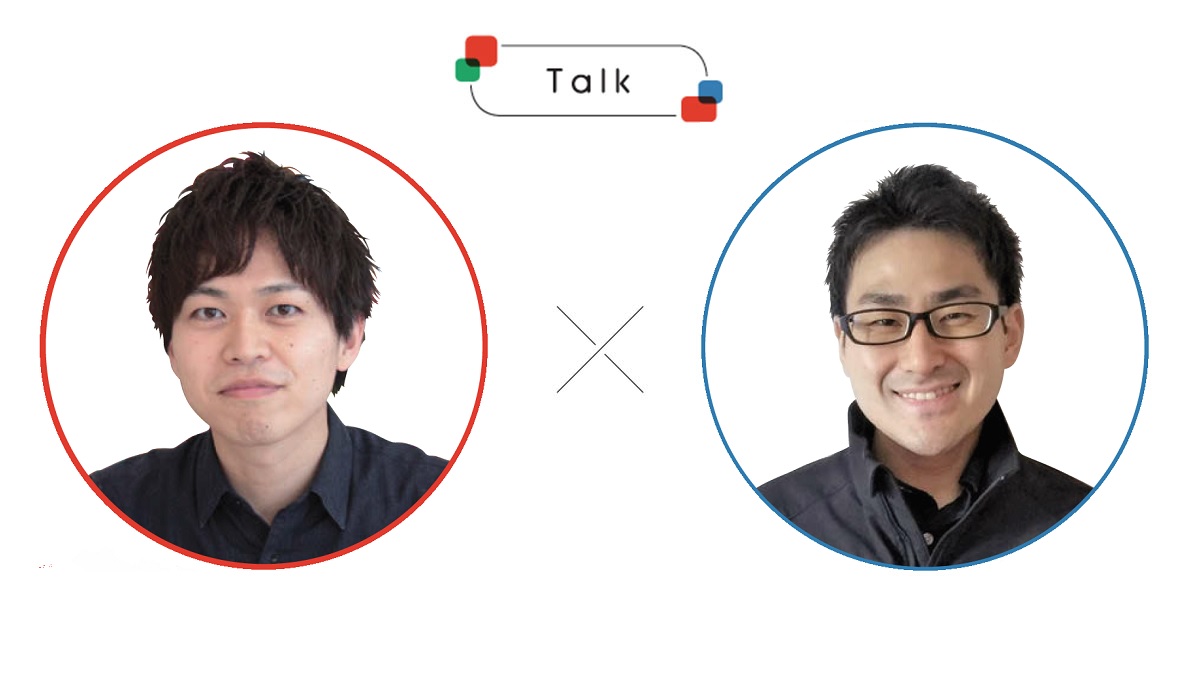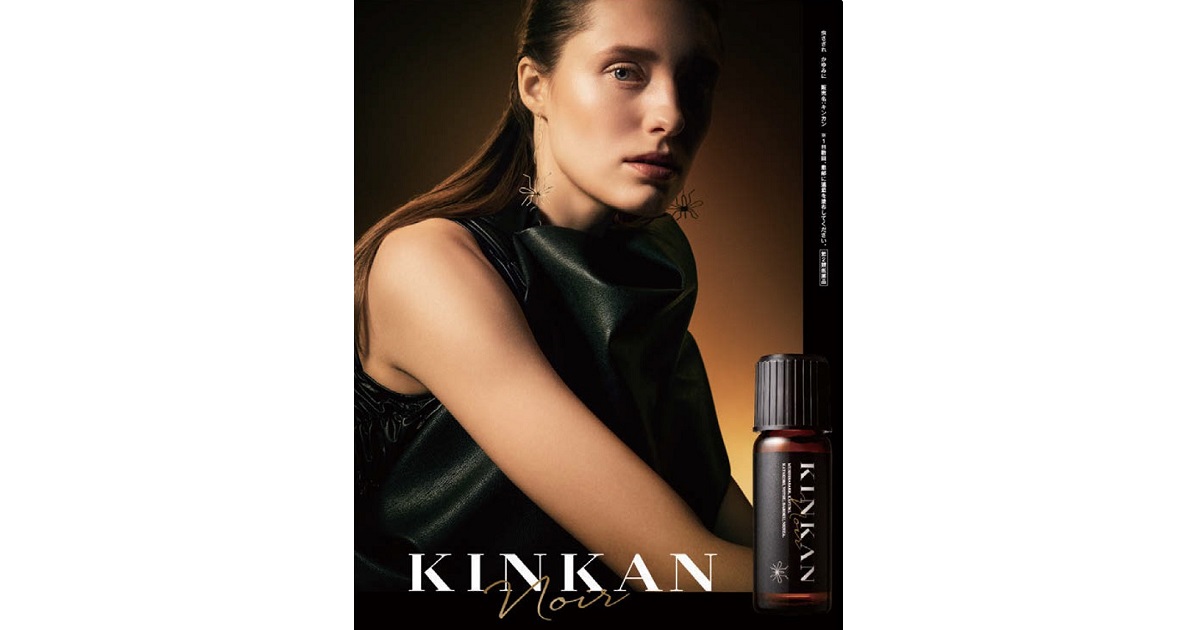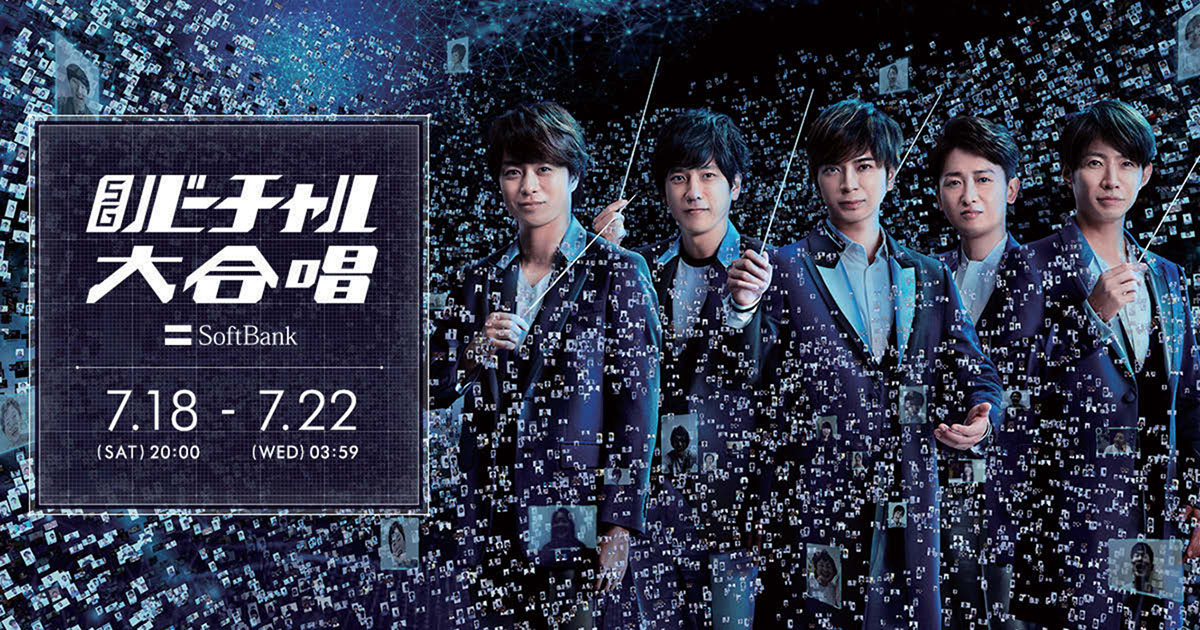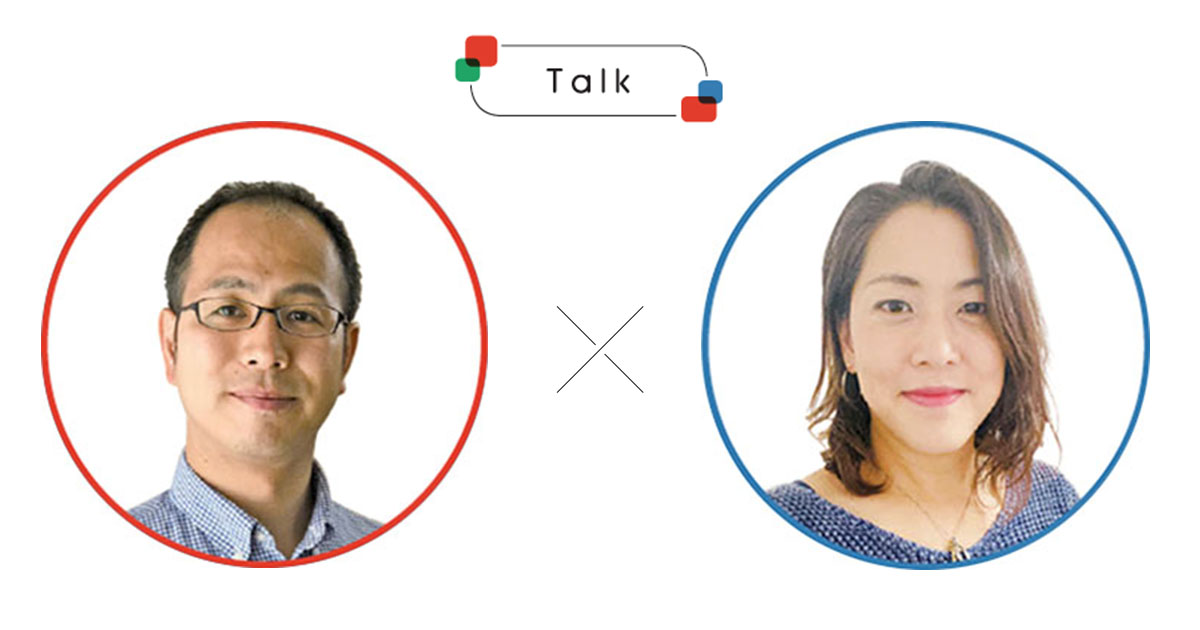過去に効果を出してきた鉄板施策と、柔軟な発想が生み出すチャレンジ施策。若手マーケターたちは、両者をどのように捉えているのか。また、新たな時代に必要とされるマーケティング・コミュニケーションとは。カルビーとピップという長い歴史を持つ企業に属する、若手マーケターの2人に意見を聞いた。
鉄板とチャレンジ企画 それぞれのメリット、デメリット
──若手マーケターとして活躍されているお2人。まずは、現在の業務内容を教えてください。
松浦:私は現在ピップでスポーツライフブランドのブランドマネジャーを務めています。「プロ・フィッツ」というサポーターやテーピングなど、スポーツケア用品を扱うブランドを担当していて、ブランドの4P戦略の立案や現場のディレクションなどを行っています。
松井:私はカルビーのマーケティング本部に所属しており、コーポレートのPRや商品PRに関わっています。特定のブランドを担当しているわけではなく、商品PRについてブランドに横断的に関わっています。そこで現在は各商品担当と一緒に二人三脚でPR戦略を企画・実施しています。
──過去に効果を出してきた鉄板施策と新たな発想で行うチャレンジ施策。両者のメリットとデメリットをどう考えますか。
松浦:「プロ・フィッツ」は昨年リブランディングしたばかりのブランド。そのため、昨年は認知獲得を目的に、テレビCMなどの鉄板の手段を選択。マーケティング投資におけるテレビの配分を厚めに設計しました。1年たった現在も引き続き認知の獲得を優先事項として、Webにシフトして広告施策を実施しています。
マス広告のような鉄板施策は、これまでの実績から、投資に対するリターンが予測しやすいのがメリットだと思います。一方で、デメリットについては、これは鉄板施策というよりテレビCMに寄った話になるかもしれませんが、単価が高いだけに、頻繁にクリエイティブを変えるといった柔軟な対応ができず、それゆえどうしても堅実路線の表現に落ち着いてしまうところでしょうか。
それに対して、デジタルなどの新しい施策は低予算からテスト的にスタートできる反面、効果予測の難しさがあります。また、どう工夫したら話題になるのか、その方法論が確立されているわけではないので、チーム内で何度も打ち合わせする試行錯誤のプロセスも必要です。その結果、施策がハマれば良いですが、うまくいかないと骨折り損になりかねません。
とは言え、チーム内で知恵を出し合うので一体感が生まれ、新しいことに取り組む風土づくりにはつながると考えています。また、成功すれば低予算で爆発的な効果を生み出すことも可能で、それは効果の予測が難しいからこその、メリットかもしれませんね。
松井:松浦さんがおっしゃるように、確かにテレビCMは、投資効果をある程度は予測できますし、量販店や小売店にもインパクトを感じてもらいやすいです。お客さまや社内でも「あのCMの商品」と話題にしてもらいやすく、わかりやすさという面ではデジタルに勝っているのではないかと思います。
デジタルなどの新しい施策は、正解・不正解が読みづらいので、松浦さんと同様でパートナー企業と手を取り合い探りながら進めている状況です。ただ、デジタル施策はマス広告やイベントと違って成果がすぐに測定できるため、スタート時は効果が予測しづらくても、施策を走らせながら振り返りがしやすく、軌道修正を重ねつつ...