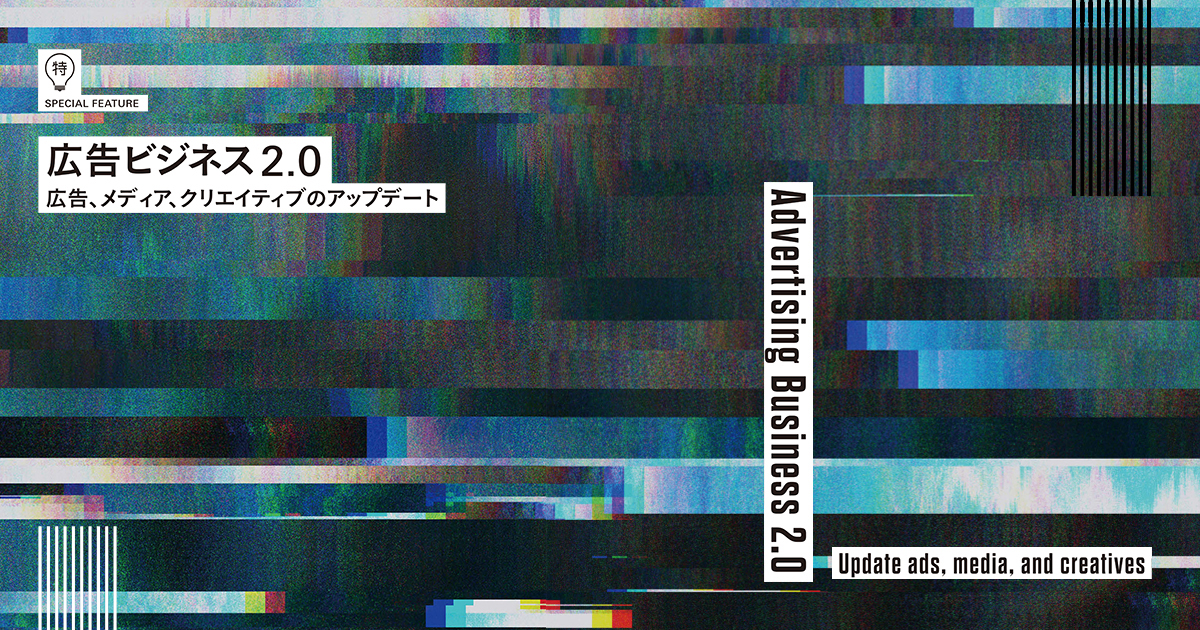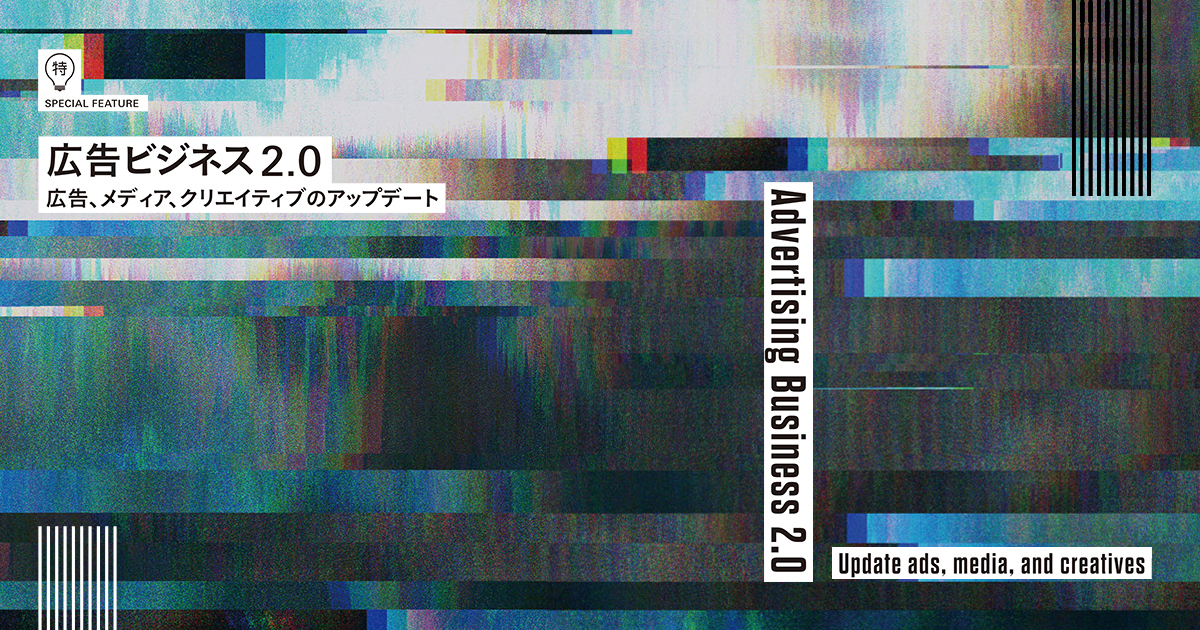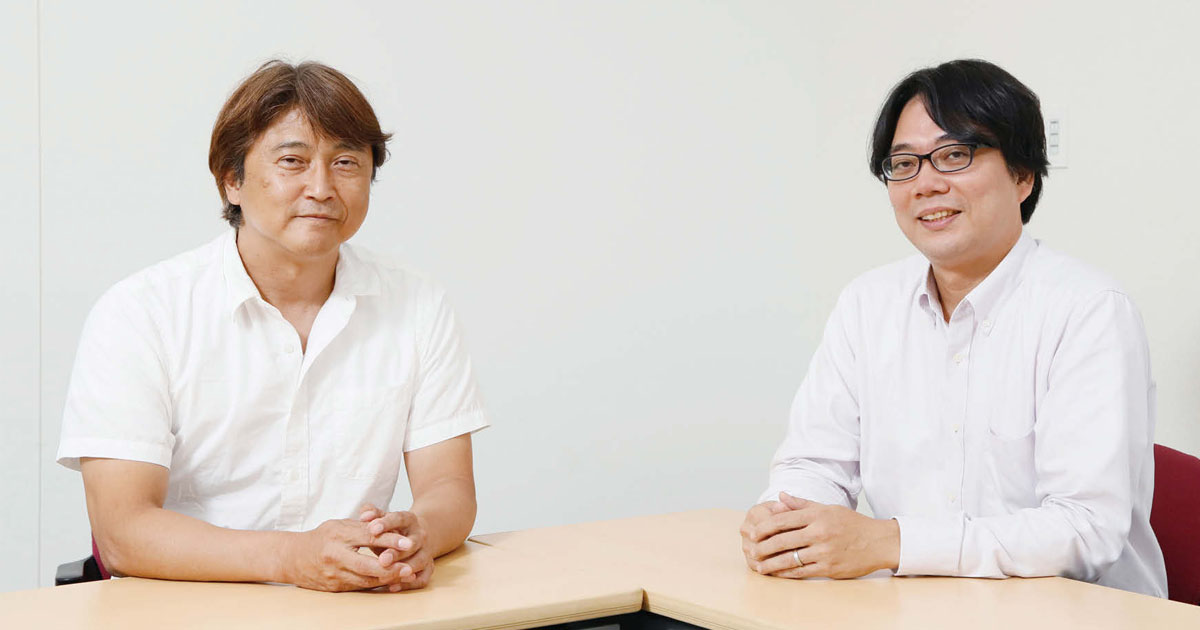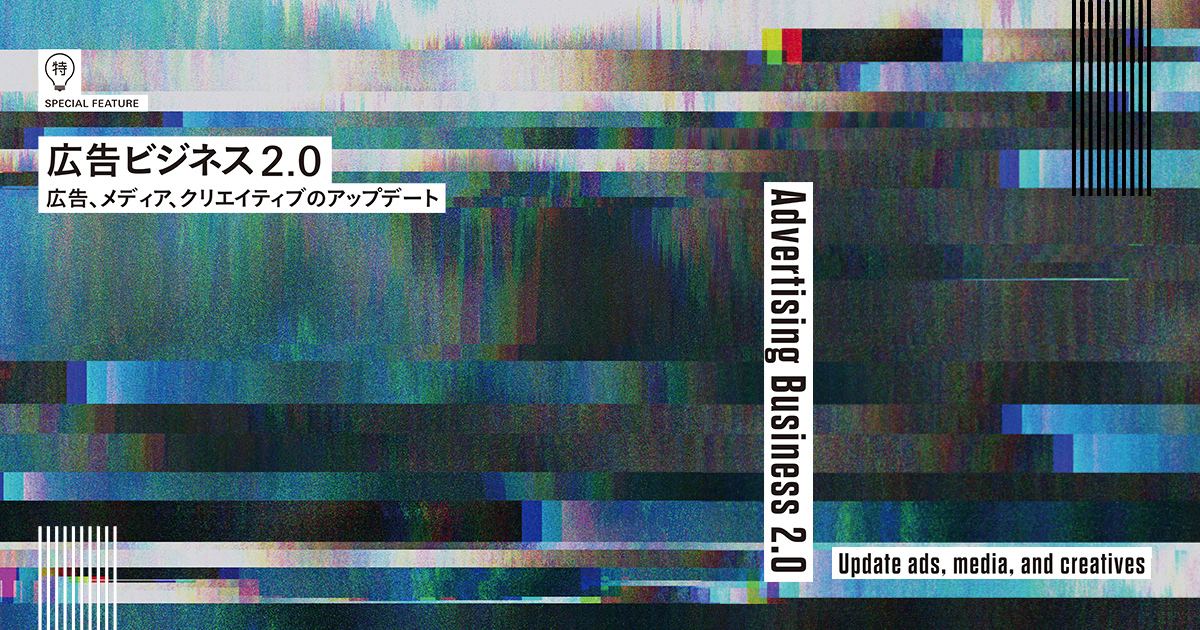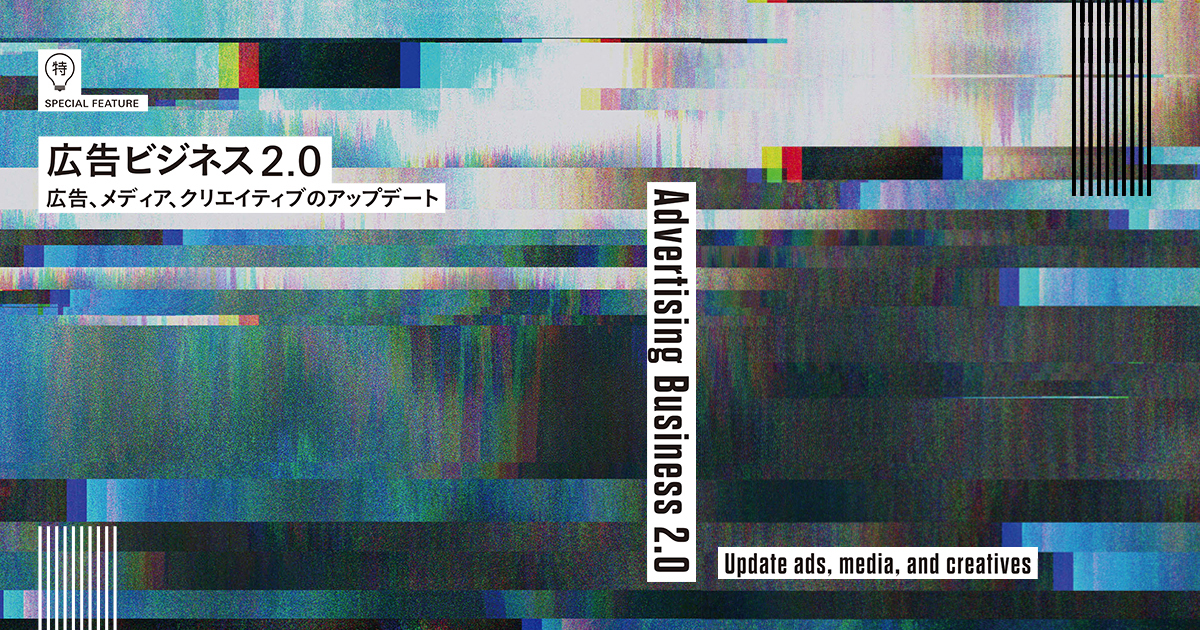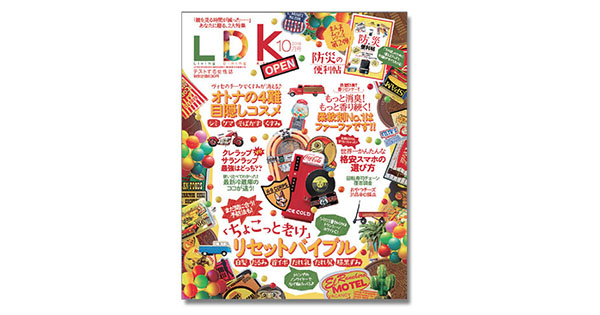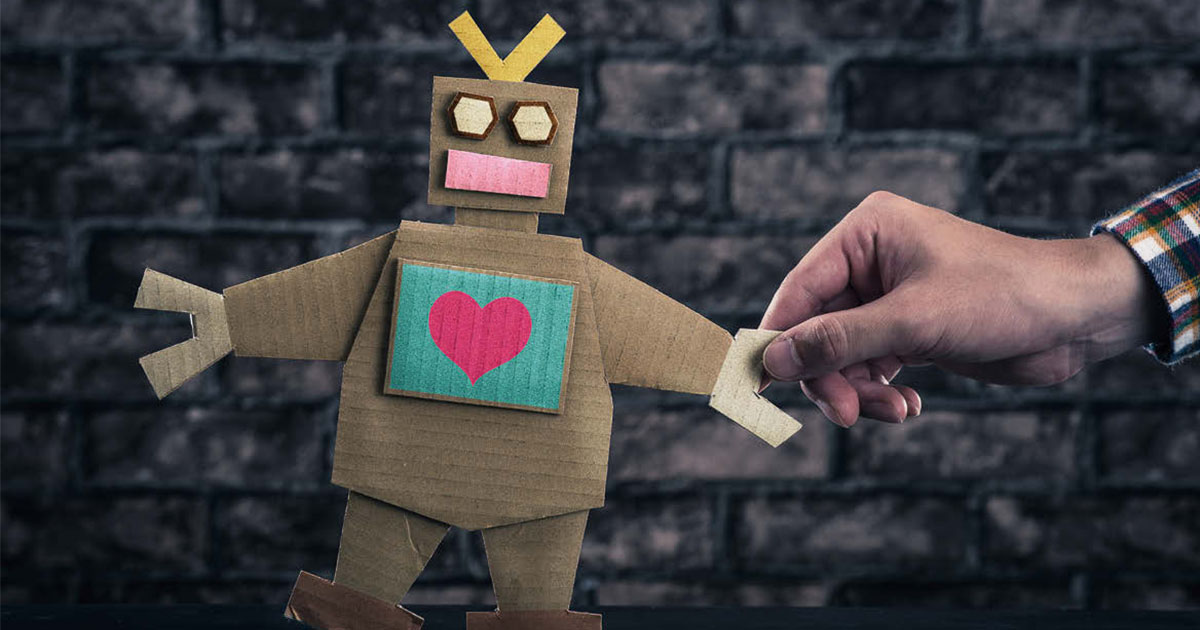デジタルシフトが叫ばれる中、既存のビジネスモデルに危機感を覚え、新たなビジネスモデルに向けたチャレンジが続く。デジタル時代におけるマスメディアの影響力やテレビのあり方はどのように変わっていくべきなのか。今後、予想されるデジタルシフトの揺り戻しなど時代の潮流も踏まえて、各局でマーケティングに携わる3人に話を聞く。

デジタルに流れる広告費 テレビ局のアプローチとは?
―現在、テレビ業界のビジネスモデルに課題があるとすれば、それはどんなところでしょう。皆さんの担当領域を踏まえてお聞かせください。
高橋:私は日本テレビで、広告付無料動画の事業立ち上げに携わるなど、主にデジタル上のコンテンツ配信に関する仕事を担当しています。この10年で、人々の生活習慣や人口動態は大きく変化し、日本の社会は多様化が進みました。これまで我々は、長らくテレビの視聴率を唯一の指標としてきましたが、それだけでは対応しきれなくなっている。視聴者のライフスタイルの変化に応じて、広告を掲載する媒体やコンテンツの出し方なども工夫する必要が出てきました。
放送かデジタル配信か、視聴者にとっては境目がなくなってきている中、放送は視聴率、配信はインプレッションというように指標が異なります。この環境下で全体としてどのくらい見られたのかをどのように把握するかは、大きな課題です。
青柳:視聴率は、どれくらいの人が見てくれたのかという数値。ここ最近広告主が求めているのは、放送や配信によってどれだけ商品が動いたのかという結果だと感じることが増えました。企業の説明責任として、この要望に応えていくことが課題だと考えています。
私は、民放テレビ局5社が連携した公式テレビポータルサイト「TVer(ティーバー)」の、見逃し配信に関するセールスをメインに担当しています。その中で感じるのは、視聴率一辺倒の既存のビジネスモデルに対する危機感です。当社としても、地上波放送の依存度は下げたビジネスをつくりたい。とはいえ、現状として地上波放送による収益割合は高い。そこで、現在デジタルに使われている広告費に対してどうアプローチをしていくのか、どうすれば取り返せるのか、日々模索しています。
堀:私はテレビ東京コミュニケーションズで、動画ビジネスの事業開発とシステム開発、オペレーション、グループ全体の統合的なマーケティングを任務として業務を行っていますが、現在はデータ活用に課題を感じています。データを生かすには、エンジニアリングやテクノロジーの知見・技術を持った人材の確保や育成が欠かせません。端的に言えば「ITのパワーをどれだけ高められるか」というのが課題だと思っています。
テレビ局には周辺ビジネスのデータなども含めて自社独自のデータがたくさん溜まっています。それにも関わらず、活用できていない。そこを何とかしたいです。
TVerで属性データの取得開始 3カ月で数百万のデータ集まる
―新しいビジネスモデルの構想、あるいは構想に基づいた取り組みについてお聞かせください。
青柳:ここ3、4年でどこの局も地上波放送をマネタイズするためのデジタル上での事業開発に取り組み始めていますよね。昨今のコンテンツ配信のプラットフォームとして、拡散型のメディアが浸透していますが、FacebookやTwitter、YouTubeなどもうまく使って視聴者との接点を増やし、最終的に地上波でも見てもらうところまで持っていけないだろうかと考えています。
確実に、デジタルでの接触頻度やリーチできる層は増えてきているので、地上波と一緒に面白い施策を打ちたいです …