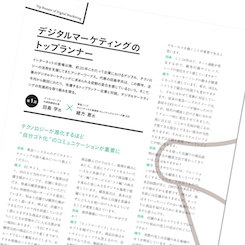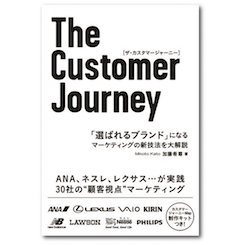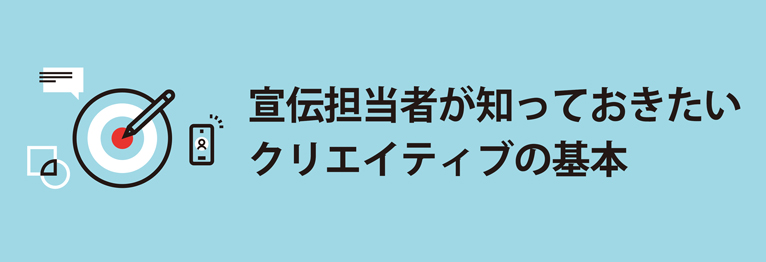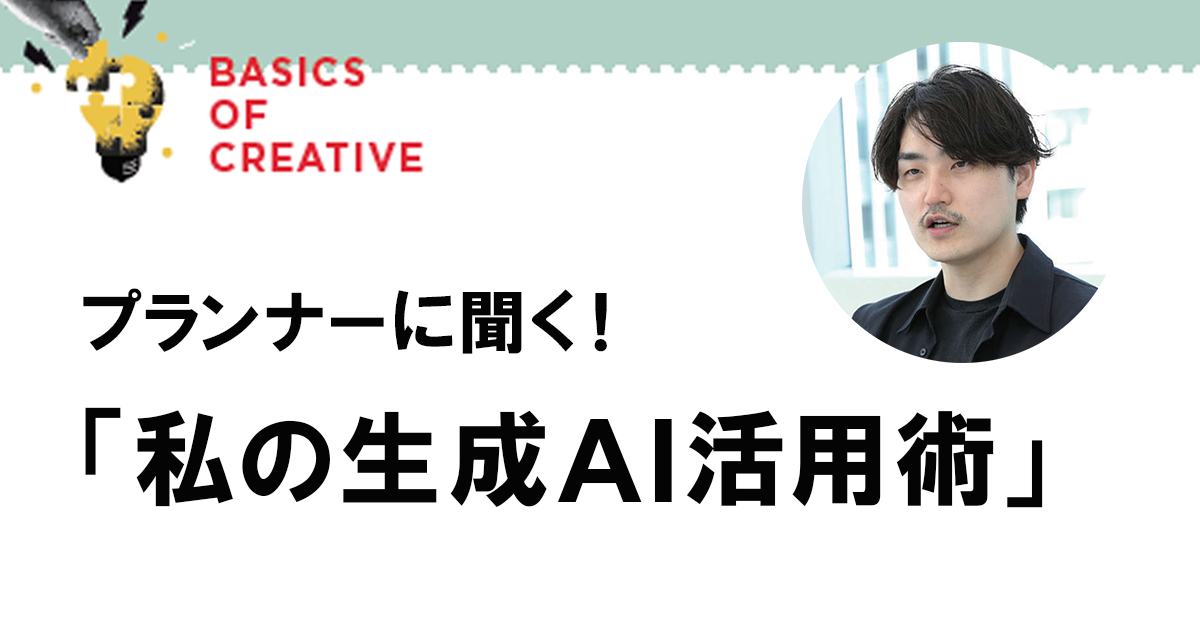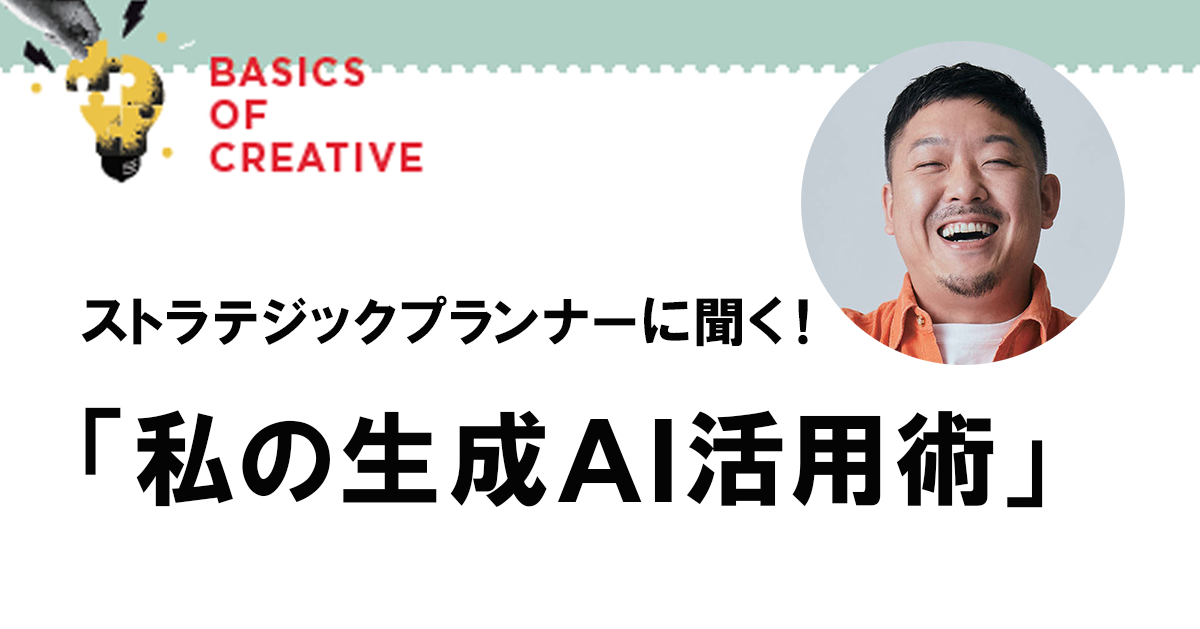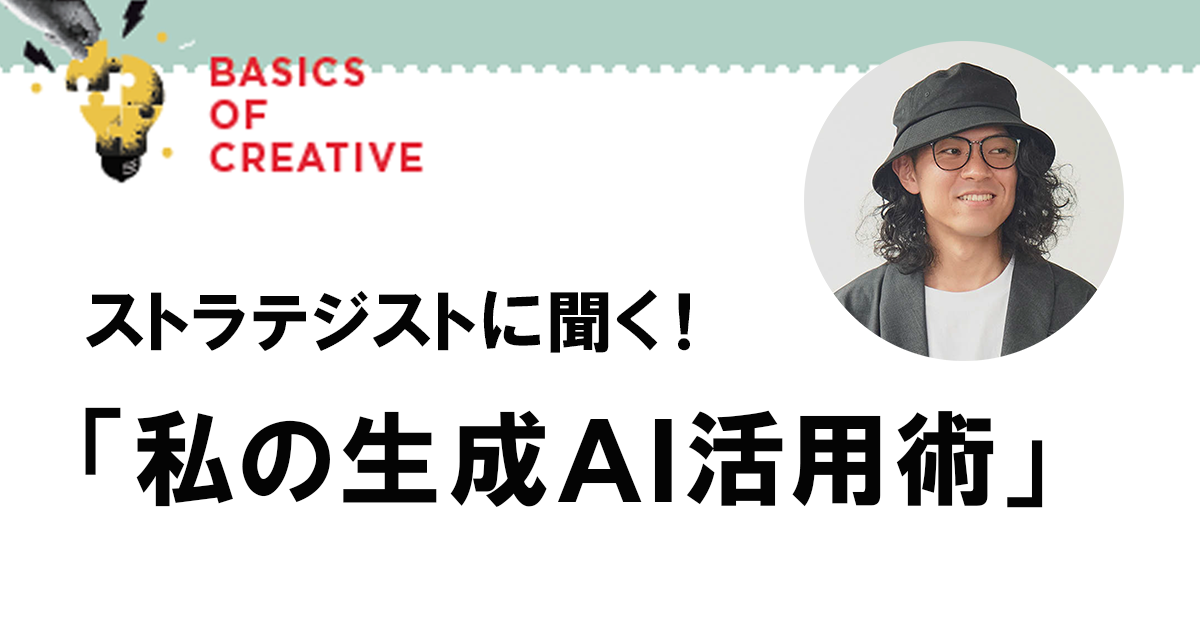市松模様で自社を探る。
先日、江戸切子を建築のモチーフとした、東急プラザ銀座がオープンしました。空間デザインに限らず、日本の伝統的デザインを、現代の日本の価値観、生活環境に合わせて進化させる動きがあらゆる領域で起きています。成熟社会が成長社会と違うことは、スクラップ&ビルドではなく、持続させることを価値とすることです。そして持続社会では、物事の本質を見つめ直し、そこから続く未来を見据えて行動することが必要です。故に、日本人が日本の良さに注目し、それを持続させる活動をすることは本質的であり、トレンドではなく価値観のシフトと言えます。
東京2020大会で採用された組市松紋のロゴは、誰もが日本らしさを感じました。それは、日本人に、日本らしさを感じ取る感覚があるからです。一方で、グローバル企業を含め、日本らしいデザインを資産としている日本企業は多くありません。世界では、日本らしさが価値になるにもかかわらず、です。東京2020大会は、世界に日本をプレゼンテーションする機会です。新国立競技場やロゴのやり直しには別の問題がありましたが、結果的にどちらも日本らしさを表現したデザインに落ち着いたのは、「日本らしさを世界に発信しよう」という世論だと言えるかもしれません。
では、この機に企業が何をするべきか。市松模様を使った商品や空間開発も、もちろんやって良いと思います。しかし私は、企業規模に関わらず、日本をDNAに持つ企業として、自社ブランドに眠る日本らしさを見つめ直す機会にして欲しいと思っています。
そこに具体的なアイデアを提示するとしたら、例えば「自社のエントランス空間を再考する」というテーマのワークショップを社員でやってみてはどうでしょう。5年、10年変わらない企業空間をつくるということは、中期的にどの様な企業であるべきか、というブランディングに近いプロセスになります。そこには、どんなデザインがあり、どんな音楽が流れていて、どんな香りがあり、どんな受付スタッフが接客するか。そして市松模様ではなくとも、日本らしい要素を入れ、自社にある日本を可視化する機会にすれば良いと思います。そこで出た会話やアイデアは、その後の製品開発やマーケティング戦略にも生きてくるはずです。
今年は、日本の良さを見直す元年です。日本のグローバル化とは ...