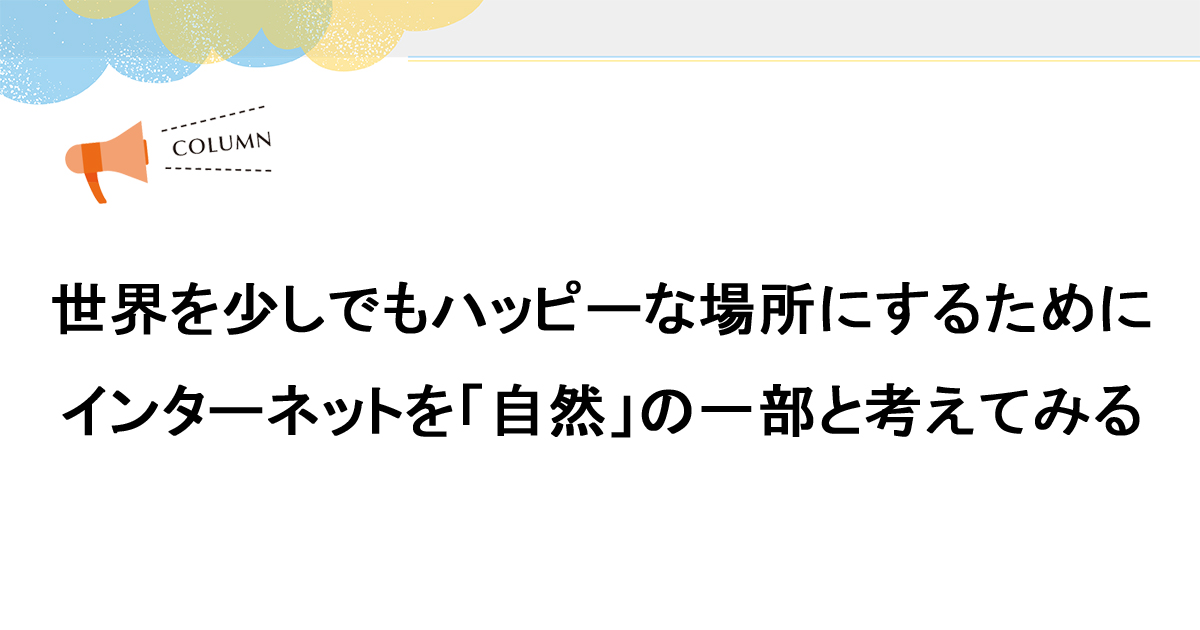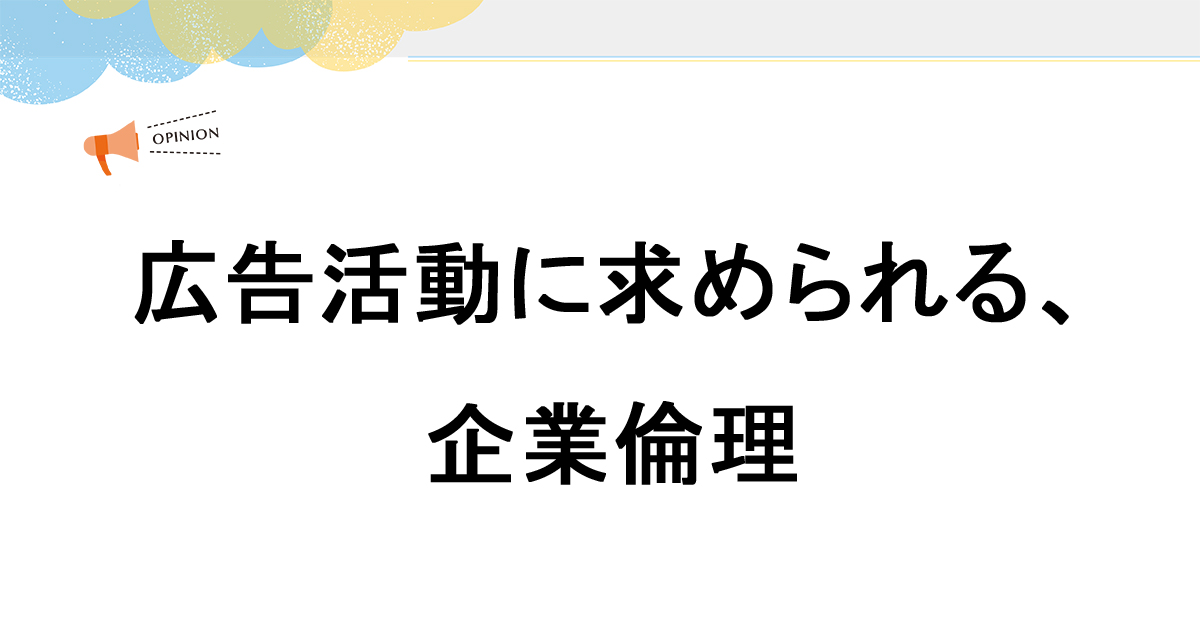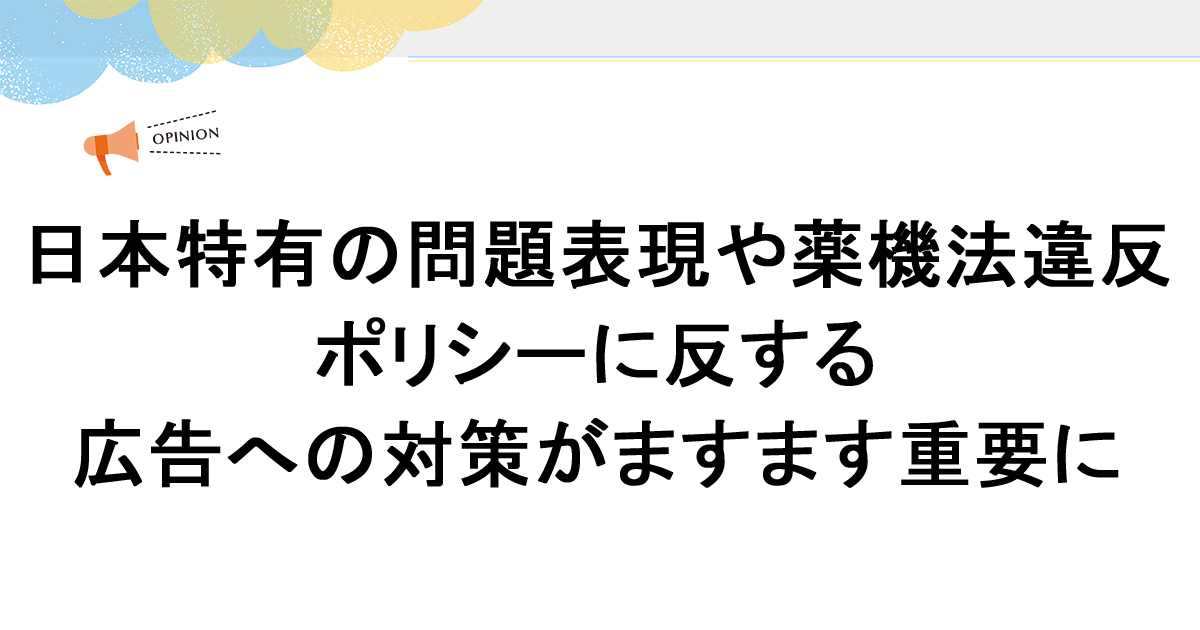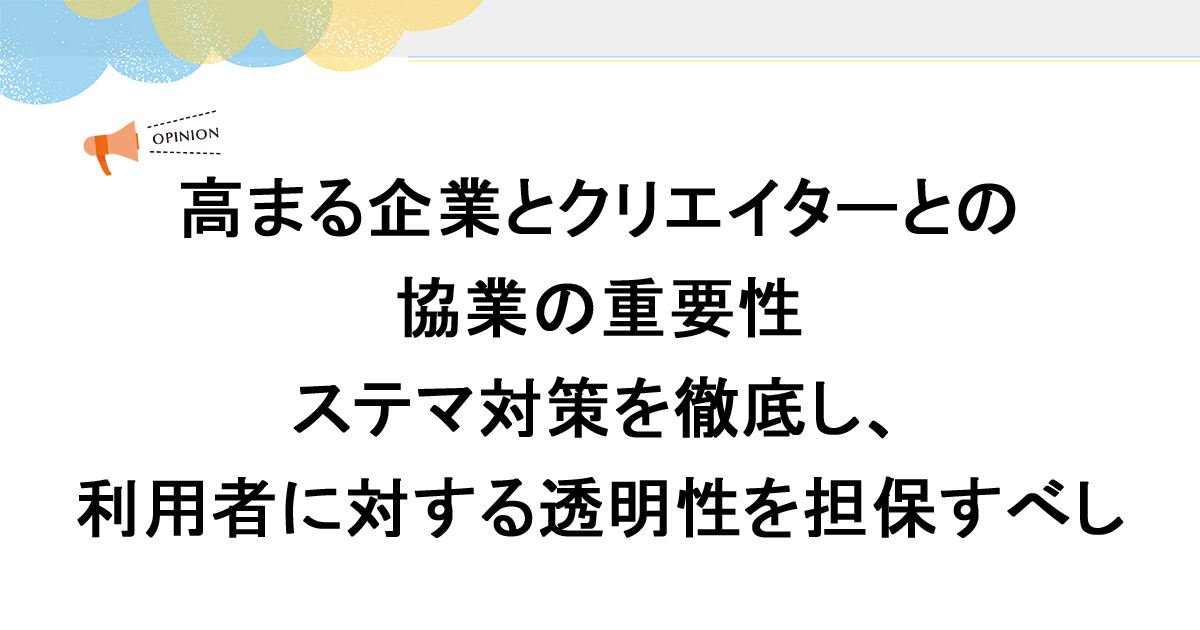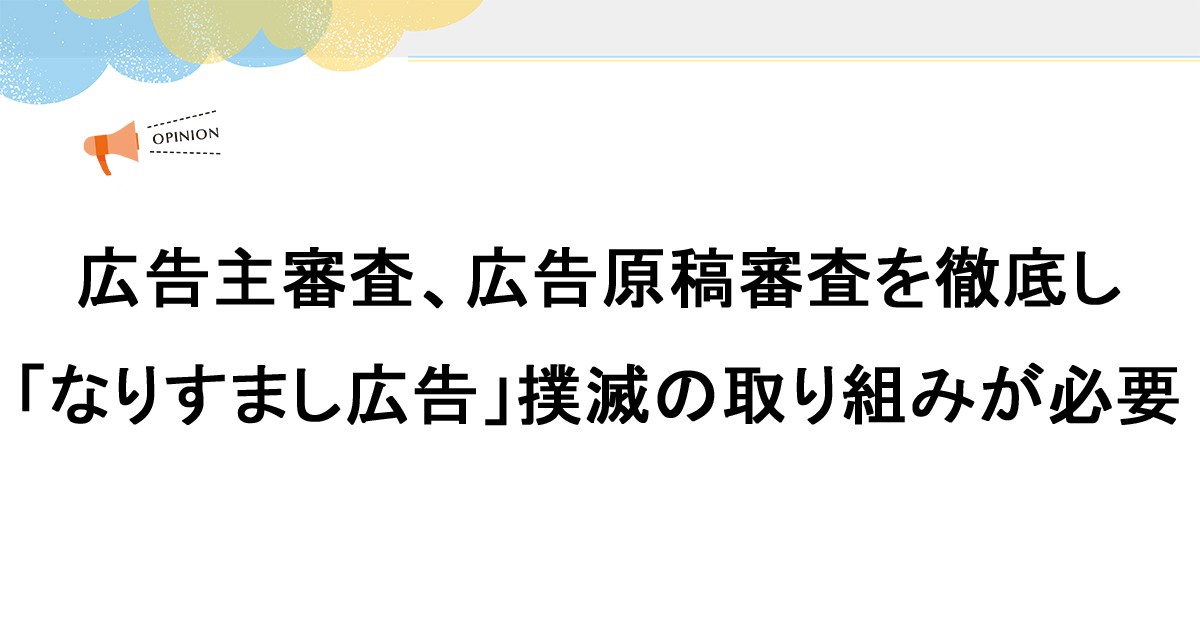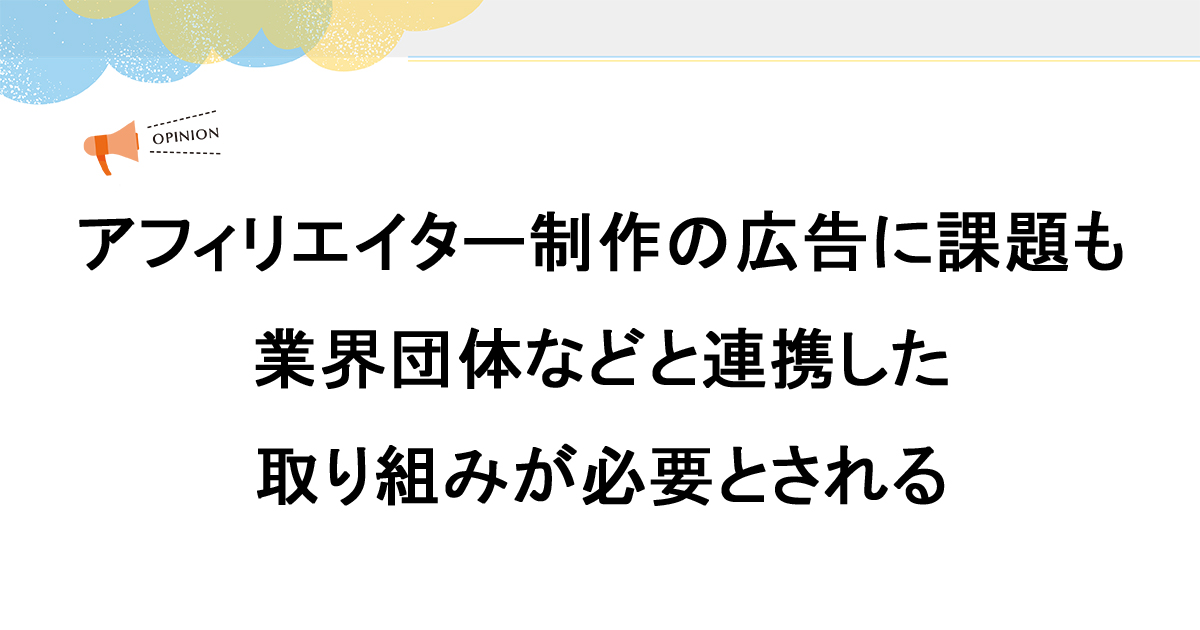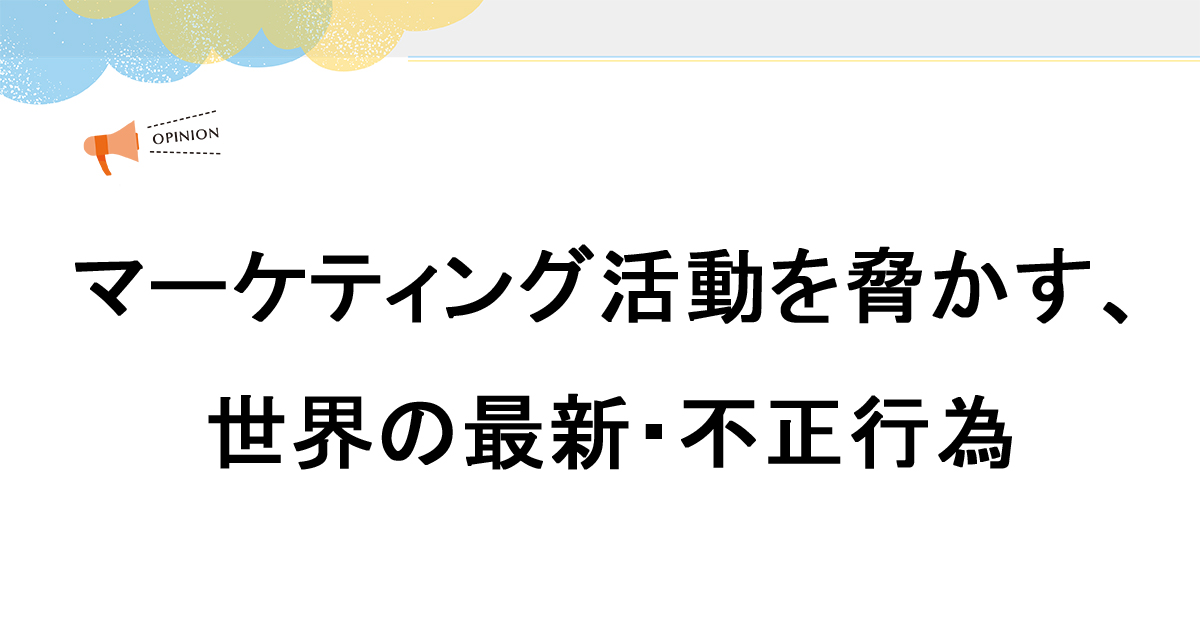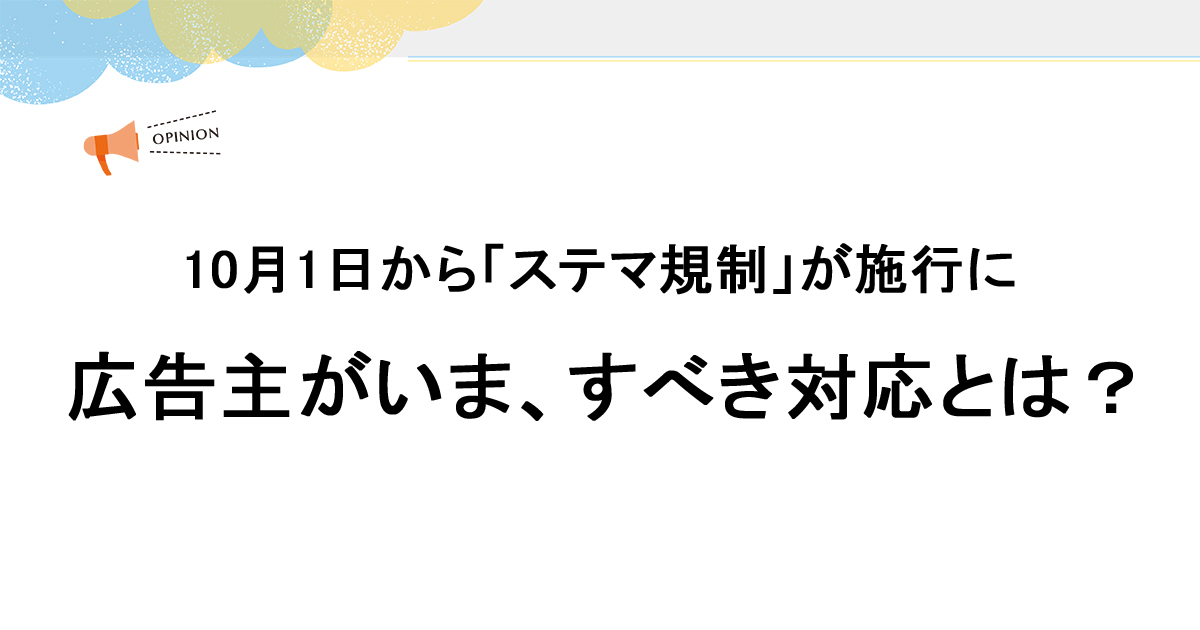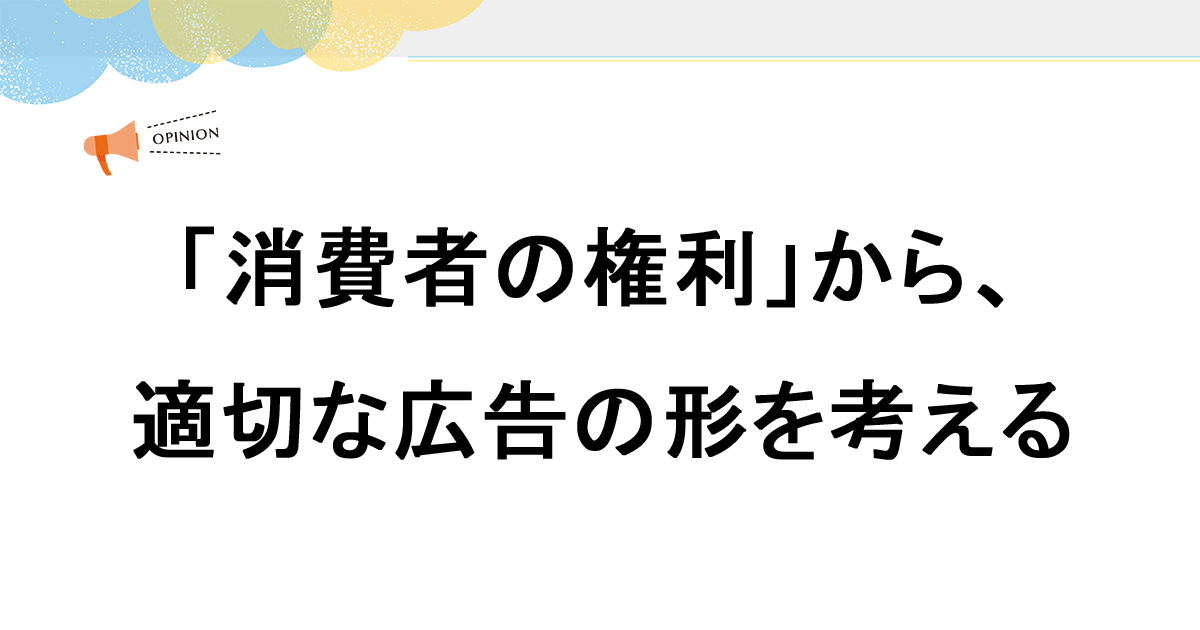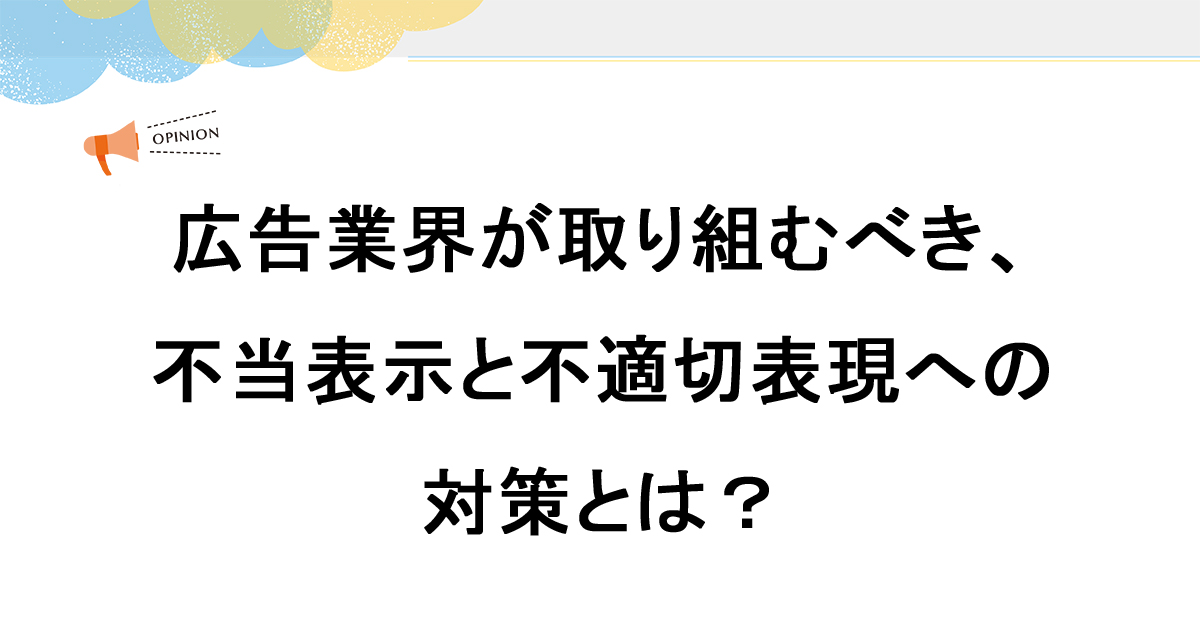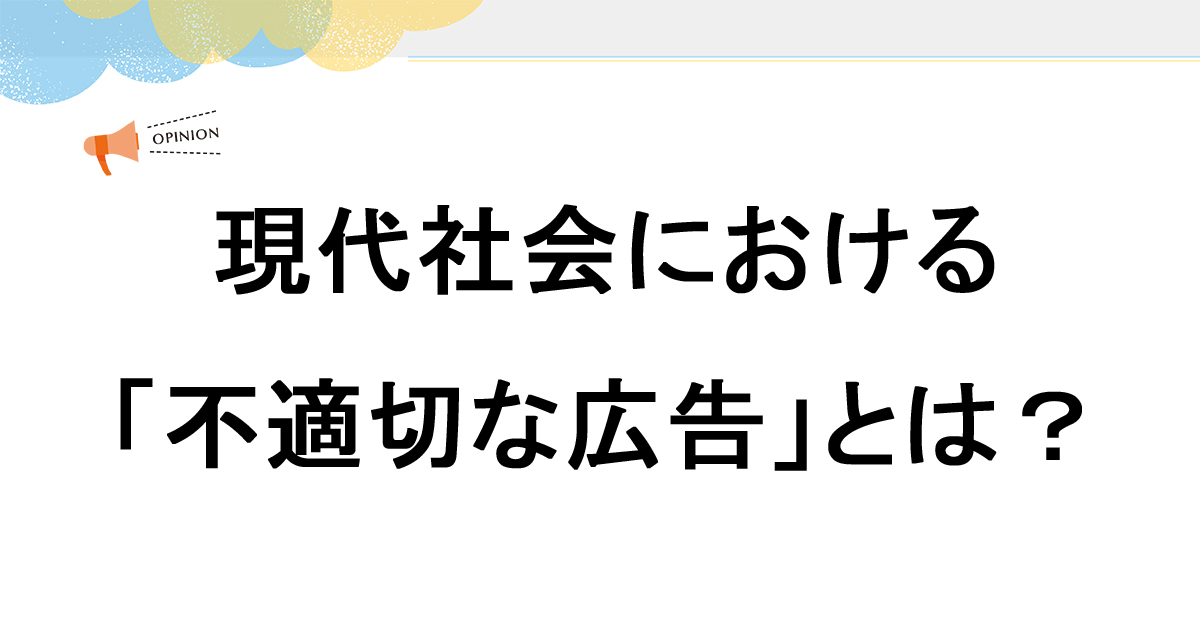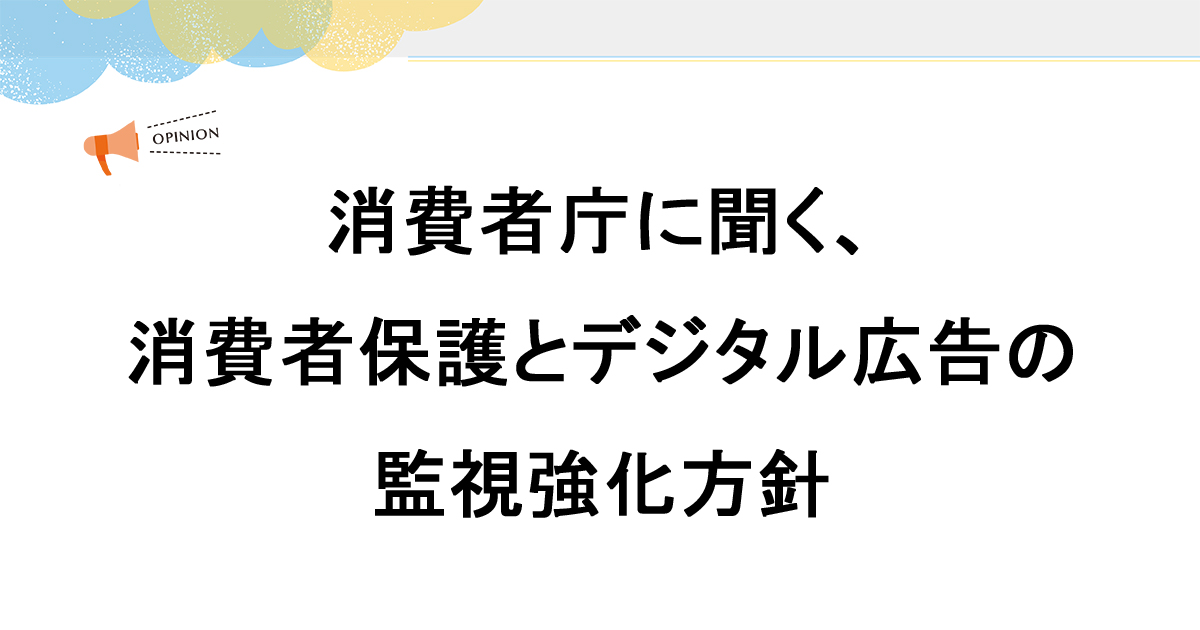ユーザーにとってのインターネット広告の印象を良好なものとしていくためには、広告主、広告会社のみならず、インターネット広告の枢軸を担うプラットフォーム側の対応が欠かせない。昨今、広告の体験品質の問題が顕在化するなか、国内で活動するプラットフォーマー大手企業は、どのような課題を認識し、また対応を進めているのか。各社の取り組みを聞く。
Q. ユーザーにとっての広告体験の品質を向上させるための取り組み。
A. Googleは、利用者がオンライン上のあらゆる場所で十分な情報に基づいて意思決定できることを大切にしています。
2020年には『広告主適格性確認プログラム』の導入を開始しました。これにより、利用者は広告の広告主名や所在地など詳しい情報を確認することができるようになりました。昨年は『マイ アドセンター』の提供も開始しました。利用者は広告のプライバシー設定の管理を容易に行うことができ、デリケートな広告の制限や、パーソナライズド広告を完全にオフにすることが可能となります。今後も透明性の高い情報やユーザーの意向に基づいた広告表示に関する取り組みを進めてまいります。
Q. 表示内容に問題のある広告を排除するために取り組んでいること。
A. Googleは、全てのステークホルダーを保護するために厳格なポリシーの策定や適用を続け、悪意ある広告利用を防止しています。現在、何千人もの従業員とAIによるシステムが24時間体制で問題のある広告の...
あと60%