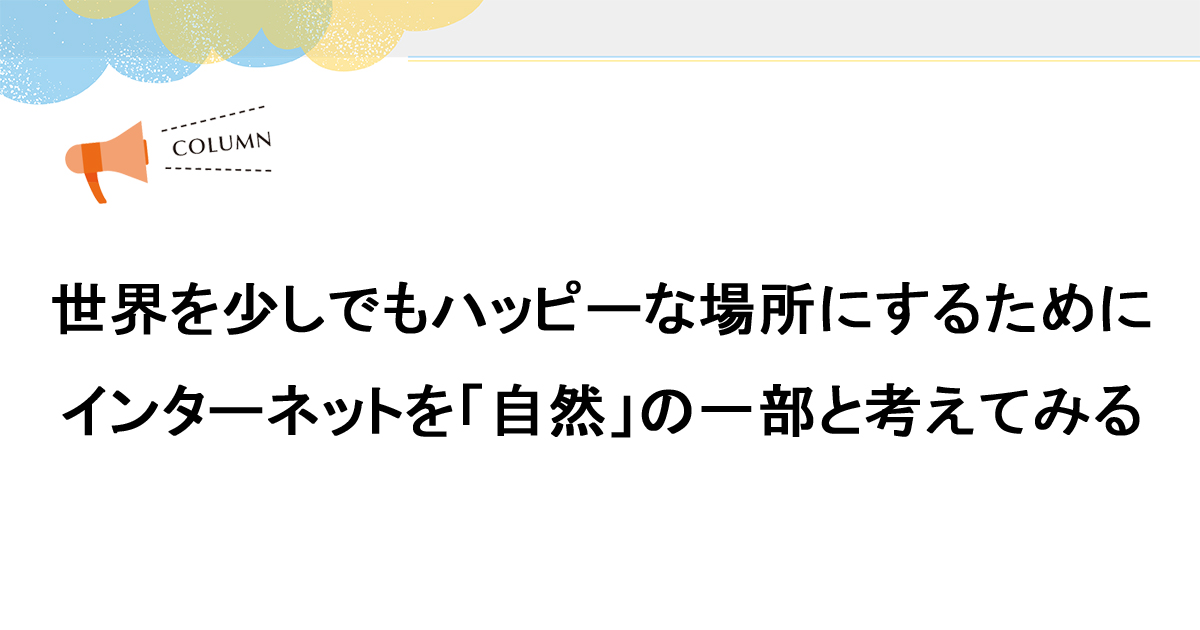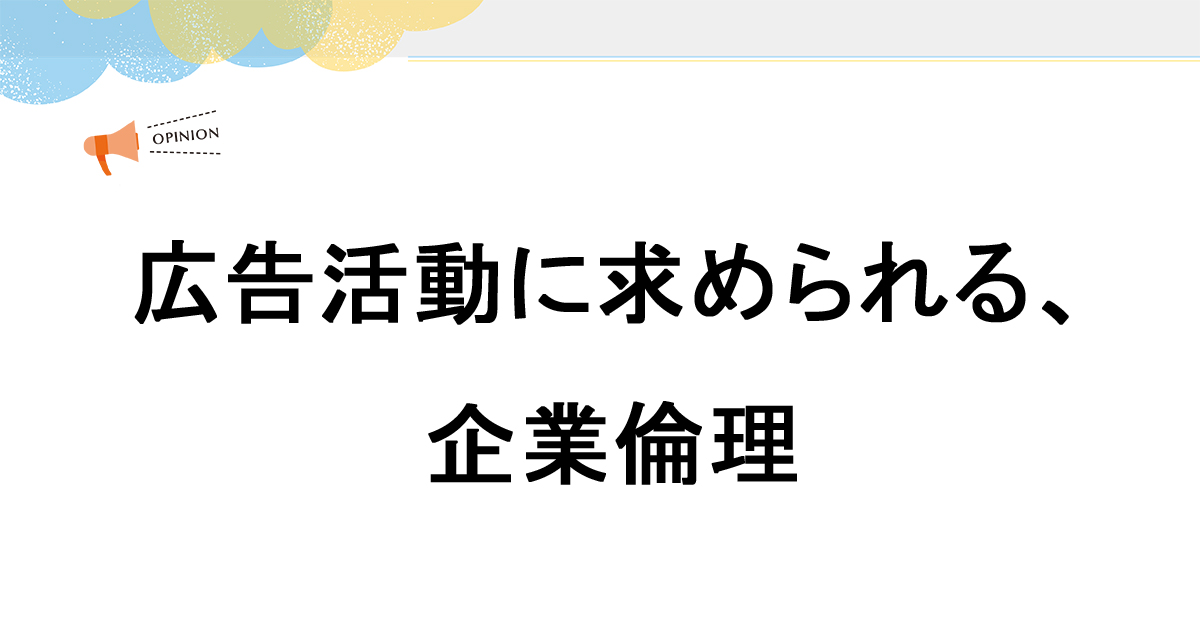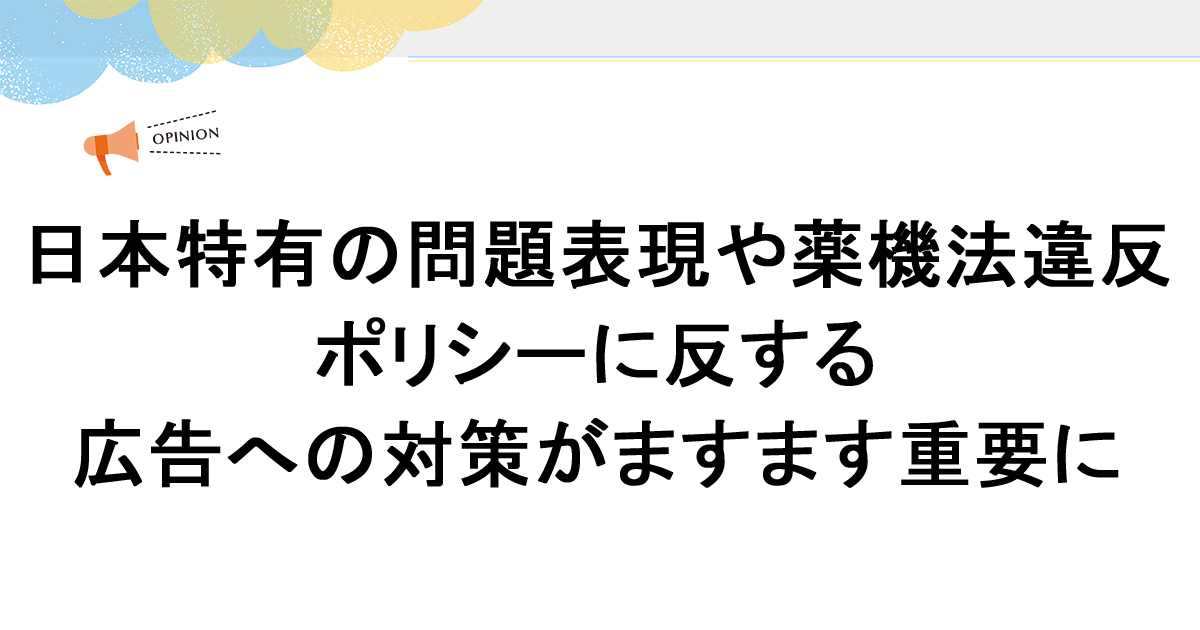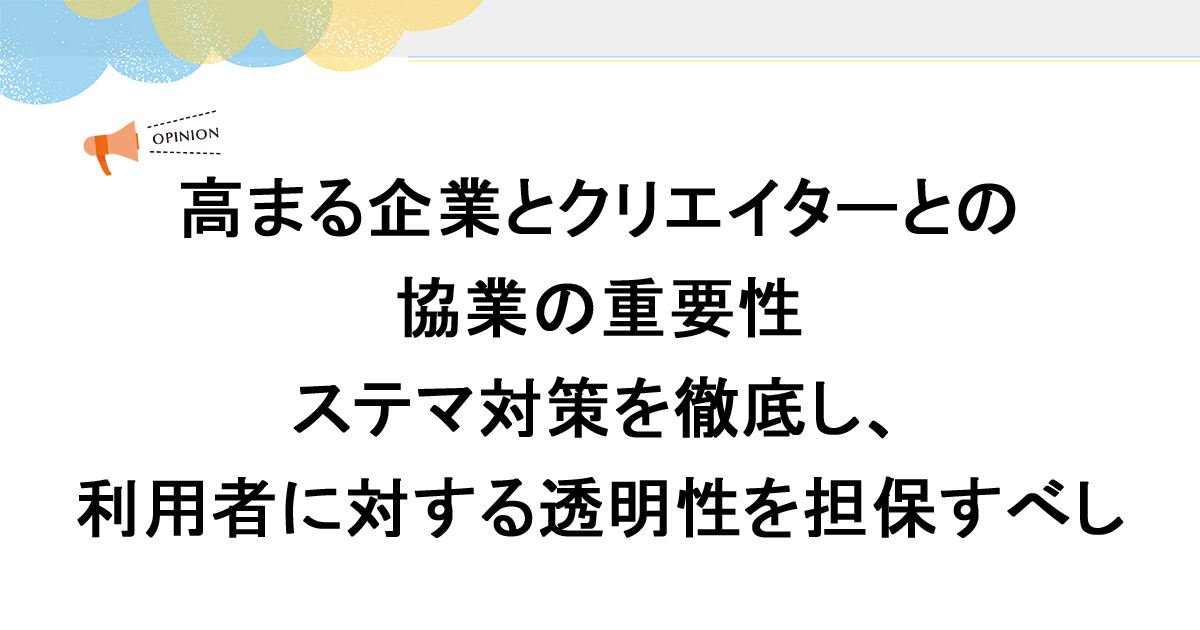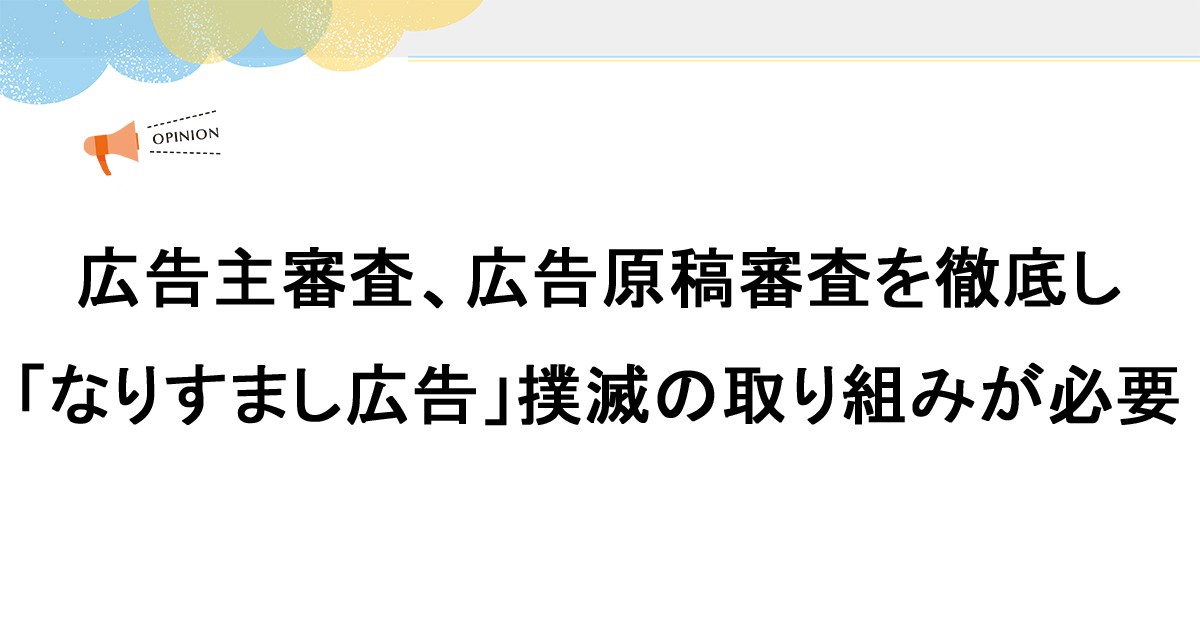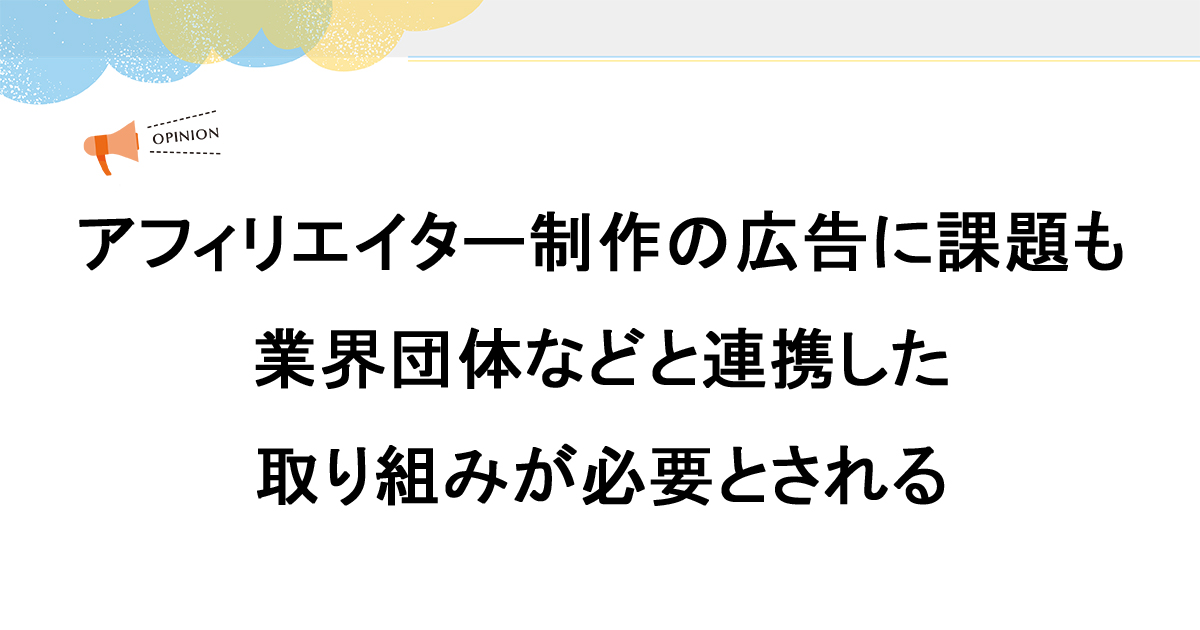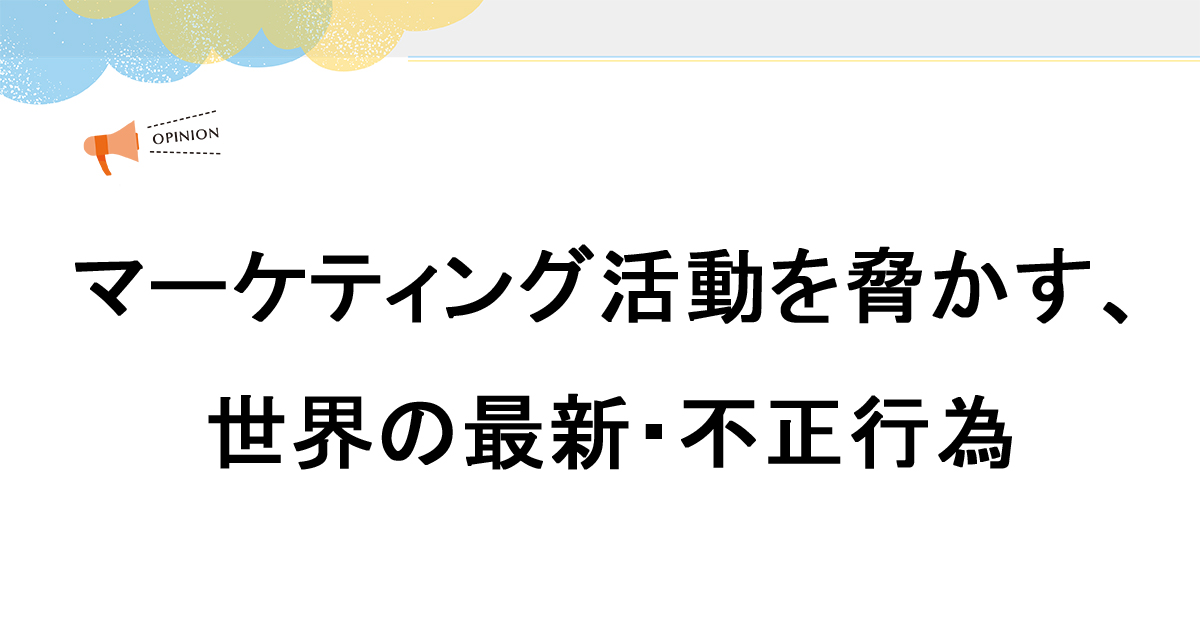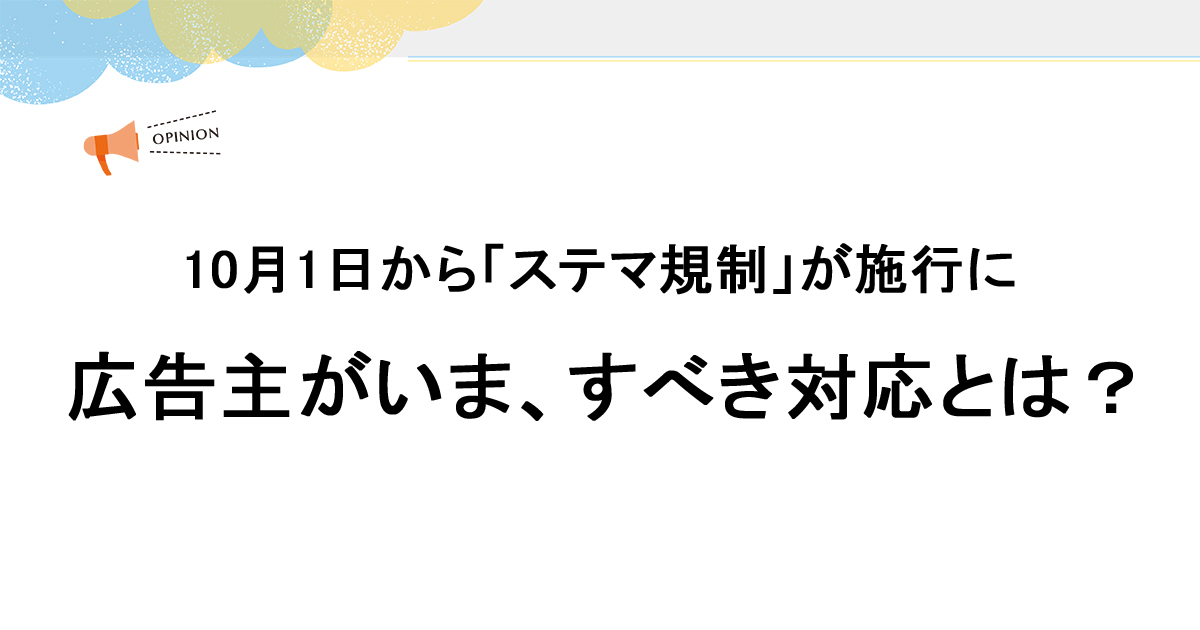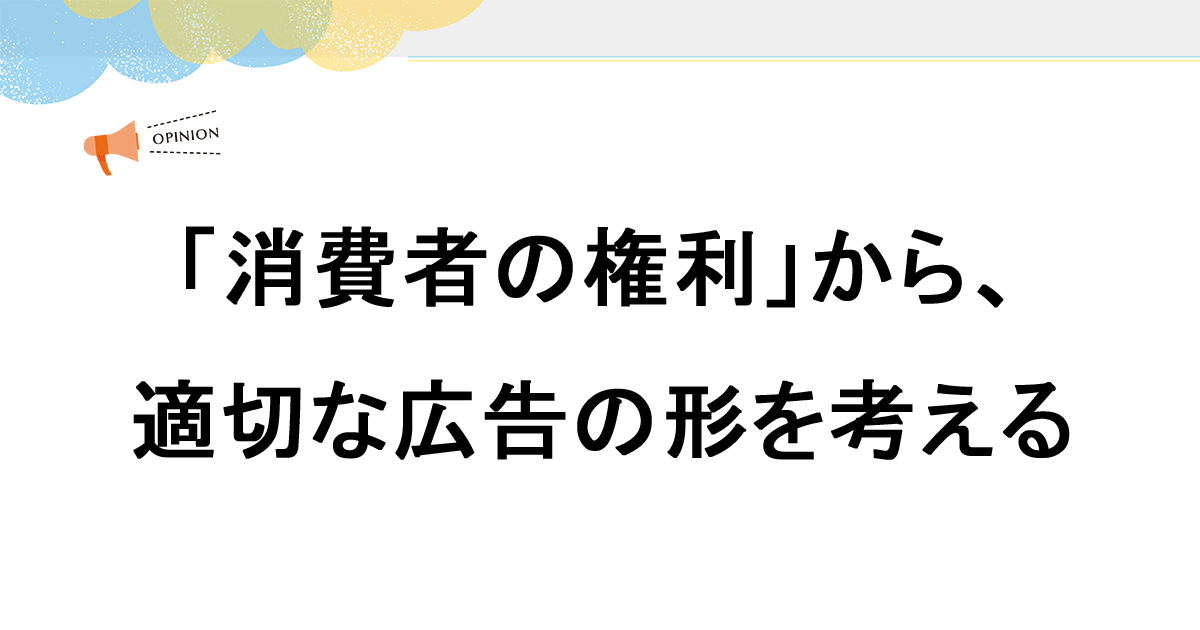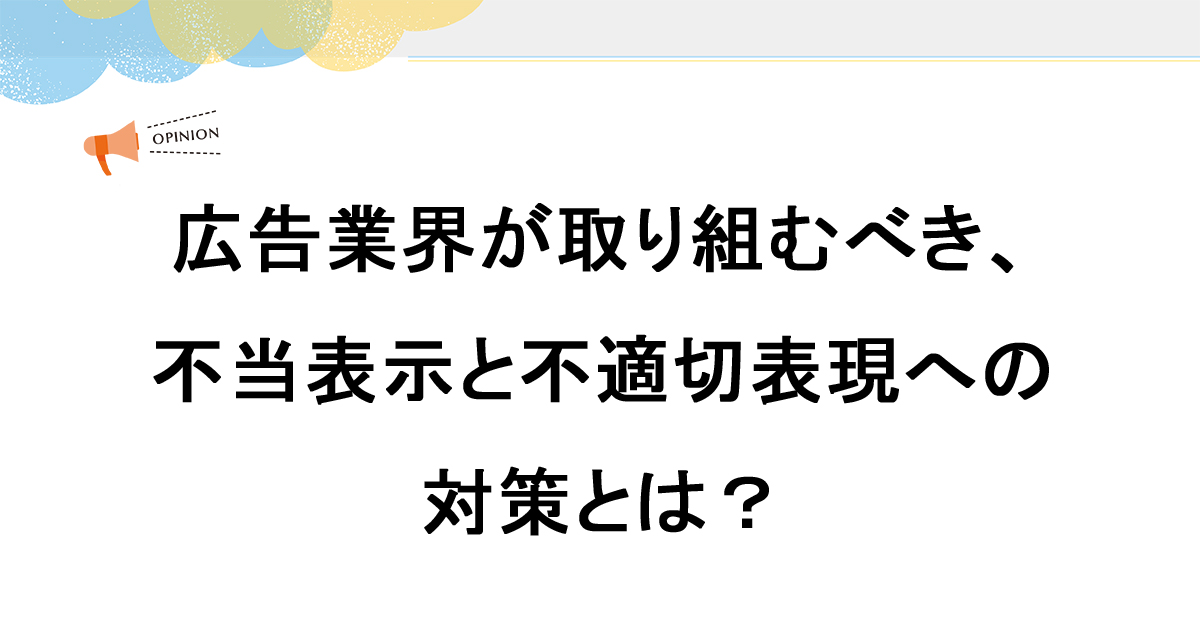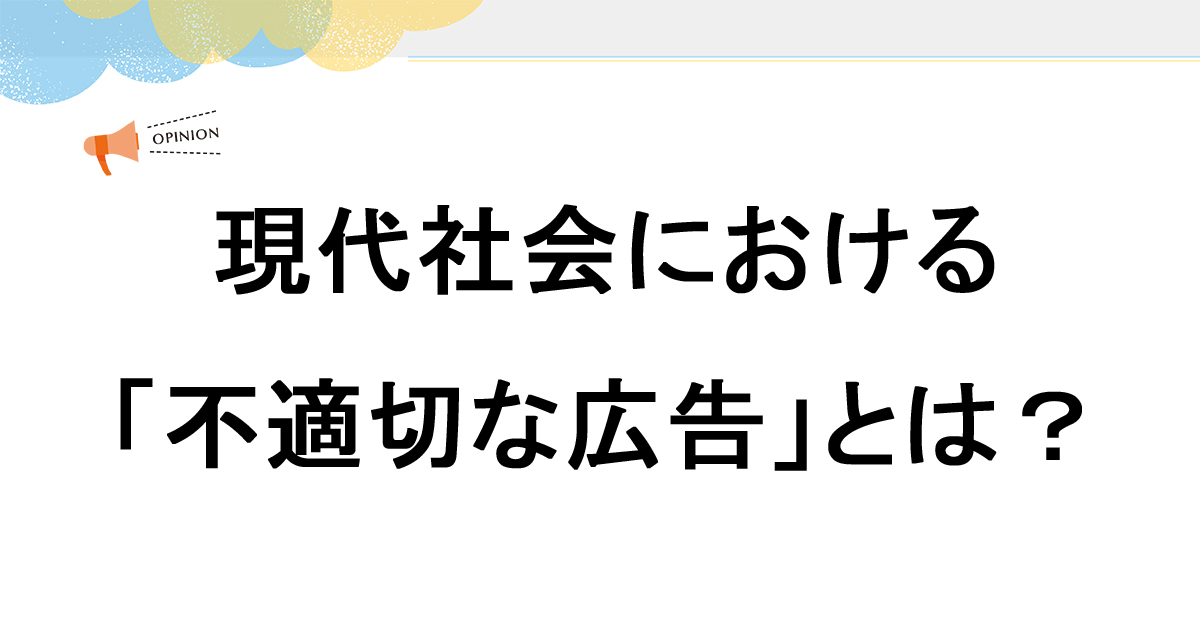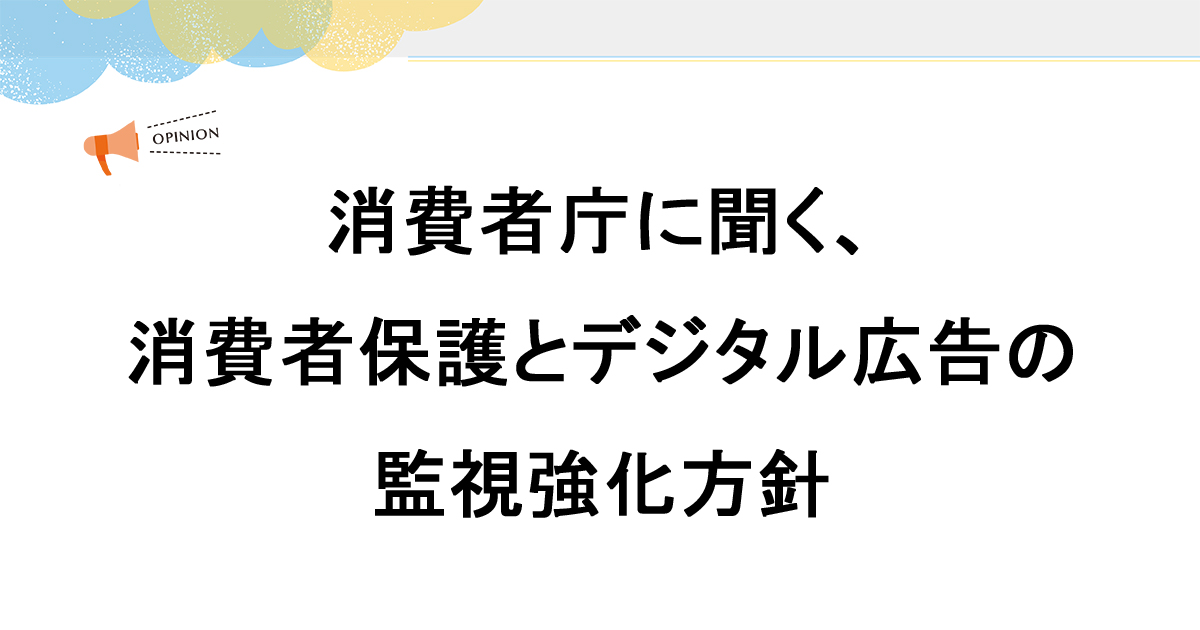消費者のインターネット利用時間が急増する中、事業者はよりネットやSNSのアプローチが必要になっている。では悪質なネット広告から消費者の権利保護を促進し、EC上で適切な広告活動が行われるために必要な視点とはどのようなものなのだろうか。一般社団法人ECネットワーク理事の原田由里氏に話を聞いた。
都が悪質なネット広告に対応する専門家チームを発足
2006年4月に設立された一般社団法人ECネットワークは、安心して参加できるインターネット取引市場の実現を目指して活動している非営利の民間組織だ。ネット通販やネットオークションなどのインターネット取引に関する一般消費者の方からの相談を受けているほか、教育機関向け・事業者向け・省庁向けに啓発活動や講演などを行っている。
ECネットワークで理事を務める原田由里氏は、2023年7月に東京都が発足した不当なネット広告の調査のための専門的知識を有する助言員チーム「東京デジタルCATS」にも選出をされている。助言員はデジタル広告に関する不当表示に対する事業者調査、指導、情報提供などに関する措置への助言などを行っていくとしている。
原田氏は「ネット広告によって私たち消費者も恩恵を受けることもありますし、ネット広告すべてが悪いわけではありません。ただ、現在はフェイク広告やステマなど消費者を欺くような広告にクリックが集まり、悪質な事業主が利益を得てしまっている状態です。このままでは、ますますグレーな広告を出稿する事業主が増えてしまうことになりかねません。そうならないために、CATSではネット広告の適正化を目指す活動をバックアップしています」と語る。
事業者と消費者の利益の共存にはプラットフォーマーの自制が鍵に
ECネットワークでは、主に消費者からの相談などに対応している原田氏。設立当初は不当請求やワンクリック請求の詐欺に関する相談が多く寄せられていたが近年、増えているのは、プラットフォームやSNSに表示される広告から誘導されて悪質なサイトにアクセスし、取引してしまったという通販トラブルだという。
SNS広告にまつわるトラブルで多いのは、ダイエットやアンチエイジングなどのコンプレックス系商品が目立つという。中には、芸能人の画像を無許可で使用して、あたかもその芸能人が商品の愛用者であるかのように捏造した画像を使用するケースや、情報番組で取り上げられたかのような文言や番組のキャプチャ風の画像を掲載しているフェイク広告も見受けられる。若年層は、投資や資産運用など情報商材にまつわるトラブルに巻き込まれる人が増加傾向にあるという...