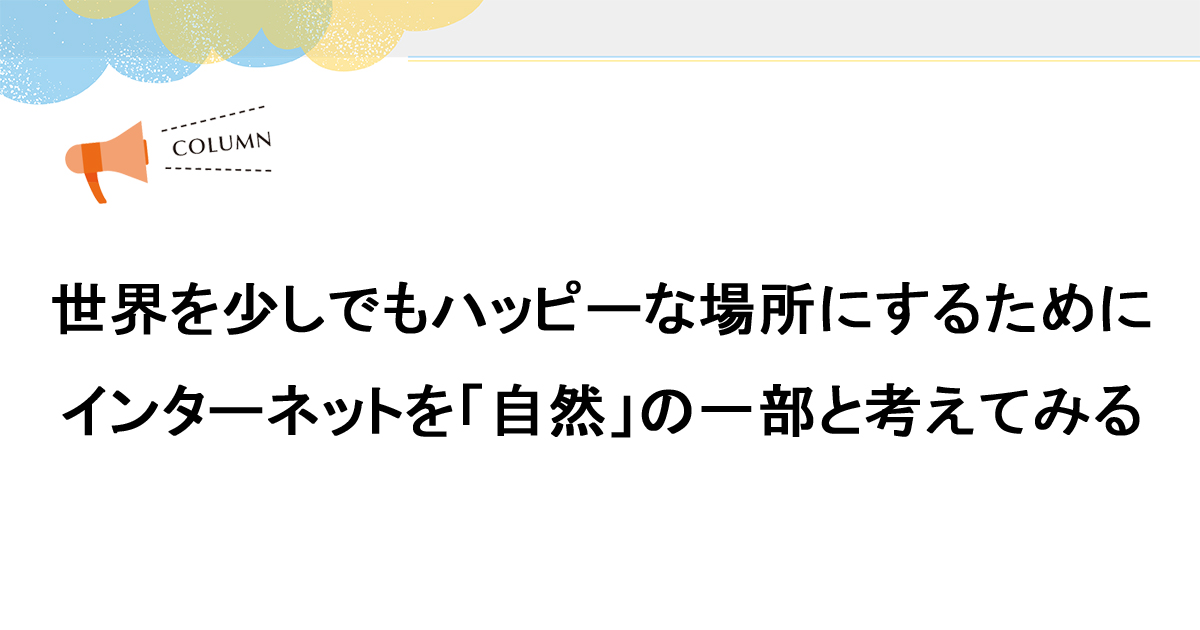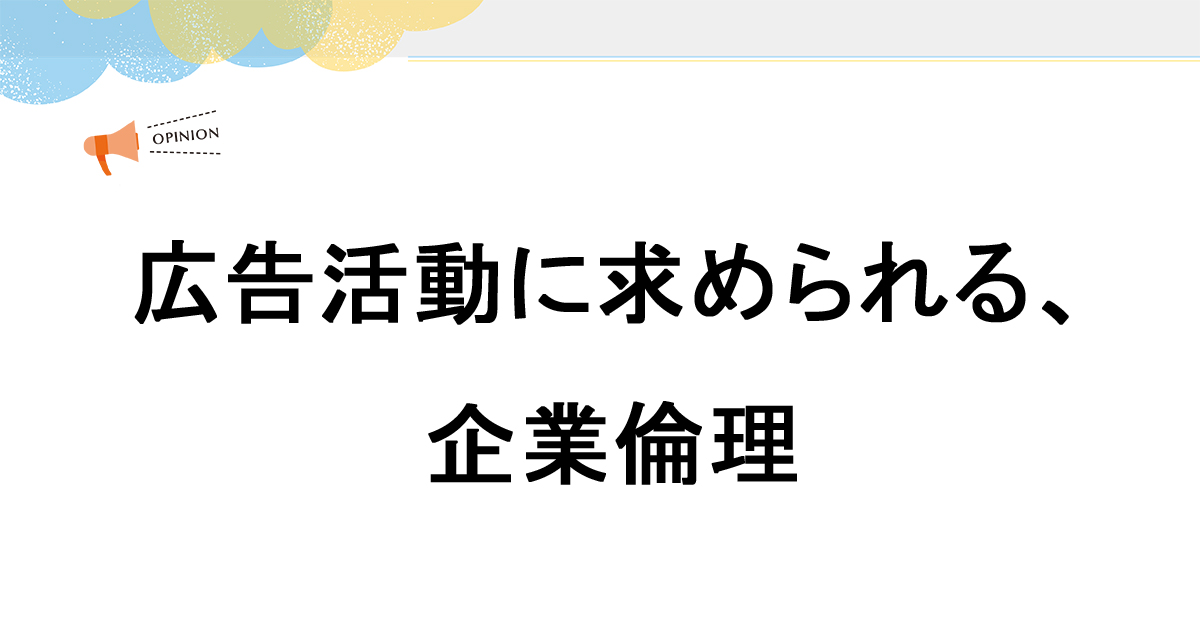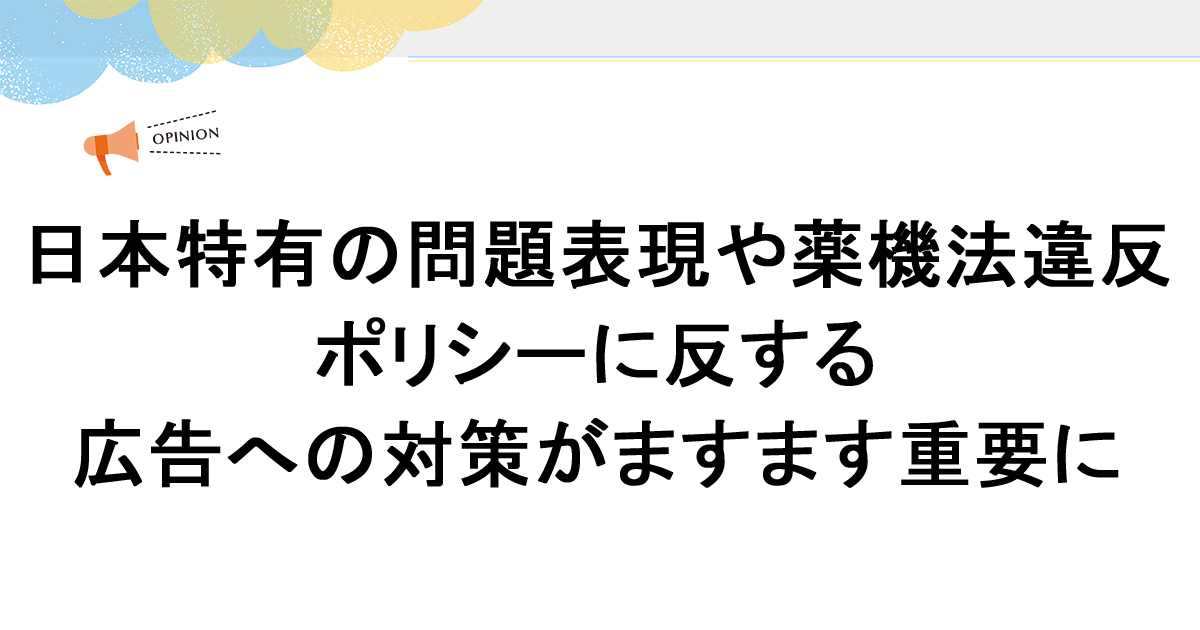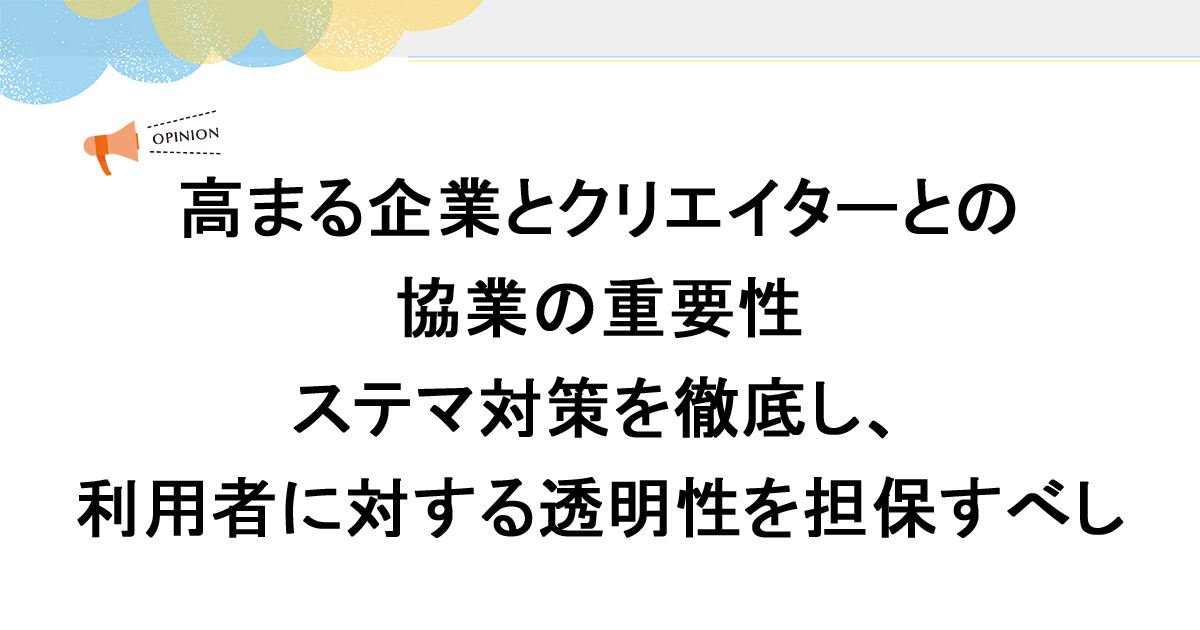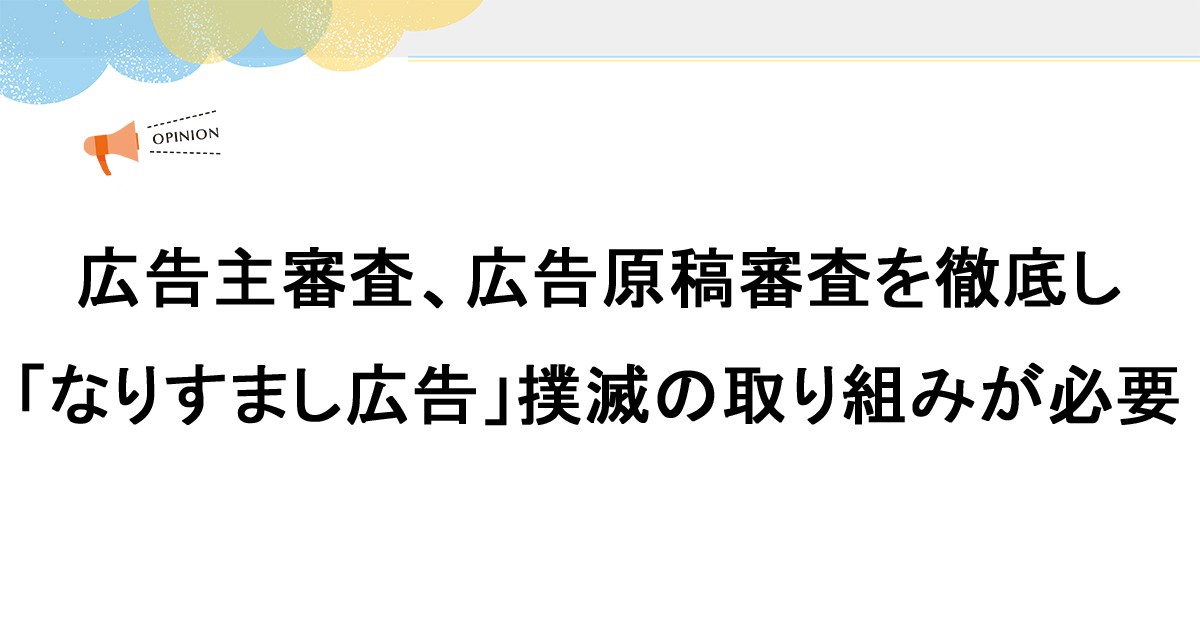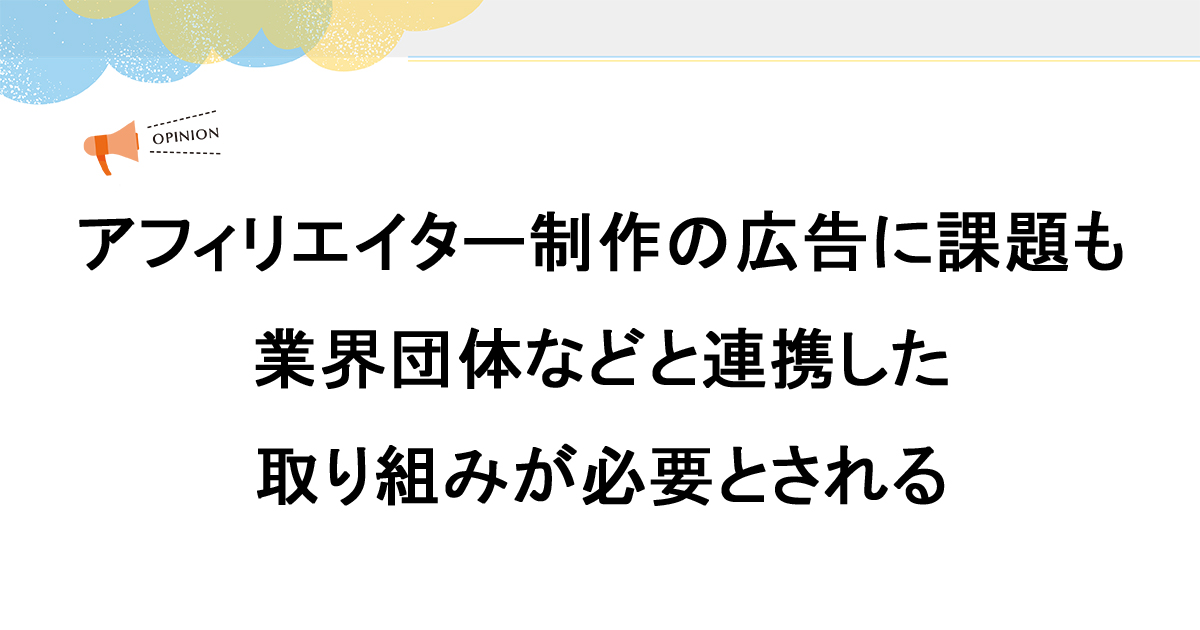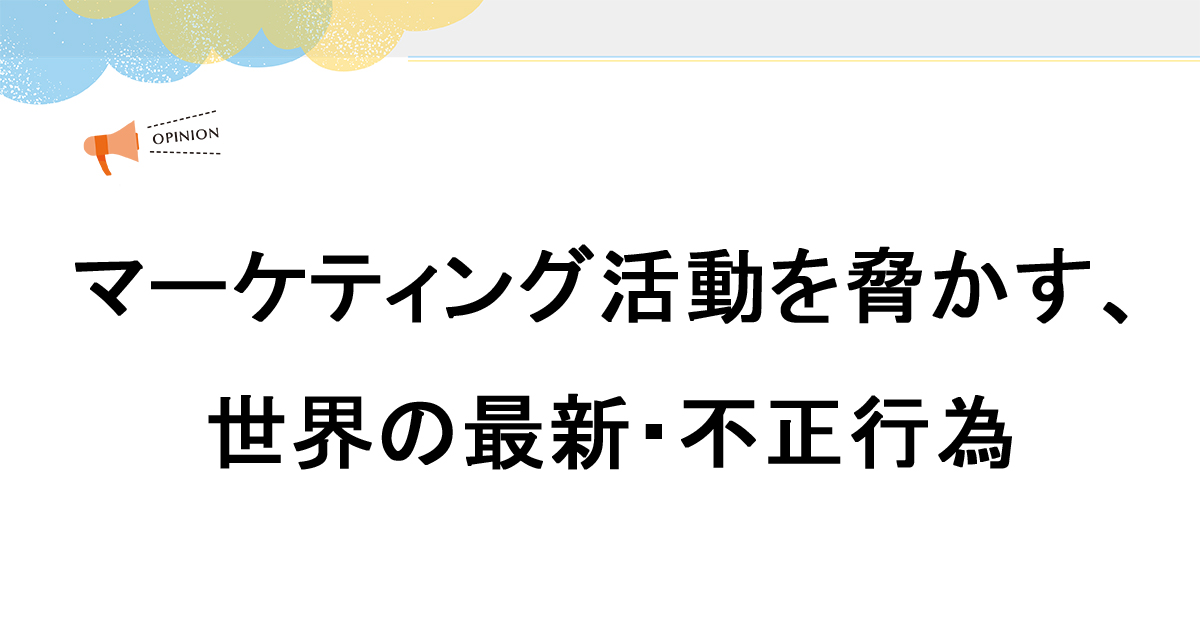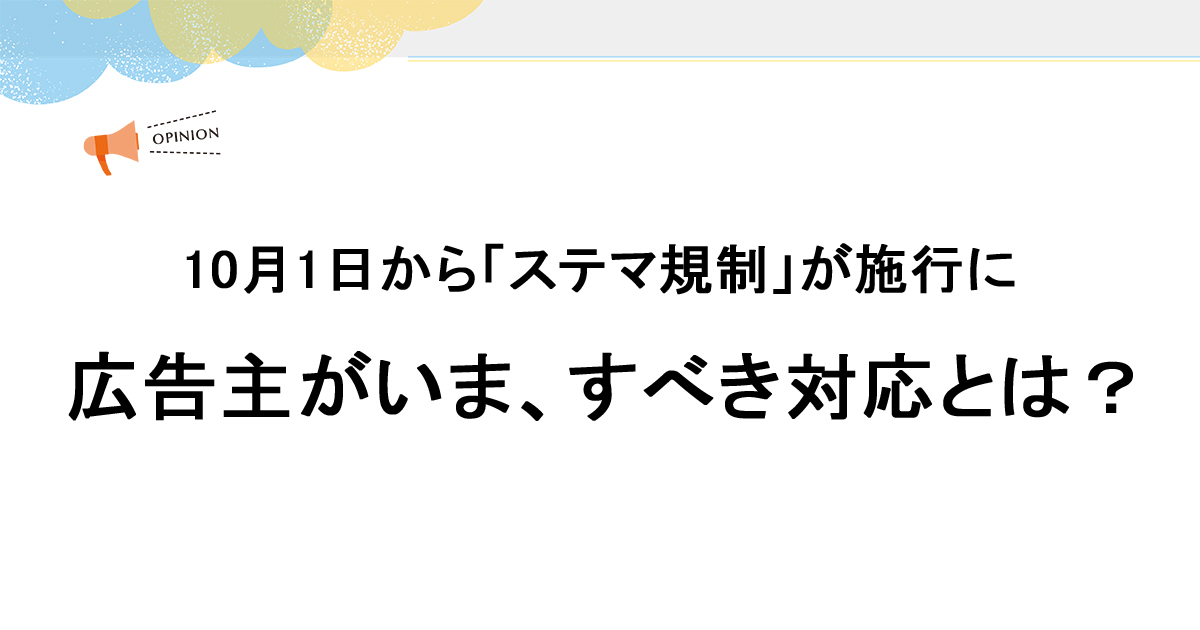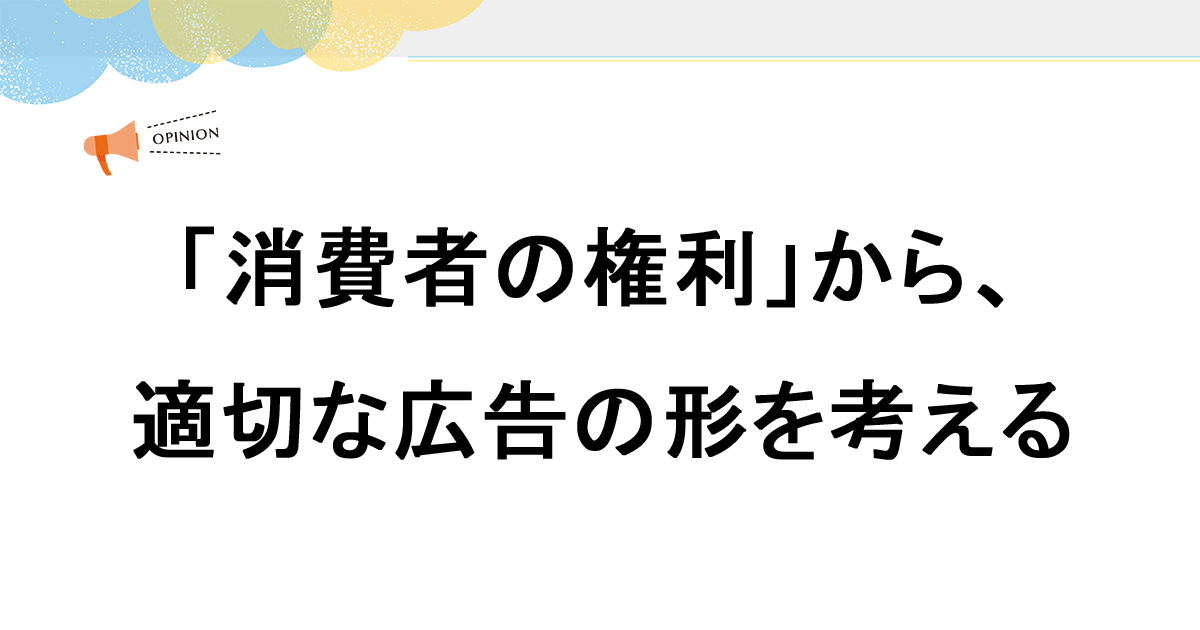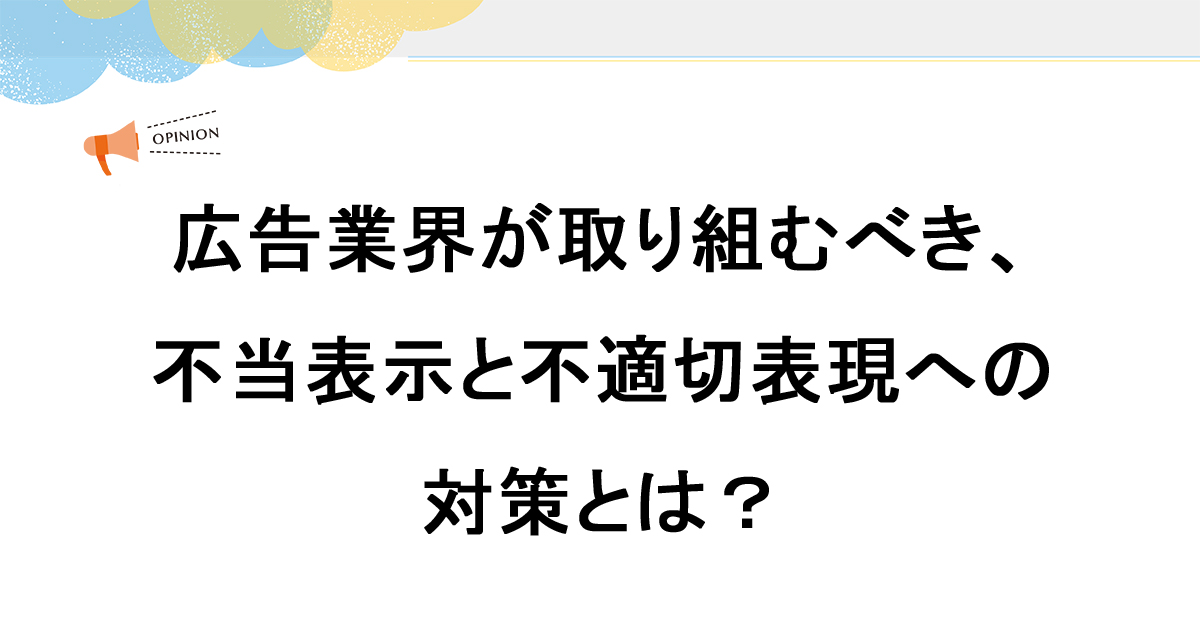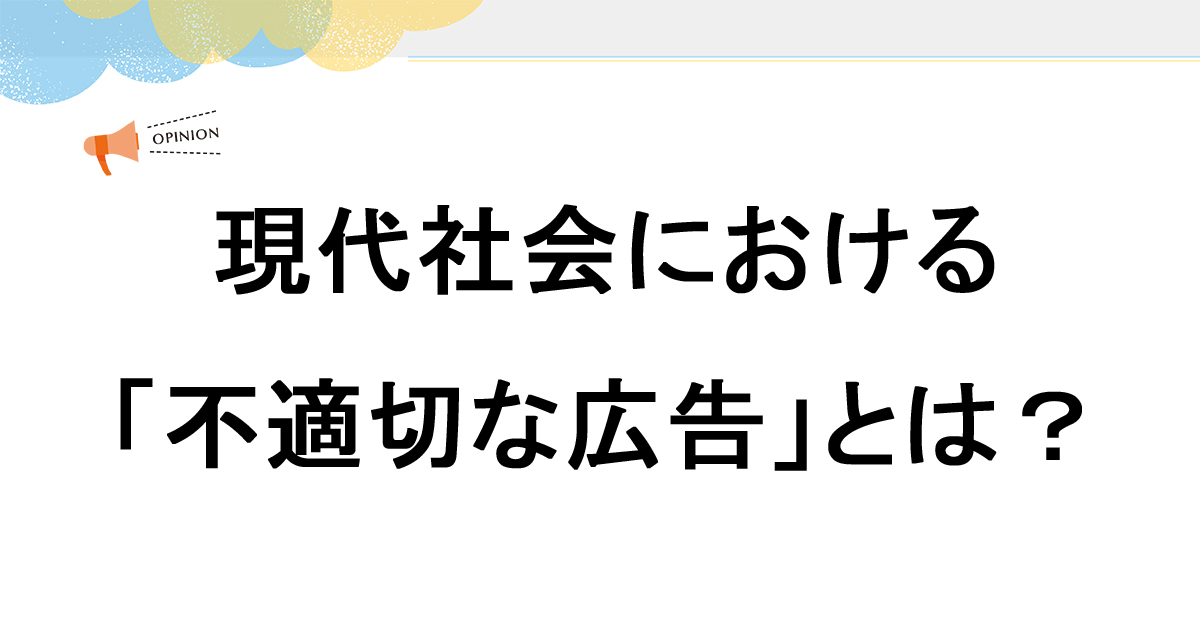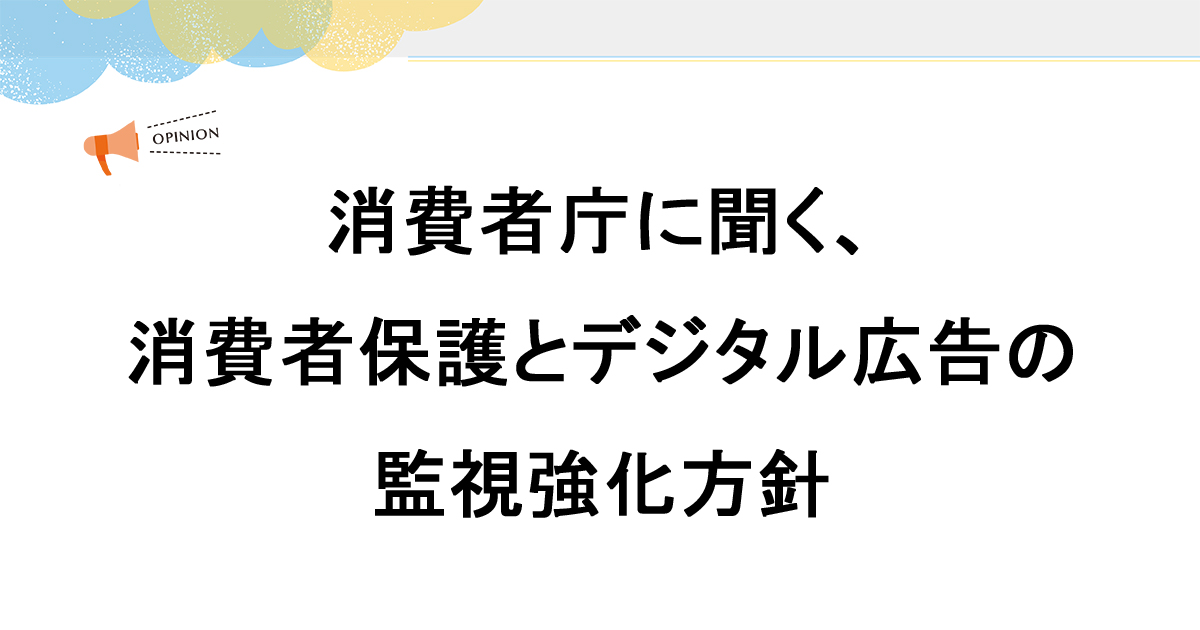ユーザーにとってのインターネット広告の印象を良好なものとしていくためには、広告主、広告会社のみならず、インターネット広告の枢軸を担うプラットフォーム側の対応が欠かせない。昨今、広告の体験品質の問題が顕在化するなか、国内で活動するプラットフォーマー大手企業は、どのような課題を認識し、また対応を進めているのか。各社の取り組みを聞く。
Q. ユーザーにとっての広告体験の品質を向上させるための取り組み。
A. 広告掲載に関するガイドラインを設け、広告主から入稿される入稿物に対してユーザーにとって不利益となる表現などがないか、ユーザーに誤解や誤認を与えるような表現がないか、ユーザーが不快と感じるものや、青少年の保護育成上好ましくないもの、肌の露出度の高いクリエイティブなどがないかなど、様々な項目において事前確認を徹底し、それらの基準は広告主にも提示しています。
Q. 表示内容に問題のある広告を排除するために取り組んでいること。
A. キーワードに紐づき表示されるような広告については、放送禁止用語やアダルト系のワードなど、ユーザーが不快に感じるようなワードでの広告表示がないよう、システムでの制御も実施しています。この他、ユーザーから通報の内容、法律などの変更、景表法など行政からの指導についても随時確認し、不適切であると判断した際には広告の配信を停止する対応もしています。
Q. 広告を受け取るユーザーのプライバシー保護の観点から取り組んでいること。
A. 楽天グループにおけるプライバシー保護は、各国のプライバシー関連法令...
あと60%