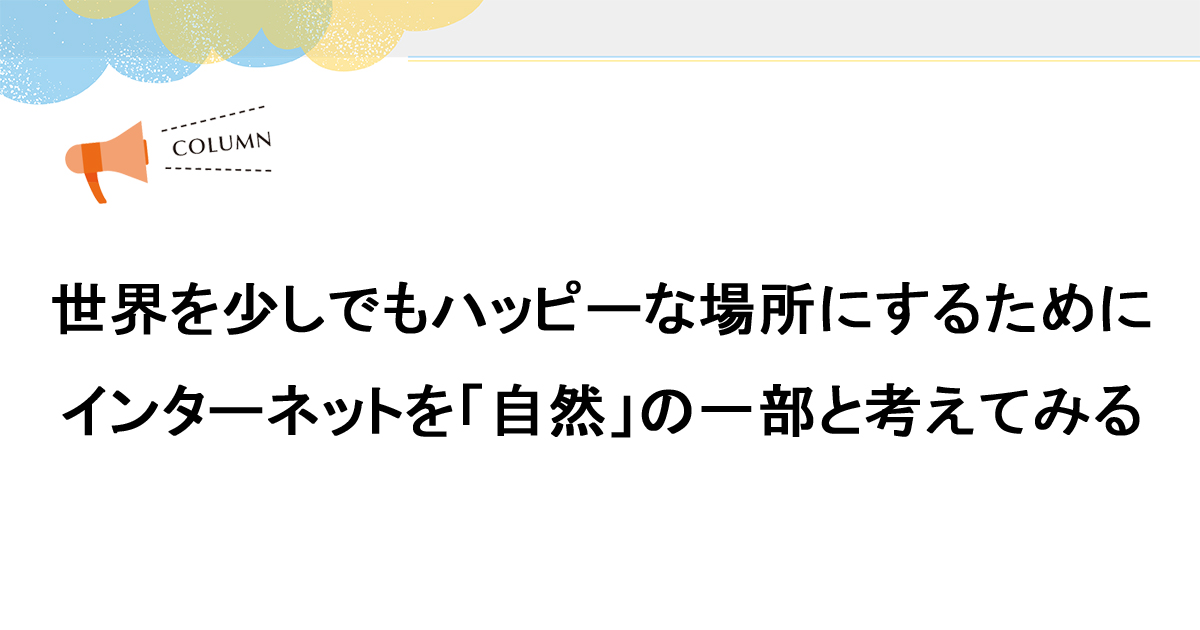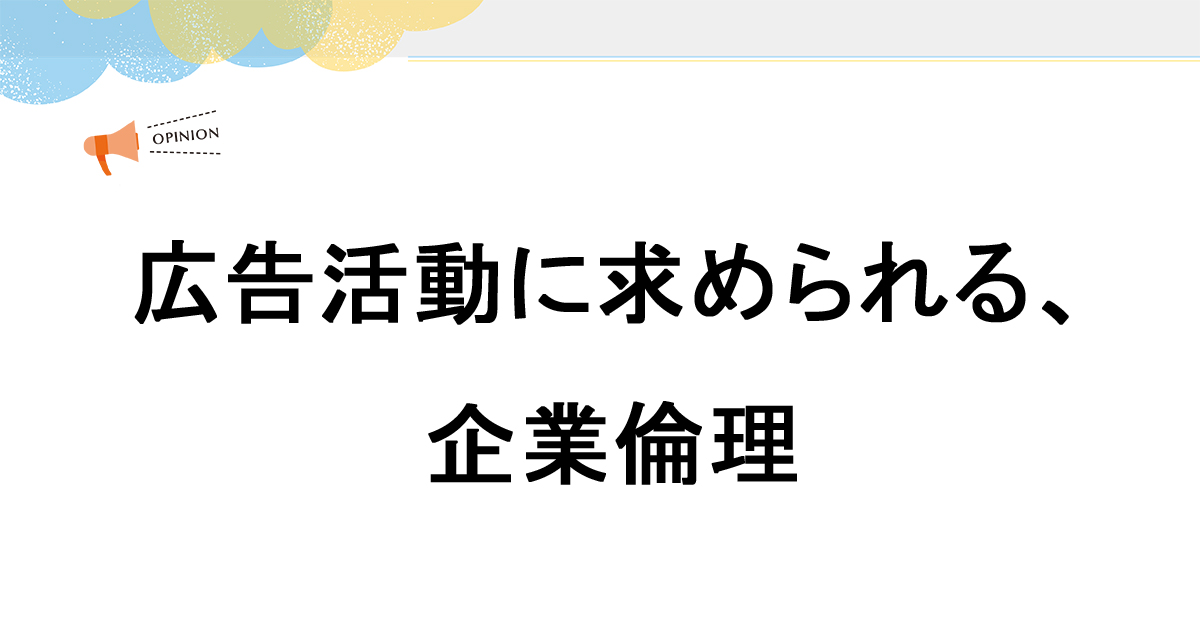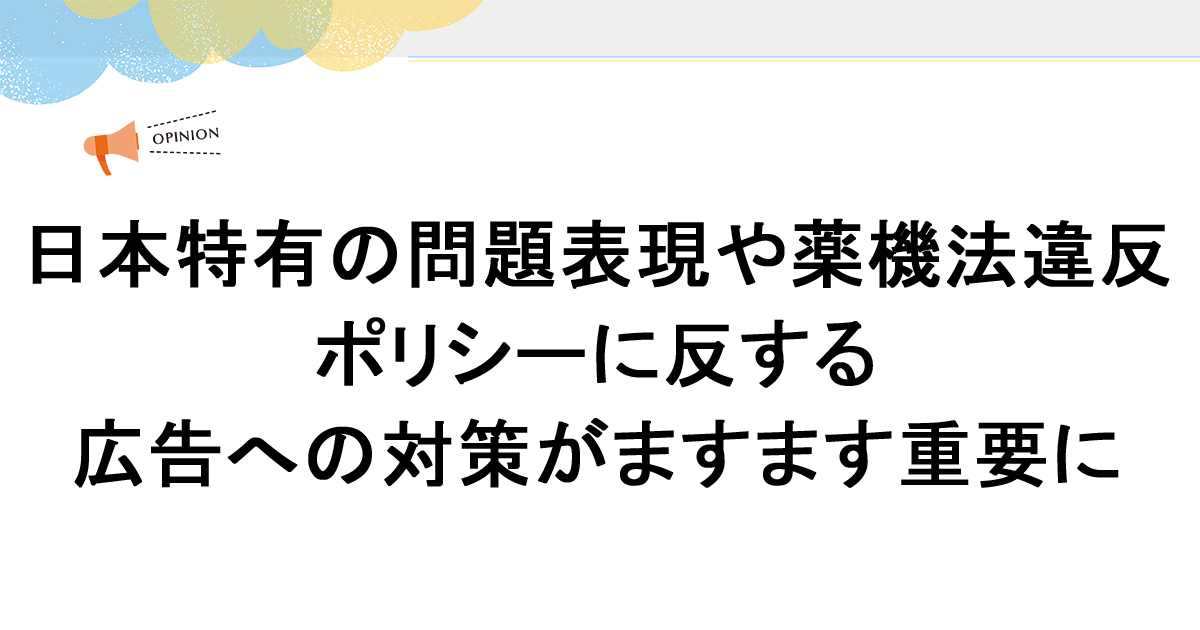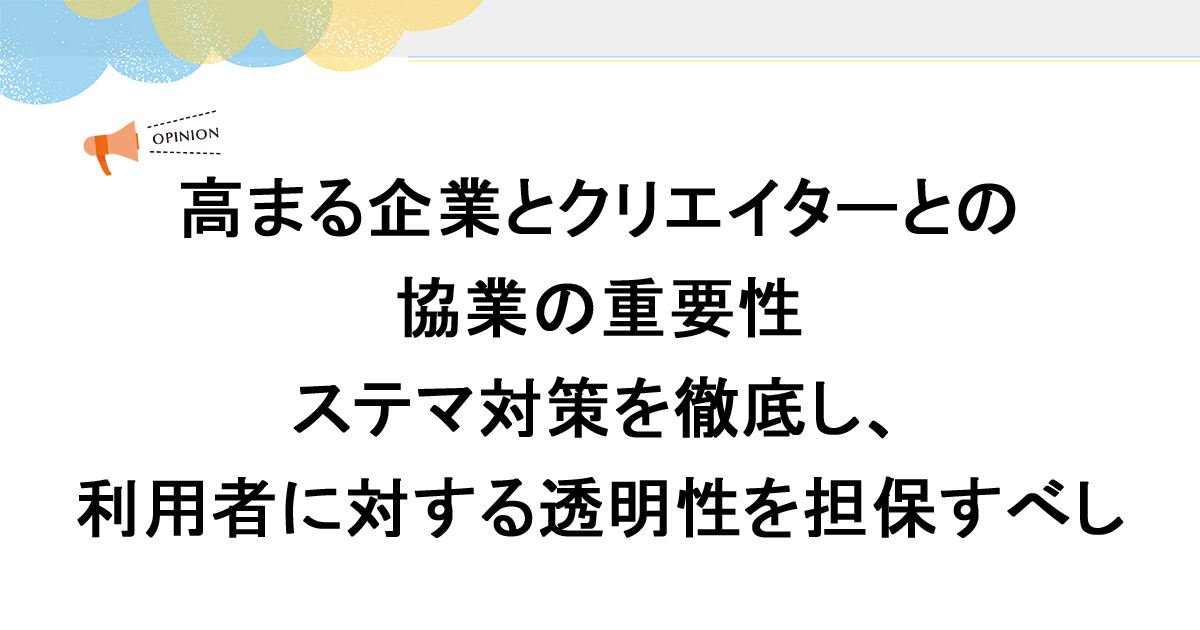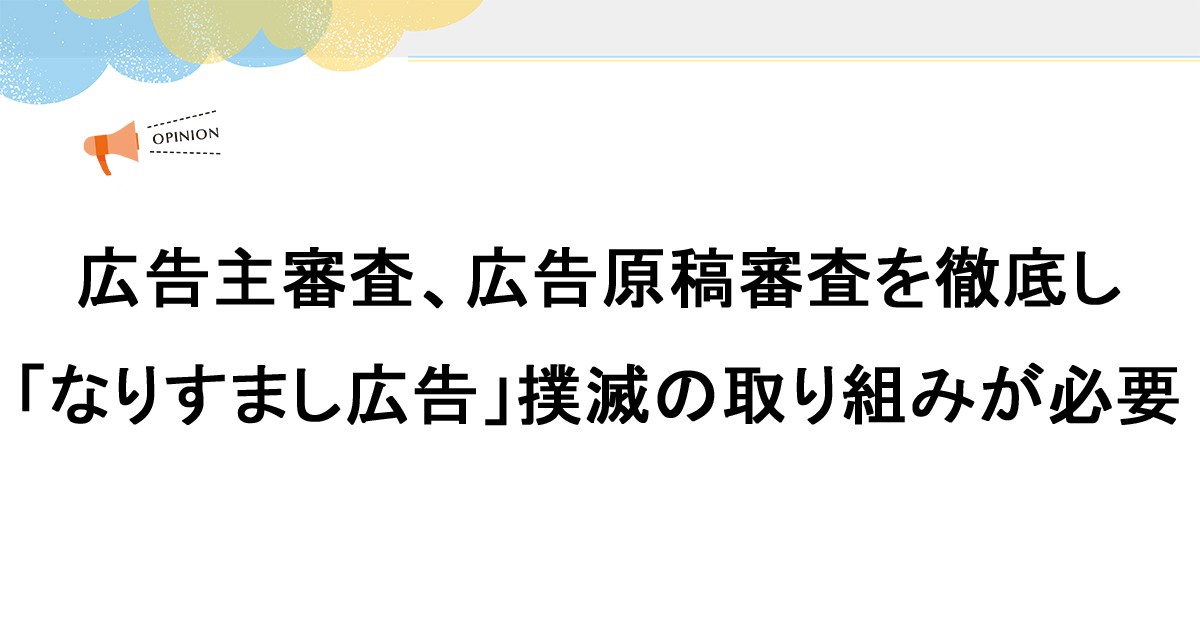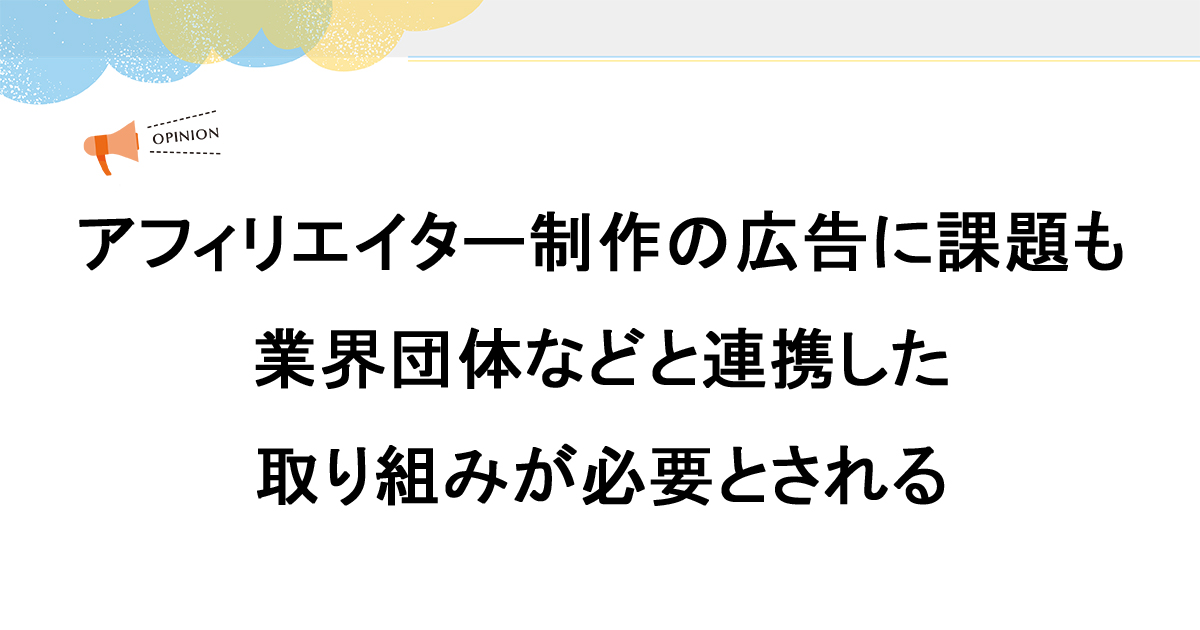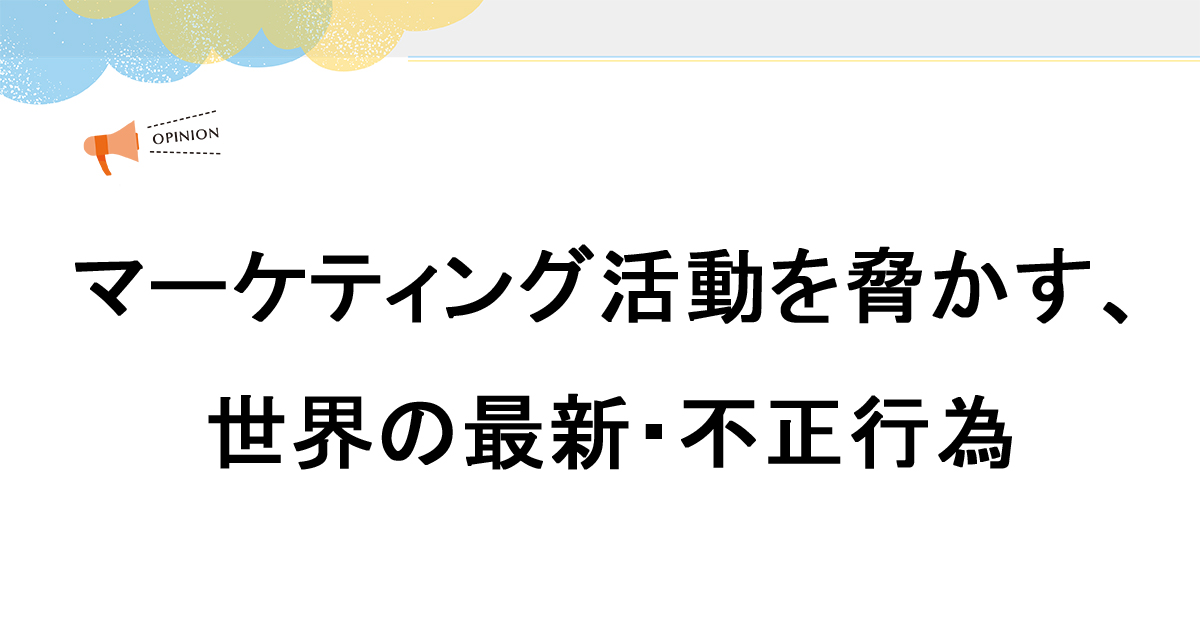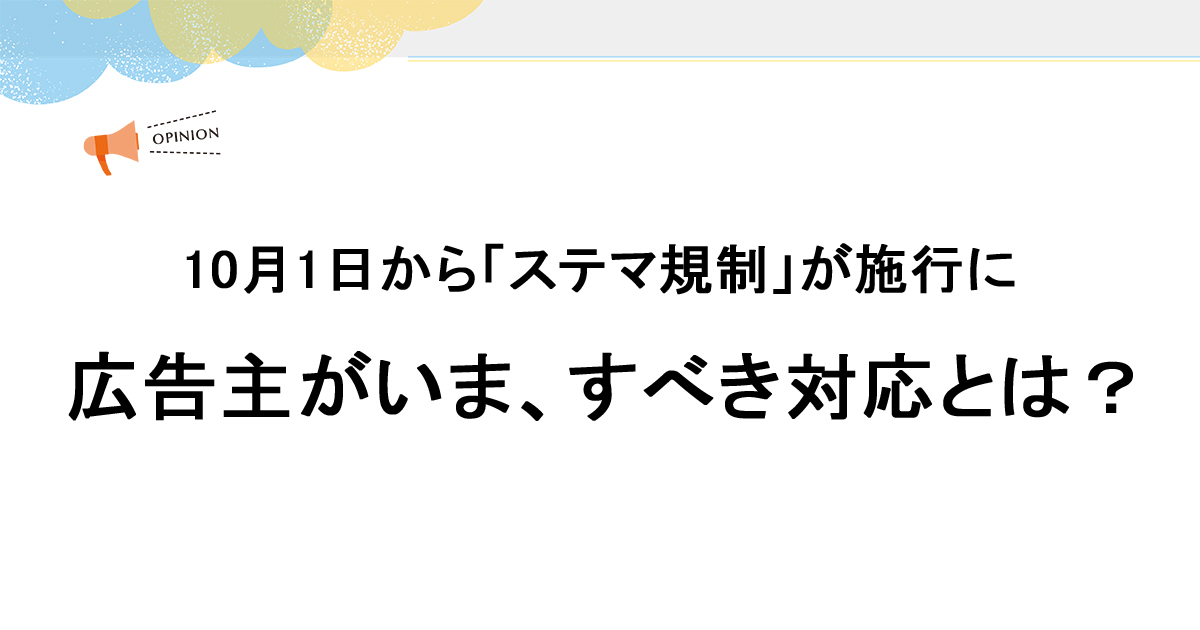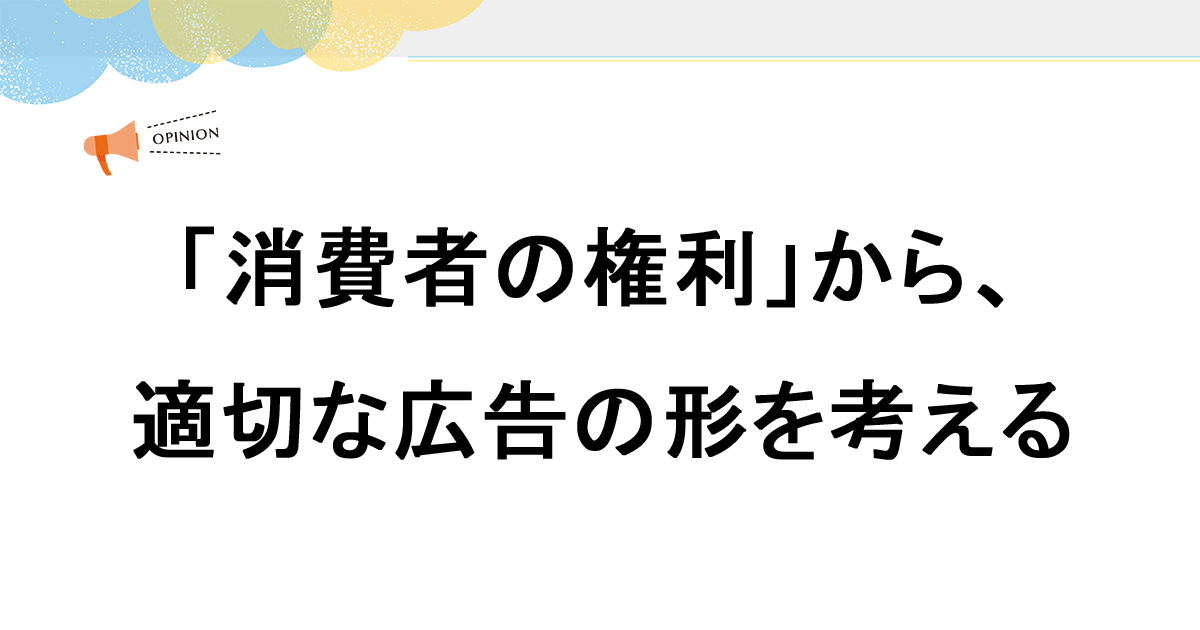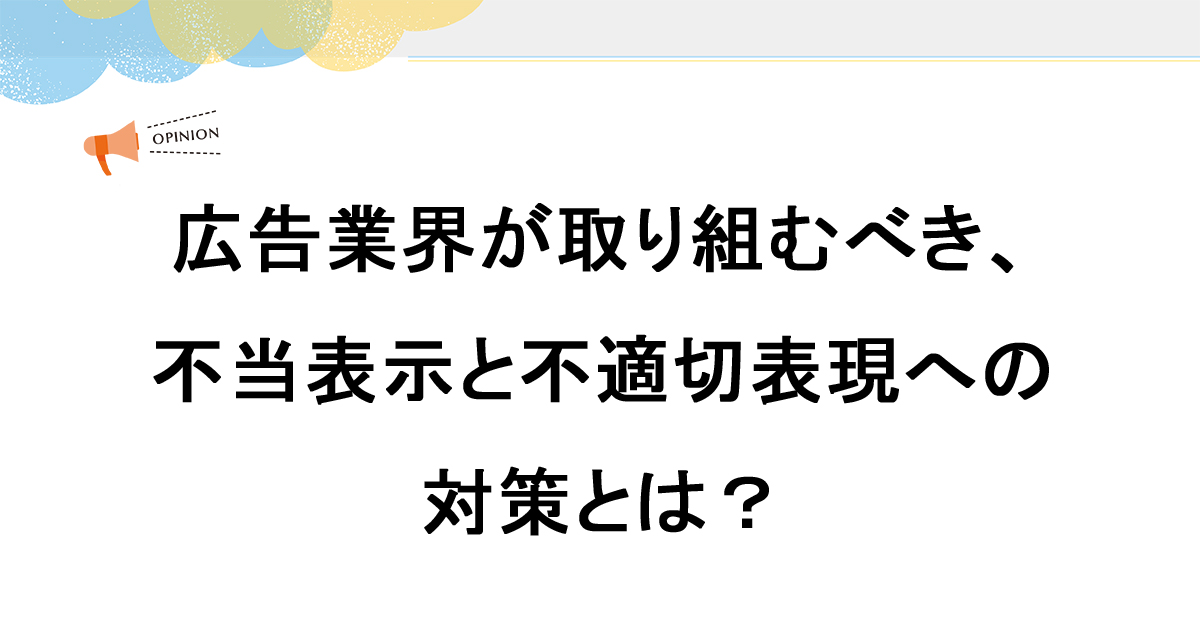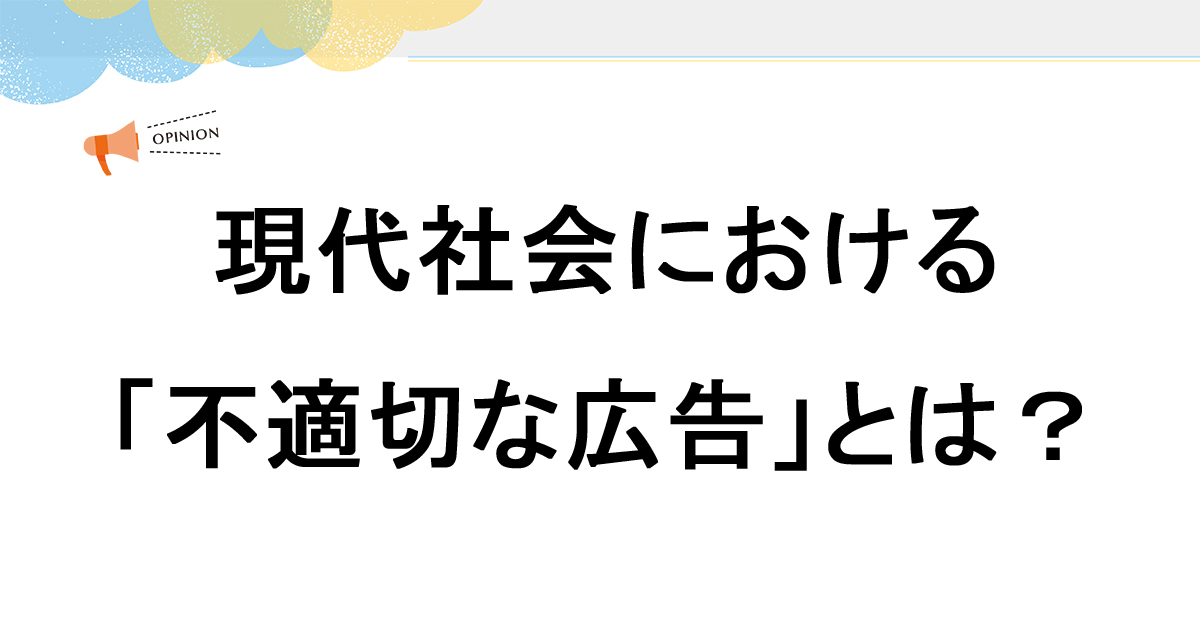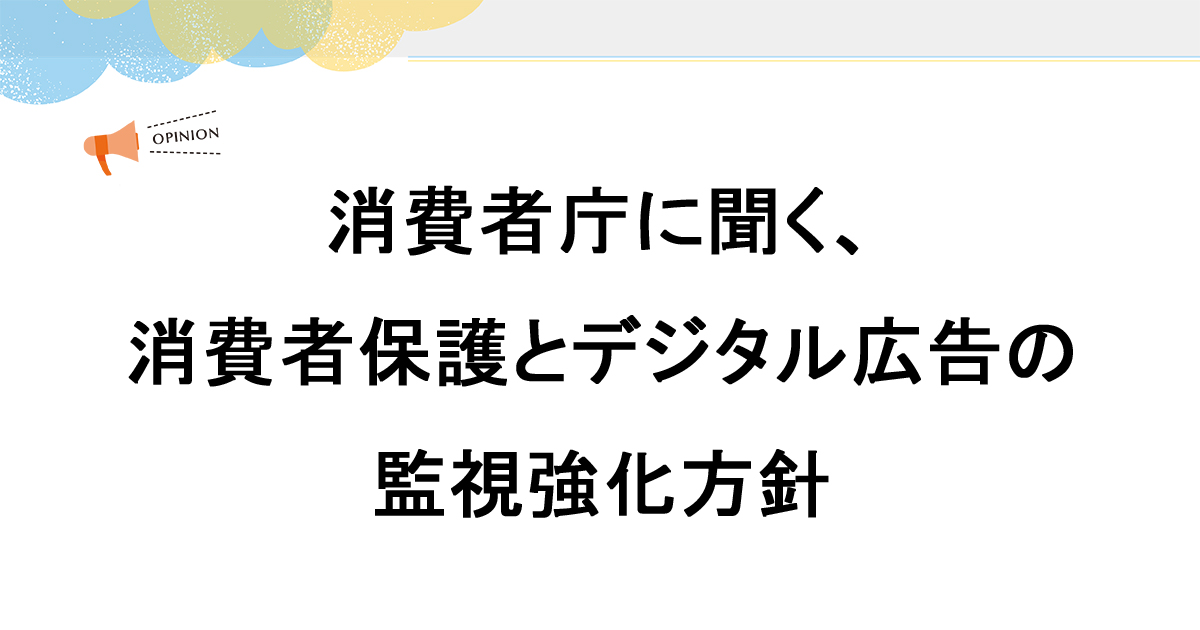デジタルマーケティングの急速な発展により、オンライン上での顧客接点やビジネス活動が増加。その一方で、不正トラフィックへの対応などセキュリティリスクへの備えも企業にとって急務となっています。ネット広告にひそむ多様なリスクとその対策についてチェク・ジャパンの林田幸恵氏が解説します。
Webサイトのトラフィック 平均で27%が不正!?
近年、デジタルマーケティングの世界においてセキュリティの問題が注目されてきました。5年程前までは、多くのマーケターにとってセキュリティ戦略は未知の領域であり、また自分たちの課題ではないと感じられていました。しかし、デジタルマーケティングの急速な発展により、オンライン上での顧客接点やビジネス活動が増加するにつれて、個人情報の保護やデータ漏洩のリスクが浮き彫りになりました。
しかし、今のデジタルマーケティングの風景は、ボットや偽ユーザーなどの不正トラフィック、またそれだけではないセキュリティのリスクに直面し、この変化が、マーケターにとってセキュリティ戦略の重要性を認識させる契機となりました。
当社の調査によれば、Webサイトのトラフィックの27%が不正トラフィックであり、その手法には、ボットネットやデータセンター、クリックファームなどが含まれています。これらの実態のないトラフィックは、マーケティングの効率を低下させ、企業の収益に大きな打撃を与えています。例えば、スーパーボウルやブラックフライデーなどの大規模なイベントが実施される時期には、偽ユーザーによる広告表示や偽造サイトなどのオンラインショッピングが顕著に増加します。
当社がECサイトに特化した調査をした結果、スーパーボウル当日にECサイトへ流入したトラフィックの21.6%が、偽物であったことが判明し、スーパーボウルのパフォーマンス指標が広告主にとって過大評価されている可能性があることが明らかになりました。
ペイドマーケティングの領域でも、不正クリックの問題が深刻化しています。ボットやクリックファーム、さらには競合他社による不正クリックは、広告予算の浪費を引き起こしています。このような不正クリックによる機会損失は、年間で4兆2000億円にも上ると言われています。
また、偽ユーザーのデータ流入は、ペイドマーケティングのオーディエンスセグメントや...