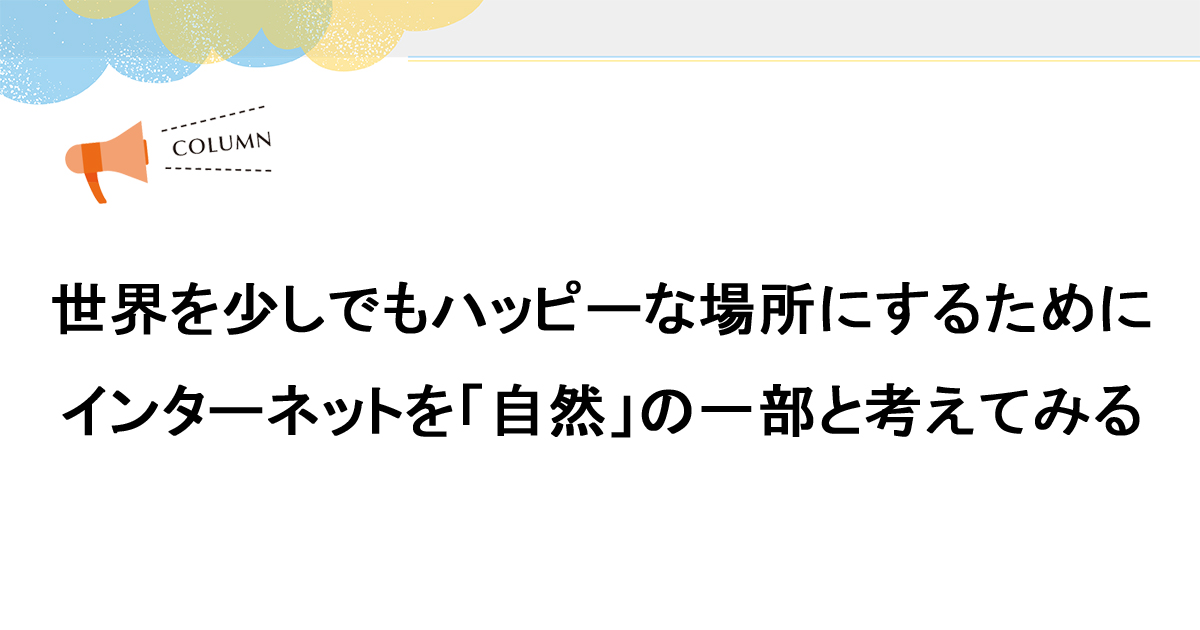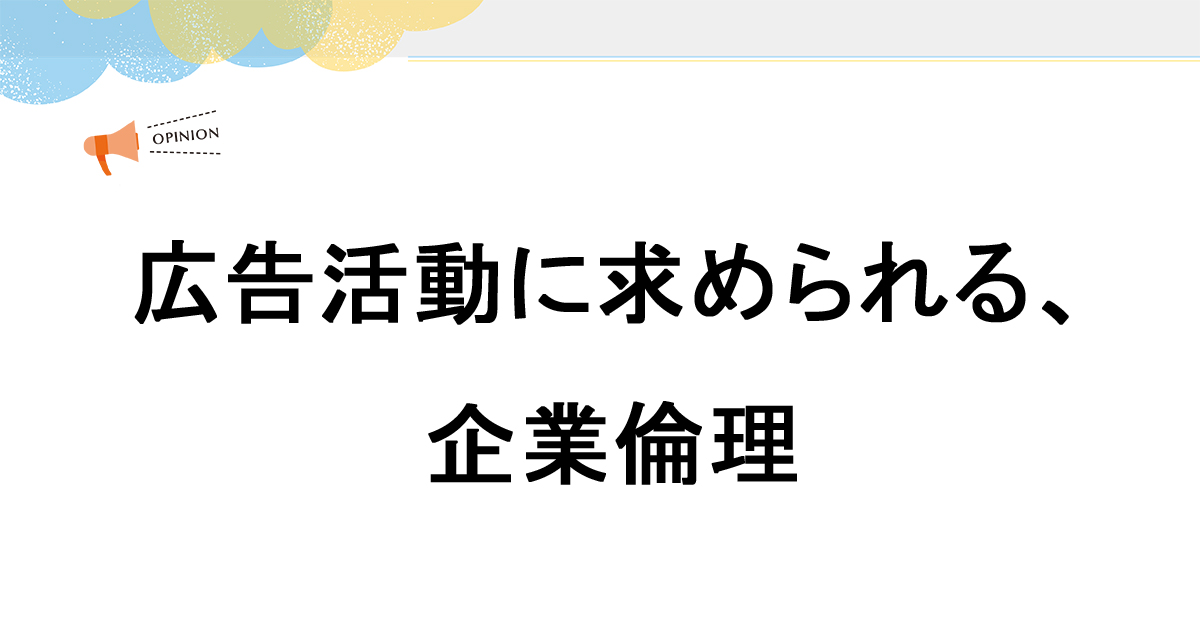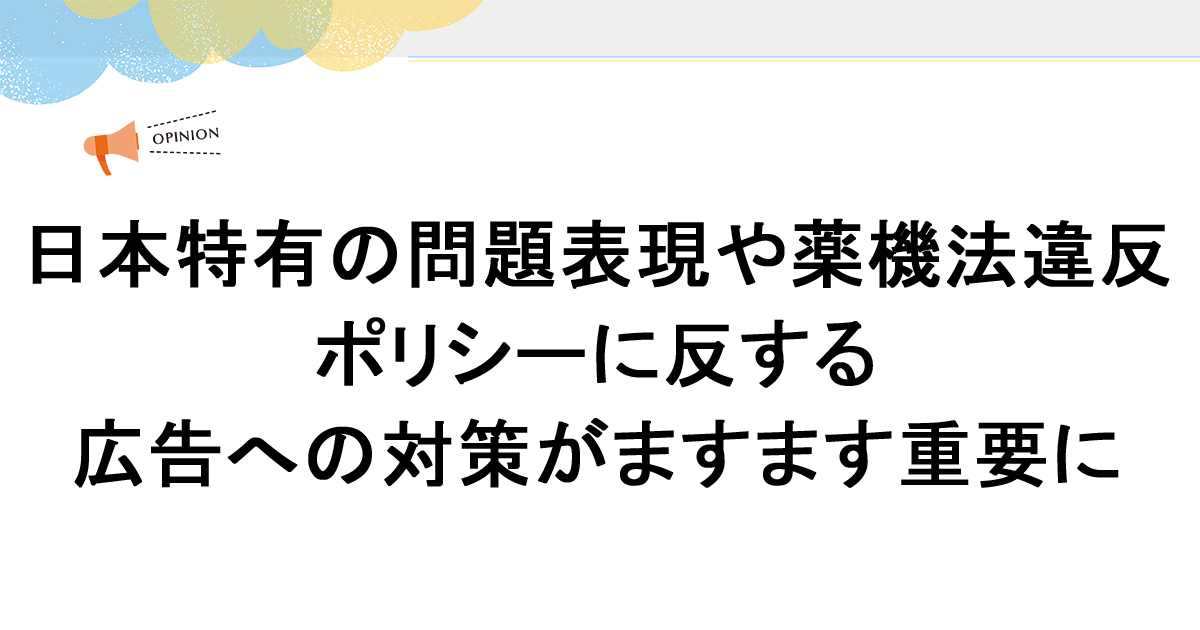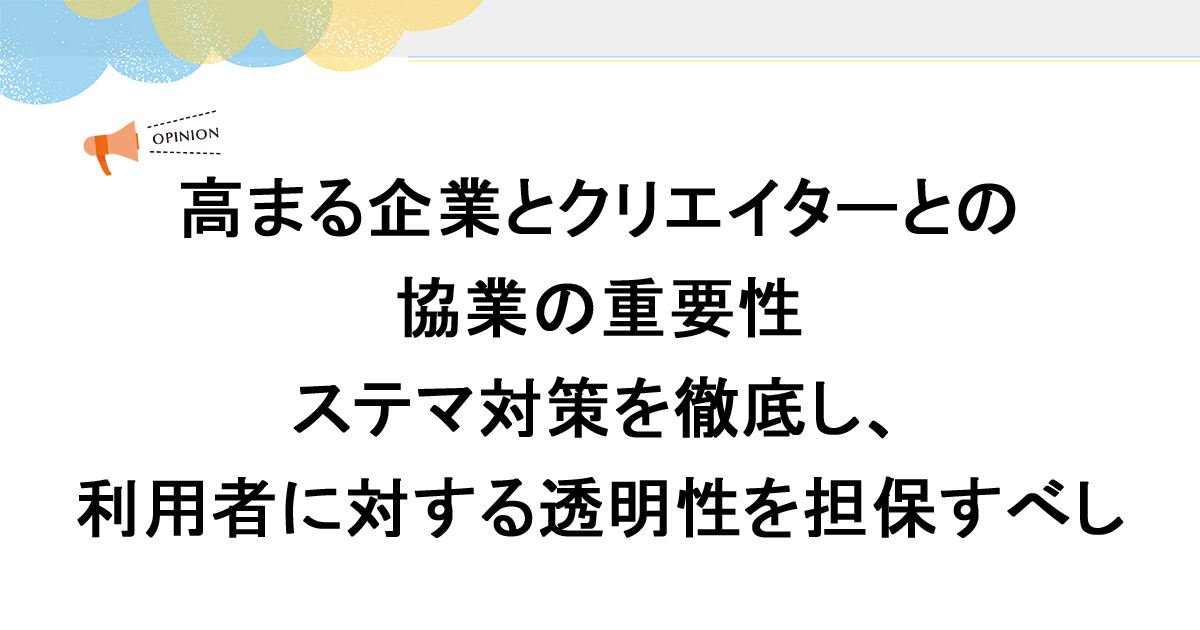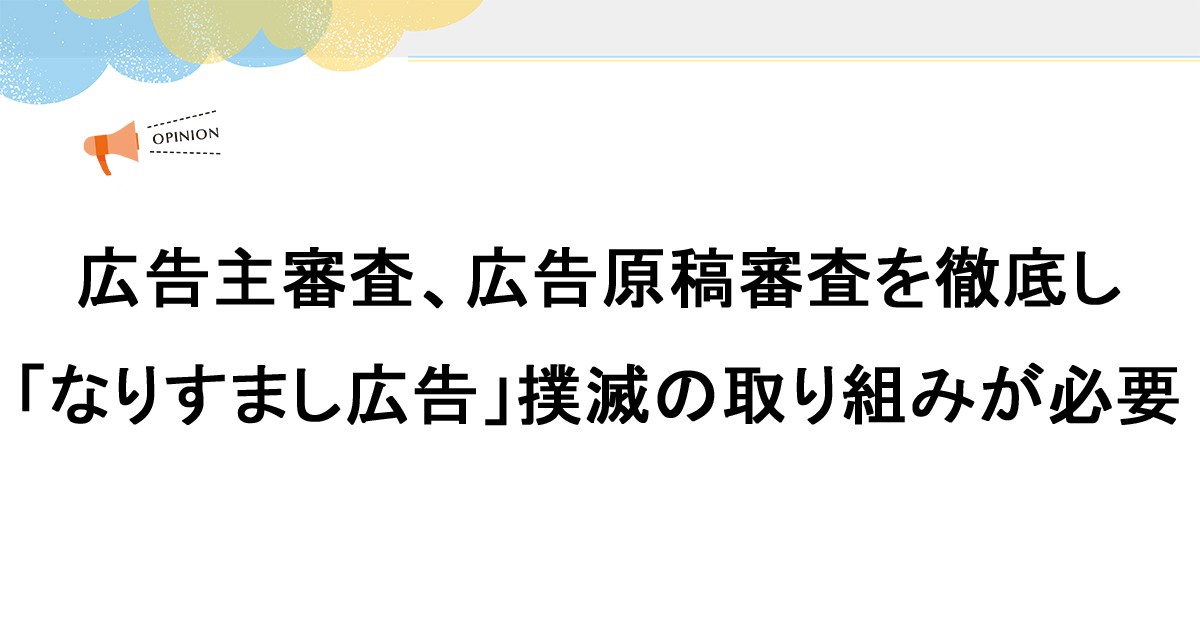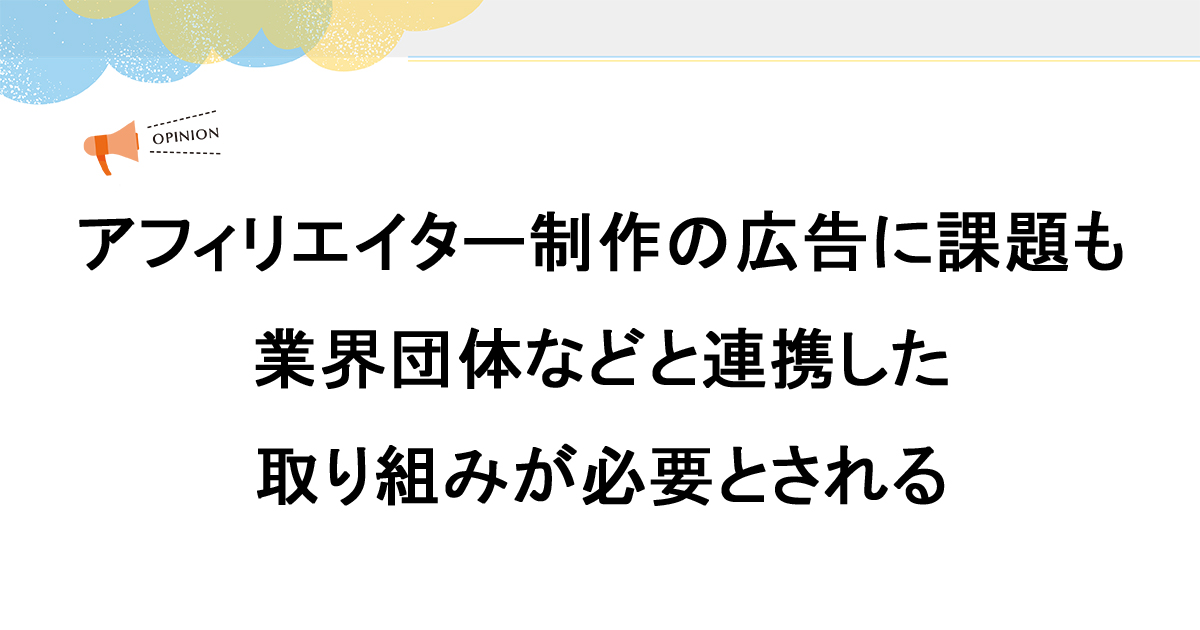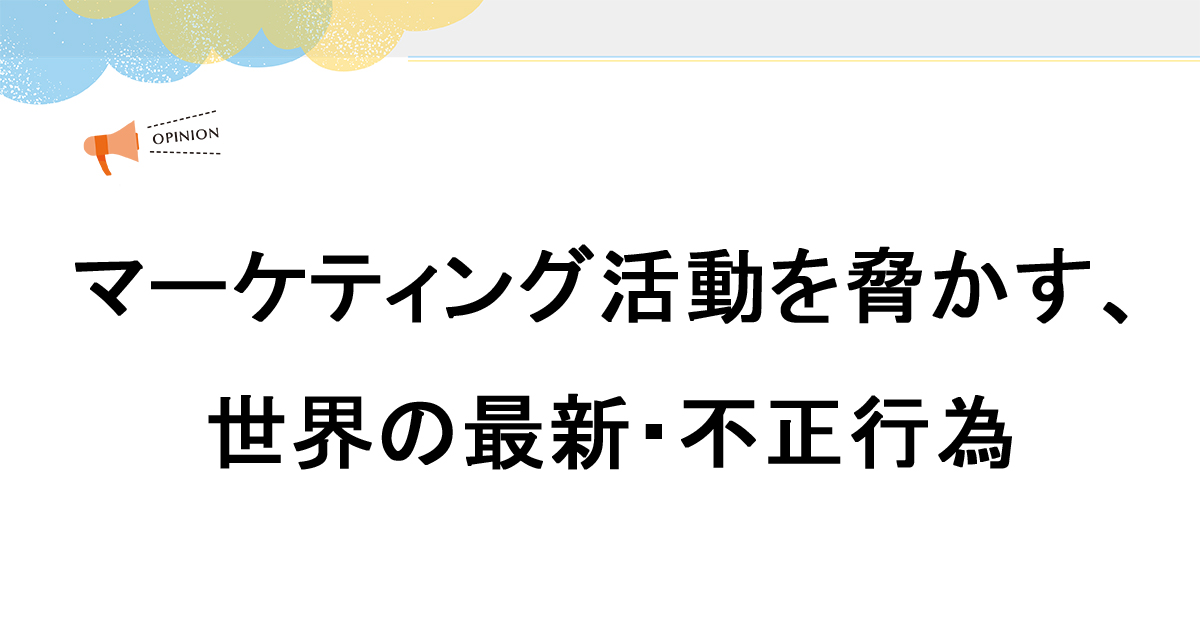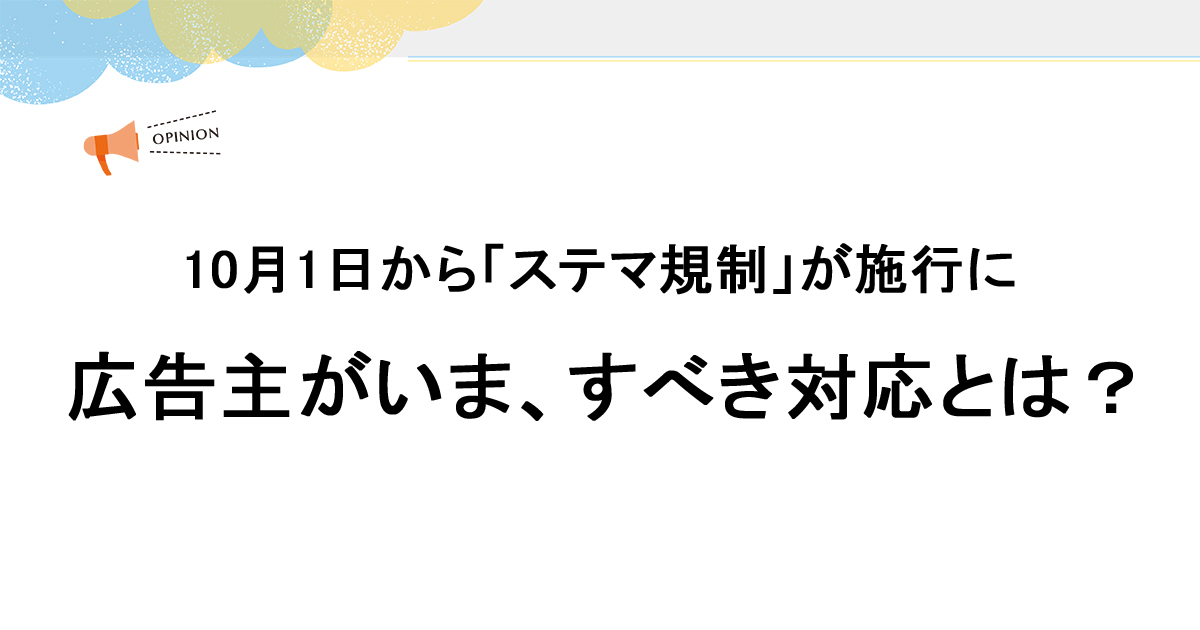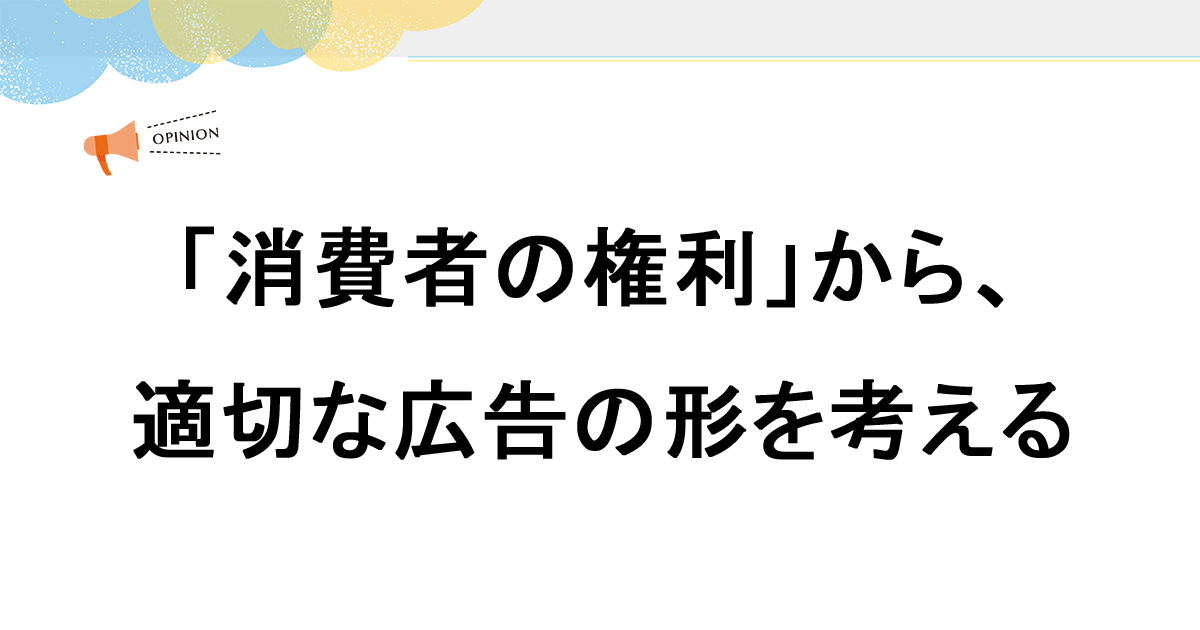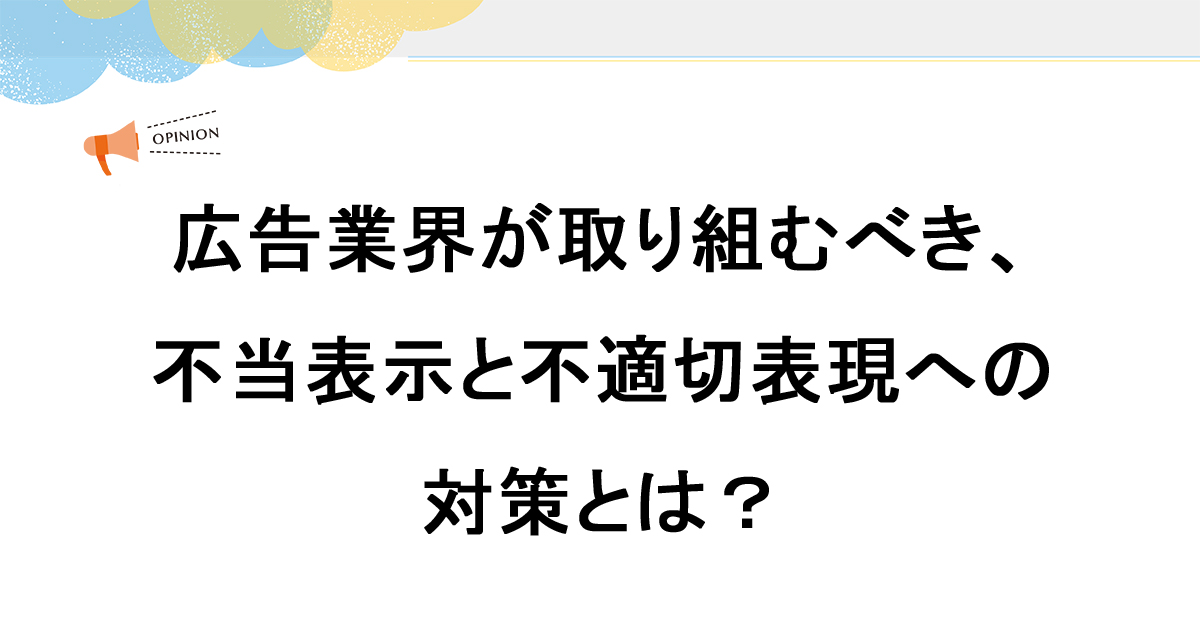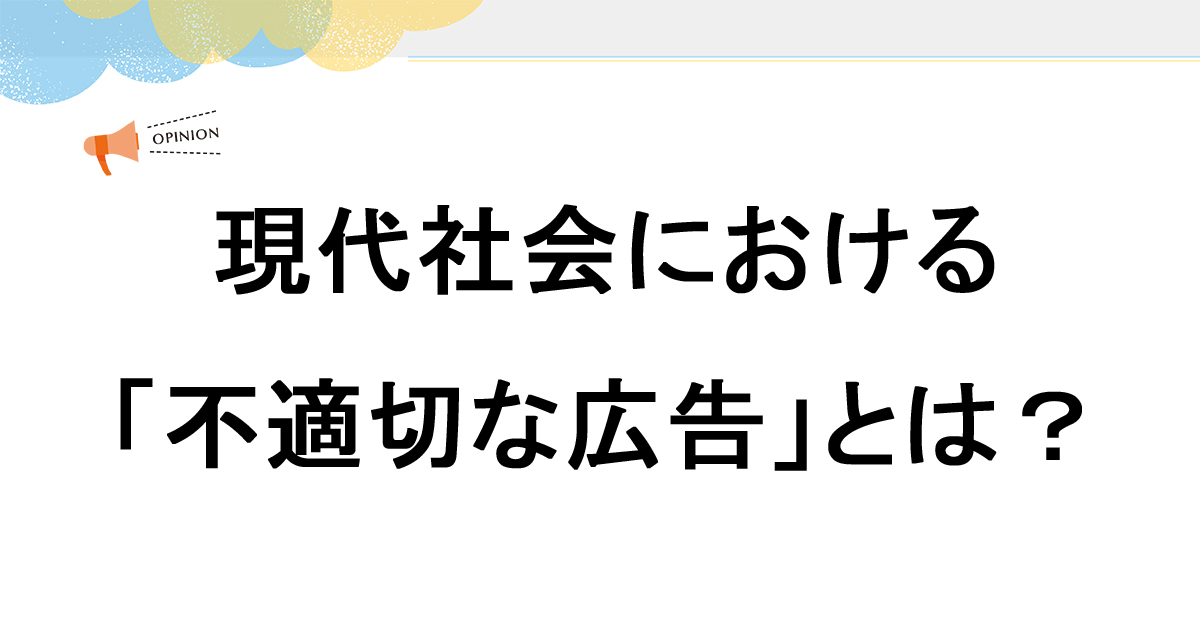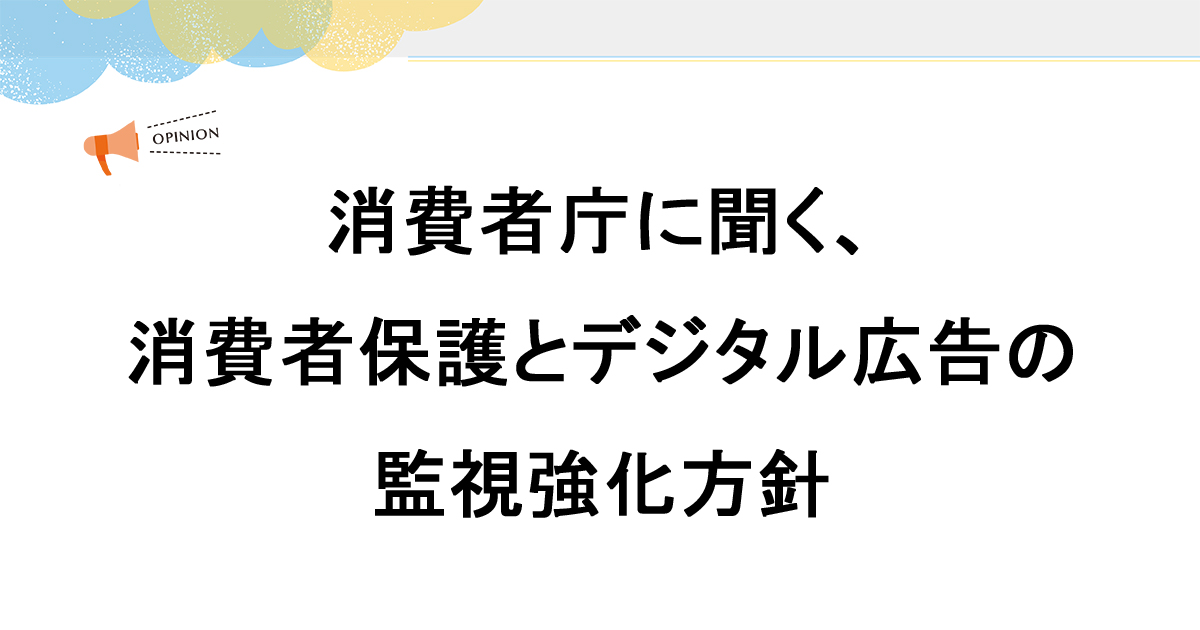ユーザーにとってのインターネット広告の印象を良好なものとしていくためには、広告主、広告会社のみならず、インターネット広告の枢軸を担うプラットフォーム側の対応が欠かせない。昨今、広告の体験品質の問題が顕在化するなか、国内で活動するプラットフォーマー大手企業は、どのような課題を認識し、また対応を進めているのか。各社の取り組みを聞く。
Q. ユーザーにとっての広告体験の品質を向上させるための取り組み。
A. Metaが提供する広告の最大の特長は、マス広告と異なり、利用者ごとの興味関心に合わせてパーソナライズされた広告を表示することです。利用者の情報や普段のアクティビティに基づいて広告を表示することで、利用者は自分に合ったブランド・商品と出合うことができ、これが良質な広告体験を生み出すと考えています。2022年には「広告トピック」という、利用者が特定のトピックに関する広告の表示を減らすことができる機能も導入しており、利用者自身が広告体験を管理しやすくする取り組みも継続しています。
Q. 表示内容に問題のある広告を排除するために取り組んでいること。
A. 当社が許可あるいは禁止する広告コンテンツの種類やポリシーの詳細は広告規定として定めており、Metaのプラットフォームに掲載される広告は、すべて自動審査および場合によってはマニュアルで審査しています。また、違反コンテンツに共通する特徴を分析し、それを基にポリシーの施行を改善すべく検出技術モデルの規模を拡大するなど、ポリシーに違反する...
あと60%