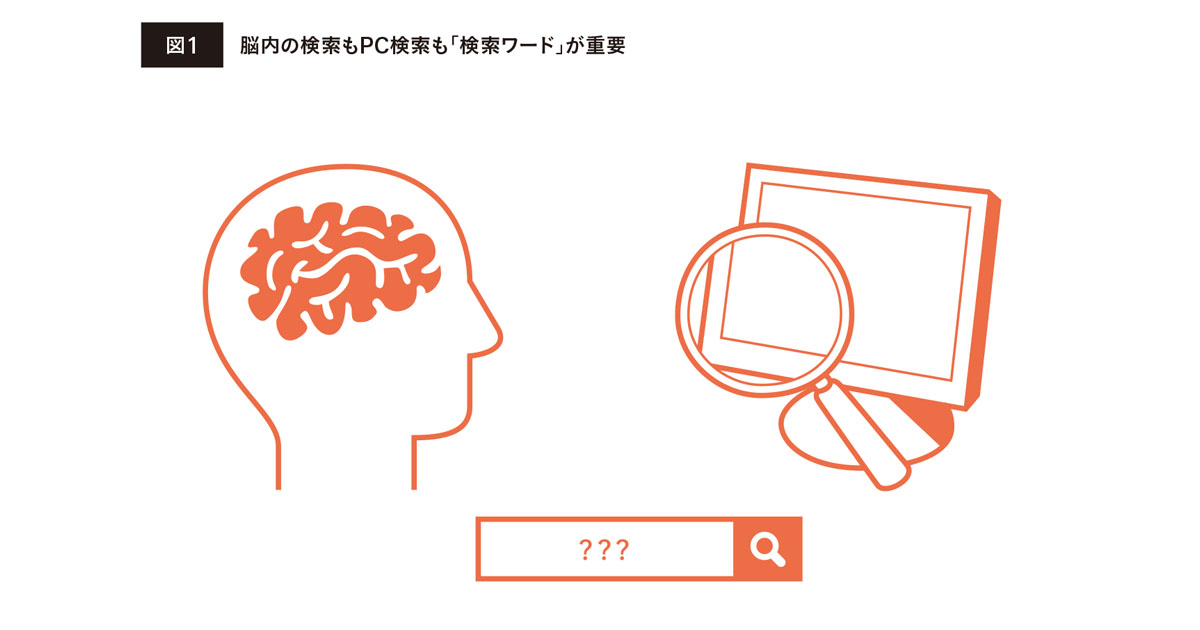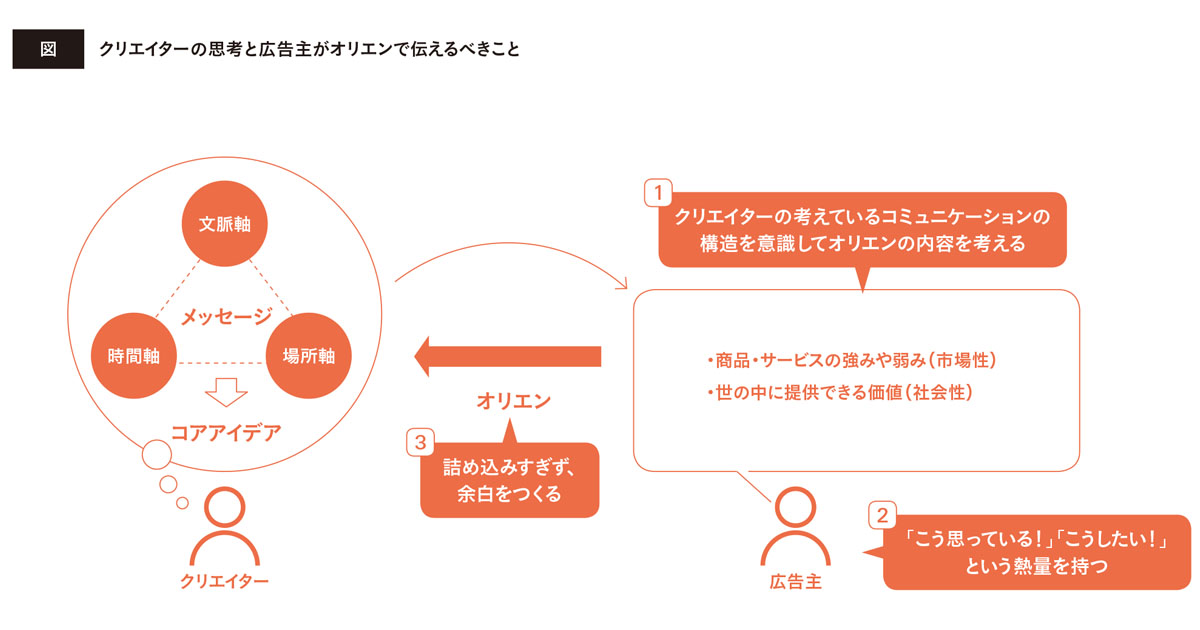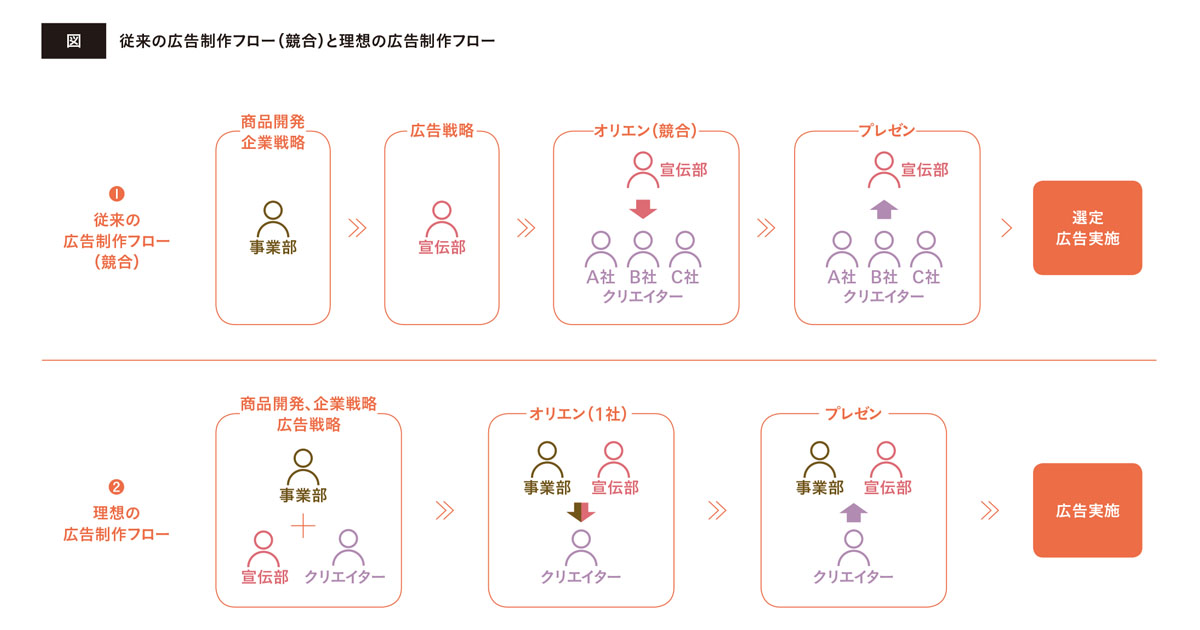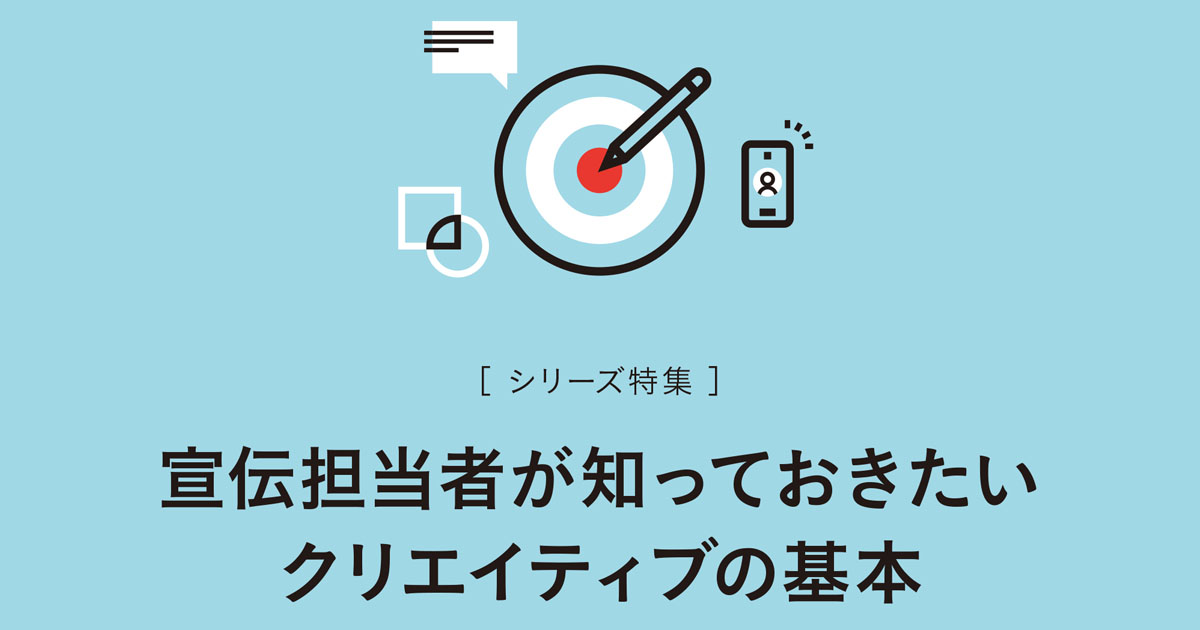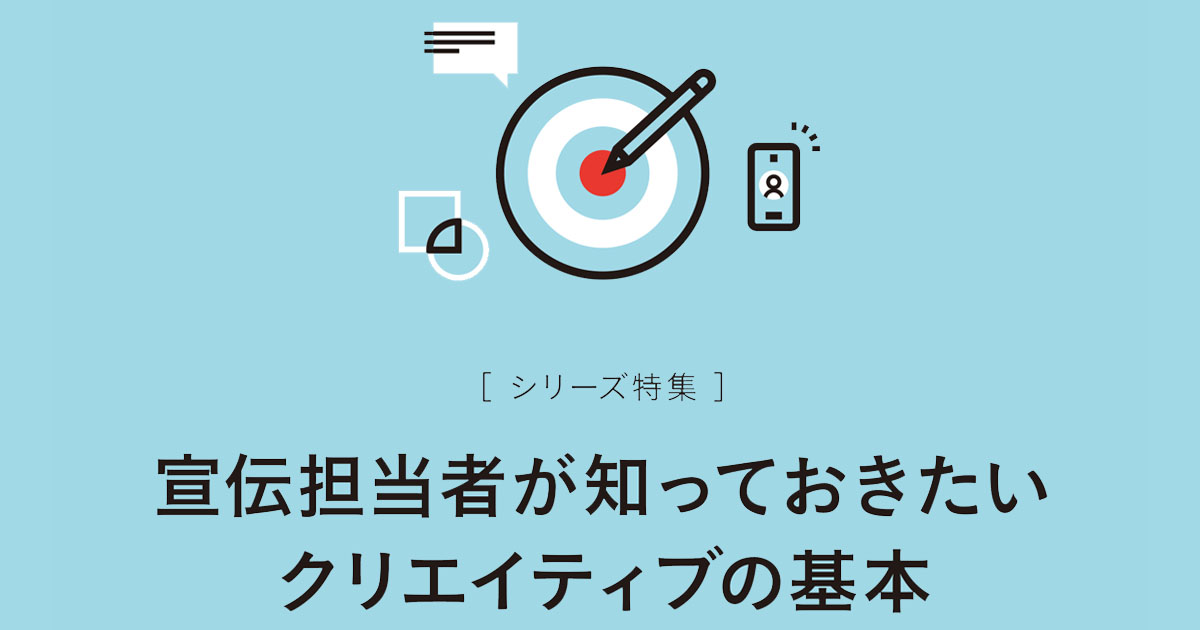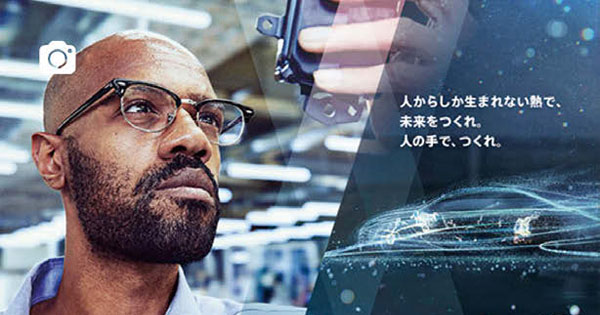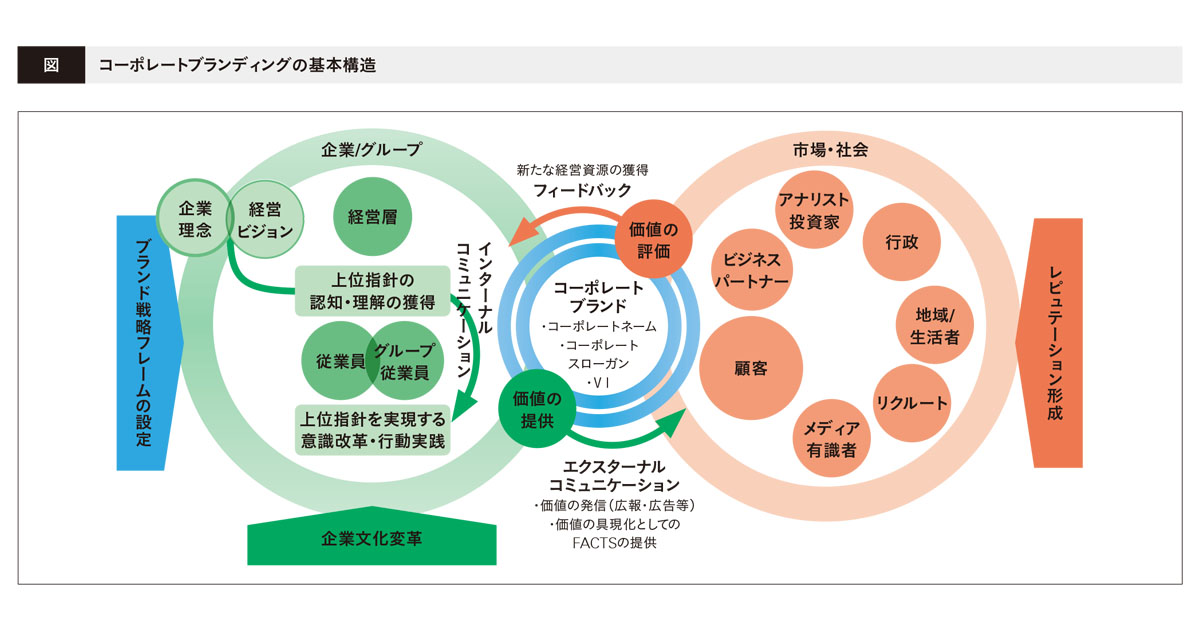今月のテーマ:企画の仕事に携わる人のための「情報収集・整理術」
日々、大量の知識と情報をインプットし、その情報から新たなインスピレーションを生み出すマーケターやクリエイターなど企画に携わる仕事においては、「情報の収集」はもちろん「整理」も重要な仕事と言えます。本特集ではマーケティング、広告クリエイティブの仕事において、広くアンテナを張り巡らせ、積極的に情報を収集し、アウトプットにつなげているマーケターとクリエイターが、それぞれの「情報収集・整理術」について解説します。
- 自ら新しい体験をし続けて、一次情報を増やす。
- インプットと同時にアウトプット。瞬間に感じたことを記録し(Twitterでもメモ帳でも)、まとめて、人に話してみる。
- 情報の整理はしない。一度、インプット・アウトプットをしておくと、大切なことは思い出せる。
企画の仕事に携わる人のための「情報収集・整理術」
日頃から情報をインプットして3つの能力を磨く
週明け月曜日、のんびり出社すると、部長が近づいてきます。「最近、若者のあいだでXXが流行しているらしい。うちはXXについてどう考えているんだ?」と(「部長」は、あなたの環境に合わせて、「社長」「CMO」「課長」「クライアント」などと読みかえてください)。
あなたはどう答えますか?
A:「XXですか。本格的な普及はこれからではないでしょうか」と、仕事を増やさないよう守備固め。
B:「XXをご存知なんですね!当社の課題を解決できる可能性があります。情報をまとめて報告します」と、前向きを通り越して前のめりなスタンス。
私は自他ともに認める「新しもの好き」なので、後者のBを選びます。部長が「XX」なる謎のバズワードに興味を持ったのは絶好のチャンス。数日のうちに企画書をつくります。
このXXは、少し前ならTwitterやFacebookなどのSNS、スマートフォンアプリ。最近ならInstagramやTikTokなどの新興SNS、MA(マーケティングオートメーション)あたりでしょうか。
早速、XXを調べようとしたものの、情報量が多くてどこから手をつけたらよいのかわかりません。そうならないよう、常日頃から情報をインプットし、整理しておこう、というのがこの記事の狙いです。
しかし情報のインプットはともかく、整理はしません。良くも悪くも、マーケティングの情報は年々増加し、もはや氾濫しています。Webの記事、専門誌、書籍、セミナー、展示会など、情報を集めるには時間がいくらあっても足りません。しかし、日常の情報への接し方を変えるだけで、報告書づくりや企画は簡単になります。そこで、大量の情報から高速にまとめるための「情報インプット即アウトプット術」を紹介します。
情報インプット即アウトプット術① 中国武術に学んだ「身体に通すこと」
「身体に通しておけば、大切なものは身体に残る」──情報インプット即アウトプット術は、中国武術の漫画からヒントを得ています。主人公の少年が、正式に武術の門人になったところ、多くの先輩たちがさまざまな武術を教えようとします。たくさんのことを覚えられないと混乱する主人公に、老師が2つのことを語りました。
(1)身体に通せば、大切なものは身体に残る。
(2)本質をつかめ。枝葉に惑わされるな。
〈出典:松田隆智原作、藤原芳秀作画の『拳児』(小学館)〉
武術の修練のように、マーケティング情報を身体に通すため、インターネットの情報発信やマーケターとの会話を組み合わせるのです。
マーケティングの情報が増大しているので、XXを常日頃からウォッチしていることは、まずありません。XXをさくっと調べられるよう、以下の3つの能力を磨くのです。それぞれ、企画を考えるうえで必要な情報に紐づいています。
(1)高速要約力:XXって要は何?誰のどんな課題を解決できるの?
(2)事例収集力:XXってほかの業界ではどう使われているの?
(3)ツッコミ対策力:XXのデメリットはないの?どれだけのコストがかかるの?
マーケティングの情報に日々接しているうちに、3つの能力がレベルアップするのが理想です。
情報インプット即アウトプット術② 新しい体験で一次情報を増やす
マーケティング情報を、まず一次情報と二次情報に分けます。
①一次情報(自分自身の見聞と体験):日々、目にするさまざまな企業によるマーケティング活動全般や消費者行動。
②二次情報(他者から得た情報):メディア経由、マーケター経由、自分の関係者経由。
まず、最優先すべきは一次情報。二次情報は他者を通した情報なので、他者の意図やフィルターの影響を受けています。私は自身で体験し、感じたことを重要視し、体験と同時にアウトプットします。
具体例を紹介します。2019年5月9日、牛丼の吉野家が「ライザップ牛サラダ」を発売しました。早速、お昼にいただき、TwitterとFacebookに投稿(※高速要約力がアップ!)。
Twitterはほとんど反応がなかったものの、Facebookではたくさんのいいね!をもらい、いくつかコメントもありました。
では、なぜTwitterとFacebookで反応が異なったのでしょうか? …