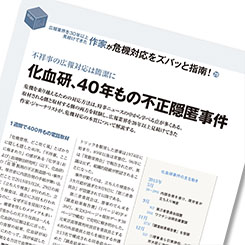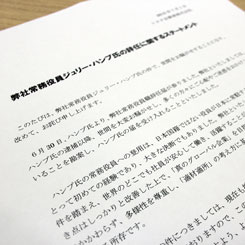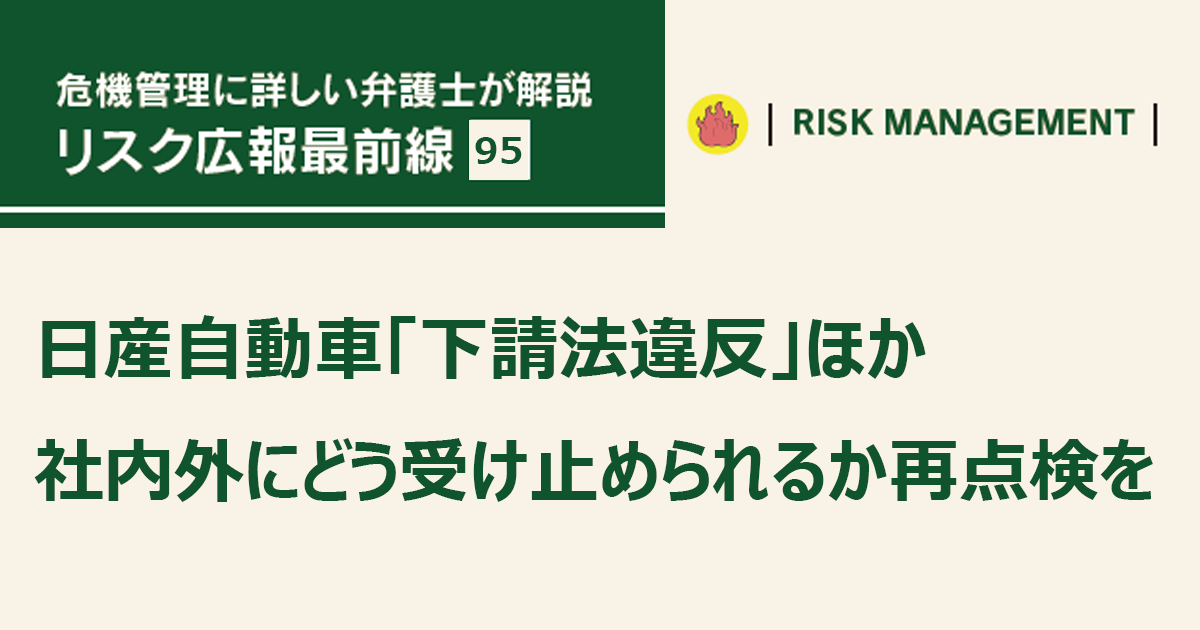危機を乗り越えるための対応方法は、時事ニュースの中から学べる点が多くある。取材される側と取材する側の両方を経験し、広報業界を30年以上見続けてきた作家・ジャーナリストが、危機対応の本質について解説する。
1週間で400件もの電話取材
「危機管理、どこ吹く風」とばかりに隠しも隠した40年。「不祥事、ここに極まれり」の感がある「化学及(および)血清療法研究所」(以下、化血研)の「血漿(けっしょう)製剤の不正製造隠ぺい事件」は、厚労省に内部告発の手紙が舞い込んだことで2015年5月28、29日の両日に「立ち入り検査」が行われた。立ち入り検査は、過去に20回も行われているのに、なぜ不正を見抜けなかったのか。癒着を怪しむメディアも多いが、厚労省からの天下り役員は一人もいないと化血研の広報は私に言った。
厚労省の査察の結果、化血研が40年もの長きにわたって、国が承認した製造方法と異なる方法で血漿製剤を量産しながら、推理小説さながらの巧妙な手口で徹底的に隠蔽し続けるという、組織ぐるみの“前代未聞の悪事”が露呈、メディアの追及の標的と化した。
書体を変えた二重帳簿の作成、紫外線照射による紙を古く見せるといったトリックを駆使した悪事は1974年に始まり、89年以後は常態化、96年には「常勤常務会」で報告されたが、異議は出ず、組織的隠蔽が黙認されることになった。
事件が動くのは、立ち入り検査から3カ月超が過ぎた9月9日に「第三者委員会」が設置されて以降である。
第三者委員会は、悪事のてん末を「調査結果報告書」(1ページ40字×36行。本文83ページ+個別データ38ページで構成)で克明に解き明かした。元東京高等裁判所長官を委員長とする6名の外部委員と彼らを補佐する弁護士13名で構成される同委員会がまとめた「調査結果報告書」は、11月27日に化血研に届けられたが、「東芝の利益水増し事件」で第三者委員会が作成した中立性に問題を残した報告書への対抗意識が強く感じられ、記述内容が濃密である。
《本委員会が本件不整合(筆者注:不正と同義)や隠ぺいの調査を通じて問題の根幹として感じたのは、化血研における「研究者のおごり」と「違法行為による呪縛」である》(第5総評)
メディアの取材は、化血研が熊本市にあることから、12月2日に厚労省内で行われた謝罪会見を除くと、電話で行われているが、会見翌日から9日までの1週間に化血研の広報が受けた電話取材は約400件に達したという。
化血研は一般財団法人ではあるが、大手薬品会社に位置づけられる470億円超の売上規模があり、インフルエンザ4種混合ワクチン、日本脳炎、B型肝炎など重要薬品のシェアが高く …