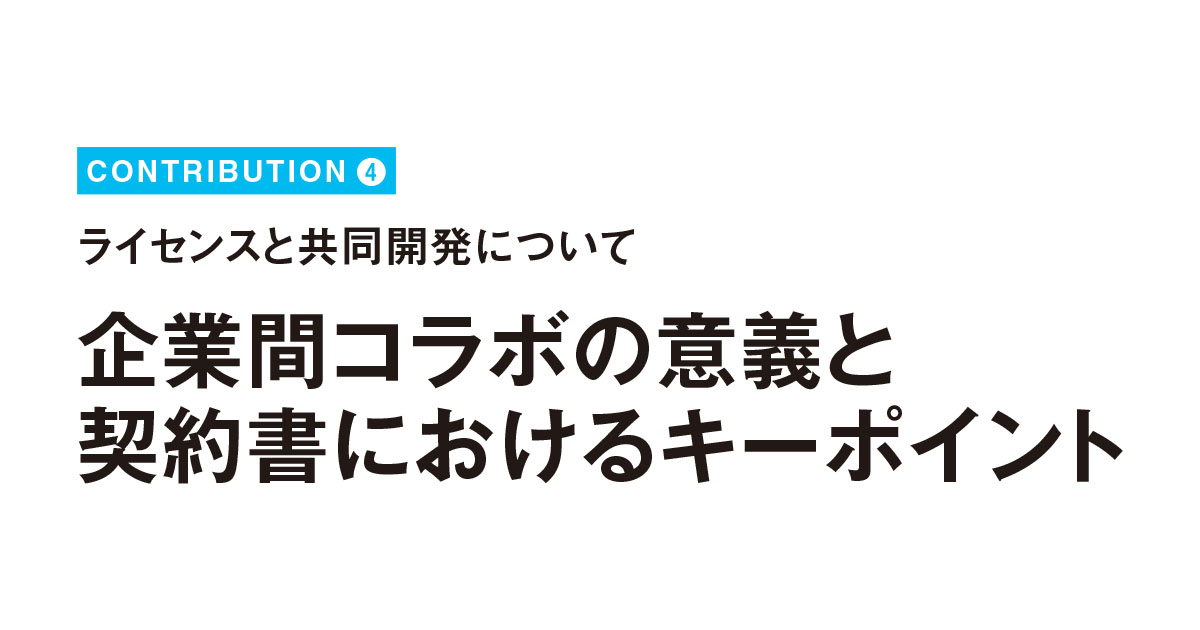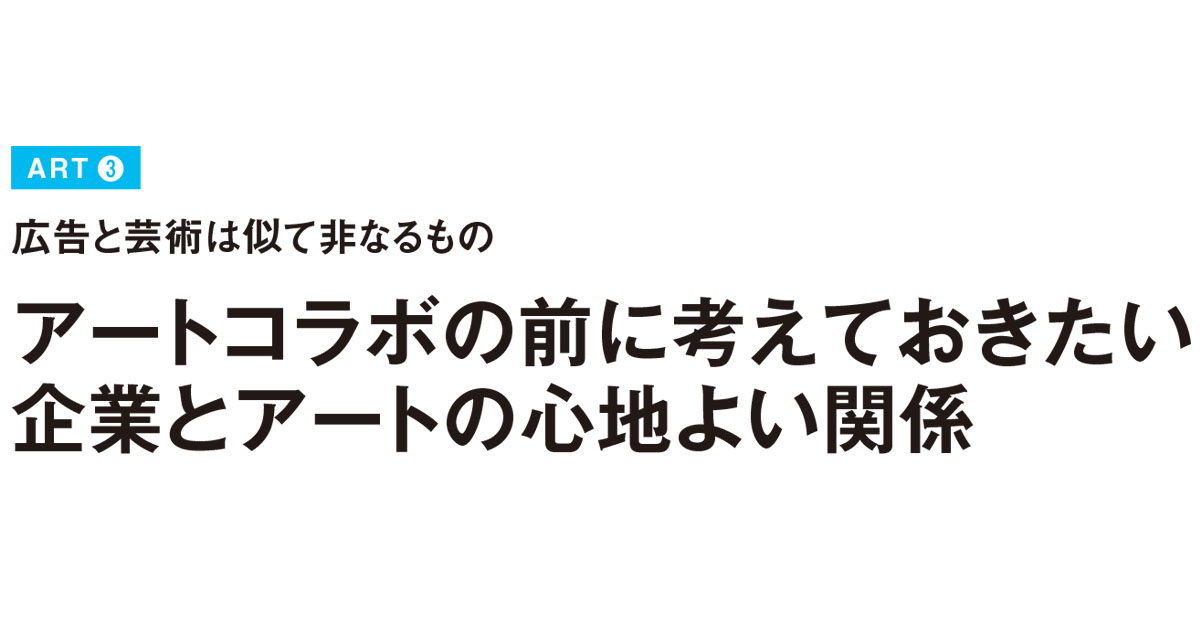キャンペーンレベルかプロダクトレベルかを問わず、コラボレーションは「共同戦線を張るプロジェクト」である。だからこそ、関係者をひとつのチームとして束ね、力強く推進していかねばならない。コラボプロジェクトの指針について、プロジェクトエディターの前田考歩氏が解説する。

強力な駒だけに頼るのでは負ける。局面に応じて、さまざまな個性を連携させることが、勝利への道筋となる
(写真=123RF)
「目的と手段」について明確に合意しておく
プロジェクトとは目標に向かって、所与のリソースや制約条件のもと、複雑性を減らし、未知を既知に塗りかえていく行為である。ルーティンワークでない仕事は、すべてプロジェクトと言っていい。プロジェクトは携わるステークホルダーなどの変数が増えるほど、また、未知の要素が多いほど、その難易度は上がっていく。この意味で、他社とのコラボレーションは非常に難易度が高い。
数多くのコラボ事例が世に出ているが、コラボレーションには企業それぞれの目的や思惑がある。売り上げが落ち込む時期の購買意欲を高めるため。まだ買ったことのない人に手に取ってもらうトライアル促進のため。仕入量を増やして店頭での露出を高めるため、等々。
こうした目的を定めることが第一歩だ。すると手段はある程度絞られてくる。
手段が決まれば、それが短期で終わるものなのか、それとも長期にわたるものなのか、という「時間」が定まる。「空間」も同様だ。共同企画商品をどのチャネルで売るのか、あるいはコラボイベントをどの会場で開催するか。そして必要な作業の特定や、工数の把握、それに伴うコストの算出など、細部が決まる。
もちろん、目的達成のための手段はひとつとは限らない上、実のところ、「その手段なら目標が達成される」という根拠は必ずしもない。だからこそ関係各社がなるべく早い段階で、「この手段を採用しよう」ということにきちんと合意しておくべきだ。ここをあいまいにしておくと、後半で"そもそも論"が発生し、プロジェクトは一気に停滞、炎上する。
さらには、その手段が自社や他社にとって慣れ親しんだやり方なのか、新たなチャレンジとなるのかで、コラボレーションの難易度が大きく左右される。
たとえばビールメーカーが、別の企業とコラボしてビールを共同企画するのなら、それは本業の知見を生かせる。一方、常設店をオープンするとなれば、社内にあるノウハウだけでは立ち行かないし、揃えるべき人材や評価基準なども変わってくる。こうしたことを前提に、プロジェクトを進めるためのポイントについて論じていこう。
意思決定レベルを揃える 協力会社も早めに参画
プロジェクトでは、目標達成のためにどんなスキルや知識を持った人材がいるかを認識し、把握することが重要だ。コラボレーションには、①アニメキャラを既存商品のパッケージに採用する ②既存のインスタント食品や菓子に有名店の看板メニューの風味を再現する ③互いに要素技術や技能を持ち寄って、共同で新製品を開発する──など、色々な事例があるが、その内容によって、揃えるべき人材は変わる。
パッケージにキャラクターを使用するような、外身(いわゆるガワ)のコラボであれば、販売促進や営業企画、マーケティング、広報といったメンバーを中心に、デザイナーやアートディレクター、知的財産権の管理担当者などが加わる。食品の味など中身のコラボレーションになれば、商品開発や原料調達の担当者、技術者などを加える必要がある。
複数の主体が参画し、プロジェクトの複雑さが増せば増すほど、迅速な意思決定が求められる。コラボレーションプロジェクトなら特に、決裁権を持つ人材が互いのプロジェクトメンバーには欠かせない。
仮に片方には決裁権者がいて物事の判断スピードが早いのに、もう片方に決裁権者がいないとすれば、それがボトルネックとなってプロジェクトの進行を妨げてしまう。文字通り時間の浪費である上、同じスピード感でプロジェクトを進められないためにフラストレーションが溜まってしまい、プロジェクトの成否にも影響が出かねない。
また、コラボレーションの手段は...