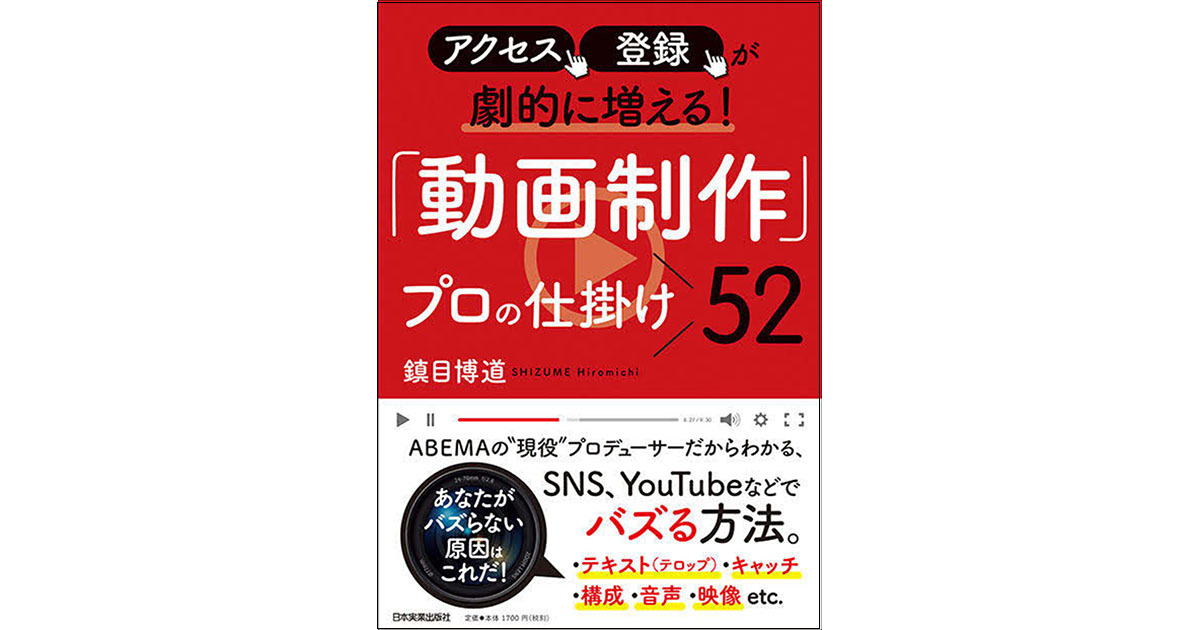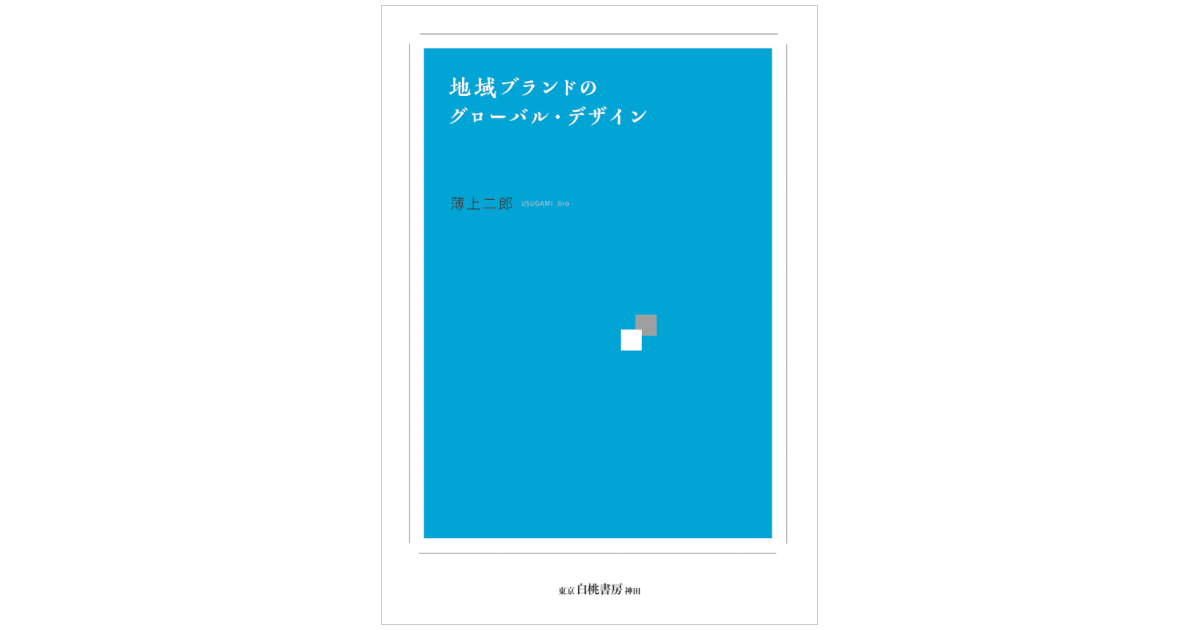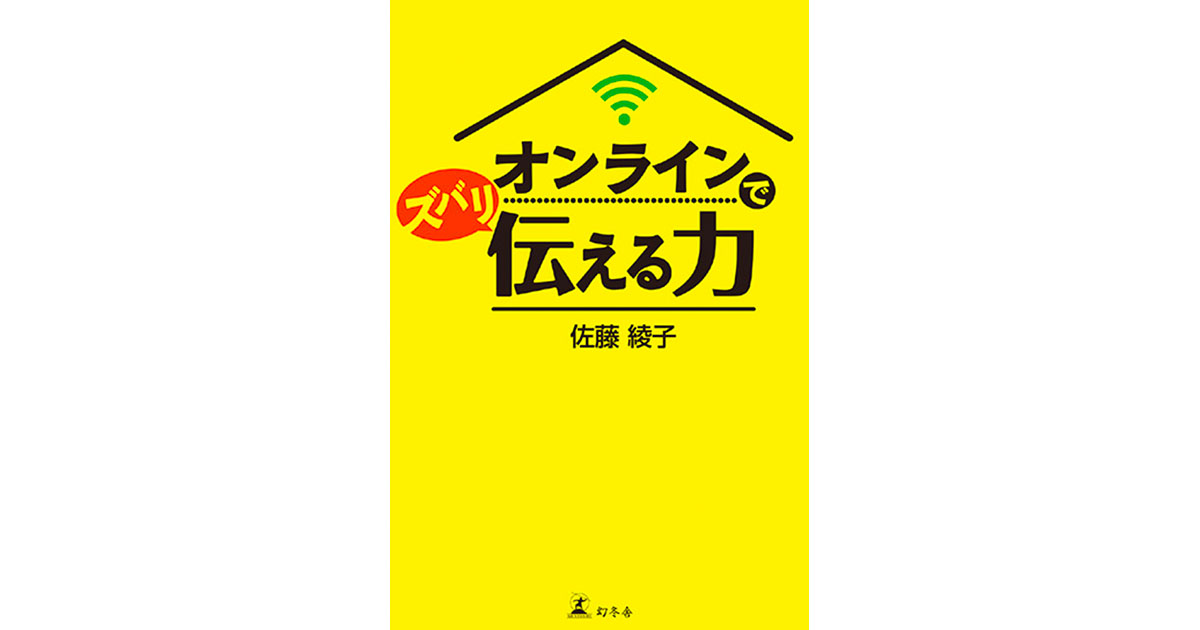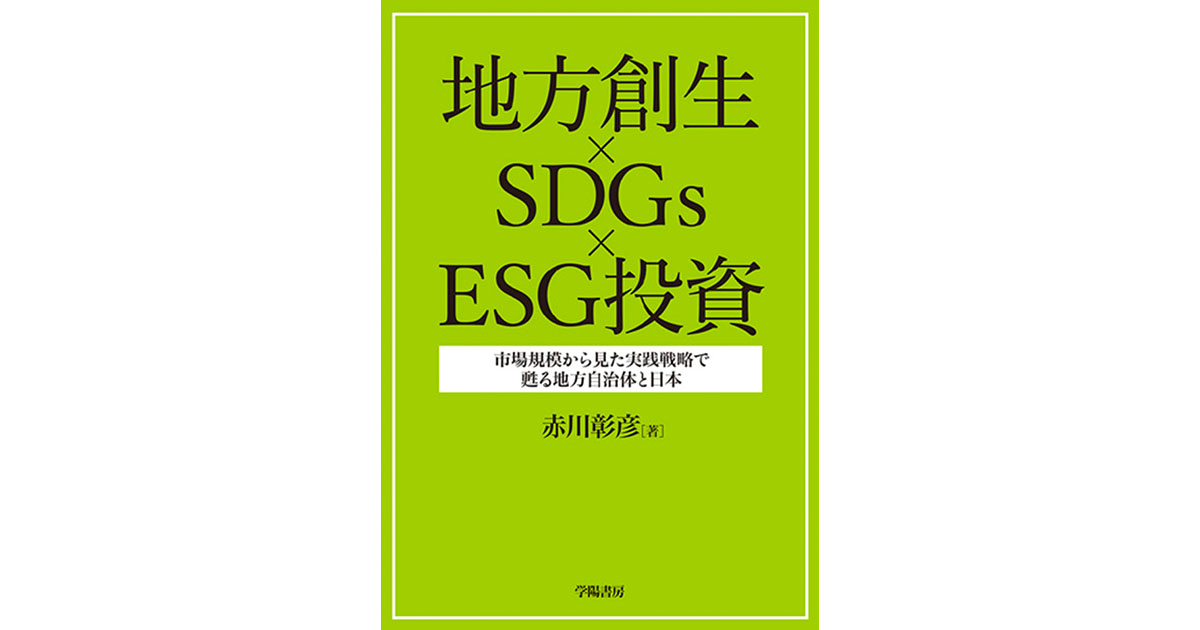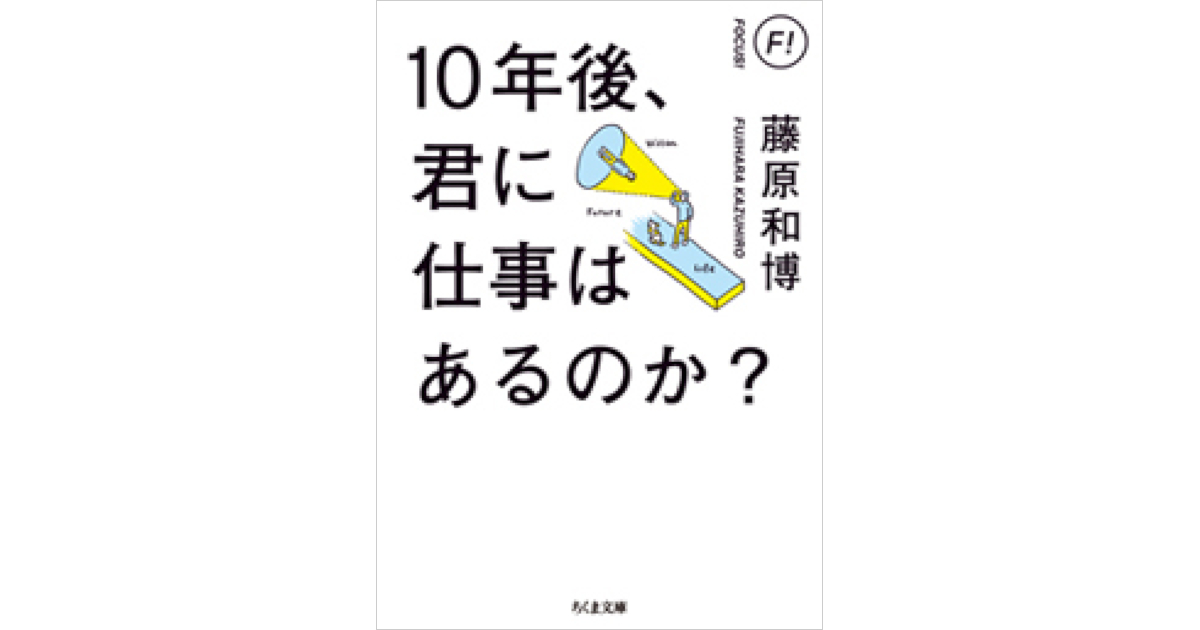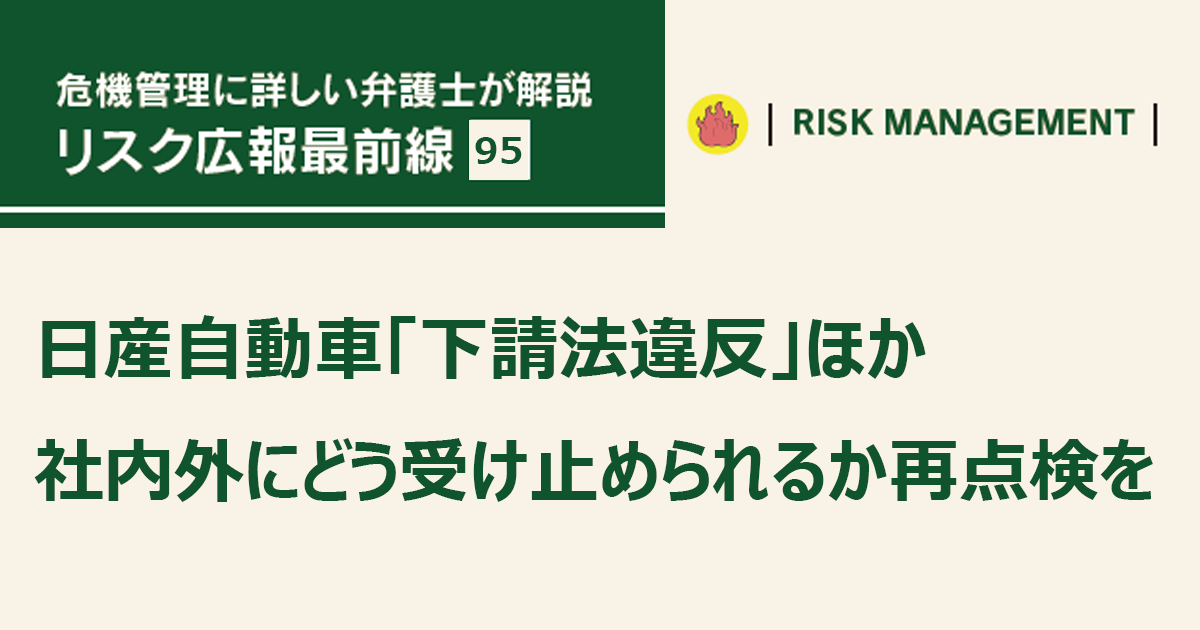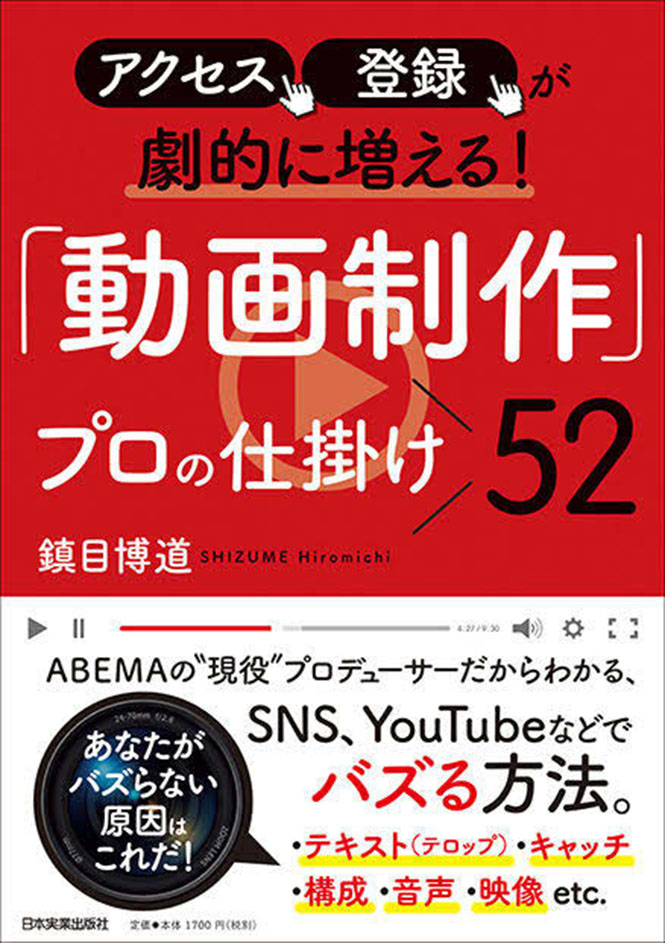
アクセス、登録が劇的に増える!
「動画制作」プロの仕掛け52
鎮目博道/著
日本実業出版
228ページ、1700円+税
新型コロナウイルスは人々のメディア接触に大きな変化をもたらした。リアルなコミュニケーションが制限される中で、Zoom会議やオンライン演劇など、仕事、エンタメ、様々なものがインターネット上で展開されるようになった。そんななかで「動画」は存在感を増している。社内コミュニケーションや企業PRのために動画制作に打って出た広報担当者も少なくないだろう。
本書では、元テレビ朝日プロデューサーであり、現在も自らが立ち上げた「AbemaTV」での番組企画、プロデュースを行う著者が、動画制作52のポイントを紹介する。
「撮影などのハウツーもそうですが、今はスマホ1台で個人が簡単に動画を撮れる時代。プロとの違いは、“面白く、伝わる”動画に出来るかどうかだと思います。私がこれまで培ってきた経験を活かし、その考え方や仕掛け方を多くの人に伝えることで、企業、個人、誰もが面白いコンテンツをつくれるようにしていきたいと思いました」(鎮目氏)。
企業の動画作成で陥る失敗例
現在、鎮目氏はPRコンサルタントとしても活躍。企業の商品・サービスの企画段階から、最終的なPRを視野にいれたストーリー設計を支援している。そのなかでよく陥りがちな失敗が、①メッセージを詰め込みすぎる ②伝えたい側の視点でつくってしまう の2つだという。
「基本動画は流れていくもの。①のような動画だと、一瞬でも視聴者が考えてしまった瞬間に他の情報が飛ばされてしまいます。10個のメッセージを伝えたいなら10個の動画をつくるべき。1回で理解してもらえるよう、シンプルに、分かりやすいテキストにするのが鉄則です」。
②に関しては、特に企業や商品のPR動画に多いという。「PRがゴールにあると、どうしても伝えたい側が伝えたい情報、良さを伝えることに終始してしまうケースが多いです。しかしそれは視聴者側の知りたい情報ではないはずです。動画はいい意味でも悪い意味でも伝わる情報は多いもの。出演者の感情や人柄、音、におい、味などまでリアルに伝わります。大切なのは“ありのまま”を伝えること。そういう映像に共感は生まれると思います」。
ラジオのような映像が伝わる
鎮目氏は、今人々に刺さる動画はかなり変化していると語る。「昔のテレビは“家族”や“お茶の間”など、同じスペースにいるみんなに同等の笑いや情報を届ける形でした。しかし、今はスマホで、ひとりで楽しむものに変わりつつあります。私はこの視聴がラジオに近いと感じています。ラジオは広くより深く、パーソナルな部分を刺激するメディアです。よりターゲットを絞った1対1の魅せ方を意識することが、今の時代の動画に求められていると感じます」。
鎮目氏自身も幼少期からラジオっ子であった。まるで自分に話しかけているかのような「共感性」。これは鎮目氏がテレビ制作やウェブ番組の制作の現場にいるときにも常に意識してきた点だという。
「共感できるストーリー、発信ができれば、個人にも、メディアにも、自然と振り向いてもらえます。商品・サービスの設計段階から“共感”を意識して、広報や動画制作者が入り込めると、伝わるPR動画がつくれるのではないでしょうか」。

鎮目博道(しずめ・ひろみち)氏
1992年テレビ朝日入社。社会部記者として活動後、『スーパーモーニング』『報道ステーション』などのディレクターを経てプロデューサーに。「AbemaTV」の立ち上げに参画し、番組企画・プロデュースを行う。2019年8月に独立。放送番組のみならず、雑誌などの多メディアで活動。上智大学文学部新聞学科非常勤講師。
ログイン/無料会員登録をする