政府の方針のもと、いわゆる「地方創生」がスタートしたのは2014年のこと。それから約10年が経ち、地域に担い手が増えるとともに、その流れはますます加速しています。今回集まってくれたのは、鹿児島県薩摩川内市でサーキュラー都市の実験拠点「薩摩フューチャーコモンズ」を運営するほか、全国各地で自治体や行政と連携したプロジェクトを数多く手がける、リ・パブリックの市川文子さん。茨城県つくばみらい市や北海道白老町のシティプロモーションに関わり、2023年9月に『Roots the hood 地域を動かすアイデアとクリエイティブ』を上梓した、ドローイングアンドマニュアルの中谷公祐さん。栃木県の黒磯でダイニングとゲストハウスを併設したマーケット「Chus」を運営、2022年7月には、那須高原に「バターのいとこ」などの製造工場を中心とした新たなまち「GOOD NEWS」をオープンした宮本吾一さん。クリエイターでありプレイヤーでもある3人が、地域のデザインのこれまでと、持続可能な地域のこれからを語りました。

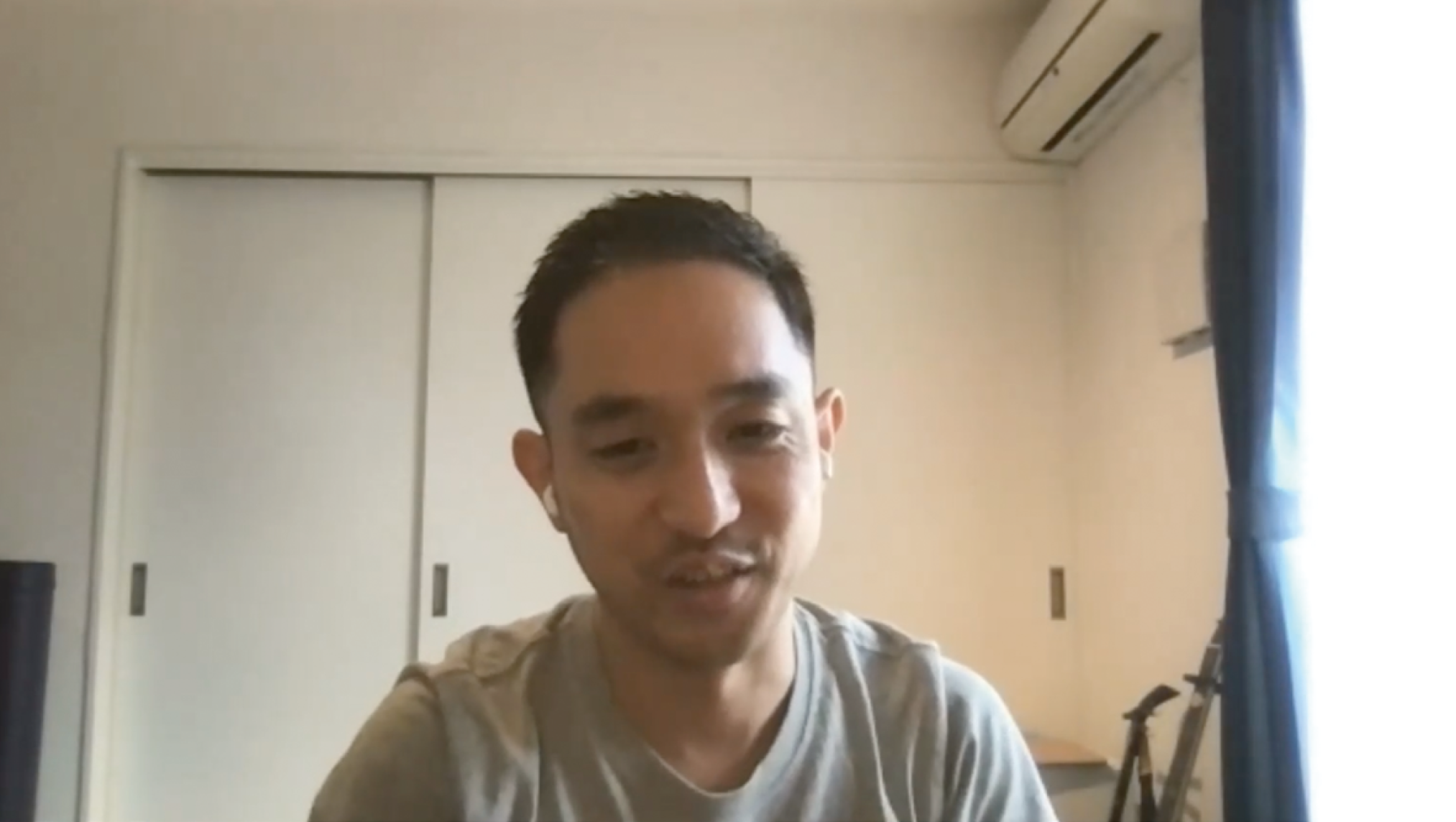

大事なのは「ちょっとずつ増える」こと
市川:リ・パブリックという会社で共同代表を務めています。鹿児島の薩摩川内市に「薩摩フューチャーコモンズ」という実験拠点をつくったり、鹿児島県内5カ所でフィールドツアーとワークショップを行う「CIRCULAR DESIGN WEEK 2023」を開催したり。イノベーションが起こる生態系を研究し、実践する「シンク・アンド・ドゥ・タンク」をコンセプトに、東京と福岡を拠点に活動しています。
中谷:僕の所属するドローイングアンドマニュアルは、映像を中心としたクリエイティブカンパニーです。映画やMV、企業の映像のほか、10年ほど前から地域のブランディングも手がけていて、僕は茨城県つくばみらい市や、地元の北海道白しらおい老町のプロモーションに関わっています。
宮本:栃木県の那須高原でGOOD NEWSという会社をやっています。元々、東京から移住して飲食の仕事をしていたのですが、2010年に地元の生産者を集めたマーケットを始めたんです。7年ほど続けたのですが、ちょっと疲れてしまって……。ただやめるのはつまらないので、マーケットをそのまま飲食と食物販に置き換えた「Chus」というお店をつくりました。
中谷:2019年から始まったつくばみらい市のシティプロモーションでは、外に向けて発信する前に、市民に「地元愛」を持ってもらうことが重要であるという考えから、市民100人のポスターをつくったり、「MIRAI ART FESTIVAL」というイベントを開催したりしてきました。白老町は、自分の生まれ故郷で、2020年に「ウポポイ」というアイヌ文化を伝える国立博物館ができたんです。もちろんアイヌも魅力のひとつですが、もっと違った文化もあるんじゃないかと感じて、「僕と、先輩と、初夏の白老」という観光ムービーをつくったことが、このまちに関わるきっかけになりました。
市川:今まで、地域を元気にするというと、商品のパッケージをつくるとか、映像をつくるとか、“点”でやっているところがありました。でも、お二人の活動を拝見しても感じますが、たぶんもう、ひとつの産業とかひとつの会社を起点に何かをやるというのは、あまり意味がないのかなって。
宮本:よくわかります。僕は元々マーケットから始まっているので、みんなでやるというのが当たり前だったところがあって。そもそも田舎だと、ひとつでやっても弱いじゃないですか。
中谷:ちなみに、映像業界と地方創生の関係ってこの10年間で激変していて、特に最初の5年間ぐらいは、とにかくバズる動画をつくって、どれだけ話題になったかばかりが重視されていました。それじゃあダメだということに、ようやく気付き始めたのが今なんだと思います。
宮本:Chusがある黒磯は、那須のお膝元にある人口5万人くらいの小さなまち。店の隣にはカフェブームの先駆けともいわれる「1988 CAFE SHOZO」があって、東日本大震災の前後くらいから、そこで働いていた人たちが独立して周りにポツポツお店を出すようになりました。
市川:関係人口が徐々に増えていっている。
宮本:コーヒーを飲んだあとはご飯が食べたいよねとか、本屋や雑貨屋もあった方がいいよねという感じで、本当に1年に1軒くらいのペースで増えています。今では20軒ほどが集まって「SHOZO Street」と呼ばれるようになって、そこを目がけてお客さんがやって来るという流れができた。
市川:パン屋さんとかコーヒー屋さんとか本屋さんって、本当に大事ですよね。
宮本:2~3軒いいお店があったら、そのまちに行きたいと思わせることができますから。さらに、インバウンドという刺激的な視点が加わったことも、ここ10年のまちづくりに起こった大きな変化ですね。
中谷:白老町も、ウポポイをきっかけに、ゲストハウスができたり居酒屋ができたり。最近、東京から移住して本屋を始めようとしている方は、白老は「ブルーオーシャンだ」と言っていました。そもそも本屋がないから求めてもらえるし、しかも家賃が安いので低コストでスタートできる。挑戦しやすいというのが、地方の大きな価値になっていると感じます。
宮本:観光需要が盛り上がっているときはいいけれど、コロナ禍などの要因で止まった瞬間やっていけなくなるみたいなケースもあるので、ちょっとずつ増えるのはポイント。「醸している」というか、その早すぎない感じが僕はすごく好きで。
市川:お店もちょっとずつ増えるし、関係性の中で、みんながちょっとずつ豊かになる。先日、富山県の南砺市井波で「Bed and Craft」という宿をやっている山川智嗣さんに話を聞いたのですが、まさに毎年少しずつ、まちに関わる人たちが増えていると言っていました。
宮本:この間、長野県の野沢温泉でまちづくりをしている友人とも、「ファイナンス的なスピード感は重要だけど、店のクオリティは本当にゆっくりとしか上がっていかない」という話をしたんです。その比例しない部分を、どうコントロールしていくかがテーマなんじゃないかって。
市川:住んでいる人たちがおいしいパンを食べられるようになったとか、そういう日々の実感と並行して、お店が“発酵”していくことが大事なんでしょうね。
クリエイターは地域とどう関わるべきか
中谷:まちづくりって、1年や2年では絶対に結果が出ないし、10年20年、いや50年100年ぐらいの長いスパンで考えなければいけないもの。いくら映像がバズっても、プロジェクトが終わったらすぐにいなくなってしまうような関わり方は嫌だな、といつも思っていて。
市川:地域のデザインと聞くと、完成させたものをつくるというイメージが付きまとっている気がするんです。でも「終わりをつくるんじゃなくて、始まりのデザインが大事」という話を最近よくしています。
宮本:Chusをやっていると、農家さんが野菜を届けにきたり、酪農家さんがチーズを持ってきたり。毎日会っているうちに、いつしかその人たちの問題や課題も一緒に持ち込まれるようになったんです。
中谷:僕も地元のおじいちゃんから「中谷くん、スマホ教室をやってくれ」とお願いされて、やったことがあります(笑)。
宮本:「バターをつくると、スキムミルクが余ってしまう」と聞いたことから生まれたのが、「バターのいとこ」というお菓子。生産者からもらった課題をデザインすることで、皆がハッピーになるプロダクトができると気付きました。そこで2022年には、那須高原の森の中に、工場とレストランなどが一体になった「GOOD NEWS」という施設をつくったんです。
中谷:素晴らしい。でも、始めるのも大変ですが、続けるというのもめちゃくちゃ大変ですよね。人の繋がりもないといけないし、行政の担当者も変わってしまう。自分の中のエンジンが効かなくなったら、誰もアクセルを踏んでくれない、というか……。
宮本:僕は那須には月に1週間ぐらいしかいなくて、あとはいろんなまちをフラフラ回っています。そうすると今度は、そこで出会った人が那須に戻ってきてくれて、プロジェクトが生まれることがあるので。
市川:地域に関わっていると、どんどん中の視点が強くなって、時々それで行き詰まることがある。こんな楽しいことをやってる人がいるよ、一緒にやろうよみたいなことで、物事が進むことってありますよね。
宮本:今進めているのは、生のもみの木のツリーを貸し出すプロジェクト。クリスマスが終わったらGOOD NEWS の森に植えて、来年また新しい苗木を育ててレンタルする。
市川:素敵ですね。
宮本:それから最近、食品だけでなく化粧品にも廃棄ロスがたくさん出ていることを知りました。そこでクリスマスに、バターのいとこの箱をキャンバスにして、子どもたちに口紅で絵を描いてもらうプロジェクトも進めています。僕は「リジェネラティブ(環境再生)」という考え方がすごく好きで、今はそんなことばっかり考えていて。
中谷:僕の場合は、地元にUターンしようと考えたこともありましたが、あえて東京に残りつつ地域に関わるというスタイルを選びました。というのも、移住した人を見ていると、すごく感度が高いし、ビジネスのセンスもある。自分は白老町の東京支社みたいな立場でいた方が、力になれることが多いのではと感じて。
市川:きっと「ちゃんと移住せい!」みたいな圧力もあると思うので、無理しないで、と思っちゃいました...



















