コンパクトシティや日本版MaaSの実現、人口減少や高齢化、エネルギー問題など社会課題の解決にも繋がる、新しいモビリティの開発が次々と進んでいます。集まってくれたのは、2023年8月、国内では75年ぶりの新規開業となる路面電車「芳賀・宇都宮LRT」をはじめ、パブリックプロダクトや街路、広場など公共分野のデザインに幅広く関わる、GK設計の入江寿彦さん。「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をコンセプトに、椅子タイプやスクータータイプの近距離モビリティを開発する「WHILL」のデザイナー・塚本皓之さん。東京とパリを拠点に、空飛ぶクルマとして話題となった「SkyDrive」をはじめ、物流ドローンや水素燃料電池船など、さまざまなモビリティのデザインを手がける山本卓身さん。EVやパーソナルモビリティ、ドローンにLRT……。未来のまちづくりに欠かせないインフラとしても注目を集める、次世代モビリティを飛躍させるデザインの力とは?
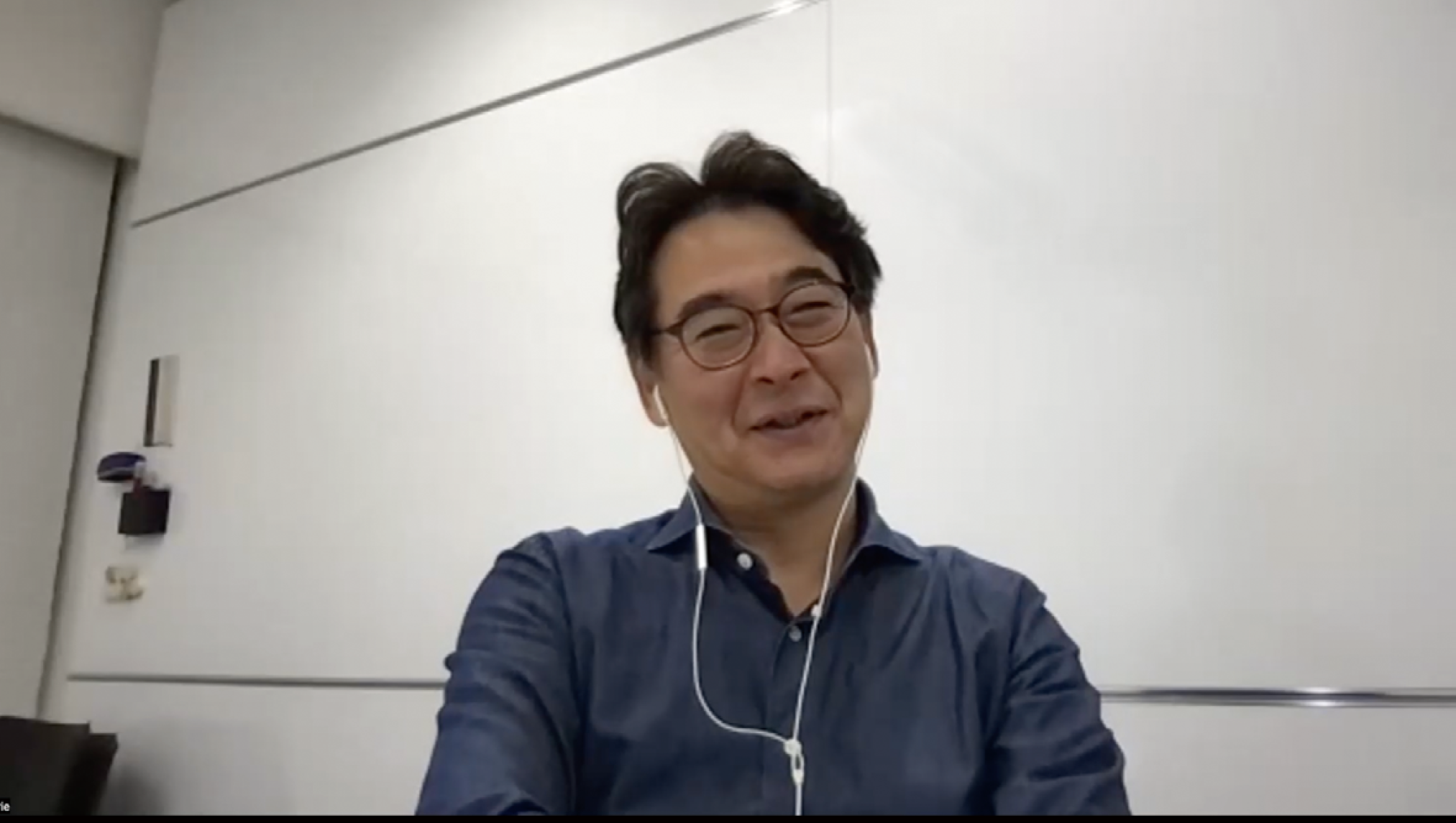

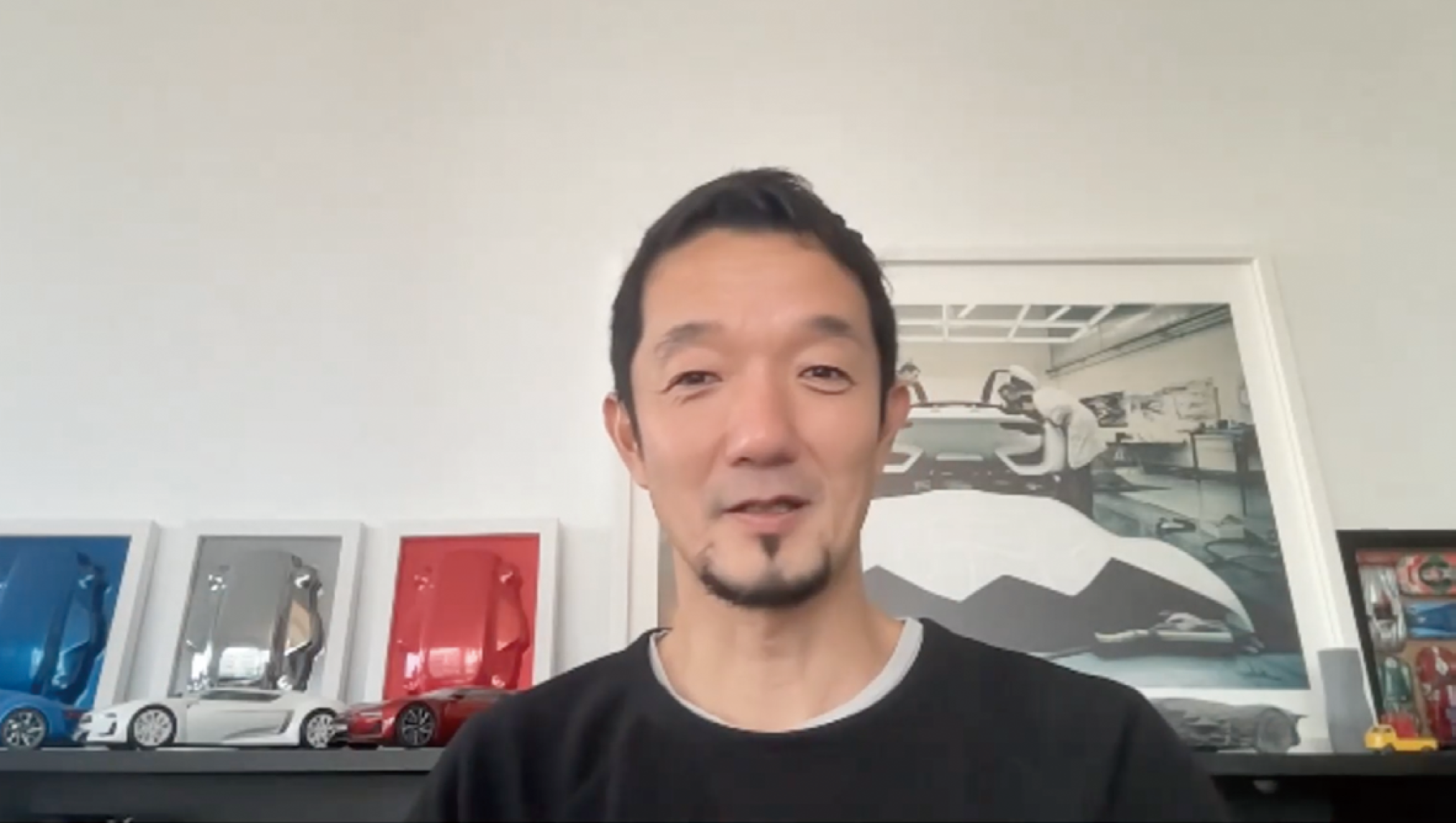

モビリティ同士がシームレスに繋がるデザインが今こそ必要(入江寿彦)
次世代モビリティの現在地
塚本:以前はスズキで自動車のデザインに関わっていたのですが、もう少しアグレッシブな仕事をしたいなと感じて、5年ほど前に、近距離モビリティ(パーソナルモビリティ)の開発を行っているWHILLにジョインしました。
山本:僕は小さなデザイン事務所でキャリアを始めて、イギリスの大学院に留学したのち、プジョーとシトロエンに7年ずつ勤めました。そのあとは少しサイドを変えて、ゲームの『グランツーリスモ』を制作するポリフォニー・デジタルという会社で自動車業界の外から車をデザインし、2017年に独立して現在に至ります。
塚本:WHILLでは、プロダクトのデザインはもちろん、開発方針の検討から量産、プロモーションまで。創業年数が若い会社らしく、幅広い業務を担当しています。
山本:僕もデザインだけというよりは、上流から下流まで全部をやりたい人間。ブランディングから始まって、デザインして、それをどう伝えるか。スプーンのような道具から、SkyDriveをはじめ空飛ぶクルマに船、鉄道まで、大小さまざまなプロジェクトに関わらせてもらっています。
入江:GKデザイングループは、インダストリアルデザインを中心に出発し、プロダクト、モビリティ、環境、コミュニケーションなど、幅広い領域のデザインを行っています。私の所属するGK設計は、道路や広場、建築などのデザインが主な業務。グループでは、広島のアストラムラインや多摩モノレール、富山ライトレールといった公共交通にも関わっていて、最近では2023年8月に栃木県に開業した芳賀・宇都宮LRTのトータルデザインを手がけました。
塚本:ここ10年ほどの間にさまざまなモビリティが登場し、その反応にも少しずつ変化が見られつつあります。ただ、WHILLにしても、まだまだ車椅子の"バイアス"や移動そのものを変えるところまでは至っていない、というのが現状だと思うんです。
山本:僕たちが目指しているのは、どんな人でも簡単に移動ができて、それをより楽しく快適にするということ。環境や技術の進化に伴って、陸から空まで、カバーできる範囲がだんだん広がってきているという実感はありますね。
塚本:トヨタのウーブン・シティのようにインフラからつくろうというプロジェクトもあるし、いろいろな企業が参入して、さまざまな切り口でトライを続けている。こうした動きが社会に浸透して、実装されていくといいなと思いますね。
入江:我々はまさにインフラ側がメインなのですが、たとえばLRTという次世代型路面電車はヨーロッパを中心に各国に普及していて、2006年に富山、2023年に宇都宮と、日本でも徐々に広がっています。超高齢化を背景に、車に乗れない人の移動手段をどうやって確保するかという社会課題を解決する、ひとつの答えになっている。
山本:一時期、日本では路面電車がいくつも廃線になったのに、それがまた盛り返して、逆輸入されているというのが面白い。僕の会社があるパリでは、トラムが走る市街地の中は、できるだけカーレスにしようという流れになっています。
入江:おっしゃる通り、地方都市においては、一度は車に駆逐された路面電車が公共交通と共存しようという流れになってきた。一方、都心部では、道路空間を歩行者や小型のモビリティにも分けて、車依存ではない移動を増やしていこうという流れがあります。
山本:そうした流れが、すごくアジア的というか、ダイバーシティというか。ちなみに10年前、パリには自転車に乗っている人なんていませんでしたが、ここ数年で自転車専用道路の整備が爆発的に進みました。
塚本:WHILLは、椅子型とスクーター型を開発・販売していますが、前者は介護保険が適用されるモデルもあるため、どちらかというと身体状況が重度の方、後者は免許返納した方や、歩けるけれど長距離となるとつらいシニア世代などが主なターゲット。また、都心部では椅子型、車社会の地方ではより長い距離を走れるスクーター型が好まれる傾向にあります。
山本:今、モビリティの主役は間違いなく車ですが、その歴史はわずか130年ほど。ドイツにあるメルセデス・ベンツ博物館は、「車が馬を凌駕するわけがない」という王様のコメントから始まるように、かつては誰も信じていない乗り物でした。高齢化が進む先進国ではこれから、どんな人でも動ける自由を担保することが重要になります。それこそ何十年後には、全く新しいモビリティがスタンダードになるかもしれません。
TOSHIHIKO IRIE'S WORKS

芳賀・宇都宮LRT(宇都宮市、芳賀町、宇都宮ライトレール/2023)
D:GKインダストリアルデザイン+GKグラフィックス+GK設計 Photo:YohHashimoto
専用レールを走行するため時間に正確で、段差がなくスムーズな乗り降りが可能、環境にもやさしい次世代型路面電車。2023年8月に開業し、全国初となる全線新設のLRTとして注目を集めている。

富山ライトレール(富山市、富山ライトレール/2006)
D:GKインダストリアルデザイン+GKデザイン総研広島+島津環境グラフィックス+GK設計 Photo:室澤敏晴

G-FENCE(サンポール/2015)
D:GK設計

ETC Tall Gate(日本道路公団/2000)
D:GK設計

新潟BRT(新潟市/2015)
D:GKインダストリアルデザイン+GKグラフィックス+GK設計

BAYSIDE BLUE(横浜市/2020)
D:GKデザイン総研広島+GK設計 Photo:Yoh Hashimoto



















