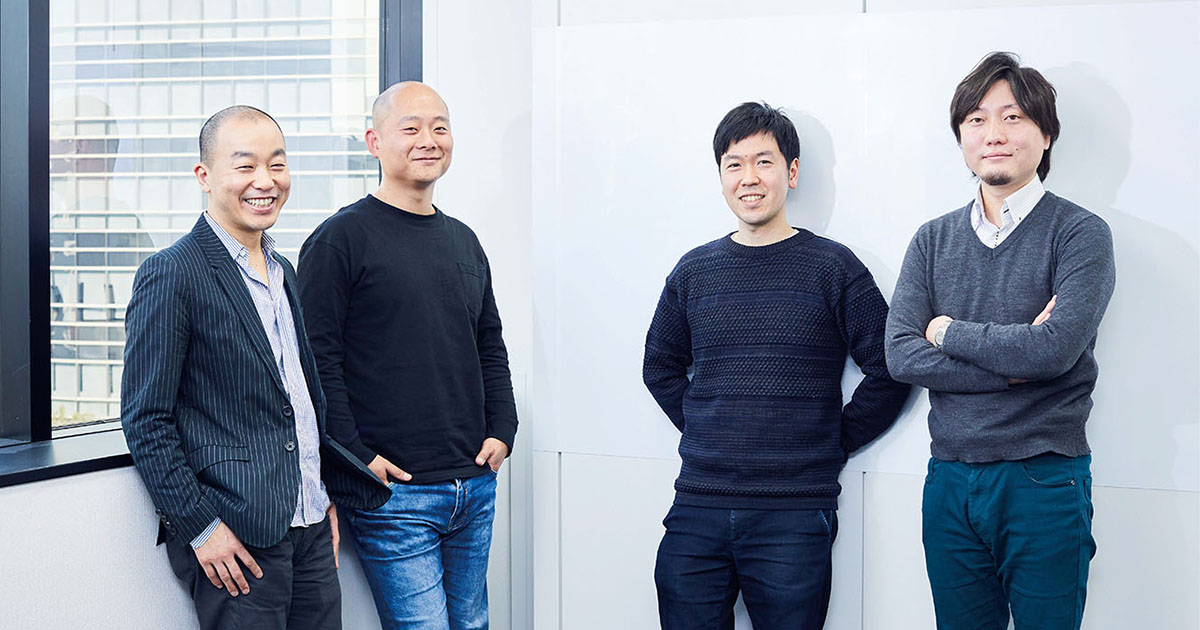ものづくりには、さまざまな形態があります。広告であれば、さまざまな職種が集まり、チームをつくって、ひとつのクリエイティブをつくりあげていきます。アーティストであれば、基本的に一人で自分が思うままに作品をつくりあげていきます。そんな中、ここ数年、アートやクリエイティブの世界に「ユニット」という形態でものづくりをする人が増えています。一人じゃなくて、二人、あるいは三人だからつくることができるものとは何であるのか。また会社という形態ではなく、ユニットとして活動する意味とは?
今回は、アートディレクターと料理人の夫婦ユニット「holiday」、「福祉とあそぶ」をテーマに活動するユニット「HUMORABO」、そして横浜で日用品店を運営しながら、アートを中心に活動する「L PACK.」の3組のユニットに、それぞれのやり方や活動も含め、お話を伺いました。

Photo : Hokuto Shimizu/parade/amanagroup for BRAIN

それぞれのユニットの成り立ち
中嶋:大学時代の同級生である小田桐と2人で「L PACK.」というユニットを組んでいます。僕らは学生のときに建築を勉強していましたが、周りが建築模型の勉強をしているなかで「それって本当に建築なのか?」とリアリティを感じられなかったんです。それよりも、もっと建築の概念や空間を広く面白く捉える活動ができないかと感じたことがきっかけで、大学4年のときにL PACK.をスタートしました。建築に限らずアートやデザイン、民藝、フードなど、いろいろな領域を横断しながら面白い活動をしたいと考えています。
小田桐:僕らの活動のテーマは「コーヒーのある風景」です。例え何もない原っぱでも、そこにコーヒーが1杯あれば人が集まるきっかけになりえて、その光景を俯瞰してみたら建築的だったり、何か空間ができるんじゃないかと思っています。最近は主に現代美術の分野で活動しています。展覧会に参加することが多々ありますが、絵をつくる、彫刻をつくるわけではなく、美術館の中のベンチのように"人が佇むことができる場所"をつくるなど、アウトプットがモノではなく空間や時間など、形のないものになっていることが多いですね。
雄一:僕ら「HUMORABO」は夫婦2人で「福祉とあそぶ」をテーマに活動しています。障害のある人のアートを、デザインを通して社会に発信するエイブルアート・カンパニーとものづくりをしたことがきっかけとなり、ユニットでの活動を始めました。その一つが、宮城県南三陸町の福祉施設「のぞみ福祉作業所」との協働です。手漉きの再生紙「NOZOMI PAPER(R)」を一緒に制作し、商品として販売しています。
それから、これとは別に、珈琲×活版×福祉をテーマに「COFFEE PAPER PRESS」というプロジェクトをバリスタの「Tool do coffee」、活版印刷の「紙成屋」と共に各地で展開しています。基本的には、社会と福祉の楽しく新しい関係を探りたいと考え、福祉商品の企画、デザインから販売までを手がけています。
亜希子:それから最近、まさにL PACK.さんの話に出た「コーヒー」を軸にし、福祉施設の方々との新たな場づくりを試みています。例えば地域の福祉施設内にコーヒースタンドを置くことで、周辺の人が施設にコーヒーを飲みに訪れ、交流が生まれる。いま全国の福祉施設と連携していることもあり、そういうきっかけをつくる場所を生み出したいと考えているところです。
堀出:僕は妻と2人でクリエイティブユニット「holiday」として活動しています。テーマは、料理とデザイン。僕がデザイン担当、妻が料理をつくります。もともとは個々で活動していましたが、僕がデザインを担当していたクライアントからケータリングを頼まれたことが、ユニット結成のきっかけです。
そのときに料理を普通に提供するだけでは面白くない、そこに自分のデザイン要素も足してみようと思い、クッキーにフラッグをつけたり、ロゴを載せたりしてみました。パーティ当日はファッションやデザインの関係者もたくさん来ていたので評判になり、SNSで拡散されて、自然発生的にholidayとしての活動が広がっていきました。現在はイベントの演出や企画運営など、仕事は多岐に広がっています。
holiday'S WORKS

生産者の写真が載っている野菜などのパッケージをヒントに、今から食べる私(お客さん)の似顔絵とフード・ドリンクのセット企画「I EAT holiday」。

葉山芸術祭に出展した「サンドイッチスタンド」。はさまれてサンドイッチになって記念撮影をしてもらったり、休日などには中で実際にサンドイッチを販売。

「まるでパリじゃん」と名付けたサンドイッチ。フードの味、見た目のデザイン、プラスお客さんがクスッとしてくれるようなネーミングなどの演出を考えることもholidayの大切な要素。

ALESSIと共同で行ったワークショップ。「目を閉じてカトラリーにキスをしよう」というコンセプトで目隠しをして触感だけでALESSIのカトラリーを楽しんでもらった。

結婚式の余興からスタートした、一期一会の気持ちで苺に扮したholidayがマジック1本で似顔絵を描くプロジェクト"苺一絵"。

2014年に三重県立美術館で開催された、食とアートをテーマにした展覧会「ア・ターブル」でアートディレクション・フードディレクションを担当。テーブルクロスのような封筒・紙ナプキンのような招待状・パンをちぎって入場するようなチケットなどを制作。また「絵になるデザート」と題したケーキ作りのワークショップも開催した。
役割分担はどうしている?
堀出:ユニットの役割分担は、みなさんどうしていますか。holidayの場合、僕がまずコンセプトを考えて、それを二人で具体的に形にしていきます。ただ妻は料理人になる前は洋服のパタンナーだったので、デザインについては結構意見を出します。面白いのは、デザイナーである僕は1ミリ違うことにこだわるけど、妻は「どこが違うの?」と言って、女性的な感覚でかわいいものをポンポン選ぶんです。それは僕にはなかった感覚で、2人で意見を出し合って一つの形にしていけるところが、ユニットであることの面白さだと感じています。
亜希子:私たちも同じです。私はもともとテキスタイルデザインが仕事だったので、多少のズレや誤差は楽しむという考えです。でも、夫とグラフィックの仕事を始めたら「何て細かいんだ」と驚いて…。だから、私は一般的な目線で意見を言い、夫が"こだわり"を披露して、ケンカになって、だいたい第三者が止める、という流れでものづくりをしています(笑)。
雄一:妻とはデザイナー同志だから領域は近いものの、僕のバックグラウンドは広告にあるので、持っていきたい角度が違うときがあります。ただ、ユニットだと同じ側に他者の意見があるため客観的に見える機会が多い。まずは1回身内で確認できるというところが強みになっている気がします。
小田桐:僕らは役割分担をしていません。最近はどっちが先にメールの返信をするかで決まりますね(笑)。返信した人が担当になりますが、何となくバランスを見て、手の空いているほうが返信をします …