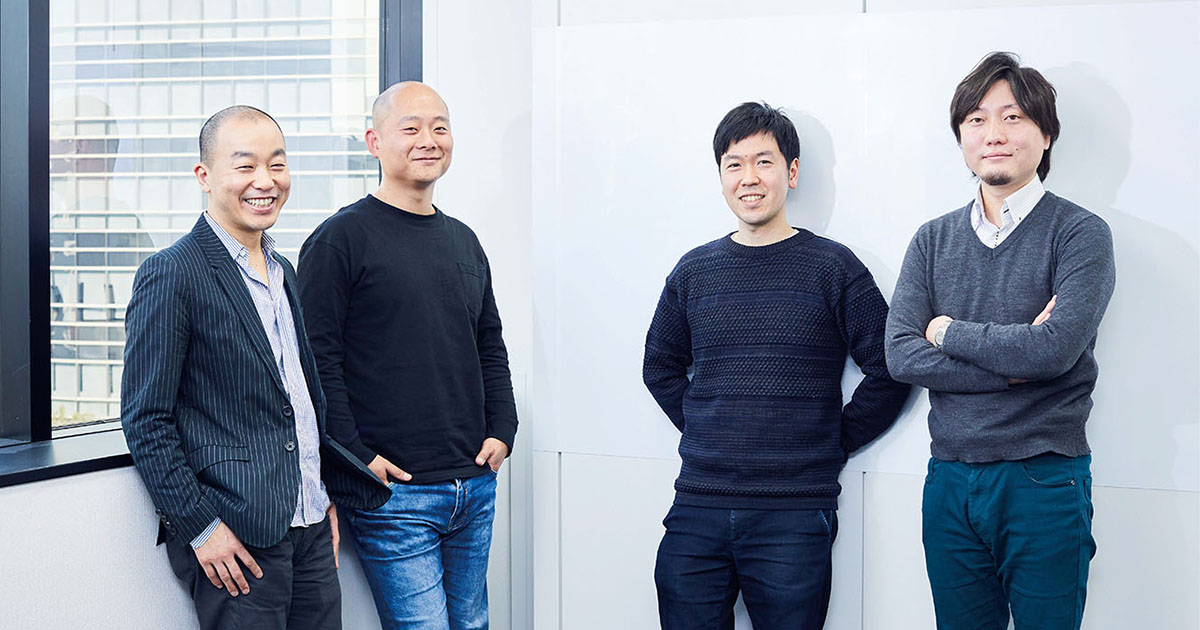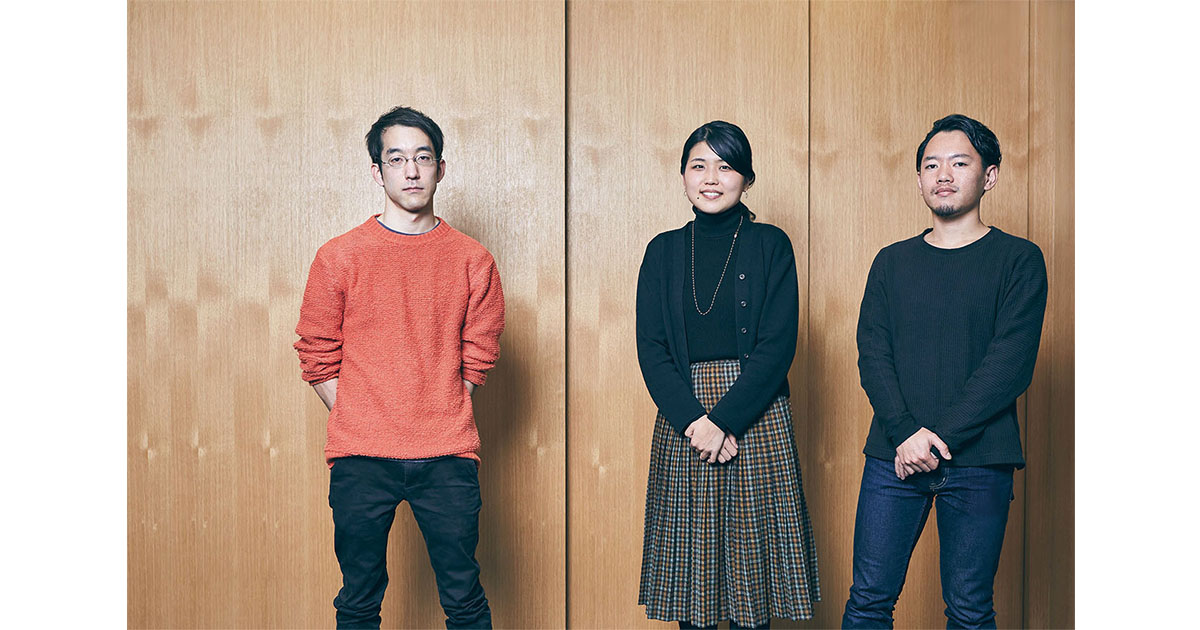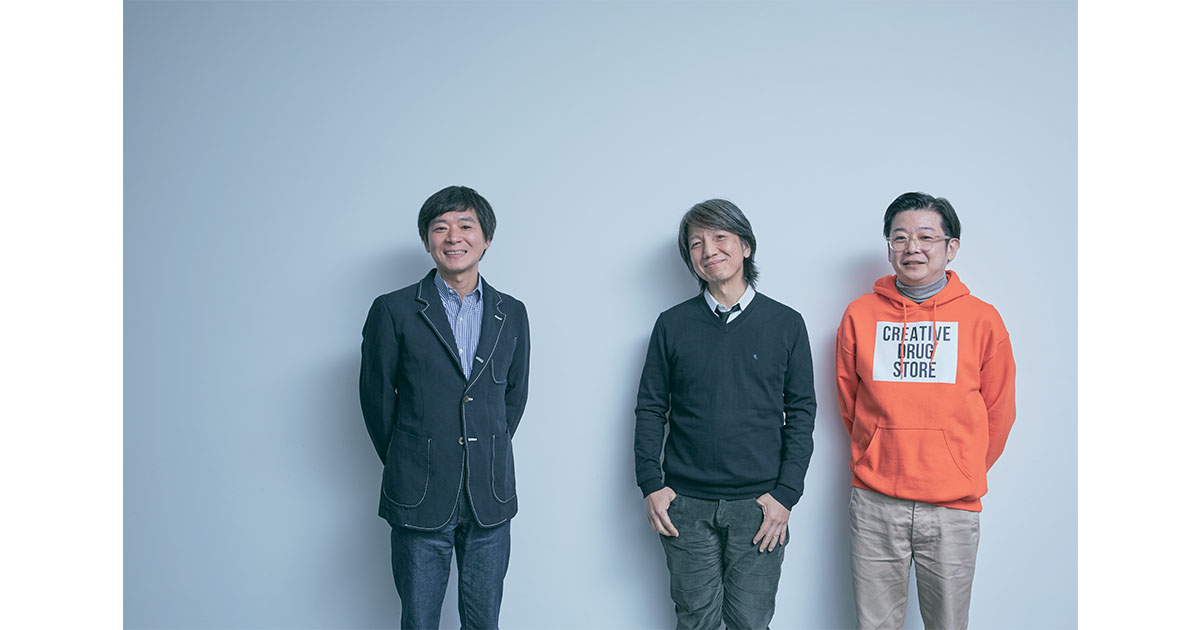Facebook、インスタグラムなどのSNSに始まり、いまや誰もが当たり前のように写真を撮る時代になりました。写真とは本来、私たちの目の前にあるものを写し出し、記録として残すことに重きが置かれていましたが、2011年の震災以降、写真そのもののあり方や活用方法が変わってきました。多くの写真家が自分自身の地元やさまざまな地域を訪れ、その地域と結びつく形で写真を発表しています。
そして、それはかつてのようにその地域や社会の問題をドキュメンタリー写真で見せるということとは違います。写真家自身が活動の中心となり、地域を、社会を巻き込んでいく。それによって、地域が活性化し、コミュニティができ上がっていく。そんな様子が見られるようになってきました。
そこで今回は、全国津々浦々を撮影で訪れている浅田政志さん、ご自身の故郷である塩竃を中心に活動を続ける平間至さん、ローカルフォトを推進するMOTOKOさん、そして日本の写真界を俯瞰している写真評論家の飯沢耕太郎さんにお集まりいただき、それぞれの取り組みと写真を通していまどんなことができるのか、お話をいただきました。
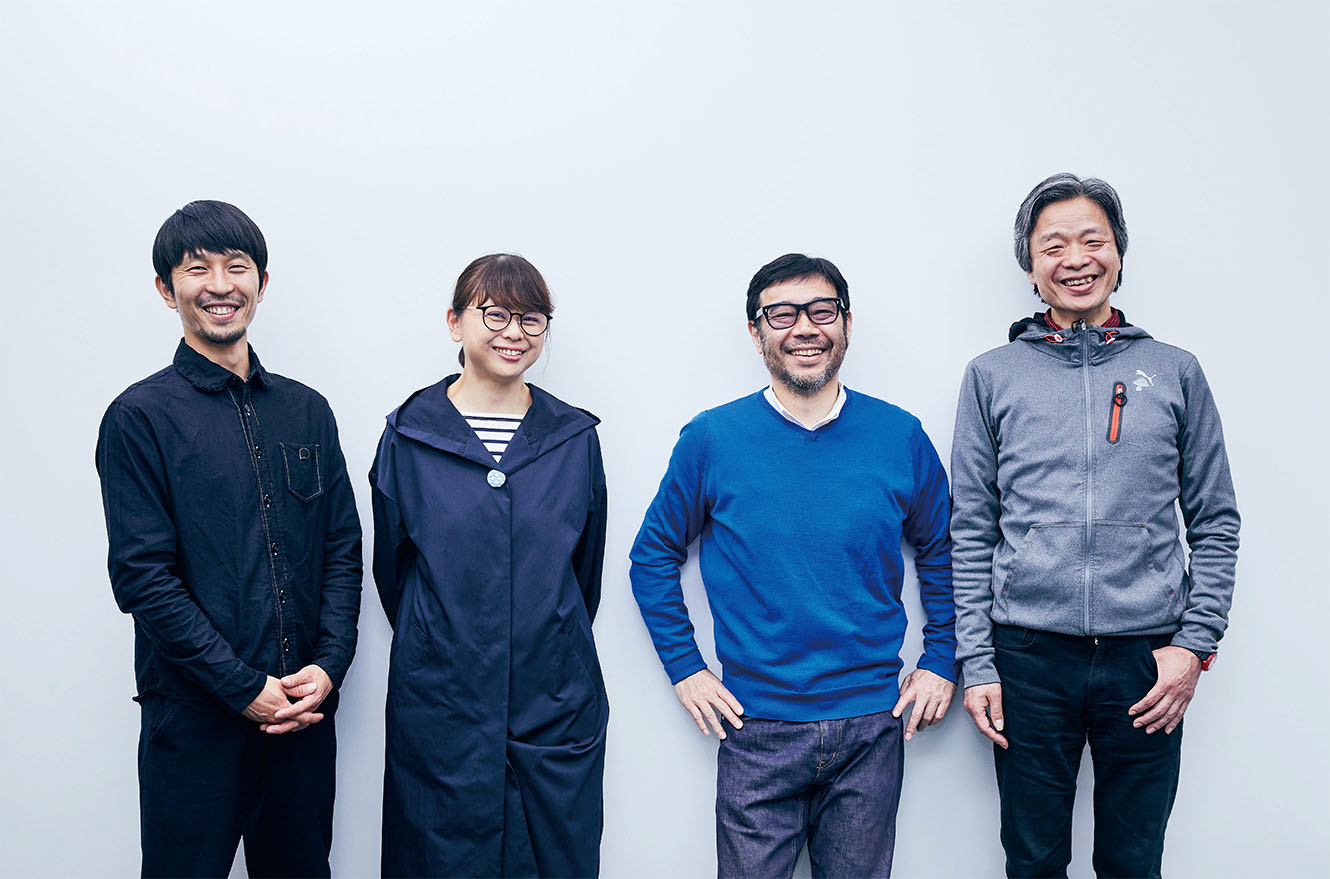
Photo:parade/amanagroup for BRAIN

震災後に増えた地域との関わり
飯沢:皆さん、最近どんな活動をしているのか、教えてください。
浅田:僕は東京に活動拠点がありますが、実際に東京で撮影するのは6割程度で、今では各地域での撮影が増えています。ちょうど震災の半年前、青森県八戸市に建設中の「八戸ポータルミュージアムはっち」のこけら落としに向けて、八戸で暮らす人々のポートレートを撮影してほしいと依頼がありました。無事、写真展はオープンしたのですが、会期終了まで1週間を切った頃に震災が起こり、写真展の場所も避難所になってしまいました。それ以降ですね、いろいろな地域との関わりができたのは。
僕としては地域での撮影を特別望んでいたわけではないのですが、地域に行けば行くほど楽しくなってきて、最近は町をPRする"町おこし"の活動の中で写真を撮ることが多くなりました。
平間:僕は高校まで宮城県塩竈で育ちました。当時は地元で最先端の音楽、ファッションを楽しみながら、東京にはもっとすごい文化があるはず、と大きな期待がありました。ところが、大学に入るため上京したら、そんなことはなくて(笑)。そのとき、何となく自分の町が面白かったな、とぼんやりと思ったんです。
その後、東京で活動を続けていたのですが、2000年に生涯学習センター「ふれあいエスプ塩竈」ができたことが、塩竈での活動のきっかけとなりました。エスプ塩竈の中に雑誌『ガロ』の初代編集長だった長井勝一さんの漫画美術館ができたのを知り、自分も地元で何かできるのではないかと思い立ち、2年続けて写真展を開きました。2008年からは"場"をつくるべく「塩竈フォトフェスティバル」を始め、メインイベントとしてポートフォリオレヴューを実施しています。2012年からは「GAMA ROCK FES」というロックフェスティバルも始めました。
MOTOKO:私は2006年に瀬戸内の島をめぐる旅をしたことに始まり、その後、滋賀県の農家の人たちを撮影する「田園ドリーム」という活動を始めました。その中でさまざまな人たちと出会い、農家の現状、ひいては日本の農業の現状を知るようになりました。写真で発信することを学んできた自分に何ができるかと考え、日本の農家やその現場をきちんと伝えていこうと、自分のスタンスを切り替えたのが2008年です。こうした活動をする中で見えてきたのが、ローカルフォトでした。
地元の人たちに写真を教えることで、彼らが自立して、自分たちの町を撮影して発信していく。それによって、移住や観光促進を進めることができる。こうした考えで進めていく中で、実現したのが2013年にスタートした「小豆島カメラ」です。オリンパスにスポンサーになってもらい、小豆島の7人の女の子が写真で情報発信を行っています。
私が教えたのは、どのような写真を撮ったらいいか、どう情報発信すべきかということ。現在、「小豆島カメラ」のFacebookページは香川県内では「うどん県Lovers」や「香川県三豊市観光案内所」に並んでTOP3に入り、さらに、メンバーは観光などのテーマでセミナーにも登壇するまでになりました。
コモディティ化する写真
MOTOKO:いまはスマホで誰でも写真が撮れる時代となり、メディアが"民主化"した、とも言えます。その中で私たちはプロとして考えるところがありますが、民主化したからこそやるべきことが「地域の人口減少に対して私たちができること」を考え、動くことではないかと。誰でもカメラを簡単に使えて、上手に写真が撮れる時代だから、それを少しでも地域に役立てたいと思って、現在ローカルフォトを真鶴など他の地域でも展開しています。
飯沢:最近はネットで印刷も製本もできるから、写真集のハードルも下がって、誰でも簡単につくれるようになりました。その結果、若手の自主制作作品集で似たようなものが増えて、少し問題だなと思っています。これもMOTOKOさんが言った"民主化"の現れですよね。
MOTOKO:民主化はいいところも悪いところもあります。いいところを使えたら、こんなに面白い時代はないのですが、スマホの普及であまりにもカメラが便利になりすぎていて、写真のコモディティ化が起きていると感じます。昔は誰もが目に見てわかる写真の差異がありましたが、今はみんなうまいけど、差異がなくなっているように感じます。
平間:僕は3年前から東京・三宿で写真館を始めました。「スマホの写真と写真館の写真は何が違うの?」と聞かれたら、スマホの写真は消費的で短期的な記録を目的としていることが多いが、写真館の写真は子どもや孫の写真など長期的な記録を目的にしていると答えています。
写真の均質化の話が出ると、僕もカメラの性能ありきの問題と考えていましたが、最近は「人間の均質化じゃないか」と思うようになりました。音楽も昔の録音はすごいのですが、機材のレベルは今のほうが圧倒的に上です。それでもかつていい作品が生まれてきたのは、人間力が今より高かったんだと思います。
飯沢:人間力と地域、場所は深く関係していますよね。ラテン語で「ゲニウス ロキ(地霊)」といいますが、場所には力があって、その地域ごとに神様が宿っていて、それが人にもたらす力があるのだと思います。
平間:その人のオリジナリティって、だいたい地域、場所に起因していますからね。
飯沢:今後はそこをしっかり見ていくことが大事になると思います。現在はシステム化が先に進み、「こうすれば町おこしができる!」となりがちですが、それよりも人の問題が重要です。最近、写真家の藤岡亜弥さんが東広島市の地域おこしのプロジェクトに参加して、その地域に住みながらの活動を始めました。アーティスト・イン・レジデンスに近い形で地域に移住して活動する写真家は増えていますね。
平間:写真自体がコミュニケーション能力を持っていることと、自分自身の作品としての写真も撮れるので、アーティスト・イン・レジデンスに向いていますよね。藤岡さんのような例が出てくると、地域と写真家の関係が変化していくと思います。
MASASHI ASADA'S WORKS

写真集『みんなで南三陸』より「ヤマウチのみんな」

写真集『みんなで南三陸』より「戸倉・水戸辺のみんな(上棟式)」

写真集『みんなで南三陸』より「歌津・伊里前復幸商店街のみんな」

秋田県フリーマガジン『のんびり』1号表紙

道後オンセナート2018「鷺の恩返し」

『八戸レビュウ』より『First Ice Kiss』

Otsu Festival(大津フェスティバル)「大津絵」
KOTARO IIZAWA'S WORKS

飯沢さん、料理人・おかどめぐみこさん、アーティスト・ときたまさんが運営する写真集食堂「めぐたま」。飯沢さんの蔵書である写真集5000冊が並び、自由に読むことができる。

飯沢さんがディレクターを務める写真公募企画展「倉敷フォトミュラルf」。全国から応募された写真作品を選出し、「商店街展示」、「個展部門展示」の形式の異なる2部門で展示する。

現代日本写真を読むための用語解説と写真家ごとの展覧会・写真集レビューから構成される『キーワードで読む現代日本写真』(フィルムアート社)。
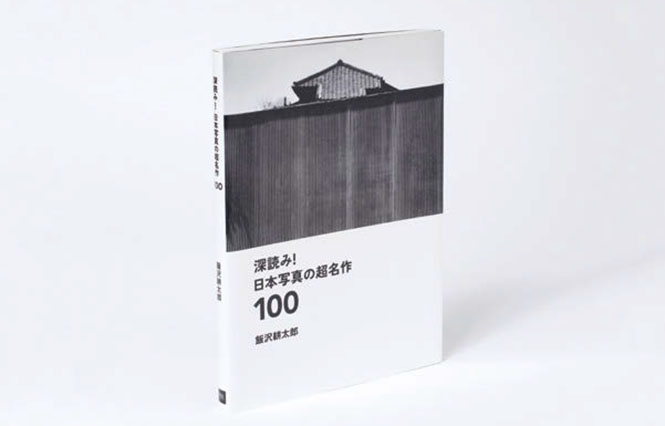
1850年から2011年までの写真101点を収録した『深読み!日本写真の超名作100』(パイインターナショナル)。
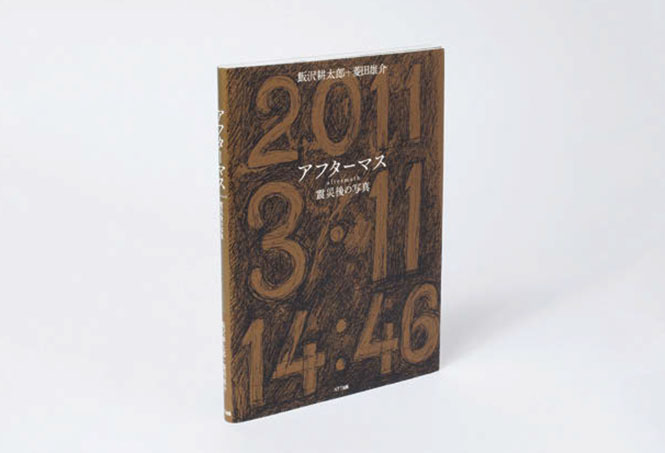
東日本大震災によって故郷・仙台が被災した飯沢さんと写真家・菱田雄介さんとの共著『アフターマス 震災後の写真』(NTT出版)。
広告の理論を地域に落とし込む
飯沢:僕は全国各地に写真展の審査で行くことも多いのですが、その一つ、岡山県倉敷市の写真公募企画展「倉敷フォトミュラルf」は15年続いています。この写真展では公募した写真を大型布に印刷して、商店街にバナーとして吊るすんです。だから、できるだけおばあちゃんが孫を撮ったような写真を選ぶようにしています …