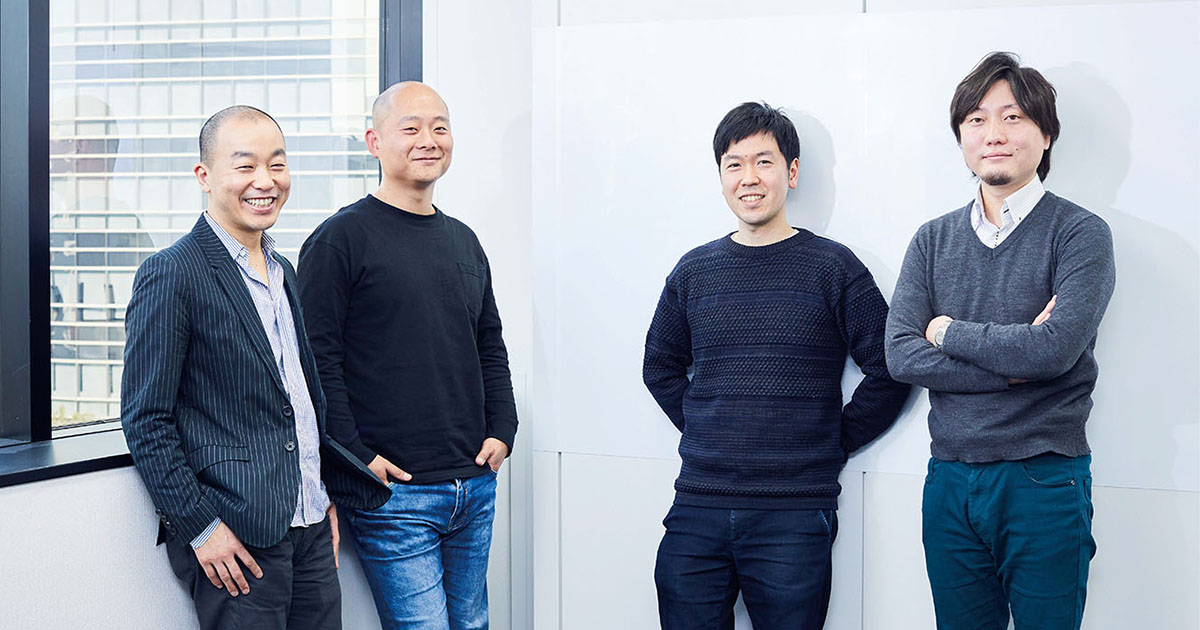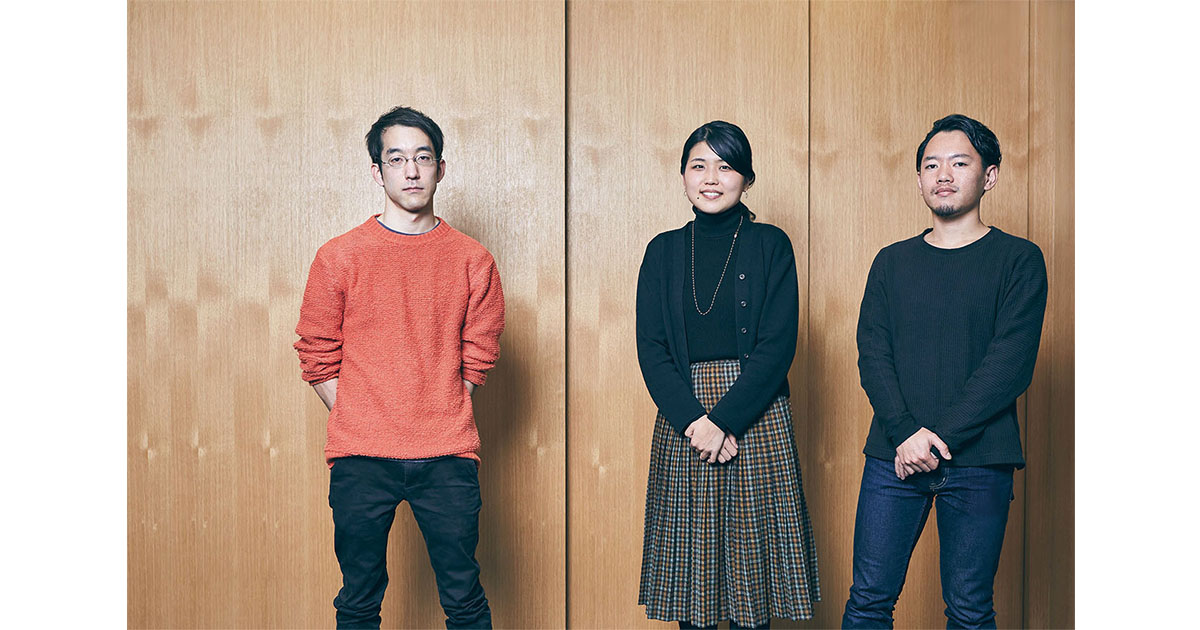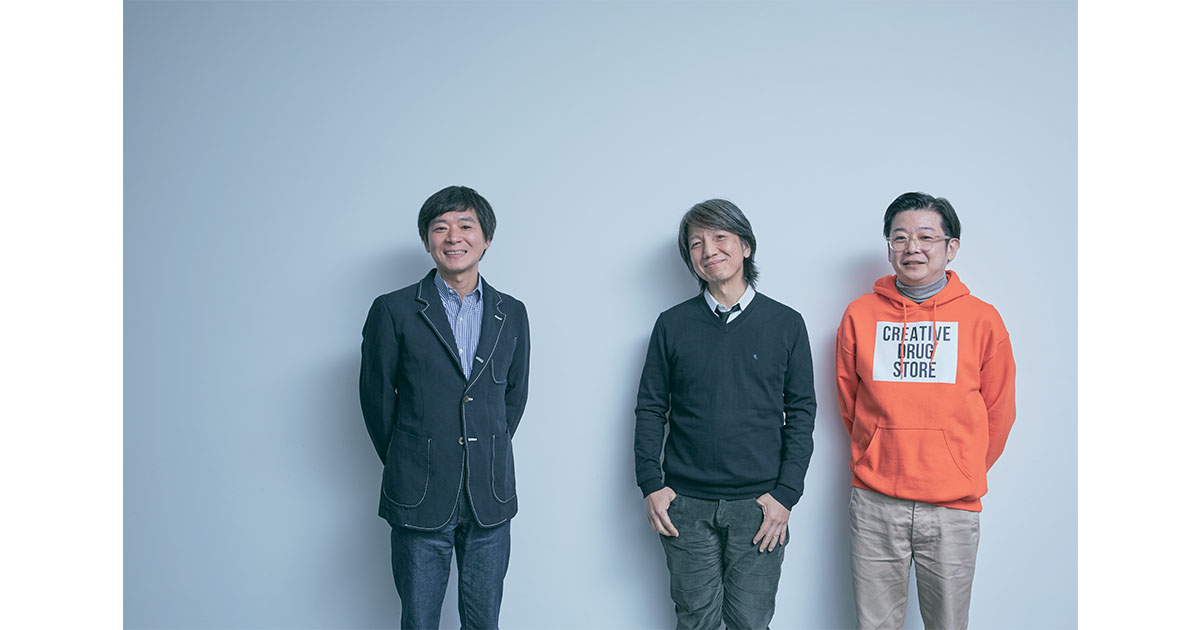いつの頃からか、アートの世界では東北の野良着に代表される、日本のヴィンテージテキスタイルが「BORO」として注目を集めています。いまや「リサイクル」「リユース」という言葉が当たり前になっていますが、「BORO」に代表されるように日本にはもともと捨てることなく、補修して繰り返し使う文化がありました。洋服に限らず、陶磁器の割れや欠け、ヒビなど破損部分を修復する金継ぎもまさにその文化を代表するものです。
こうした文化が最近はアートだけではなく、ファッションやインテリアの世界にも浸透。古いものを使いながら、そこにこれまでにない価値が加えられた新しいプロダクトが生まれ、注目を集めています。それは、ファストファッションへの反動なのかもしれません。あるいは、人の「手」を感じるモノに愛着を持つ人、それらを日常の中に自然な形で落とし込んで使っている人が増えているからなのかもしれません。一つ言えることは、もうただの「リサイクル」「リユース」ということだけで終わる時代ではなく、もう一歩先へと進んでいるのではないかということです。
今号では、金継ぎ作家として活動している、カフェ6次元のナカムラクニオさん、リノベーションの先駆け的な存在であるOpenA 馬場正尊さん、そしてBOROを使って新しいファッションプロダクトをつくる「KUON」の藤原新さんに、このテーマのもとお話をいただきました。
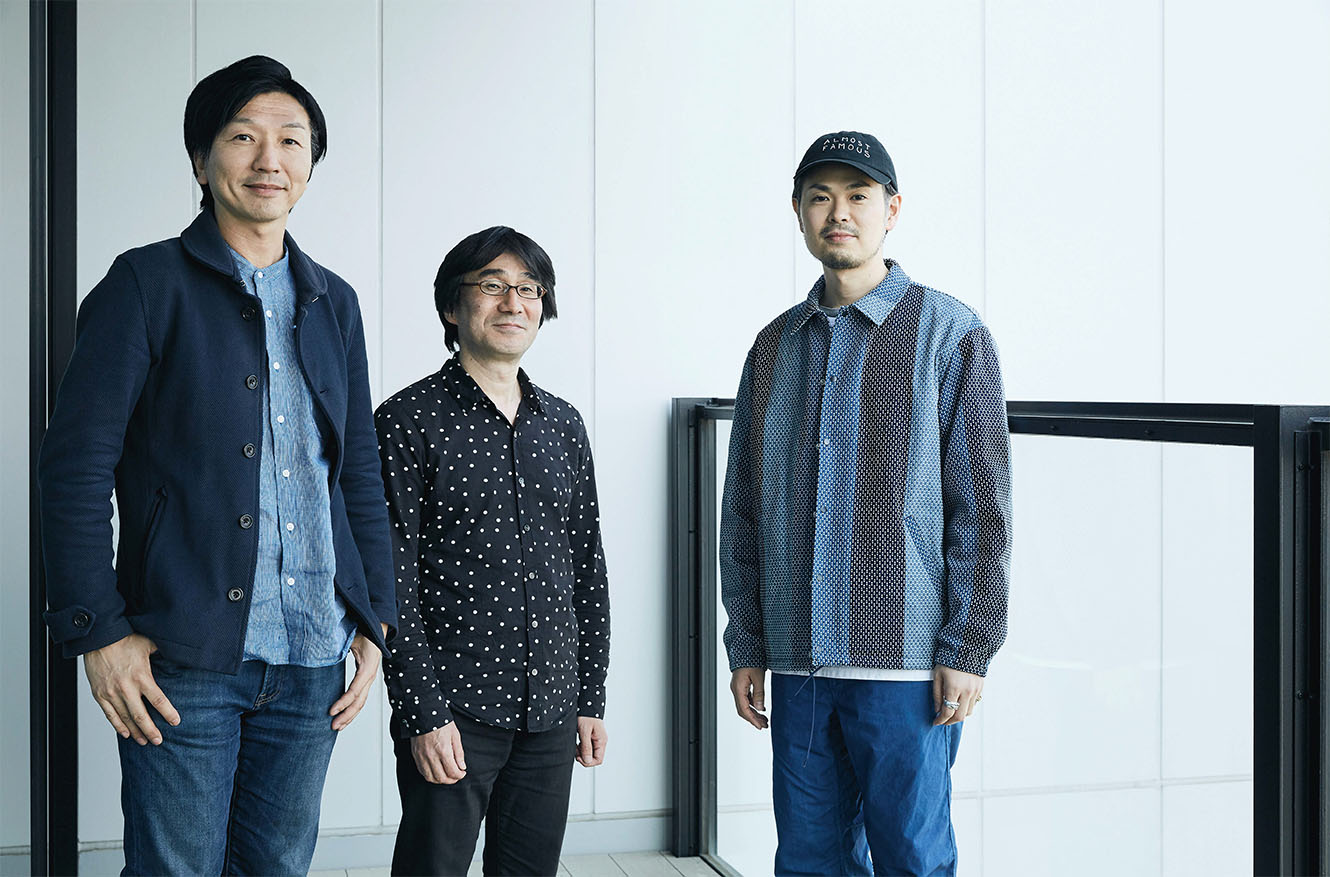
Photo:Hikaru Otake parade/amanagroup for BRAIN

新しい日本人が出てきている
ナカムラ:馬場さんは国内のリノベーションの先駆けとして知られていますが、なぜこれを仕事にしようと思ったのですか。
馬場:きっかけは、15年前。神田日本橋の裏通りの空き物件だった雑居ビルなどをアーティストたちでジャックして、町全体をギャラリー化する「CET(東京セントラルイースト)」というイベントを開催したことです。アーティストのインスタレーションによって空き物件がアート作品に変わることで、借りる人がいるかもしれない。そのときに東京R不動産が誕生しました。
ナカムラ:その後の十数年で一気に時代が変わって、いまやリノベーションはオシャレなものになりましたね。
馬場:リノベーションがこんなにも世の中に受けいれられ、一般化されるとは思いもしませんでした。いまや大企業も手がけているので、社会的な役割の変化を感じます。
ナカムラ:僕が10年前に荻窪でブックカフェ「6次元」を始めようと思ったときも、新しくつくるんじゃなくて、リノベーションするという空気を感じました。だから、6次元では前の店の内装をすべて買い取って、リノベーションしました。古着の文化を取り入れているKUONにもそういう流れがあるんじゃないかと思いますが。
藤原:僕は10代の頃からファッションが好きで、大学に入ってから服の仕事をしたいと思いつつ、一方で法律の仕事も面白いと感じていました。結局、卒業後は法律関係の仕事に就きました。僕が30歳の頃に世の中が債務整理バブルになり、僕が働く場所に相談に来る人たちと毎日話をするなかで、「良いことをすれば良いことが、悪いことをすれば悪いことが返ってくる」ことを実感しました。統計的に数字として出せるくらいに。
それから「良いことをして生きていきたい」と思うようになり、好きなファッションのビジネスで社会的課題を解決したいと、働きながら起業しました。
馬場:ファッションに入った入り口が面白いですね。世代論になるけど、僕は最近の30代、40代のそういう発想の人を「新しい日本人」と呼んでいます。僕らのモチベーションはかっこよさ、個的な欲望だったけれど、今の若い人たちは初めから素直に「社会貢献がしたい」と言える。僕らとは積んでいるOSが全く違うなと感じています。
ナカムラ:確かにそうですね。実は僕も藤原さんと同じような理由で、カフェを始めました。僕の場合、20年ほどテレビの世界でディレクターをやってきたことへの罪滅ぼし的な部分があります(笑)。「オシャレにコーヒーを入れたい」という欲望ではなく、カフェという小さなメディアに挑戦して、もう少し世の中のためになりたいと思ったことがカフェを始めたきっかけです。
藤原:僕とデザインを手がける石橋真一郎でつくる「KUON」は社会貢献というバックボーンがありつつ、あくまでもファッションなので、見た目のかっこよさと両立させることが重要だと考えています。
ファッションと器の共通点
ナカムラ:僕はいま金継ぎ作家としても活動をしています。先ほど「債務整理バブル」という話がありましたが、器の修復をずっと続けているのは「骨董バブル」が弾けたことが大きく影響しているんです。20年前は高い骨董をひたすら買う時代でしたが、世の中の経済と流れがリンクする中で、15年ほど前にそれが「直そう」という空気に変わったんです。器などの修復のための「金継ぎ」という工芸技術はその頃に復活しました。
藤原:それで言うと、ファッション界は今、ボロ布の「BOROバブル」が来ています。BOROの流れは浮世絵と同じで、今から15年前にパリでBORO展が開催されたことに始まります。そこで海外の人が「これはアートだ」と評価して、ヨーロッパで広がり、ラルフローレンが買いはじめてブームになり、それがいま日本に戻ってきています。
馬場:BOROの動きとKUONは呼応しているんですか?
藤原:僕らもBOROを使っていますが、その流れを意識してというよりは、世界のファッションマーケットに出ていくためにBOROを使い始めました。その背景には、日本のファッションマーケットは人口減少により小さくなってきていることもあります。でも、日本の伝統的なものを今のファッションにアップデートさせたブランドのほうが世界に出ていきやすいと考え、今のような生産方法を構築しました。
ナカムラ:ファッションと器の世界はよく似ています。例えば、最近古唐津の破片が1万円するなど、古い陶片が高くなってきています。その理由はここ1、2年で金継ぎが「KINTSUGI」という名前で海外でも普及し始めたからです。うちにも海外からの問い合わせが増えました。金継ぎは日本独自にガラパゴス的に進化したオリジナルの技術で、海外では綺麗に修復することを重視しているので、割れたところをあえて目立たせるという概念はありません。
今は日本の金継ぎを真似して、イギリス風、アメリカ風の金継ぎが広がっています。金継ぎというのはヒビの部分を川や木の枝に見立てる、いわば「見立て」の文化なんです。昔の茶人は茶碗をわざと割ってヒビを入れて、名前をつけてお茶を立てたといいます。だから、服のBOROやヴィンテージをかっこいいと思うのと一緒です。
藤原:海外ではBOROをアートとして見ている人が多いですね。アートの中でも、抽象画に近いかもしれません。
馬場:オーセンティックなアートというより、モダンアートに近いものとして捉えられているんですね。逆にリノベ―ションは輸入ですね。僕らの世代はDADAから入って、アンディ・ウォホールがニューヨークの自分たちのスタジオを「ファクトリー」と名付けて、内装を全部銀色に塗ったのをかっこいいと感銘を受けた世代。そういうものをカスタマイズして自分たちのカルチャーに同化させています。
でも、最近の若い世代は日本の文化を最初から組み込んで、西洋の文脈にないリノベーションをやっているので、僕も頑張らないと、と思います。
MASATAKA BABA'S WORKS

神田、秋葉原あたりの東側一帯の空き物件を時限的に借りてギャラリーとして活用したイベント「CET(東京セントラルイースト)」。

「一度棄てられたモノを、再び社会に投げ返す」というコンセプトのもと、産業廃棄物を新たなプロダクトに生まれ変わらせるプロジェクト「THROWBACK」。 写真:THROWBACK

静岡県沼津市で30年以上にわたり愛されてきた「少年自然の家」を、現代的にリノベーションした泊まれる公園「INN THE PARK」。 写真:阪野貴也

2018年3月8日~21日の期間にスターバックスのCSRキャンペーンの一環で実施されたJUN KITAZAWA & STARBUCKS FIVE LEGS PROJECTで、デッドストック工務店が制作したオリジナルの移動式屋台が銀座の街に繰り出した。 写真:鈴木裕矢
「昔」と「今」を組み合わせる
ナカムラ:僕は最近、ある器にそれとは違う器の破片をくっつける「呼継ぎ」にハマっているんです。昔の茶人もそれをやっていて、バラバラの破片をつなげた古い志野の茶碗を東海道に見立て「五十三次」という名前を付けたり。今テストしているのは縄文土器。古代の縄文土器を日常使いにするプロジェクトを進めようと思っています。
馬場:(器を見ながら)これはすごい!時代も文脈も素材も全部アッセンブルされて、見たことないものになっていますね …