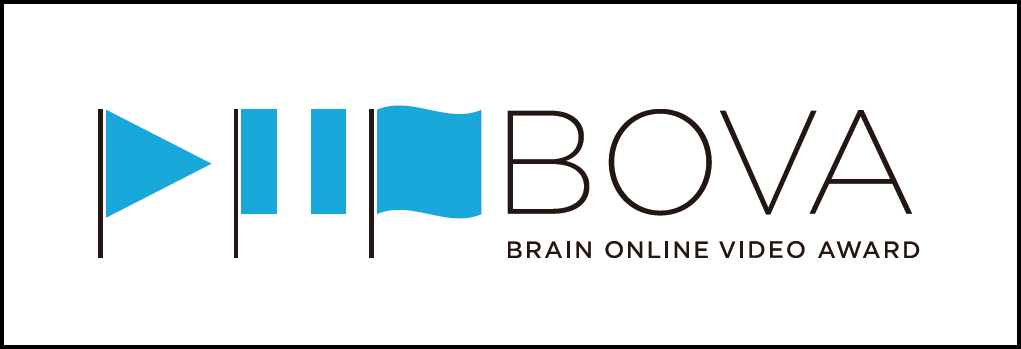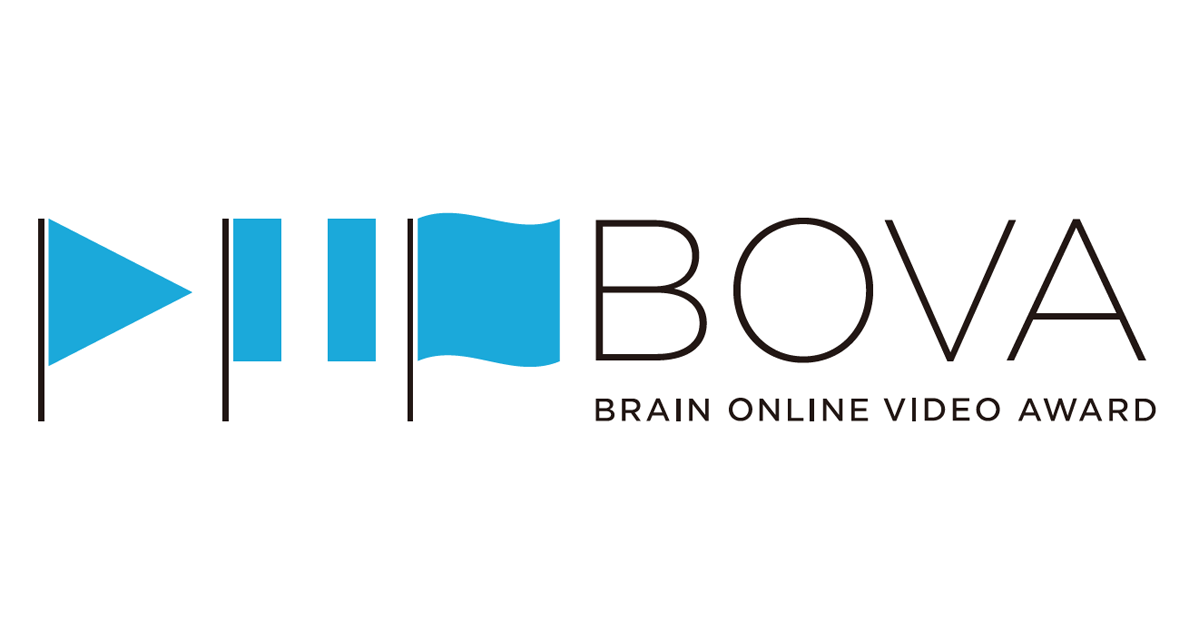近夏、ハウステンボスが開業する「変なホテル」。一度聞いたら忘れられないインパクトのあるネーミングとブランディングを手がけたのはGRAPHの北川一成さんだ。クリエイティブディレクションの根幹には、そのデザインの限界という俯瞰した視点があった。

北川一成(きたがわ・いっせい)
1965年兵庫県加西市生まれ。87年筑波大学卒業。89年GRAPH(旧:北川紙器印刷)入社。2001年、書籍『NEW BLOOD』(発行:六曜社)で建築・美術・デザイン・ファッションの今日を動かす20人の1人として紹介される。同年国際グラフィック連盟(世界約250名のトップデザイナーによって構成される世界最高峰のデザイン組織)の会員に選出。04年、フランス国立図書館に、“近年の印刷とデザインの優れた本”として多数の作品が永久保存される。
デザインの限界を思い知った出来事
私は、デザインには限界があると思っています。たとえば、どんなにデザインにこだわったスタイリッシュな店舗であったとしても、店員の態度が悪かったら繁盛店にはなりません。それは一流ブランドでも小さな定食屋でも同じだと思います。突き詰めていけば、デザインが担うのはブランディングのほんの一要素にすぎません。ブランド力を高め、会社の業績を上げるのは、最終的にはデザインではなく「人」なのです。
それは、20年以上前、自社GRAPHのブランディングを手がけたときに痛感しました。世界でも戦える印刷とデザインの会社を目指そうと、社名を変えロゴも新しくデザインしたときのことです。
印刷の現場で働いてみると、これまで営業がクライアントに「刷れない」と断っていた色は、努力や工夫次第で刷れる可能性が十分にあることがわかりました。現場の職人は、手間がかかるし経験値もないため、何かしらの理由をつけて「できない」と断っていたのです。そうした悪い慣習を、社名とロゴを変えるタイミングで改めようと考えました。
たしかに、社名とロゴの変更は、会社が改革する意思があることを社内外に知らせるきっかけにはなりました。けれども、最終的には働く人が本心で変わろうとしなければ何も変わりません。一番苦労したのは、社内の人間の意識改革だったのです。そのとき、デザインには限界があることを思い知りました。そうした経験から、私は「働く人が置いてきぼりにならないブランディング」を心がけています。
今、ブランディングを手がけているハウステンボスの「変なホテル」は、「変わり続けることを約束するホテル」というコンセプトを掲げています。このコンセプトは、顧客となる人はもちろん、働く人に向けたメッセージでもあります。
変なホテルというネーミングと
変わり続けることを約束する理由
ハウステンボスから依頼されたことは、新規ホテルのロゴマークや館内サインのデザインなど、ホテル全体のビジュアルコミュニケーションのディレクションです。決まっていたことは、泊まり心地やサービスのクオリティを維持しながら、世界一生産効率の高いホテルを目指すということ。最新の空調設備やロボットを駆使することで電力や人件費を削減するという合理性を追求したホテルであることから「スマートホテル」と呼ばれていました。
その名前を聞いたとき、「スマートという言葉は既に一般化されており ...