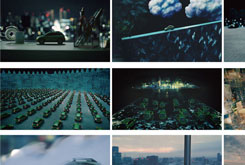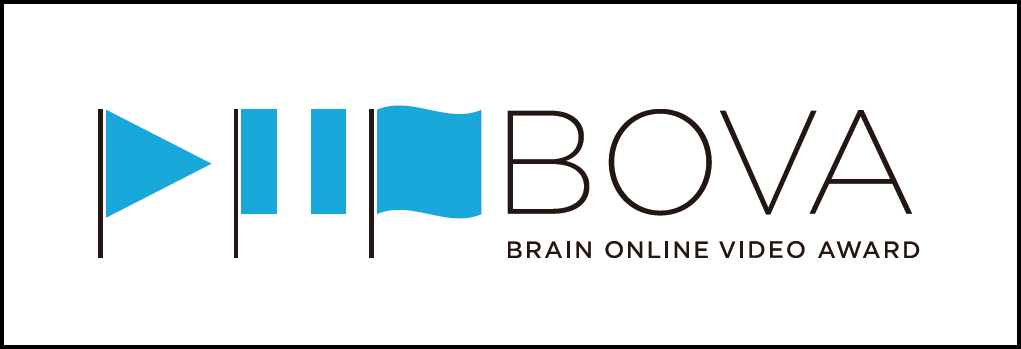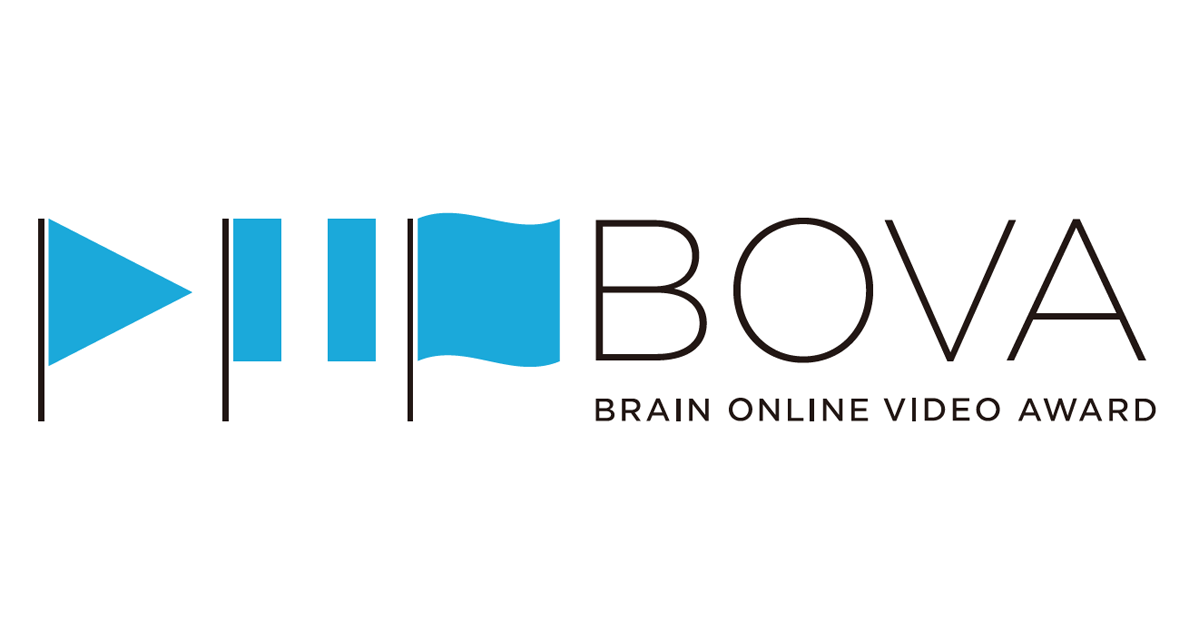ライブステージの白い幕が下りると、そこにあるのはロボットバンドが音楽を奏でている姿。6月24日、東京 恵比寿のライブハウスリキッドルームでは、そんなSF映画のワンシーンのような出来事が実現していた。
パーティを進化させる
「パーティシーンに対する貢献をしていきたい。そのために、未来のパーティというものを作っていきたい。それによってZIMAの掲げる『FUN FORCE』というコンセプトを表現できるのではないか」。ZIMAを提供するモルソン・クアーズ・ジャパンのこの想いが、ロボットバンド「ZMACHINES」が誕生するきっかけだった。
音楽の歴史をひもとけば、ロックギターが生まれたことによって60年代以降にロックのムーブメントが広がり、80年代にはシンセサイザーが一般的に入手しやすい値段になったことで、エレクトロニカのような電子音楽が普及していった。「そんなふうに、テクノロジーの発展が表現そのものを発展させてきた歴史が音楽にはあります。テクノロジーで表現の可能性を広げられれば、クラブカルチャーへの貢献は意味深いと思いました」と、Z-MACHINESを手がけたクリエイティブエージェンシーSIXの斉藤迅さんは言う。
そして斉藤さんが思い描いたのが、極めて演奏能力の高いロボットをつくり、それをさまざまな人に使用してもらうことだ。人間の能力を超えた演奏をロボットが実現できれば、新たな表現が生まれる。「非常に難しいチャレンジではありましたが、素晴らしいスタッフと組むことができたので、形にできる確信はありました。そして非常にクオリティの高いものをつくれば、ただの一キャンペーンではなく、音楽というカルチャーそのものに貢献しZIMAのファンを増やすことができると思いました」。
音楽好きの「夢」が人を集めた
人間の能力を超えたロボットが楽器を演奏する。これは、音楽に携わる人間であれば、その多くが一度は想像したことのあるもの。そんな、いわば音楽好きの「夢」のアイデアが軸としてあることが、実現への大きな鍵になったと斉藤さんは考える。
「とにかくわからないことだらけだった」と斉藤さん。「でも、何かわからないこと、足りないことが出てくるたびに、その分野におけるプロフェッショナルな人に出会い、いいチームをつくることができました。それは、誰もが想像した夢を実現するためのプロジェクトで、誰もが探究したいと思えるアイデアだったから、参加したいと思ってくれる人に出会えたのかもしれません」。
楽器を演奏する装置は、インビジブル・デザインズ・ラボの松尾謙二郎さんとタッグを組んだ。企画が決定した2012年9月頃から、実際に制作を開始する翌13年3月頃までの半年間。ひたすら「どうすれば演奏できるか」「いかにいい音を出すか」、松尾さんはひたすら装置をつくり、実験を続けた。
そして楽器がいい音を奏でられるようになってからは、その音を表現する人型のロボット開発に着手した。そこでメカニカルクリエイターの米塚尚史さんがチームに加わった。またライブを盛り上げるVJとして、映像作家の斉藤洋平さんも参加。少しずつチームの輪が広がり、全体の世界観がかたちづくられていった。