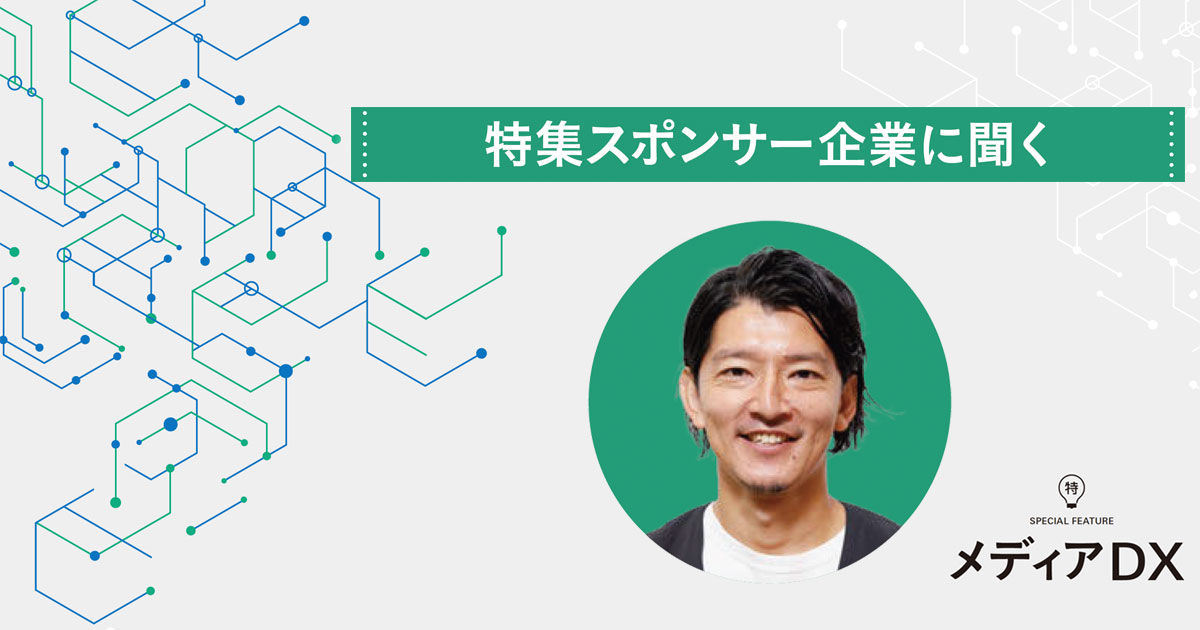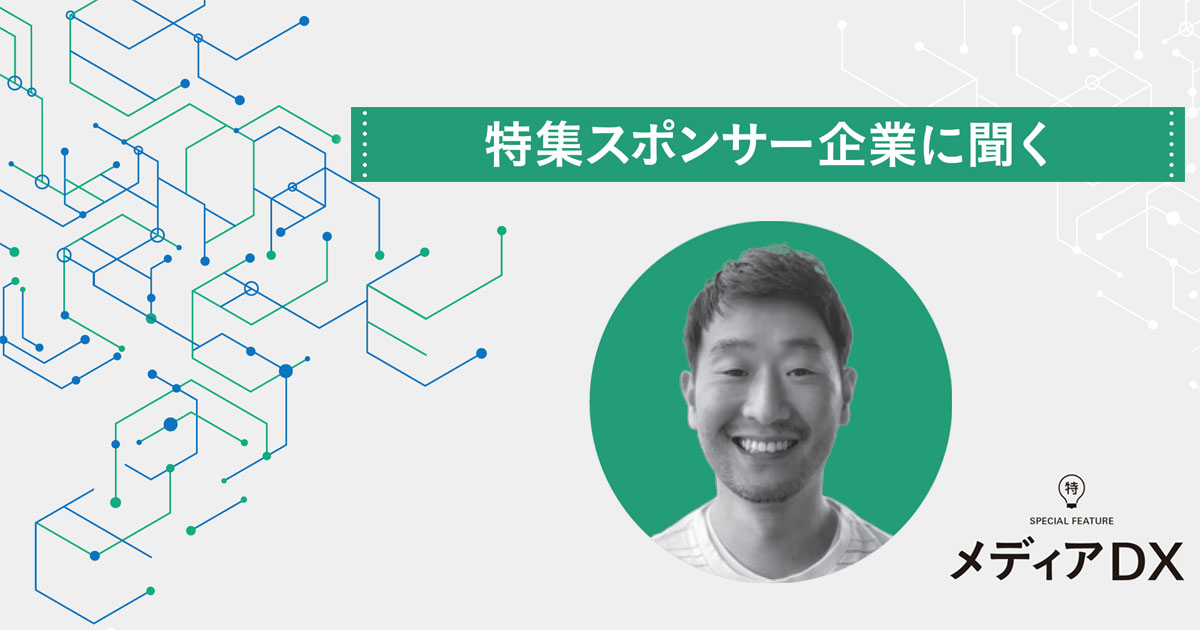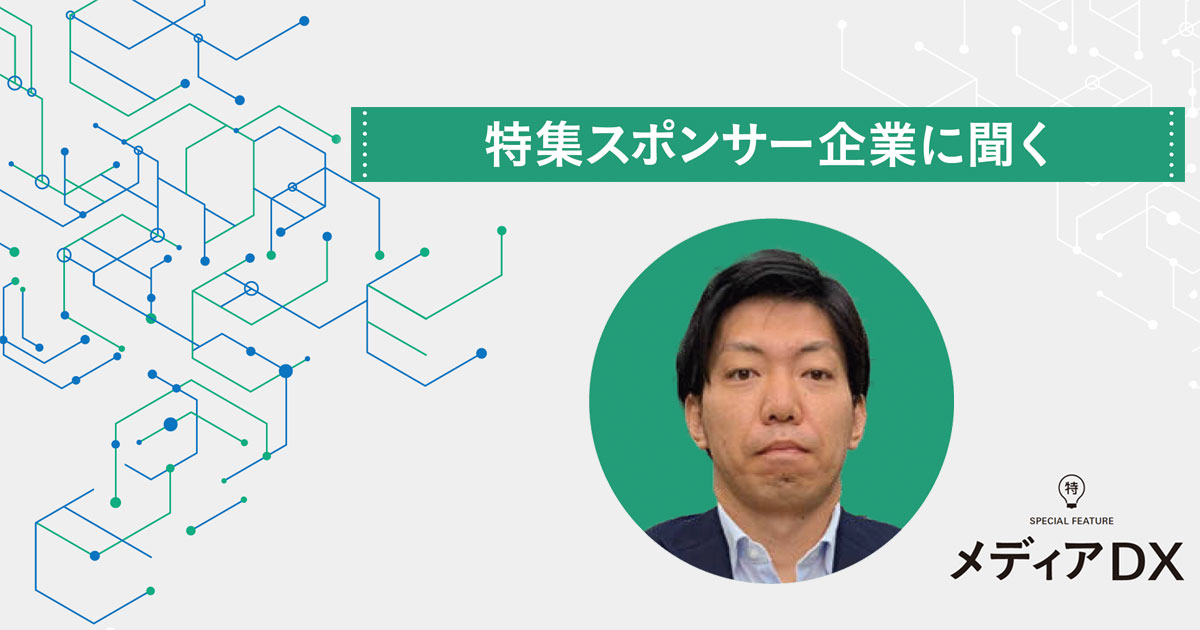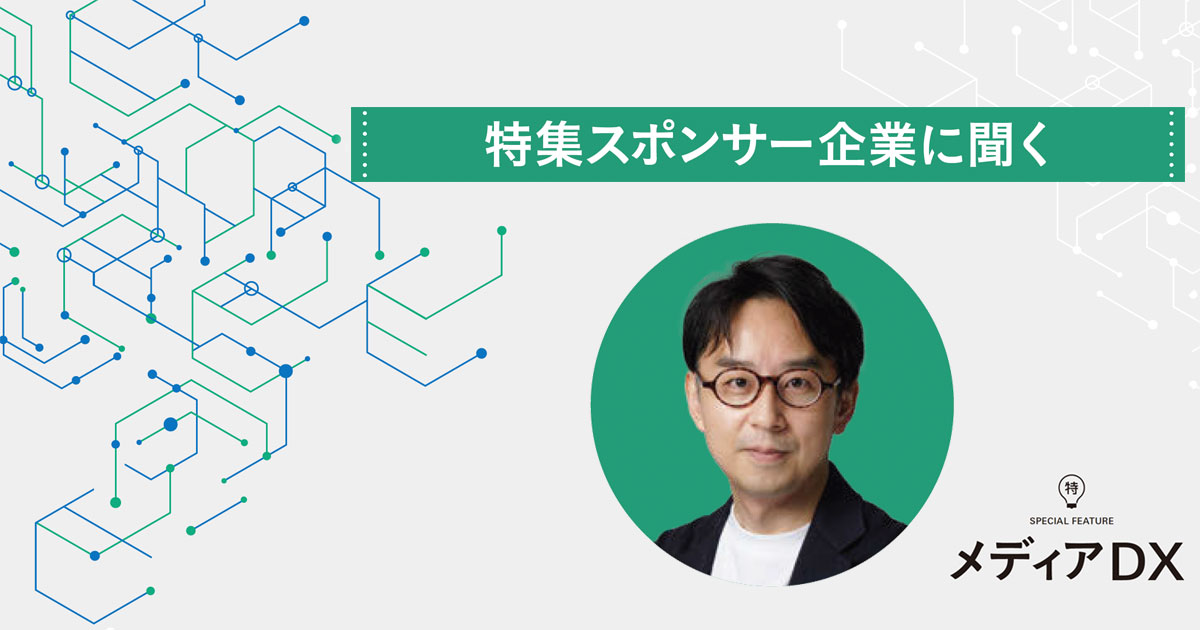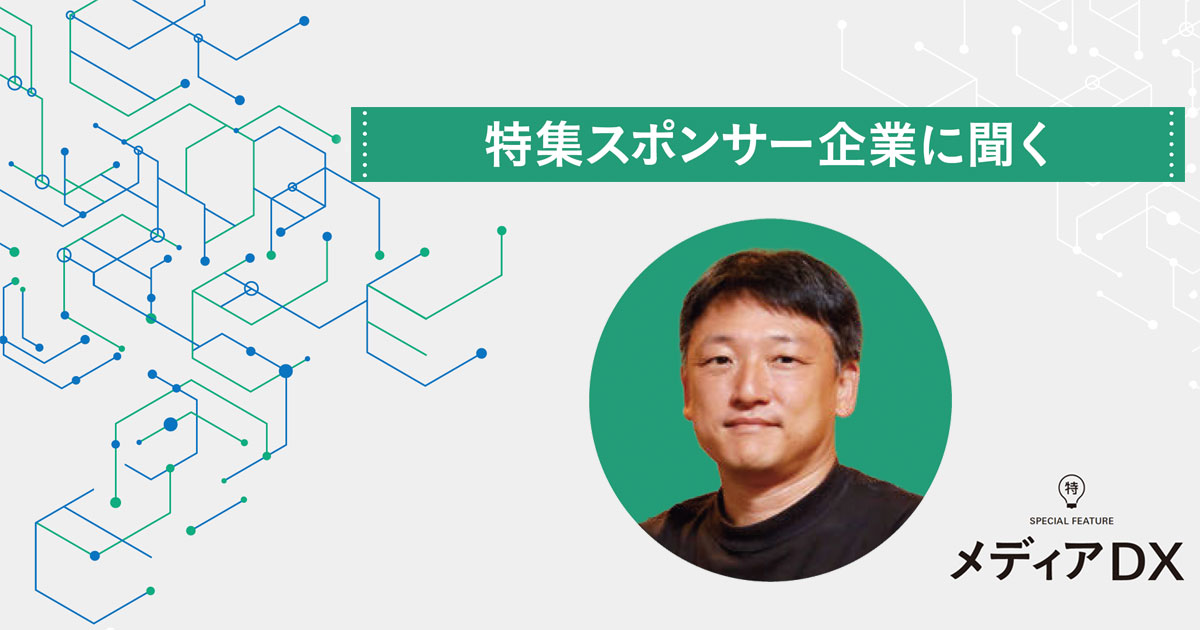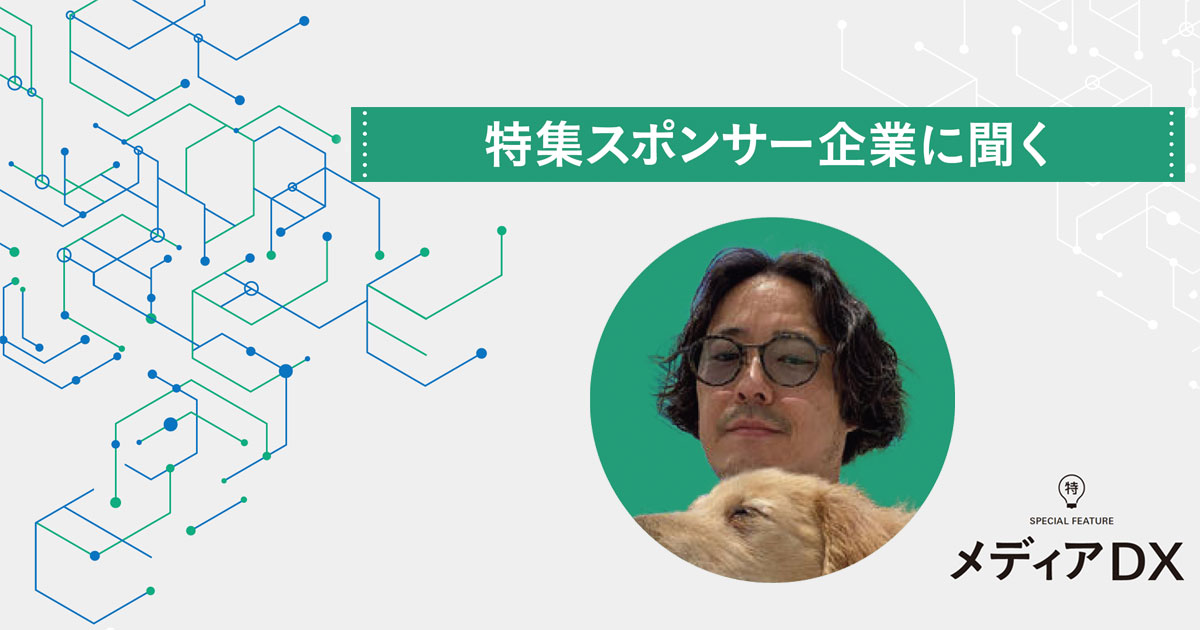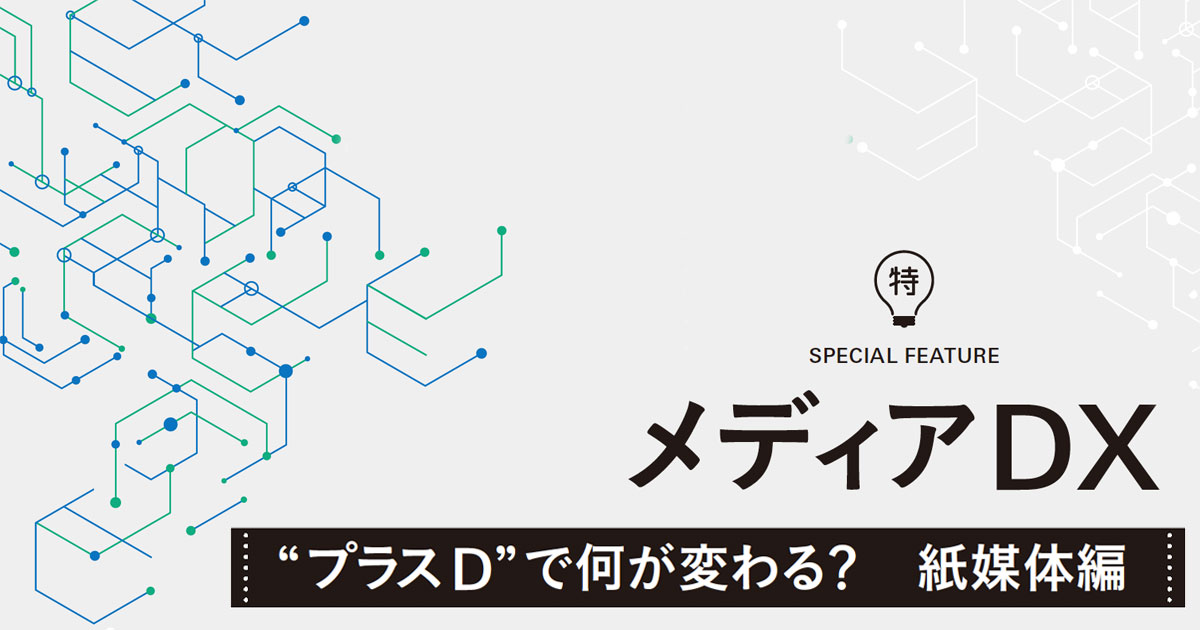業種・業態によって取り組み方は様々にある“DX”。膨大なデータを有する通販企業におけるDXとはどのようなものなのか。ファッションや生活雑貨などの自社開発商品を展開するフェリシモでマーケティングを担う橋本和也氏に、話を聞いた。
DXに関わる部署と主な役割
自社運営の機能が多く、全社でDXにかかわる。データ分析を担うマーケティングコントロールセンター、インタビュー実施をするCX推進チーム、顧客の声が集まるCS部、基盤を支えるIT推進部の支援を通じ、各事業部門での商品企画・販売企画、物流推進部のサービス改善につなげる。
データ活用で実現する 多様な価値観に応えるサービス
独創性のある商品・サービスの展開で、コアなファンがいるフェリシモ。同社では、個性ある商品ラインアップのそれぞれに共感を寄せる顧客ひとり一人に寄り添うことで、CXの向上に努めている。
1965年、企業や役所などで働く女性向けに、職域ごとにハンカチを継続的に届ける通信販売から始まった同社は、顧客IDの一元管理には早くから取り組んでいた。自社で持つ物流機能との連携、カタログやWebサイト制作の効率を上げるといった、日々の業務でデジタルを活用しているが、最終的な目的は顧客満足度を高める施策を実行することにある。
利用者から支持されているのは、ひとつのテーマで色や柄、デザインの異なるアイテムが届く「定期便」システムと、「好き」を起点に共感を広げて人や社会のしあわせを作り出す「部活動」の取り組みだ。
この定期便に関するマーケティング領域を担う橋本和也氏は、「従来の顧客データ管理に基づき、フェリシモの思いやこだわりも内包した、よりパーソナライズしたサービスの提供が必要だと考えました。そして、当社が目指す『ともにしあわせになるしあわせ』というコアバリューのもと、「こんな社会を作りたい」という願いに向けて、未来作りを生活者と進める『クラスター戦略』を取りながら、商品やサービスの価値提案を行うことを目指しています」と話す。
同社が扱うデータは多岐にわたる。単なる購買データにとどまらず、SNSやアンケートによる顧客の声やインタビューの実施、コールセンターに寄せられた意見などから、同社が展開している基金活動や、イベントへの参加データといったものもある。これらのデータを集約し活用できるよう、IT推進部やCS部と密に連携しているという。
「例えばコールセンターに寄せられたお客さまの声は、とりまとめて社内で共有する仕組みを設けています。定期便は...