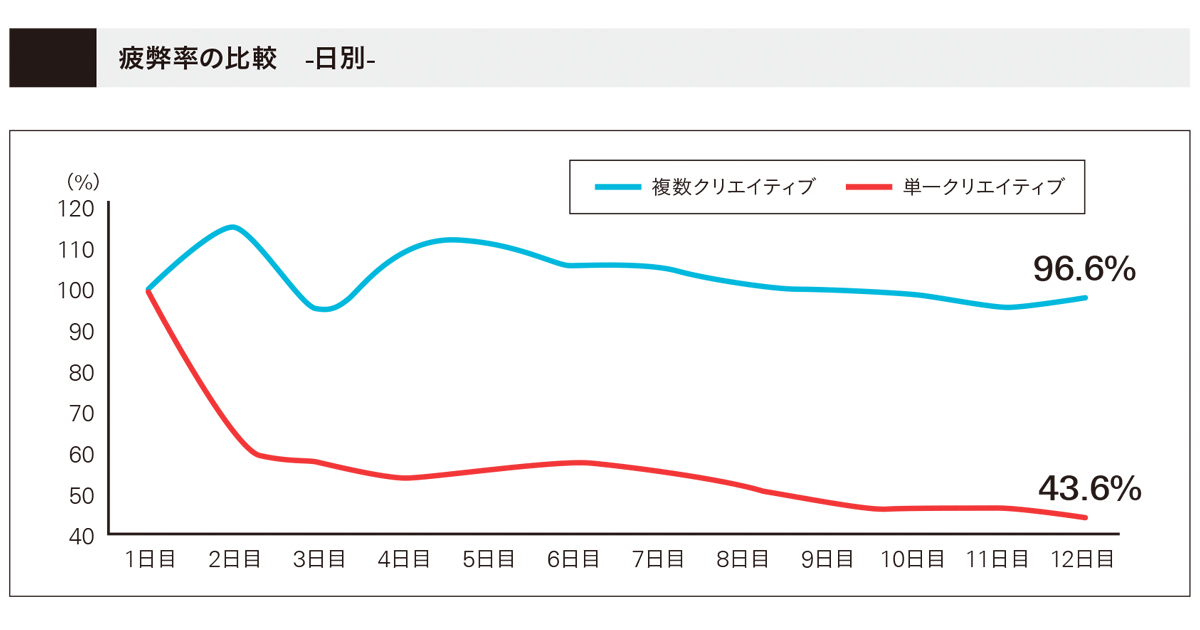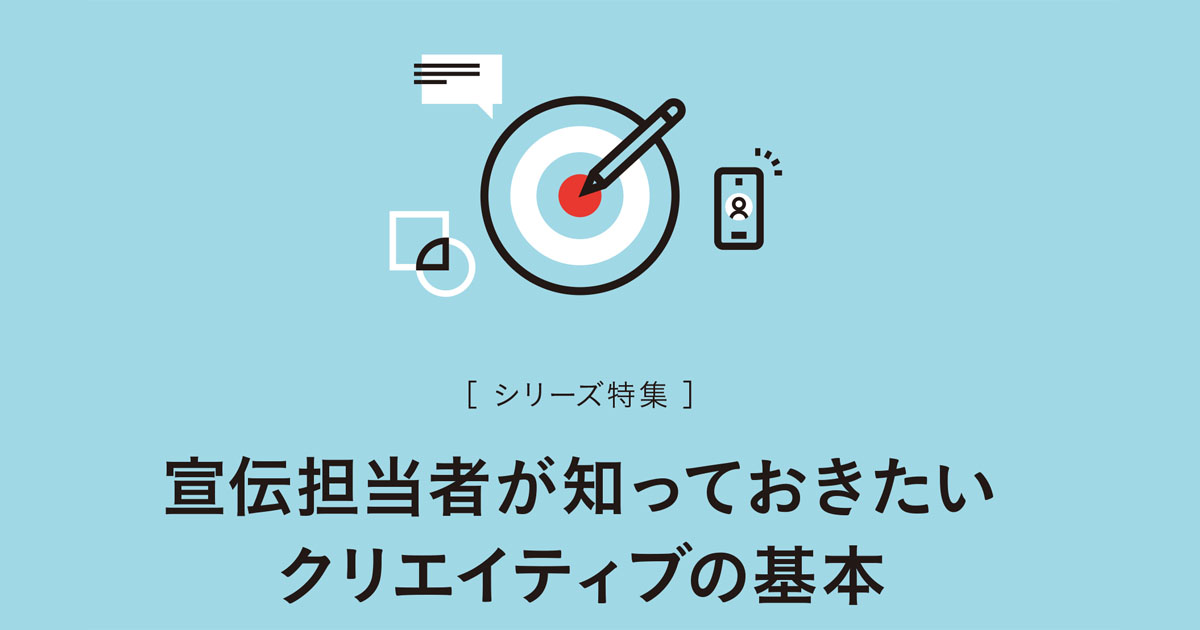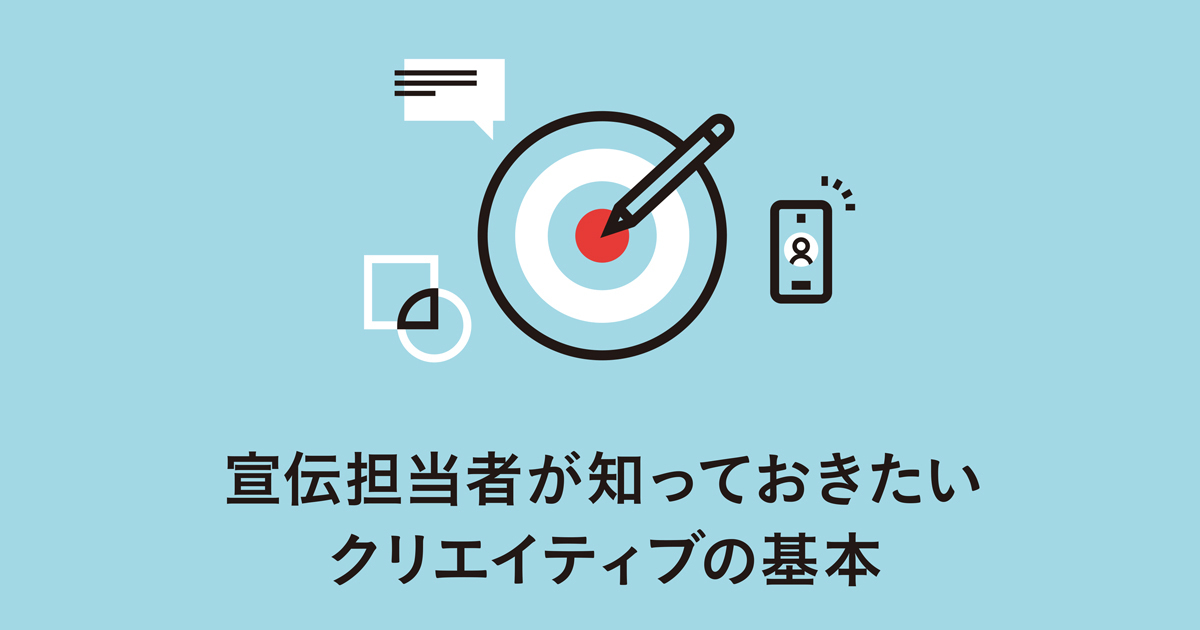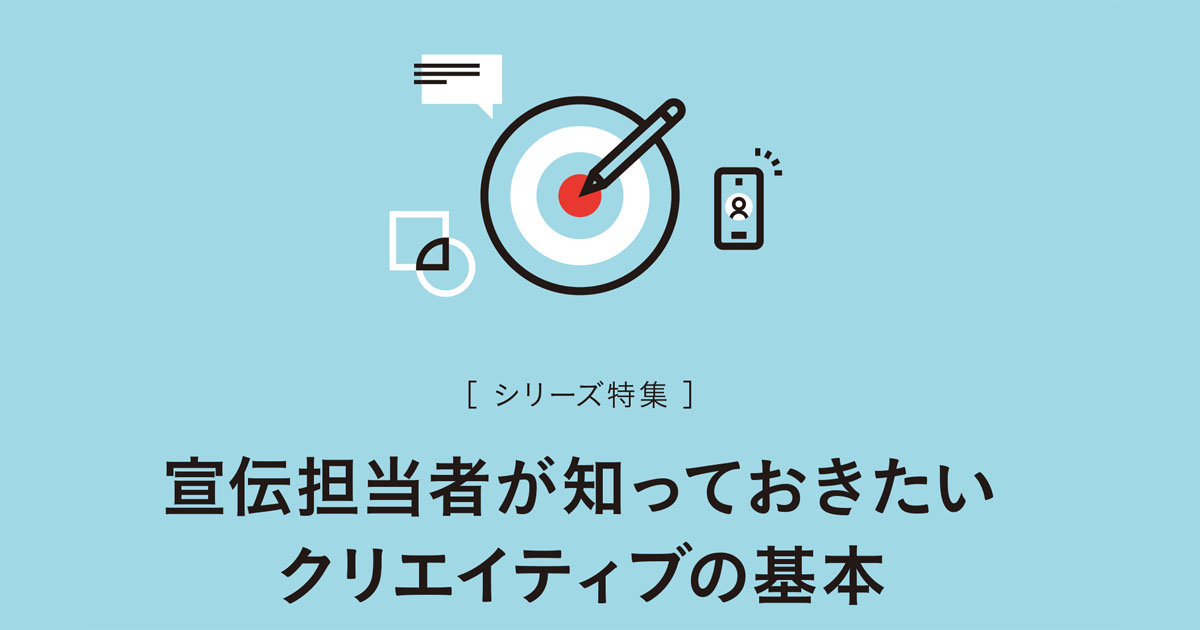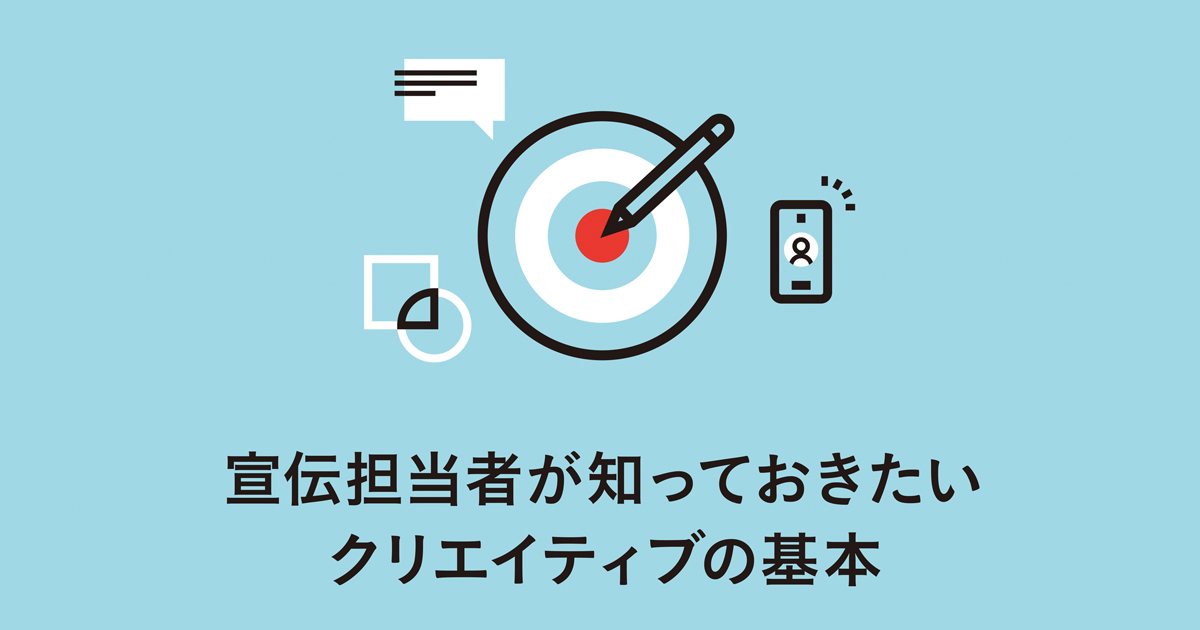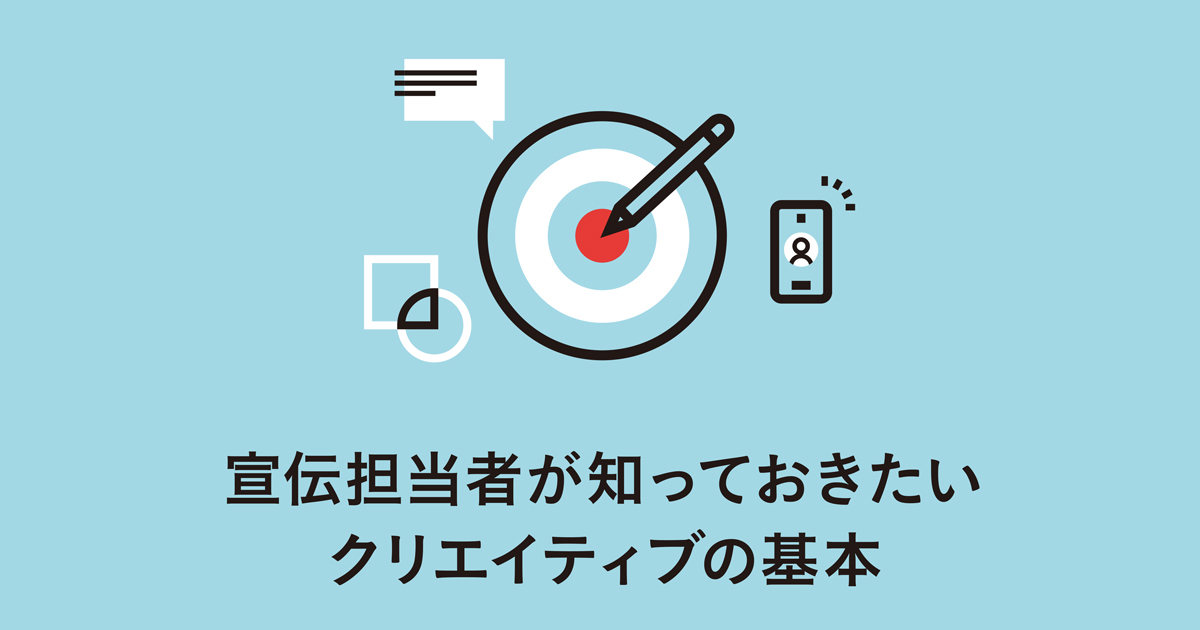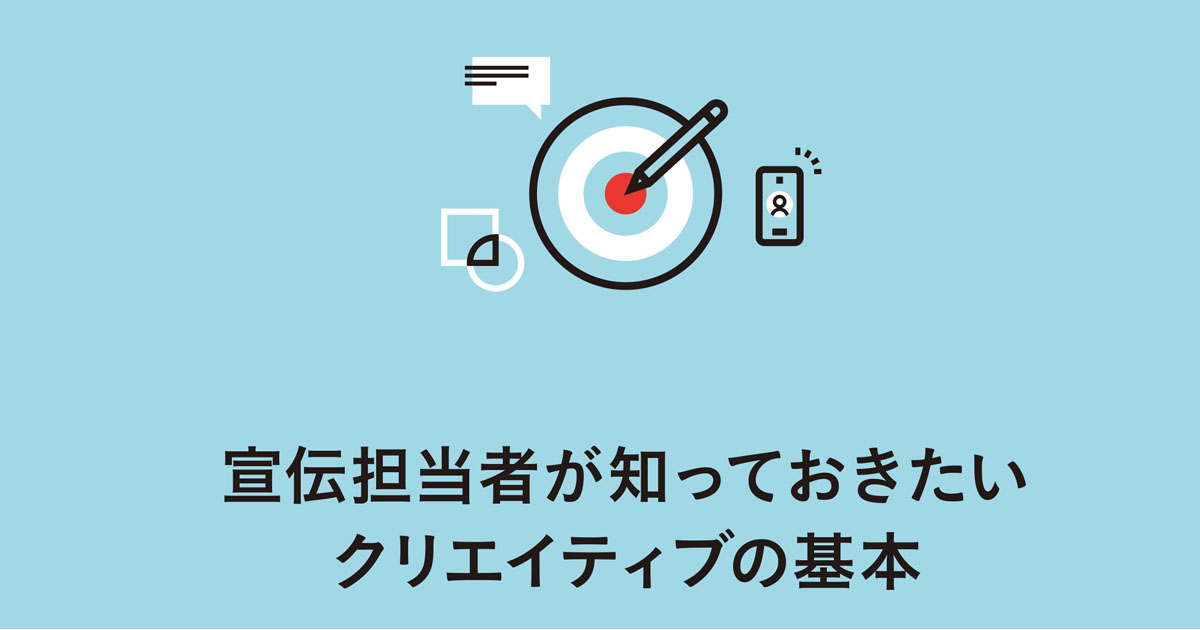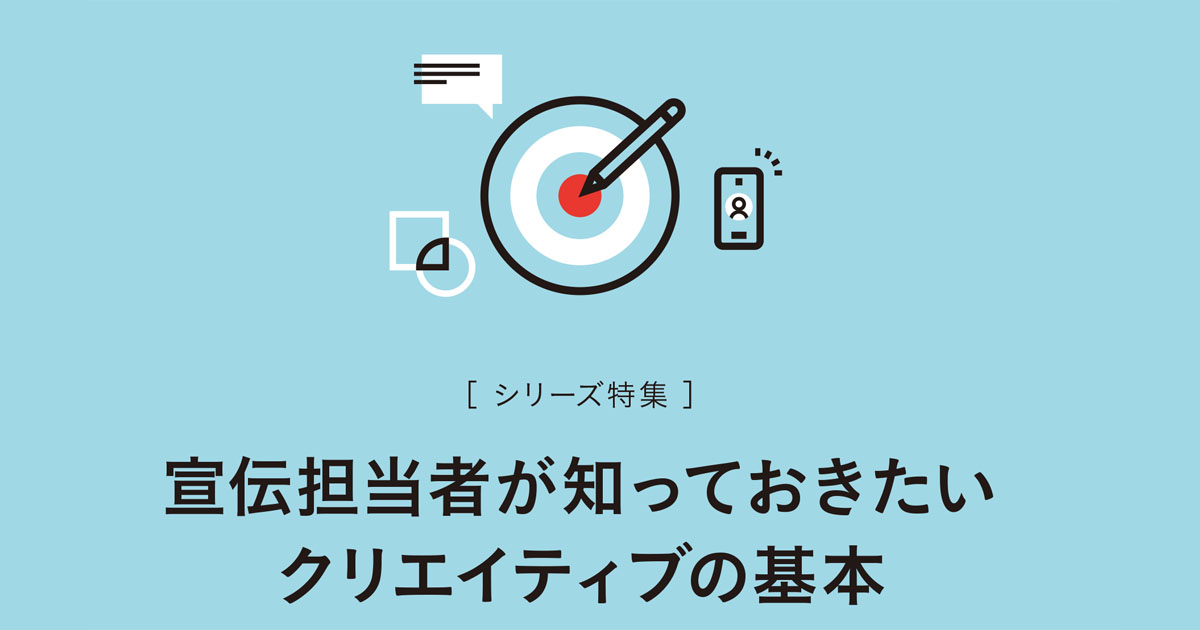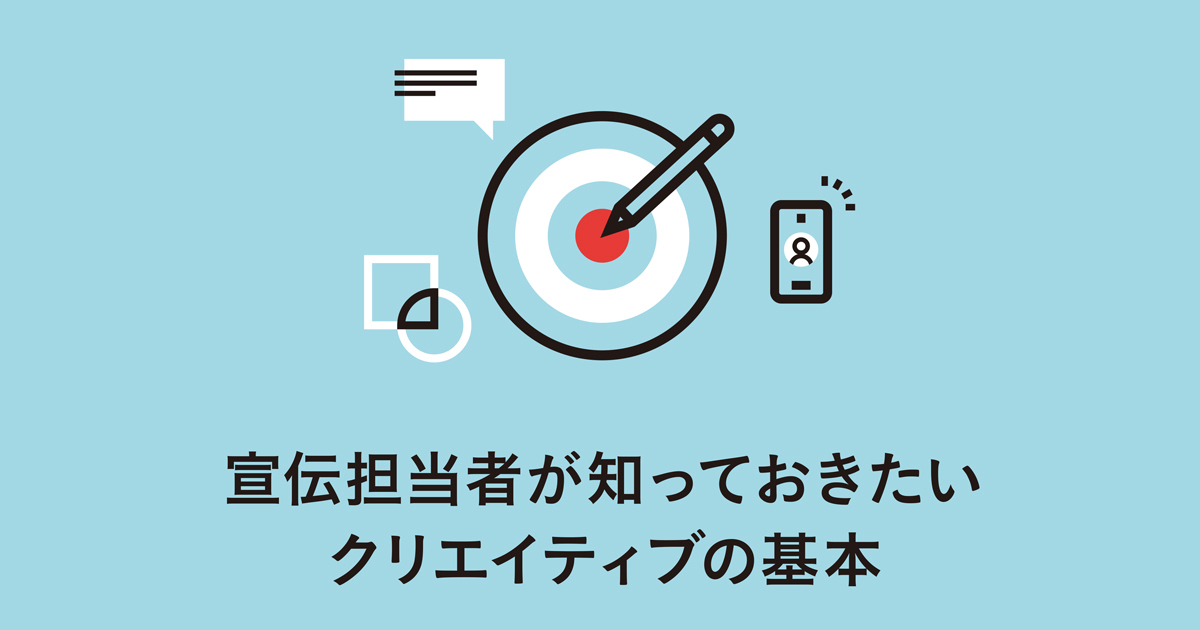今月のテーマ:動画広告におけるクリエイティブ
モバイルシフトが進んだ今、従来のテレビCMの映像とは異なる動画コンテンツの見せ方が必要になってきています。そこで、スマートフォンという接触環境において、ユーザーの心を引き付ける動画広告ならではのクリエイティブについて、宣伝担当者が意識するべき心構えや取り組み方を中心に解説します。
- 動画の冒頭の5秒ないし3秒で、動画を目にした人が「共感」し、手を止めたくなるような仕掛けを盛り込む。
- Googleが動画導線設計の戦略として「HHH」を提唱しているように、制作する動画の目的や役割を明確にする。
- クリエイティブ制作とメディアのプランニングをセットで行うことで、視聴環境を想定し、効果を最大化させる。
「動画広告のクリエイティブ」では、ここがポイント!
Web上にはいま、動画が溢れかえっている
「やっぱりいまは、Web動画が一番効果が高そうだ。SNS上で話題になる動画クリエイティブが知りたい」。きっと、宣伝担当者の皆さまは、動画に対していろんな期待をしながら、このページをめくってくださっていることと思います。でも、そんな動画広告の話を詳しく始める前にひとつ、必ず意識していただきたい、そして動画のつくり手である私たちも必ず意識している基本をお伝えしたいと思います。
「それ、本当に動画じゃなきゃダメですか?」ということです。デジタル上でコミュニケーションを行うのであれば、とりあえず動画。そんな安易な発想でうまくいく時代は、とっくに終焉を迎えました(そもそもそんな時代あったのだろうか?という気さえします)。
SNS上で話題になっている広告に目を向けてみてください。そこには、動画以外にも、屋外広告や駅張り広告、新聞広告など、企業がデジタル上で発信したコンテンツに対して直接反応するだけでなく、紙でもイベントでも、おもしろいと思ったものを自分で写真や動画に撮ってSNSにどんどん投稿しているSNSユーザーの姿があるはずです。そして、その反応を見る限り、それらの広告も十分にエンゲージメント(シェアやいいね!など、生活者の能動的な反応を指します)効果を発揮していると言えます。
つまり、生活者からの注目を集めることを目的とするのであれば、動画でなくとも、手段はいくらでもあるのです。逆に言えば、意味もなく動画を制作すれば、ただでさえ動画で溢れたタイムラインのなかに埋もれていってしまう。そういった前提を考慮した上で、「動画が最適な手段なのだろうか?」と何度でも立ち返る姿勢が必要だと私たちは考えます。
それでは「Web上には動画が溢れかえっている」という共通認識を持ったうえで、今回のテーマである「スマホ画面」においてユーザーを惹きつける動画広告について、一緒に考えていきたいと思います。
デジタル上において欠かせないのは双方向のコミュニケーション
はじめに、スマホで見る動画とは何を指すのか定義するところから始めたいと思いますが、これは当然Web動画を意味します。さらに、昨今の生活者の視聴環境を踏まえれば、その動画を見る環境はYouTubeやFacebook、Twitter、Instagramなどのソーシャルメディア上を想定しているかと思いますので本稿では、これを前提に説明していきます。
そこでまず、このWeb動画を始めとしたデジタルの動画クリエイティブがテレビCMなどと異なる大きな特徴ですが、第一に、見る人の声やリアクションがあって初めてコミュニケーションが完成するということが挙げられると思います。つくって配信して終わりではなく、動画を見た人が起こすリアクションも含めた設計が大切になるのです。
ハッピーな気持ちになってほしいのか、賛否両論の議論を巻き起こしたいのか、それとも商品の機能に膝を打ってほしいのか。ブランドのファンである人、これからファンになってほしい人と、動画を通じてどんな対話をしていくかまで、Web動画では考えることが求められます。
生活者同士が当たり前のようにSNSでコミュニケーションを取るいまの時代では、生活者との双方向のコミュニケーション、ひいては「共感」は重要なファクターであり、企業やブランドへの好意形成や購買意欲を醸成することにおいてもこの考えが欠かせないのです。
ここで、生活者との双方向のコミュニケーションを前提に動画をつくる際、覚えておいていただきたいこととして「共創の意識」をお伝えしたいと思います。これは、生活者のリアクションがあって完成する動画である=生活者もつくり手の一員を担うことを意味しますが、同時につくり手も生活者の一員であることを指します。
企業が言いたいことを一方的に押し付けないよう意識しながら、ブランドの姿勢や想いを動画に落とし込んでいけば、生活者は共感のもとでリアクションし、新たなコミュニケーションが生まれていきます。さらに、動画に出演した人がその動画をSNS上でシェアし、拡散する可能性がある。
彼らを巻き込むことで、そのフォロワーや彼らを評価している人たちへとコミュニケーションが波及していきます。広告主や制作会社だけでなく、多くの人との共創を意識することで、そのコミュニケーションがどう巻き起こっていくか変化させることができます。
動画の役割によって表現するべき内容は異なる
Googleが提唱した「HHH」と呼ばれる動画導線設計の戦略をご存知でしょうか。動画には、「HERO」「HUB」「HELP」と3種類が必要で、それぞれの役割を使い分けることがコミュニケーションの鍵になると説いた戦略です。
まず、動画をつくりたいと考えたとき、多くの人が思い浮かべるのは「HERO」動画です。たとえばAIG JAPANの「ALL BLACKSが東京に出現? #TackleTheRisk #AllBlacks」やNIKEの「Breaking2」といったようなものが有名です。どういった人が見るかに関わらず、感情に訴えかけることでより多くの人との接点を持つことを目的としており、認知を広め、潜在顧客を顧客にしていくため、間口を広げる役割を担います。
続く「HUB」動画は、「HERO」動画で惹きつけた生活者の「もう少し知りたい」「もっと見たい」というニーズに応えるための動画です。YouTubeでのチャンネル登録やFacebookページへのいいね!など、継続的なエンゲージメントへと促す役割を担っています。
そして最後に「HELP」動画。これはすでに商品を購入している人へ向けた使い方のレクチャーや、具体的に商品購入を検討している人へ向けた私用レビューなど、商品に関するある程度詳細な情報を伝える動画です。顧客の定着、企業やブランドをもっと好きになってもらうことを目的に実施します …