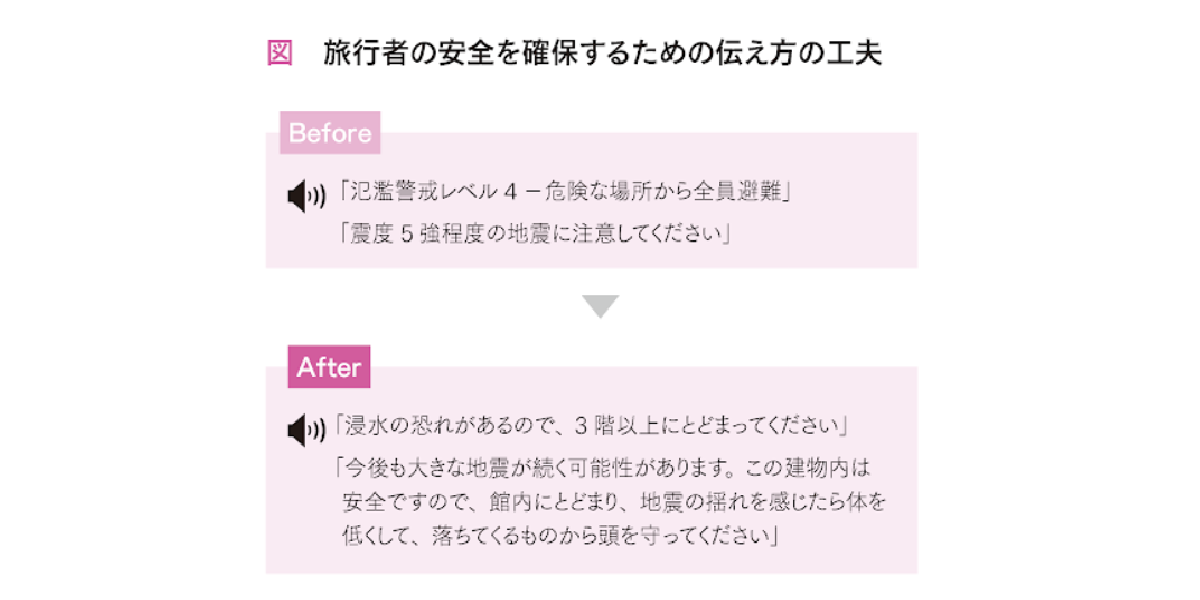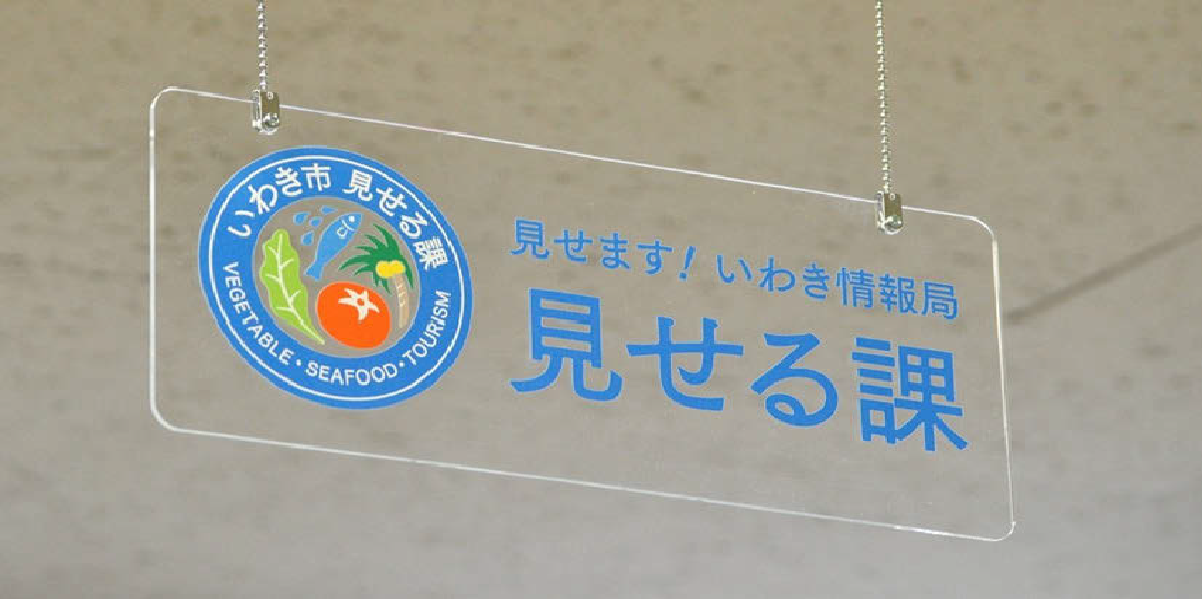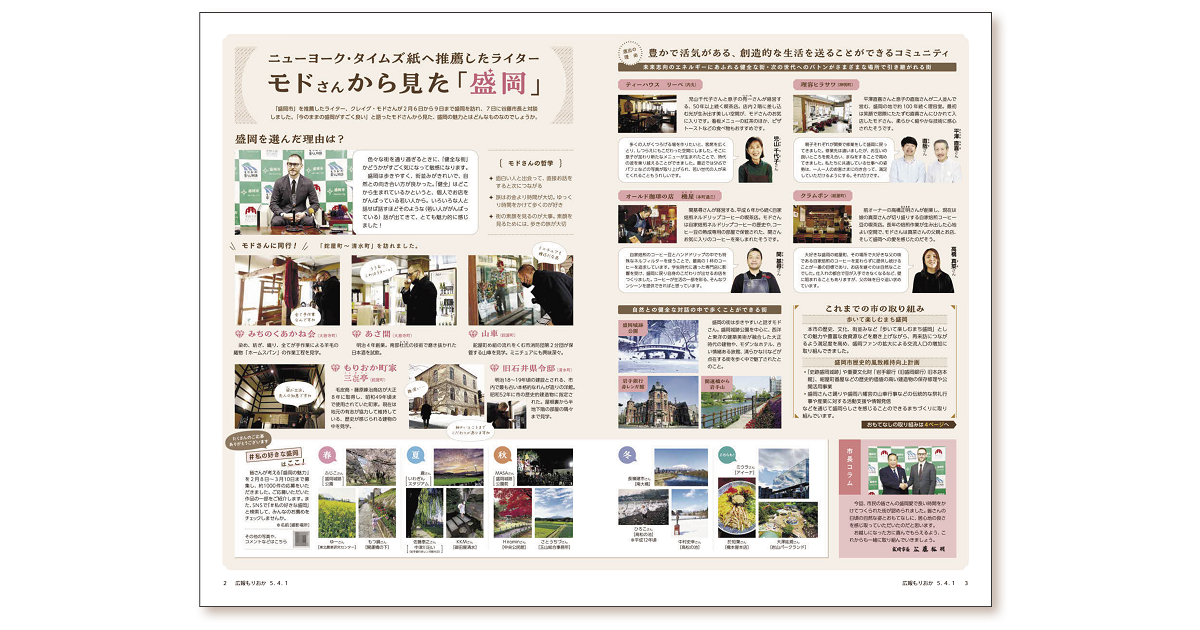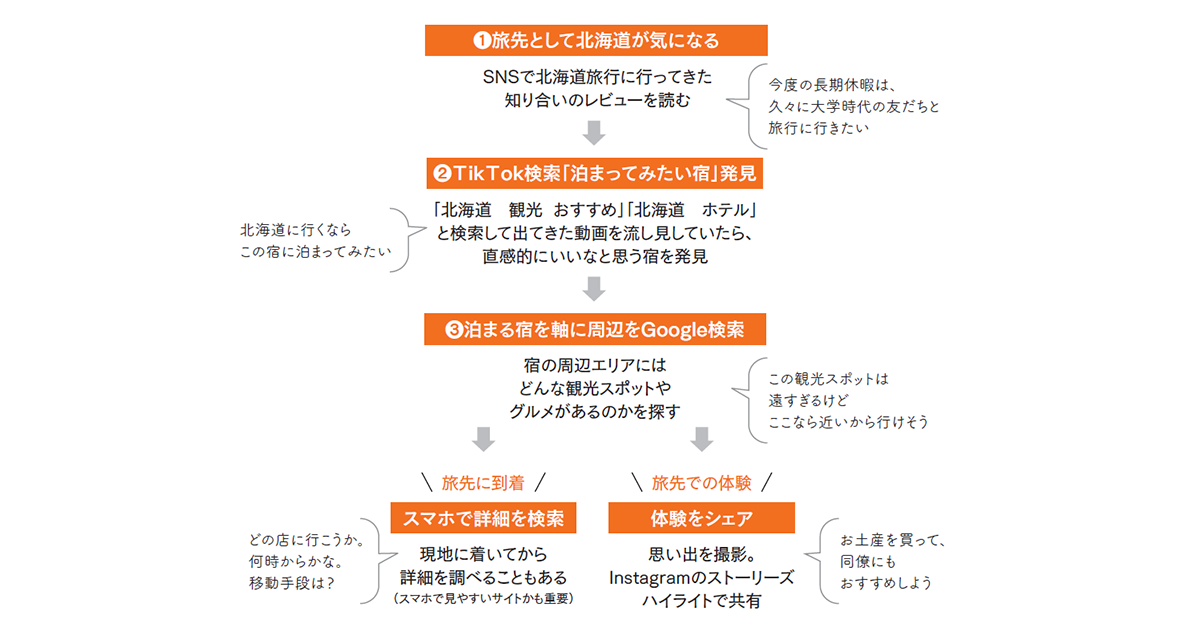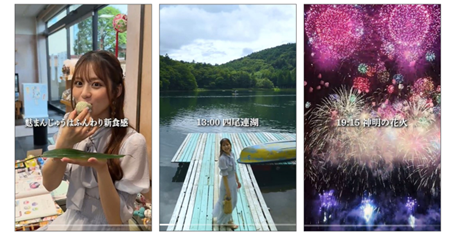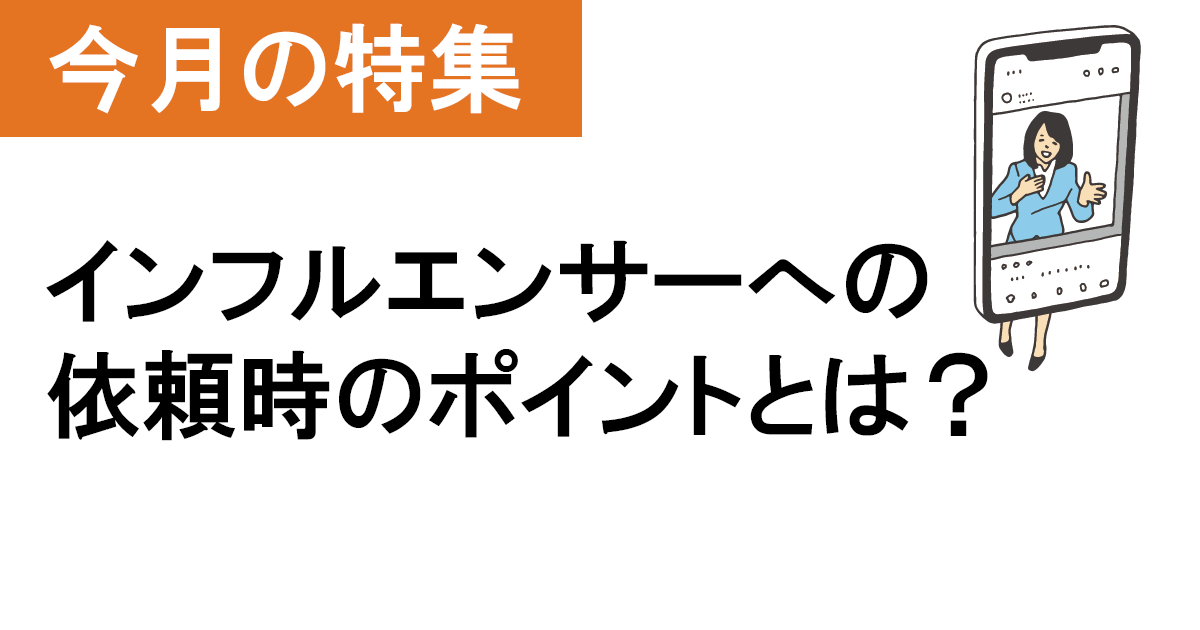ドラマが放送される以前から、岡崎市では長年、“徳川家康公生誕の地”という歴史を観光PRの軸として活用してきた。しかし、“徳川家康公のゆかりの地”というと、徳川家康が生涯の内で長い時間を過ごしたとされる静岡県などをイメージする人も多く、岡崎市が生誕の地であるという認知度は高くはなかったという。以前から抱えていたこの課題を解決し、人々に岡崎市と徳川家康のつながりを知ってもらうためにも、『どうする家康』の放送は好機だった。
「大河ドラマ館」を軸としたPR
2021年1月に『どうする家康』の放送が発表されると、岡崎市では3カ月後の4月に急遽、『どうする家康』を起点としたPRを実施する組織、「どうする家康」活用推進室を設立。当初は、専任職員2名、兼務が7名という体制で活動していたが、翌年2022年4月には専任職員5名、民間からの出向職員1名の「どうする家康」活用推進課に昇格。現在は7名体制となっている。「どうする家康」活用推進課が行う観光PR施策における誘客の要となっているのが、2023年1月21日に開館した「どうする家康岡崎大河ドラマ館」だ。『どうする家康』の世界観を楽しめるほか、徳川家康をはじめ、その周辺で活躍した三河武士に関する資料などの展示を見ることができる。
大河ドラマ館の存在について、「どうする家康」活用推進課で副課長を務める三原裕之氏は、「誘客をするにしても、“目指してもらう場所”がなければ、ファンの方が自発的に訪れてくださるのを待つばかりになってしまいます。ランドマーク的な存在があるからこそ、市としても大河ドラマ館を中心とした施策を能動的に用意することができる。そのため、大河ドラマ館は、一連のPR施策の要となる、重要なものです」と話す。
一度訪れて終わりではなく、何度も岡崎市に足を運んでほしいとの思いから、大河ドラマ館ではリピートしたくなる仕掛けも用意。年間パスポートを販売しているほか、来場者に特典として配布している「来館記念証」は、印字する武将の印を月替わりで変更。さらに、月に1日、徳川家康にゆかりのある日などに、松本潤のメンバーカラーである紫色の「特別来館記念証」を配布することで、コレクターの“通って集めたい”という気持ちを醸成。8月29日時点で大河ドラマ館への来場者数は35万人を突破しているという。

「どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」と「来館記念証」。来館記念証は月ごとに印字される武将の印が変わるほか、月に1日、紫色の「特別来館記念証」が配布される。

ファンも参画できるSNS施策
「どうする家康」活用推進課では、SNSを活用したファンとのコミュニケーションも重視。X(旧Twitter)では、「【公式】岡崎でどうする家康...