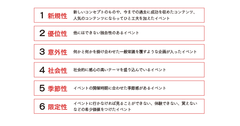2025年の大阪・関西万博でも「SDGs達成への貢献」がテーマになるなど、環境への配慮が求められているイベント業界。日本では、イベント運営とサステナビリティの両立はどこまで進んでいるのか。その現状を、サステナブルイベント協議会のメンバー企業である博報堂プロダクツのイベント・スペースプロモーション事業本部長 長田芳曉氏に話を聞いた。
国連によって2030年までの達成が掲げられている持続可能な開発目標「SDGs」。
その達成に向け、すべての企業にサステナブルな経済活動が求められている。これはイベント領域においても、同様だ。
世界観を表現するために制作される大道具や什器の廃棄、搬入や輸送時に発生するCO₂、多様性に配慮した運営など、イベントの実施もSDGs達成に向けた取り組みとの両立が必要不可欠になっている。
そこで2023年10月に発足したのが「サステナブルイベント協議会」。イベント・スペース制作の部署を持つ5社(丹青社、電通ライブ、乃村工藝社、博報堂プロダクツ、ムラヤマ)が連携し、イベント業界全体のサステナビリティ促進へ向けた活動を行っていくものだ。
今回、同協議会に参画している博報堂プロダクツのイベント・スペースプロモーション事業本部長長田芳曉氏に話を聞いた。「2025年の開催を控える大阪・関西万博で『SDGs達成への貢献』が掲げられるなど、確実にイベント業界の空気が変わってきているのを感じます。しかし、そういったサステナブルな視点を実際にイベント設計に組み込んでいる企業はまだ多くはありません。商品の製造や企業活動においては、サプライチェーン全体でのサステナブルな調達を目指すといったフェーズになってきていますが、それに比べるとイベント業界のサステナビリティ意識は発展途上だといえるでしょう」(長田氏)。


サステナブルイベント協議会の活動第1弾として開催された「サステナブル・イベントスタジオ」。子どもたちが「イベントデザイナー」としてサステナブルなイベントブースをつくる体験を提供することで、子どもや保護者の参加を通じてイベントに訪れる一般生活者のリテラシー向上を目指した。
環境配慮の必要性 理解する企業が増加
しかし、2~3年前に比べるとサステナブルな提案に対して、企業の反応は好感触になってきています、と長田氏は続ける。
博報堂プロダクツでは、イベント主催企業からの要求に対して、+αでサステナブルな提案を行うようにしている。2~3年前はそういった提案に対して全く反応がない企業が多かったが、現在は逆にその必要性を理解している企業の担当者がほとんどなのだという。