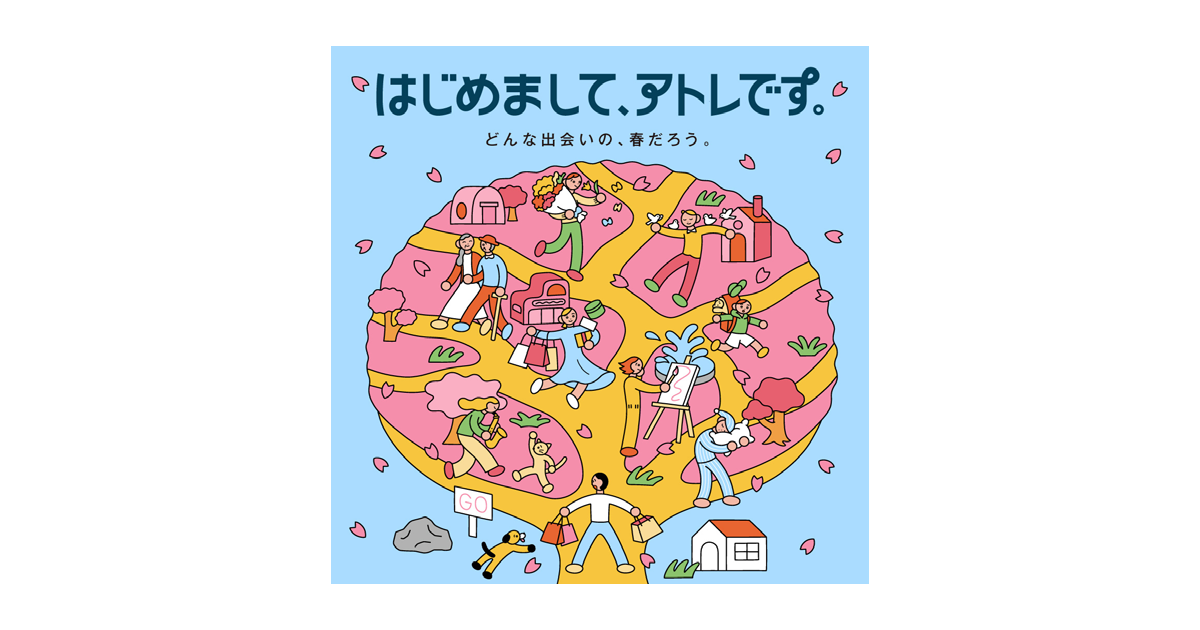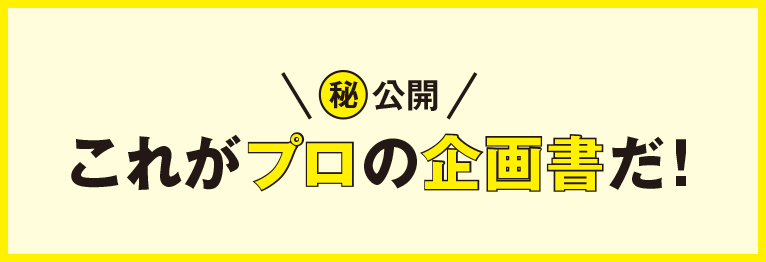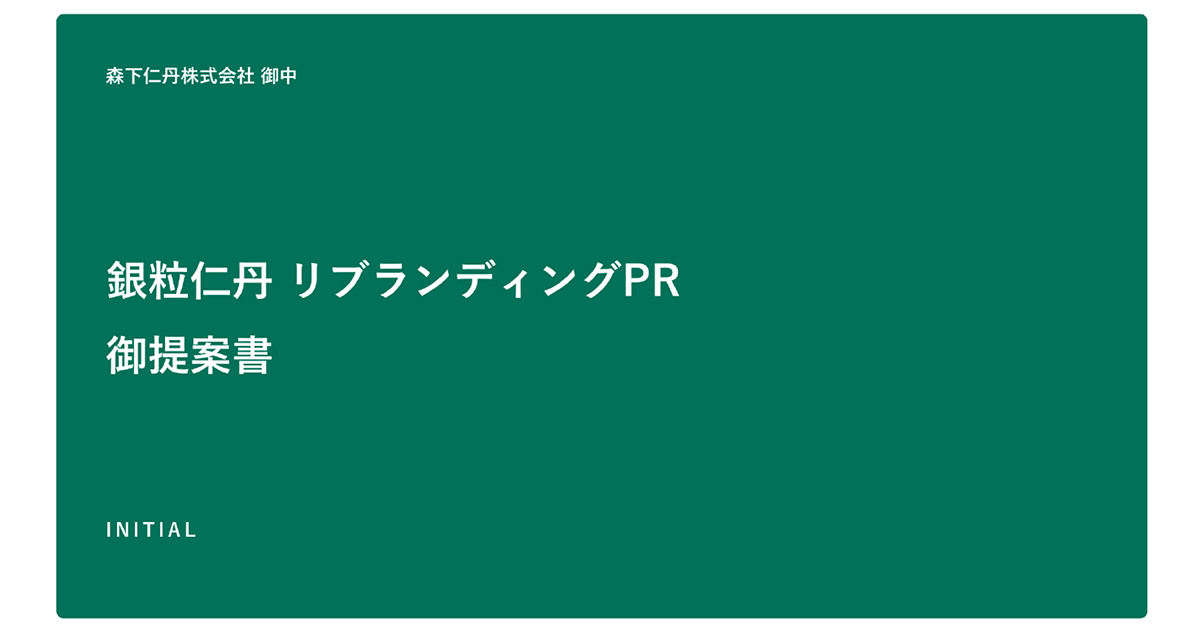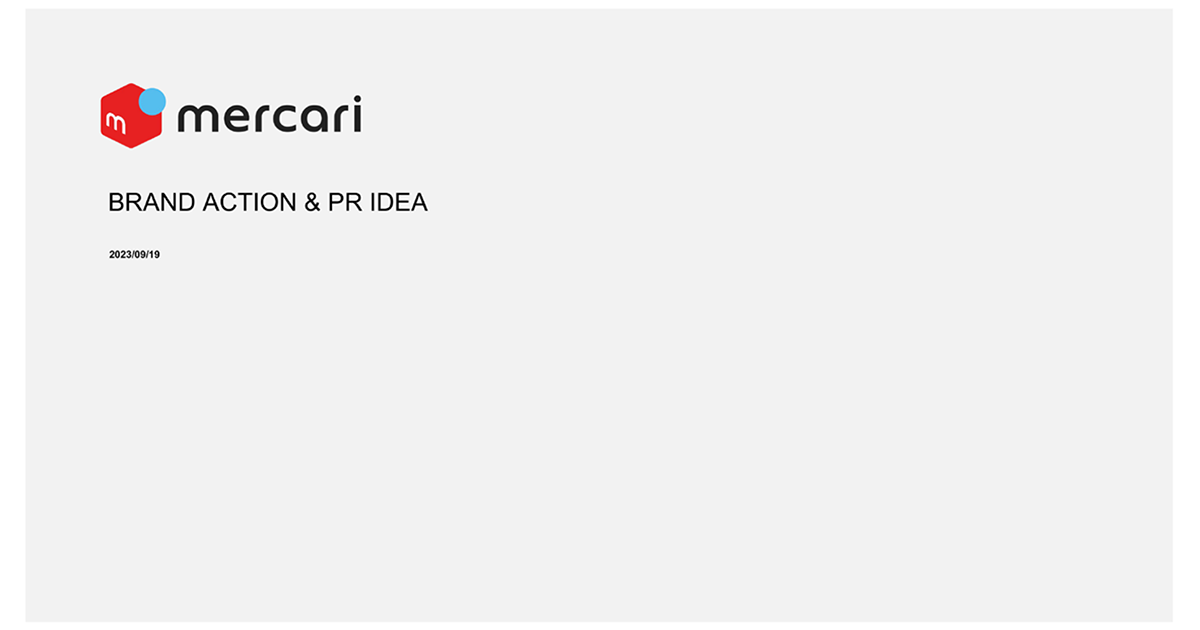2016年1月に創業30周年を迎えたテレビショッピング業界の雄、ジャパネットたかた。長崎県佐世保のカメラ販売店から売上高1500億円規模まで発展させた、創業者の髙田明氏は2015年に経営から退き、現在は息子の旭人氏が辣腕を振るう。テレビ出演はしない、顧客の声を聞ける場として店舗を持つなど、新しい経営に注目が集まる。

ジャパネットホールディングス 代表取締役 社長
髙田 旭人氏(たかた・あきと)
1979年、ジャパネットたかた創業者である明氏の長男として誕生。東京大学を卒業後、野村證券に入社。2004年、ジャパネットたかた社長室室長。販売推進統括本部長、商品開発推進本部長などを歴任。2015年1月から現職。
―ジャパネットたかたの「現場力」とは?
「現場」が何を指すのかによって現場力の定義も変わってきますね。創業者である父は番組に出演していましたので、現場というとスタジオでした。つまり現場力とは、そこでいかに商品の魅力を表現し、お客さまに伝えるかだったんです。
しかし私はテレビショッピングには出演しませんし、現在は2500人の社員がグループ8社で働いていますから、スタジオも含めて事業活動を行うすべてを「現場」と捉えています。
それぞれの現場に経営者や役員が常にいるわけではありませんが、日々、課題に直面したり、何らかの判断を迫られたりする事態が発生します。そのとき、現場の人たちがどれだけ経営層と同じ目線、方向性で判断ができるか、それが現場力だと思います。
現場力は一人ひとりの力に依存し、個の力量を高めることが重要です。個別の課題に対して指導するのではなく、根っこにある本質的な考え方を現場のメンバーと共有するように努めています。
当社では1日に2万以上のお電話をいただきます。つまり、お客さまとの1対1のコミュニケーションが1日2万件以上あるのです。テレビをご覧になって、お電話をかけてきたお客さまの気持ちに応えようと、トークスクリプトをどれだけ書き連ねても、すべてに対応することは不可能です。そのため表層的なマニュアルではなく、仕事の基盤となる土台を社員一人ひとりが持つことが大切だと思っています。

撮影に使われるスタジオ。テレビショッピングに出演していた創業者である父・髙田明氏と違い、旭人氏が出演することはなく、2人にとっての「現場力」は異なる。
―その土台づくりはどのようにして行っているのですか。
包み隠さず、何でもオープンに話すようにしています。会社には売上高や純利益など、さまざまな指標がありますが、簡単に言えば、どのような部分に投資するべきかという判断の目線が合うようになってほしいと考えています。
例えば、社用車が古くなったとします。最後まで大切に乗ろうという姿勢も確かに大切ですが、ボロボロのクルマであることによるデメリットも当然あります。その際、「買い換えよう」と声を上げられるか。もちろん何でも買っていいわけではありませんが、会社にとって必要な購買であれば反対はしません。要するにバランスの問題なのです。
社員には折に触れて「僕ならばこう考える」という話をして、判断の目線を知ってもらえるように努めています。最近はその感覚が徐々に共有できはじめたと感じています。
―ということは、社員との対話の機会も多いんですね。
そうなるように意識しています。当社では毎月 …