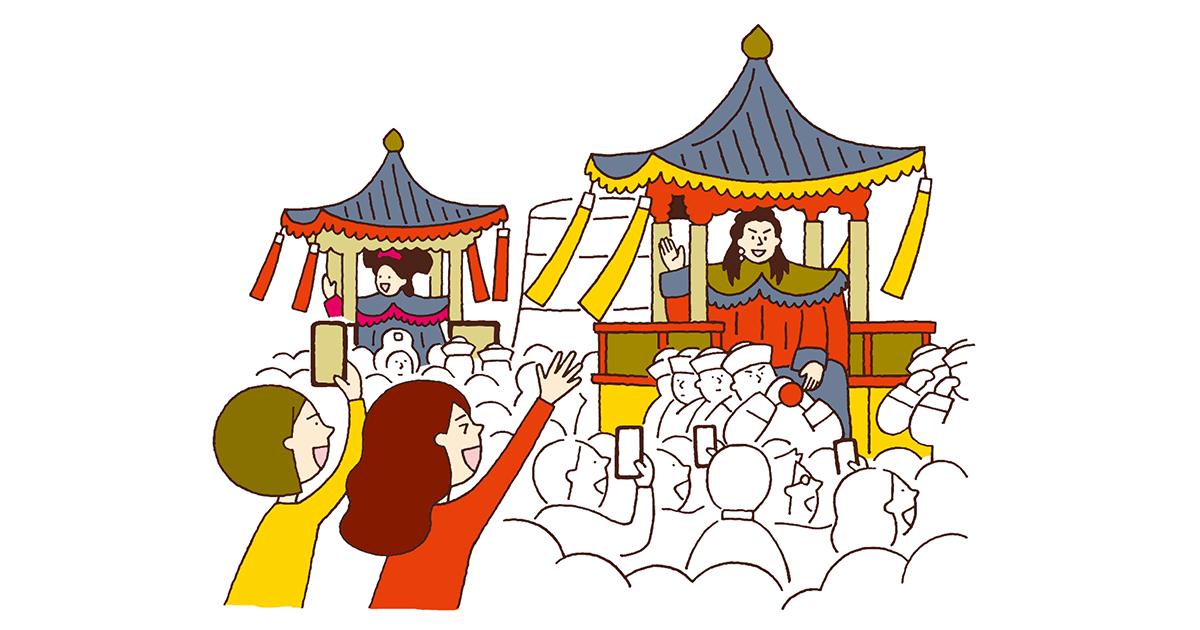「天神ロフト」「東急ハンズ」といった、福岡都心部にひしめく大手競合と激しい競争を繰り広げる地元の中小雑貨店、インキューブ西鉄。同社の特徴は“仕入れ販売員制度”によって、店舗のスタッフの力を最大限引き出した魅力的な店頭づくり。昨今では、大分・長崎・東京など福岡県外にも出店を進め、全国展開を目指している。

インキューブ西鉄 代表取締役 石川たかね(いしかわ・たかね)氏
1967年東京生まれ。大学進学を機に福岡へ。1991年西日本鉄道に入社、主に駅ビルや商業施設の開発に携わる。商業施設の館長などを歴任し、2014年6月現職に着任。現在13店舗を展開する「雑貨館 インキューブ」は、今後も年間1店舗~3店舗をめどに出店していく計画。急激に拡大している時期だからこそ人と組織の結びつきを強化し、コミュニケーションを重視する経営を行う。
―貴社にとっての現場力とは?
旗艦店の雑貨館インキューブ天神店は、約1250坪の店舗で16万アイテムほどの雑貨を扱っています。現在、出店の核となっている250坪タイプの店舗でも、取扱商品は約3万アイテムにのぼります。こうした大型の雑貨店では、商品の品揃えによる競合との差別化は難しい状況にあります。
では、どこで差別化を図るか。インキューブでは、やはりお客さまにとって魅力的な売り場だと考えています。
大型雑貨チェーンでは、本部が各支店の仕入れを一括するのが一般的です。しかしインキューブでは、商品の品揃えから売り場づくりまで、すべて各店舗のスタッフの力量に任せる“仕入れ販売員制度”を採用しています。地域のお客さまのことを最も理解しているのは各店のスタッフですから、地域に根差したきめ細かな店づくりができます。また、責任のある仕事を任されることで、スタッフもやりがいを持って売り場づくりに励むことができているようです。
魅力的な売り場を作るうえで重視しているのが、ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)です。これは「視覚的演出効果」とも言われますが、ひとつのコンセプトに基づき、品揃えや店舗デザイン、陳列方法などを連動させることです。
実際に売り場ではVMD什器を配置し、店舗スタッフ自身が季節感の演出やわかりやすいPOPを制作するなどの工夫を行っています。こうしたスタッフの実行力がインキューブの強みであり、現場力となっています。
―すべて任せるとなると、現場スタッフのモチベーションが大事になりますね。
スタッフの考える力や対応能力を引き出すために“小さなリーダー”をたくさん作るようにしています。小さなリーダーとは、店長とは別に、各店舗の小さな改善を行うリーダーです。小さな改善を積み重ねることで、結果的に総体としての改善につながり、よりよい売り場が作られるのだと考えています。
インキューブでは、複数の店舗を1人のマネージャーが統括しています。就任以前より実施していたマネージャーを集めた会議体を、より活性化させました。会議ではインキューブの課題について非常に活発な討議を行っています。
就任直後は、経営サイドから議題を出していましたが、次第にマネージャーが自分たちで議題を出して、自発的に会議を設けるという流れができました。そうなると、今度は店舗スタッフも店舗改善会議や支店ミーティングなどでも自分たちで現場の課題を考え解決していこうという体制ができました。これが小さなリーダーによる改善です。こうした風通しの良い環境がスタッフのモチベーションを上げているという手応えを感じています。
―自分たちの意見が採用されると、スタッフはやり甲斐を感じるでしょうね。
各支店の中だけで悩んでいたのでは、なかなか解決には結びつきません。会議にかけてたくさんの頭で考える方が、思いもよらないアイデアが出てきます。また、みんなで悩みを共有することで共感や助け合いの精神が生まれ、支店同士の絆も強くなってきました。現場力も磨かれていると思います。
―スタッフのレベルやスキルもアップしていきそうです。
スタッフのスキルアップのために、定期的なVMD研修やVMDコンテストを実施しています。VMD研修はプロの講師を招き、講義のほかに什器を使った実習を行うなど、実践に結びつく内容になっています。毎月開く支店長会議の際に、要望があればVMDミニ講座も実施しています。
VMDコンテストはシーズンごとに年4回開催しています。応募作品は常時共有フォルダで閲覧できるようにしてあり、募集期間中であれば、一度出品した作品に何度でも改良を加えられるルールになっていますので、ほかの人が出品した作品を見てどんどん改良を加える人もいます。そうして切磋琢磨したレベルの高い作品が応募されます。
また、コンテストに参加していないスタッフも、自分がいいと思った展示の仕方やPOPのアイデアをどんどん店づくりに取り入れていきます。インキューブのVMDコンテストは、単なる表彰では終わらせません。

同社の特徴は、商品の品揃えから売り場づくりまで、各店舗のスタッフに一任する“仕入れ販売員制度”だ。
―石川社長が店舗に足を運ぶ際、どのような点を注意して見られますか。
業績に悩む店舗やウィークポイントを抱える店舗には集中的に行くようにしていますが、平均すると各店舗に年3回ぐらいは足を運んでいます。店舗では売り場全体の雰囲気やスタッフの表情を見ます。私は全国の支店を回っているので、各店舗の良かった点を伝えることができます。それが自分の強みだと思っています。
商品に関してはすべて店舗スタッフに任せていますので …