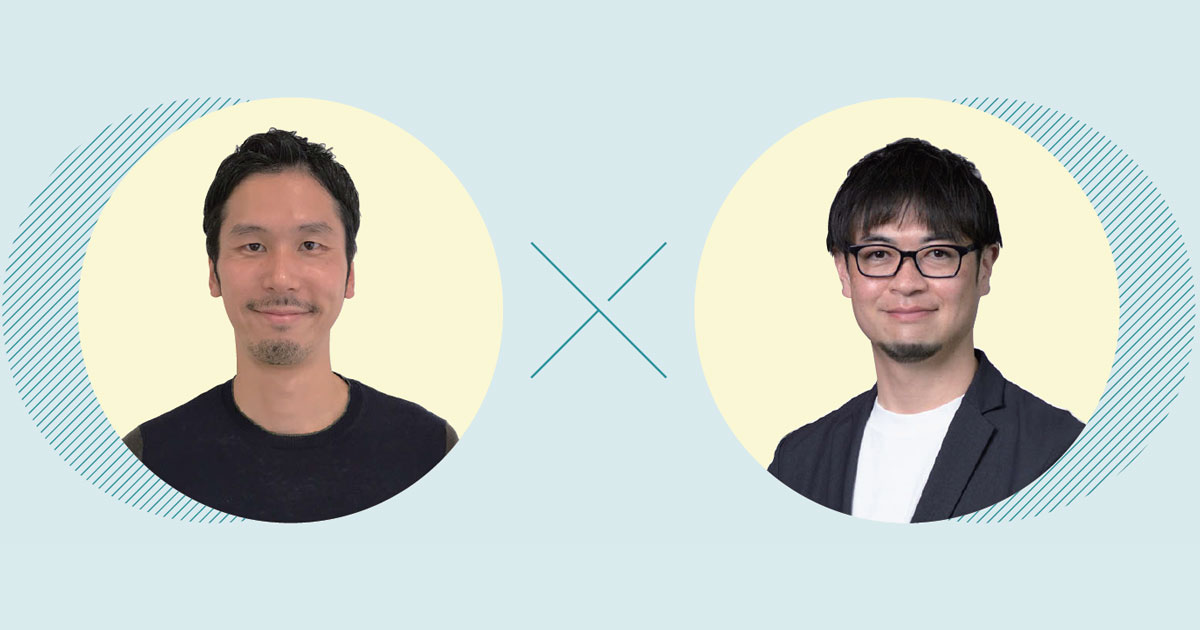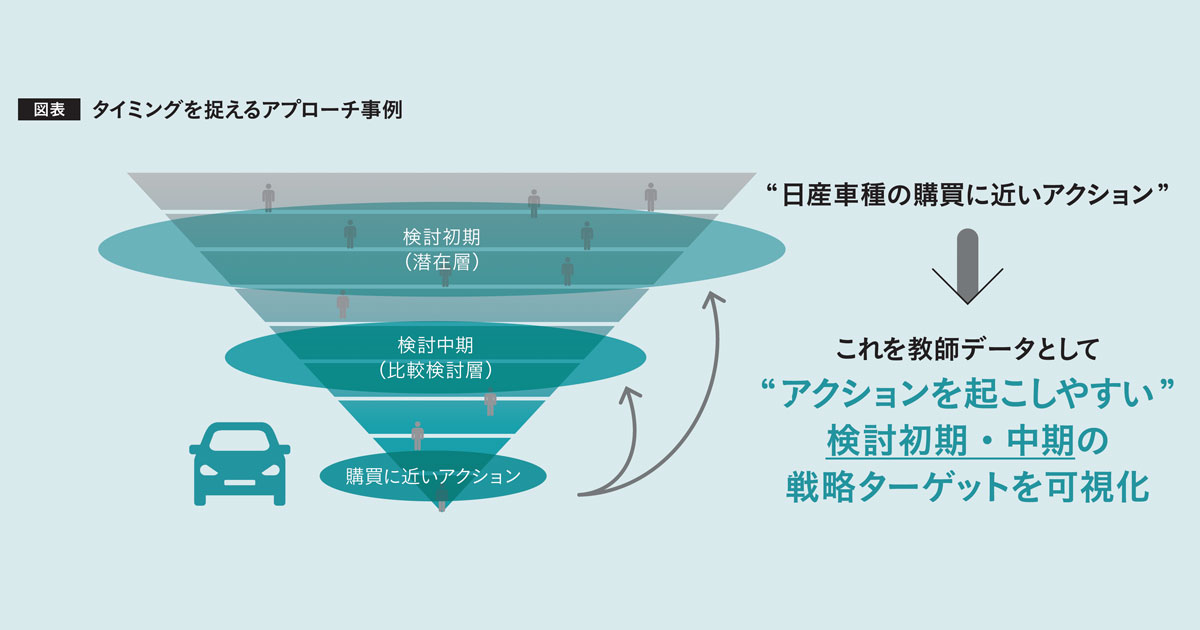世界中で次々と新しいモノが生み出され、機能だけで画期的と思ってもらえるような商品が誕生しづらい現在、単に効率よく商品を製造するだけでは、顧客に満足な体験を提供し続けることが難しくなりつつある。このような時代において、カシオ計算機とチュチュアンナの2社が、マーケティングDXをどのようにとらえ、どのような考えのもと実践しているのかを語り合う。

チュチュアンナ
デジタルマーケティング部 マネジャー
西岡和也氏

カシオ計算機
執行役員 デジタル統轄部長
石附洋徳氏
いまメーカーが直面しているマーケティングDXの必要性とは
──各社では「マーケティングDX」をどのようにとらえていますか?
石附:カシオ計算機は時計、電卓、電子辞書、電子楽器などを扱う電機メーカーです。これまでの製造業は、世の中のニーズに合わせた製品を開発し、できる限り短いリードタイムで需要に対して適切に供給をする、というビジネスモデルが前提でした。しかし、中国をはじめ世界中で技術が発達し、開発や生産の高度化が進んだことで、リードタイムだけでは戦えない時代になっています。このような状況で、世の中の需要に応えているだけでは不十分。
そこで、デジタルの力や、データの活用により、もっと能動的にユーザーを知ることで潜在的なニーズを探し、持続的にユーザーとつながりながら価値を提供し続けることが、これからの製造業には求められると感じます。また、当社の製品は先に挙げたように耐久品で、10年に一度くらいのスパンで購入される製品です。この長い期間、いかにユーザーとの関係性を続けられるかも、当社のような製品を扱うメーカーの課題です。
西岡:チュチュアンナは、インナー・靴下・ルームウェアなどを扱うブランド「チュチュアンナ(tutuanna)」を運営しており、製造小売業として、卸売・直営店・ECと多角的な販売チャネルを展開している点が特徴です。これまで当社は、店舗拡大で売上を伸ばしてきた実績があり、「良い商品をつくり、良い店舗で売る」というように、商品戦略や店舗戦略に力を入れていました。
しかし、コロナ禍で多くの小売が打撃を受ける結果に。単に良い立地の店舗を持っているだけでは、このような環境の変化に対応できないと痛感しました。そこで現在は、「つくる力」「売る力」に加え、「マーケティングの力」の向上を注力領域としており、そのためにデジタルを活用しています。石附さんのお話にもあったように、“お客さまとつながる”ためのデジタル活用は、私たちのような店舗を持つ企業も同様に重視している点です。「マーケティングDX」が指す領域は広いですが、私たちは“顧客戦略”の...