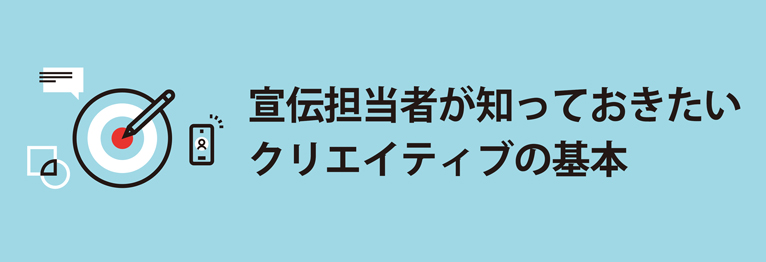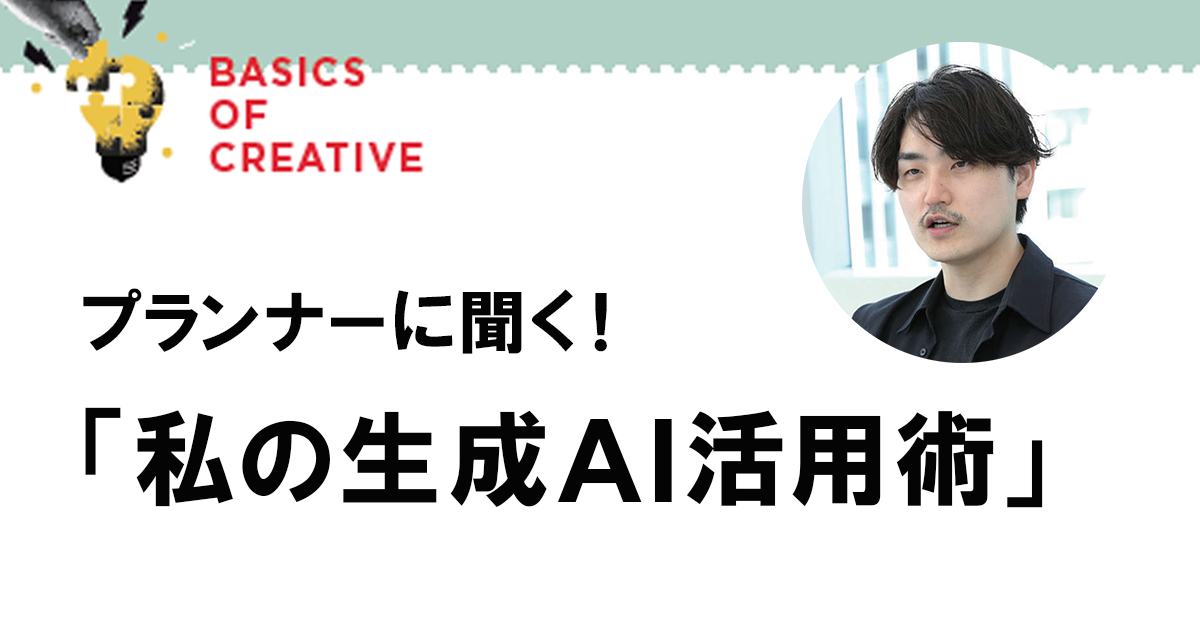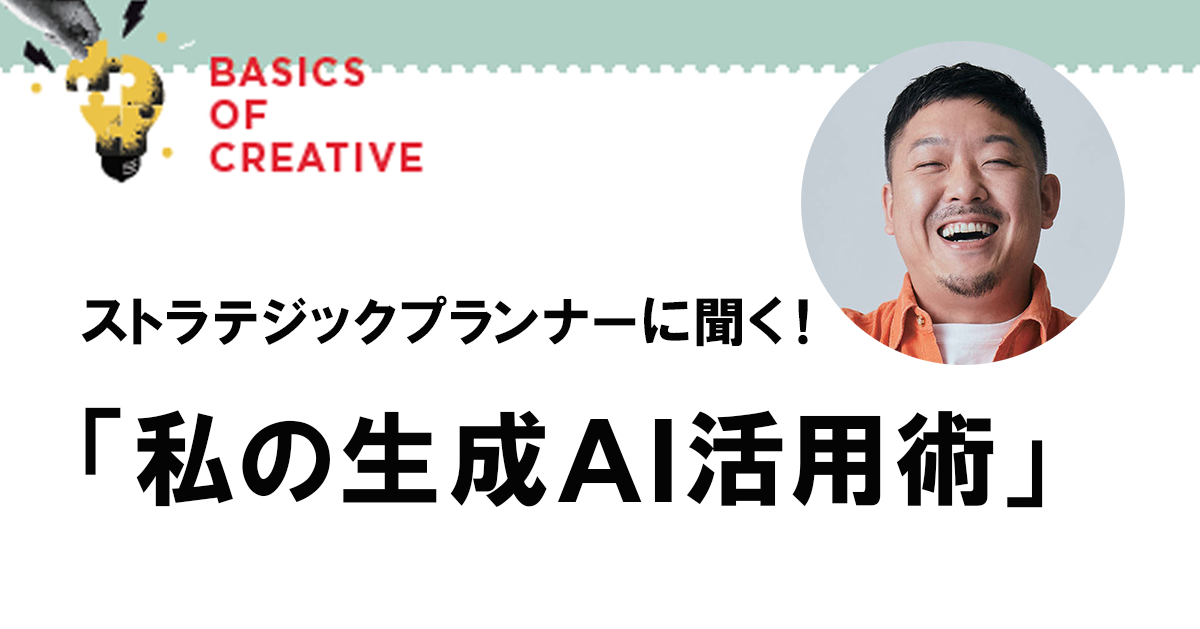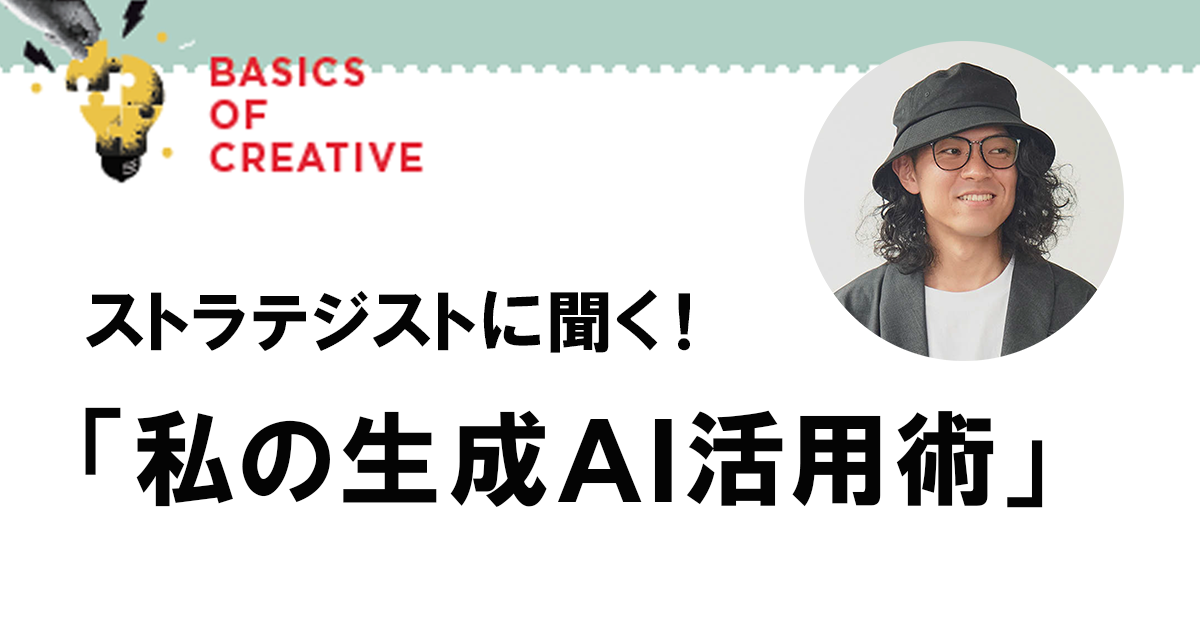深く・正しく「理解」した上で、自社の商品・サービスを選び取ってほしい―マーケターなら、当然そう願うもの。しかし、人間にとって「理解」するのは非常に労力を要し、できれば避けたいとすら思うものです。逆境の中、ターゲットの「理解」をどう得るか。脳科学の見地からヒントを探ります。

脳科学者、医学博士 中野信子氏
東京大学工学部卒業後、2004年東京大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程修了。2008年東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。2008~2010年まで、フランス原子力庁サクレー研究所で研究員として勤務。「情報プレゼンターとくダネ!」をはじめとし、テレビ番組のコメンテーターとしても活動中。フジテレビ「平成教育委員会2013!!ニッポンの頭脳決定戦SP」で優勝、「日本一優秀な頭脳の持ち主」の称号を得る。著書に『世界で通用する人がいつもやっていること』(アスコム)、『脳科学からみた「祈り」』(潮出版社)などがある。
脳科学でいう理解は、必ずしも購買行動に結びつくとは限りません。例えば「婚活」を例にとるとわかりやすいかもしれませんが、相手(=商品)を理解した上で、最終的に「いえ、結構です」となる可能性が低くないわけです。商品・サービスを消費者に選び取ってほしい企業の立場からすれば、理解してほしいとは、極端に言えば「都合の良い誤解をして(自社商品を選び取って)ほしい」ということなのではないでしょうか。科学の世界の理解とマーケティングにおける「理解」には、そうした違いがあります。
科学の領域では、「あそこに、まだら模様の何かがいる」というのが認知であり、その何かが「自分を襲う可能性がある危険な生物」「猛獣」「ヒョウ」と捉えることが理解です。その理解があって、「逃げる」「戦える人を呼んでくる」「武器を調達する」といった行動が喚起されるわけです。一方、マーケティングにおける「理解」の目的は購買行動を促すことにあるので、例えば「猛獣だけど美味しそう」「手なずけると役に立ちそう」「毛皮が高く売れそう」などと思わせることが重要です。そうした企業が望む「理解」を促すために、どのようなアプローチが効果的か。ここでは、それを考えてみたいと思います。
人間は「考えたくない」生き物
理解するためには、人は「考える」必要があります。大前提として認識しておかなければならないのは、人間の脳は「考えたくない」ものなのだということです。脳を使うには …