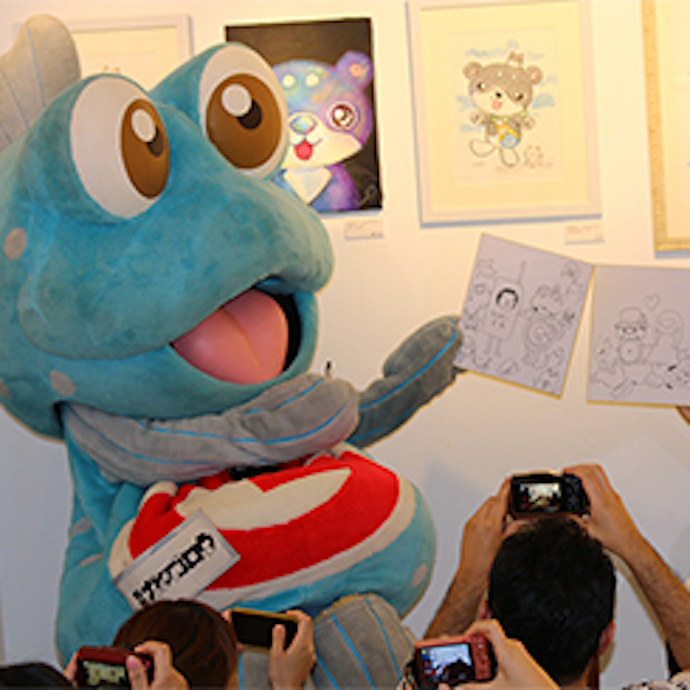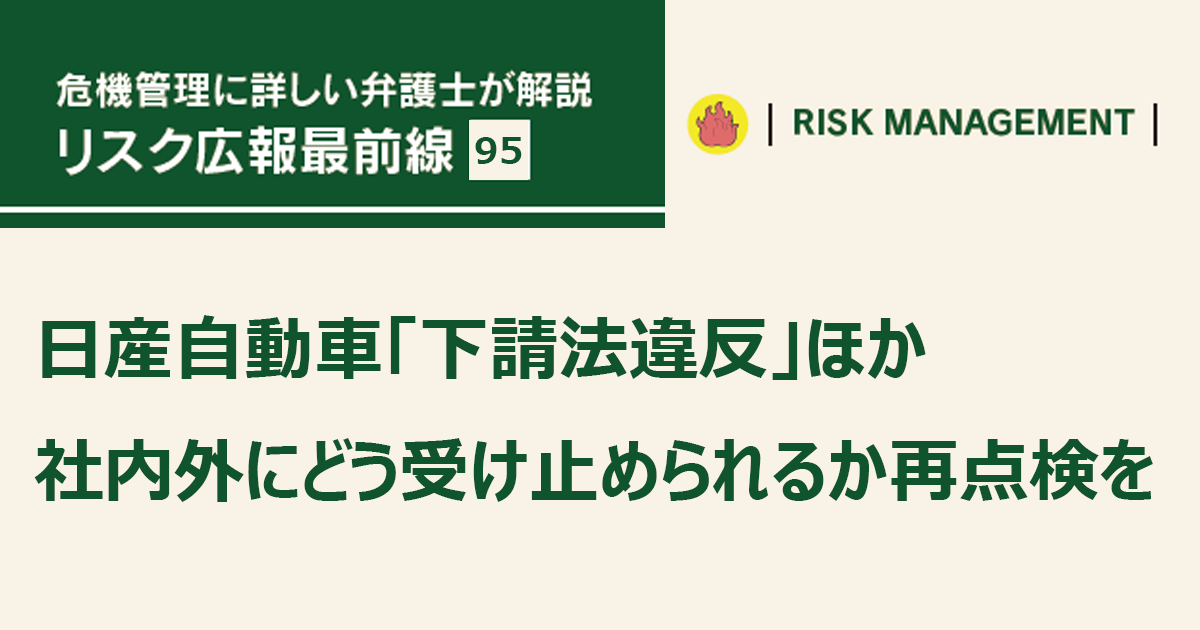プロモーションや地域振興など、キャラクターの活用目的は様々。企業や行政発でヒットコンテンツを生み出すポイントについて、キャラクタープロモーションの第一人者・野澤智行氏が解説します。

7月16日、志木市民会館パルシティで開催された「PUZZLE」でのGCB47の演奏。中央が石田洋介氏。
ご当地キャラが広く世間に注目されるようになったのは、ひこにゃん(滋賀県彦根市)が登場した10年前、2006年ごろからである。その後、インターネットや携帯電話・スマホの進化が追い風となり、せんとくん(2008年)、くまモン(2010年)、ふなっしー(2012年)などが次々と注目され、“会いに行ける身近な存在”“低予算で話題を獲得したいデフレエンタメの象徴” として受け入れられていった。
キャラ同士のネットワーク形成
ご当地キャラのブーム自体は2013年をピークに落ち着きを見せており、予算やスタッフの継続確保が厳しくなって出番が減ったキャラがいる一方、頑張り続けている中堅や個性派のキャラも多数存在する。彼らはブーム時のマスメディアやネットニュースへの露出数におごることなく、地道なイベント出演やSNS運営で獲得したスキルとノウハウを駆使し、地元ファミリーやファンに支えられ、他のキャラクターと助け合いながら、地域および立場を超えたユニークな市場を形成。共存共栄を果たしているのだ。
キャラ関係者同士のネットワークのひとつである「関東キャラ連盟」メンバーで結成されたのが「GCB47」だ。「すがもん」(豊島区巣鴨地蔵通り商店街)をはじめとしたキャラが実際に楽器を演奏するロックバンドで、シンガーソングライター・石田洋介氏(ボーカル・ギター)をバンドマスターに、カパル(ベース:埼玉県志木市)、戸越銀次郎(キーボード:品川区戸越銀座)、スパンキー(ギター:品川区)、ニャジロウ(ドラム:秋田市)などで構成される。名称は“ご当地キャラバンド・47都道府県”を意味しており、アックマ(ギター:北海道札幌市)など全国のキャラが楽器、ダンス、コーラスというような各々の得意分野で都度参加している。
視界や指の動きに制限のあるご当地キャラによる本格的かつ激しい演奏は生で見ると強烈なインパクトで …