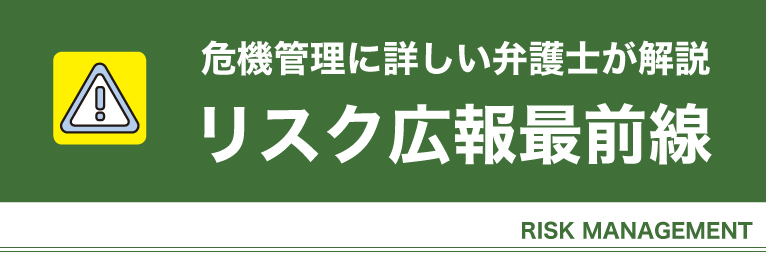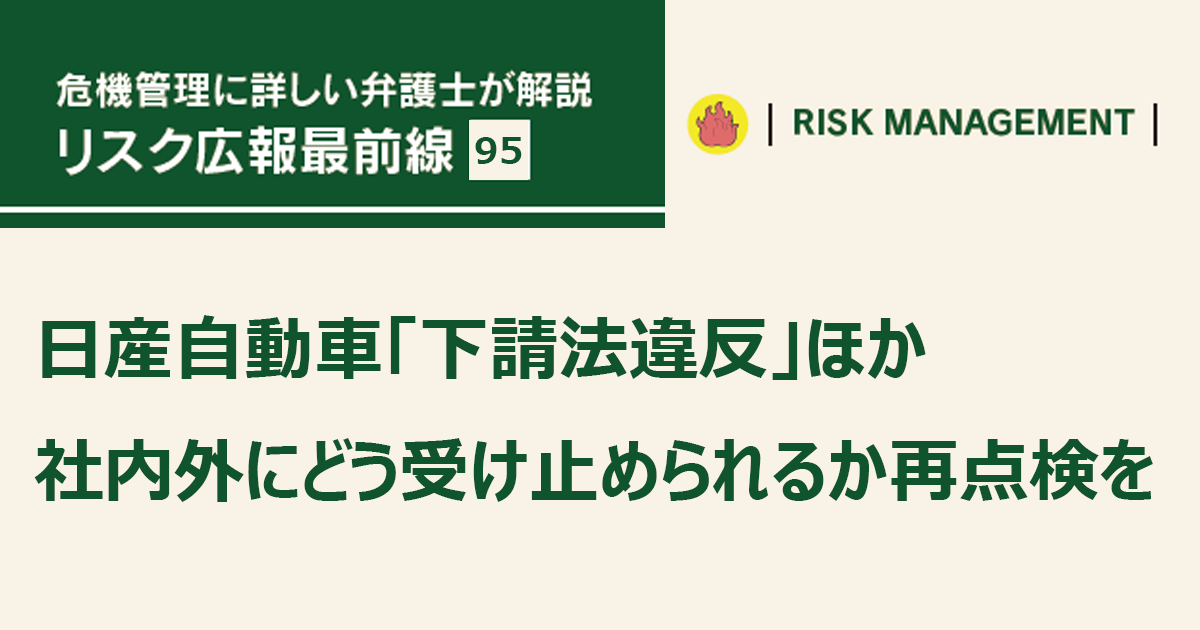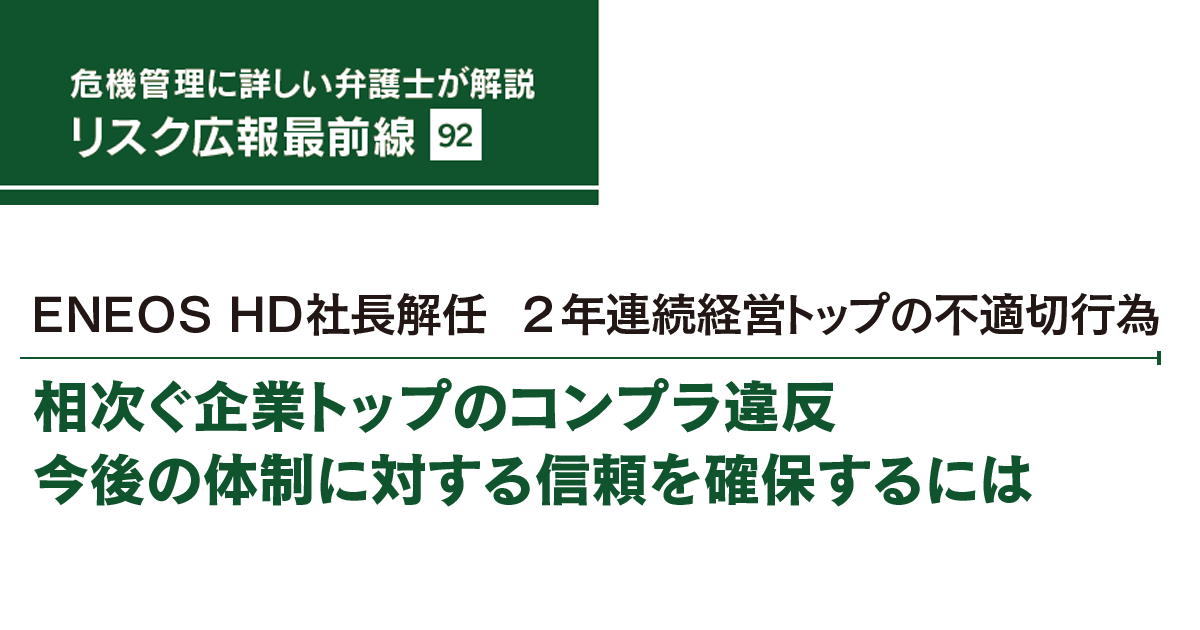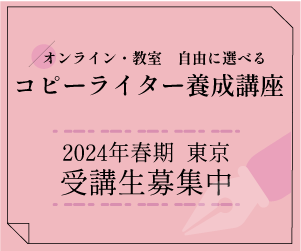アンリ・シャルパンティエ芦屋本店。創業の地でもある。
洋菓子の"アンリ・シャルパンティエ"で知られるアッシュ・セー・クレアシオン(兵庫県西宮市)の蟻田剛毅社長は創業者の長男。社長就任後の最初の仕事は、企業改革の推進だった。
業績低迷時に社長就任
父の蟻田尚邦(故人)が1969年に芦屋に開いた喫茶店が当社のルーツです。75年に神戸そごうから出店のお誘いをいただいたのをきっかけに、全国の百貨店へ販路を広げ、お陰さまで多くの方に愛される洋菓子ブランドに成長することができました。現在はアンリ・シャルパンティエのほか、シーキューブなどの複数のブランドがあります。
当初から父の後を継ぐと決めていたわけではありません。私は大学を卒業して広告会社に就職し、父は社長を退いて「アンリ」のブランドを管理する会社を立ち上げていました。しかし、社会人になってお菓子が大好きだと気づき、どうせなら好きなことを仕事にしたいと思うようになっていました。就職して10年後に、オーナーである父に入社したいとの意思を伝えました。
入社後しばらくの間、会社のことを知るために工場で働いたり、アルバイトと一緒に店先に立ったりしていましたが、当時の社長が退社の意思を明らかにしたことで後任として白羽の矢が立ち、社長就任が突然決まりました。当時は課長職でしたが一気に副社長に昇格し、前社長が退任するまでの1年間を過ごしました。この1年間は経営について学ぶために、本やメディアで知った社長に教えを乞いに行ったり、人気のケーキ屋さんを見て回ったりして知識を深め、1歩離れた位置から会社を見ていました。
ところが、当時の経営は行き詰まりとも言える状況になってきました。売上は数年のうちに大幅に下がり、地元を襲った阪神大震災が発生した1995年以来初となる赤字決算を計上したのです。オーナーである父はずっと前に経営から退いてきましたが、会社の危機を知り、再び経営会議に出るようになっていました。でも会議で檄を飛ばしたところで何かが変わるわけでもありません。

アンリ・シャルパンティエ創業のきっかけになった「クレープ・シュゼット」。グランマルニエで仕上げのフランベを行う際に青い炎がゆらめく。芦屋本店などで提供している。
経営陣だけが知らなかった
そもそも、経営が悪化したのは時代の変化について行けなかったからです。百貨店とともに現在のポジションを築いてきた会社だけに、他の販路の開拓など新しいことに目を向けようとしなかったのです。当時、洋菓子をめぐる販路は激変していました。デパ地下ブームが沈静化したのちコンビニデザートが台頭したり、ロールケーキやバームクーヘンなど単品を売りにした新業態の店がヒットしたりと、成功する企業の顔ぶれが急激に変わっていた頃です。
一方で社内はといえば、調子が悪くなればなるほど、「百貨店の販路をどうにかせねば」とますます内向きになっていました。当時は社内は混乱してアイデアも出ず、百貨店が限定商品を出したいと言えば、すべてお受けしているような状況。その結果、新商品が年間400種類も出ていたのです。流行りとなれば何でもつくっていました。「アンリはいろいろやってるけど、何がしたいのかわからない」――。そんな声がお客様アンケートなどから聞こえるようになっていました。
私も当事者の1人ではありましたが、副社長の期間に少し離れた位置から会社を見ることができたのは良かったと考えています。当時、現状を把握するために係長以上の役職者約200人とそれぞれ1時間ほど話す機会を持ちました。それで実感したのは、世間の風と経営陣の意識とのかい離でした。会社が置かれていた状況をよく把握していたのはむしろ現場だったのです。同業他社の幹部の方々も当社が置かれている状況をよく認識されていました。
そんな中で、私の中に怒りともやる気とも言える不思議な感情が湧きたっているのを感じました。私がここまでこれたのはアンリ・シャルパンティエのお陰です。それは父やお客さま、幹部をはじめとする社員のお陰でもあります。そんな素晴らしいブランドなのに、このまま終わってたまるか、と。この感情は、私が今まで経営に携わるモチベーションにもなっています。

2012年9月に実施した社員向けの経営方針発表会。同社の期末である9月に毎年実施している。
幹部が社内広報してくれた
社長に就任後、私が社員に向けて発信していることは、「父が創業したときの状況、つまり経営理念に戻ろう」ということに尽きます。私たちが実現したいこと、お菓子で人を喜ばせたい、または驚かせたいという思いがあって、「これでどうですか」と商品を通してお客さまに問うてみる。これが商売の原点のはずです。その一環として、当時250くらいあったラインナップを100程度に絞り込みました。
私たちは、100年も200年も続くものを「文化」と定義して、お菓子文化を築くことを理念に掲げています。このことは、何も新しい組織風土を社内に持ち込もうという話ではありません。古参の社員であれば、少し昔のことを思い出してもらえばいいのです。「原点を忘れてはいけない」ということは、朝礼でも会議でも、至るところで話すようにしています。
もうひとつ取り組んでいるのが数値管理の徹底です。これまでは「どんぶり勘定」の会社でしたが、経営理念を実現するためにはこれは避けて通れないと判断しました。事業部ごとに、ブランドごとに売上や利益を明確にするようにしています。もうオーナーはいませんから、自分たちの取り組みが成功したかどうかは数値で測るしかありません。役職者には「(部下に)ゴールのないマラソンをさせてはいけない」と言っています。
このことは、父が亡くなる1年ほど前に立ち上げた「経営改革プロジェクト」で決めたものです。外部コンサルタントと、生え抜きの幹部ら10人くらいのチームでした。
数値管理をめぐっては、社内から大きな抵抗がありました。これまで「イキイキと働く」といったアバウトな年間目標で動いていた会社ですから仕方のないことかもしれません。「良いものとは売れないものだ」とまで公言していた者もいたくらいです。
社長になると現場の声はなかなか耳に入らなくなるものです。社員からの不安の声が広報担当の耳にも入ってきたとも聞きました。会社が大きく変わる時期ですから、辞めた社員もかなりの数に上ります。それでも、仮に掛け声を緩めるようなことをしたら改革に向けて取り組んでいるメンバーを裏切ることになります。自分の中の小さな悩みとお客さまとの約束を天秤にかけるようなことはしてはならないと肝に銘じました。
こうした取り組みは道半ばですが、数字は何とか戻ってきました。売上は過去最高水準に回復し、利益は今年9月期、創業以来最高を見込んでいます。
数値管理の徹底は、私ひとりで進めるのは難しかったと思います。メンバーの幹部社員がその必要性をそれぞれ訴えてくれたから進みました。社内広報してくれたのだと思います。
これから取り組みたいことはたくさんあります。海外展開はそのひとつ。当社の原点でもあるカフェを東南アジアで手掛けたいと考えています。経済成長に伴って、お菓子のある少しぜいたくな時間を楽しみたいと考える人は増えるはずです。国内では、お菓子の持つ可能性をもっと掘り下げていきます。通販事業の強化のほか、企業がイベントのお土産として購入するなど法人需要も開拓できると考えています。「地域」もブランドの根っことなる重要な要素です。地元である阪神間に、ブランドとお客さまとのストーリーを構築できるような場としてカフェを今よりももっと充実させていきたいですね。

「せっかくの取材はできるだけ受けさせていただく」(蟻田社長)方針。社長就任後は、商品だけでなく企業広報を重視しているという。
アッシュ・セー・クレアシオンの広報体制

洋菓子工場「ハーバースタジオ43」(兵庫県西宮市)。建物内に本社機能も置いている。
広報担当者は3 人。メディアリレーションズ業務のほか、社内報作成など社内広報も担う。蟻田社長就任後は企業広報を重視し、会社の方針などを聞く取材は基本的に断らない方針だという。
 |
蟻田剛毅氏(ありた・ごうき)1974年兵庫県生まれ。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修了。電通勤務を経て、2007年アンリ・シャルパンティエ(当時)入社。副社長を経て、11年6月から現職。 |
- 東大発のバイオベンチャー「ミドリムシの広報マン」